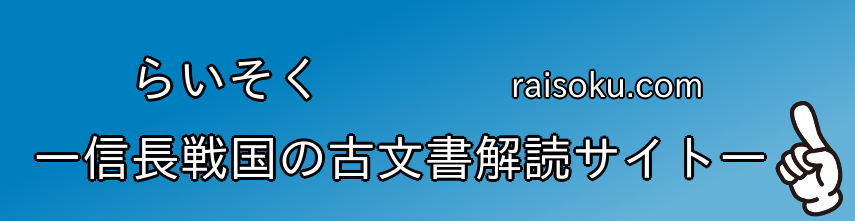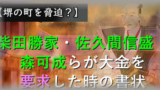こんばんはー!
今回は50回目の投稿になります。誠にありがとうございます(´;ω;`)
本項は永禄10年(1567)10月から永禄12年暮れまでを記事にしている。
(これまでの流れ)
- 誕生~叔父信光死去まで(1534~1555)
- 叔父信光死去~桶狭間の戦い直前まで(1555~1560)
- 桶狭間の戦い~小牧山城移転直後まで(1560~1564)
- 美濃攻略戦(1564~1567)
- 覇王上洛(1567~1569) イマココ
- 血戦 姉川の戦い(1570 1.~1570 7.)
- 信長包囲網の完成(1570 7.~12.)
- 比叡山焼き討ち(1571 1.~9.)
- 義昭と信長による幕府・禁裏の経済改革(1571 9下旬~1571.12)
- 元亀3年の大和動乱(1572 1.~1572.6)
- 織田信重(信忠)の初陣(1572 7.~1572 9.)
- 武田信玄 ついに西上作戦を開始する(1572 9.~1572 12.)
- 将軍・足利義昭の挙兵と武田信玄の死(1573 1.~1573 4.)
- 将軍追放 事実上の室町幕府滅亡(1573 5.~1573 7.)
- 朝倉・浅井家滅亡(1573 8.~1573 10.)
- 三好義継の最期(1573 10.~1573 12.)
この年表の見方
- 当サイトでは、信長の人生で大きな転換期となった時代時代で、一区切りにしている
- 他サイトや歴史本、教科書で紹介されている簡単な年表に書いている内容は、赤太文字
- 年代や日付について諸説ある場合は、年代や日付の個所に黄色いアンダーライン
- 内容に関して不明確で諸説ある場合は、事績欄に黄色いアンダーライン
- 当時は数え年であるから、信長の年齢は生まれた瞬間を1歳とする。誕生日についても詳細不明のため、1月1日で1つ歳を取る
- 太陽暦、太陰暦がある。当サイトでは、他のサイトや歴史本と同じように、太陰暦を採用している。中には「閏」なんていう聞きなれないワードがあるかもしれないが、あまり気にせず読み進めていってほしい
- キーとなる合戦、城攻め、政治政策、外交での取り決めは青太文字
- 翻刻はなるべく改変せずに記述した。そのため、旧字や異体字が頻繁に登場する。しかしながら、日本語IMEではどうしても表記できない文字もあるため、必ずしも徹底しているものではない。
- 何か事柄に補足したいときは、下の備考欄に書く
信長の年表(詳しめ5)
岐阜と天下布武の朱印
永禄10年(1567)
34歳
この頃
居城を小牧山から稲葉山に移転。『信長公記』
一、八月十五日、 色々降参尓て飛騨川のつヽき尓て候間、舟尓て川内長嶋へ 龍興退散去て美濃國一篇尓被仰付、尾張國小眞木山より濃州稲葉山へ御越也、井口と由を今度改て岐阜と名付させられ、明ル年之事、
(書き下し文)
一、(永禄10年)八月十五日、 色々降参にて飛騨川のつづきにて候間、舟にて河内長嶋へ 龍興退散。
去て美濃国一篇に仰せ付けられ、尾張国小牧山より濃州稲葉山へ御越しなり。
井口と由を今度改めて岐阜と名付けさせられ、明くる年の事。
同書の「(四十五) 公方様御憑百ケ日の内に天下被仰付候事」の項より抜粋
10月2日
細川六郎(のちの昭元)、山城国大原口・栗田口の山科率分領を横領か。
山城言継、三好長逸と石成友通に子細を説明し、細川六郎の行為を改めさせる旨を歎願する。『言継卿記』永禄十年十月二日条
澤路隼人佑來、内蔵寮率分東口之事、細川六郎違亂云々、折紙持來、
城州大原口栗田口山科率分今村分事、被差越上使上者、役銭等如先々可致沙汰彼代由状如件、
永禄十
九月廿八日 爲房 判
諸役所中
不能承引、上使追返云々、重可來之由申云々、仍今日隼人佑三好日向守・石成主税助所へ指下、書状如此、
急度注進申候、禁裏御料所城州大原口栗田口等率分之事、去年以来各依御入魂無別儀之段、御祝着之叡慮候、然處從六郎殿被號今村分、可有押領之由、如此被越上使候、無別儀之様被仰届候者、可為神妙候、於我等も可満足候、尚委曲澤路入道可申候、恐恐謹言、
十月一日 言継
三好日向守殿 石成主税助殿両通調遣之、
(書き下し文)
澤路隼人佑来たる。
内蔵寮率分東口の事、細川六郎(のちの細川昭元)違乱し云々。
折紙持ち来たる。
「城州大原口・栗田口、山科率分・今村分の事、上使を差し越さるるの上は、役銭等先々の如く沙汰致すべし彼代の由状くだんの如し。
永禄十(1567)
九月二十八日 為房 判
諸役所中」
承引能わず。
上使を追返し云々。
重ねて来るべきの由を申し云々。
仍って今日隼人佑を三好日向守(三好長逸)・石成主税助(石成友通)所へ指し下す。
書状かくの如し。
「急度注進申し候。
禁裏御料所城州大原口・栗田口等率分の事、去年以来各御入魂別儀無きの段に依りて、御祝着の叡慮に候。
然るところ、六郎殿より今村分を号され、押領有るべきの由、かくの如く上使を越され候。
別儀無きの様仰せ届けられ候はば、神妙たるべく候。
我らに於いても満足すべく候。
なお委曲澤路入道申すべく候。恐恐謹言」(以下略)
(備考)
山科家の名字地をはじめとする山科東庄・大宅郷・四宮川原・山科西庄・野村郷・西野山郷等は、足利将軍家に横領されて久しい。
にも関わらず、山科七郷の住人はたびたび禁中警固の任を命じられていることが『言継卿記』に記されている。
なお、この返書は『言継卿記』永禄十年十月十二日条に見える。
内容はタブ内で。
澤路入道自攝州上洛、和州之儀各取亂云々、日向守返事有之、
「尊書致拜見候、仍禁裏御料所率分儀付而、様躰蒙仰候、何も各令談合、有様才覺可申候、不可有油斷候、此由宜令披露給候、恐々謹言、
十月十一日 長逸 判
澤路筑後入道殿」
今夜就南都之儀、京中終夜馳走也、明日敵出張云々、
(書き下し文)
澤路入道摂州より上洛。
和州の儀各取り乱ると云々。
日向守(三好長逸)返事これ有り。
「尊書拝見致し候。
仍って禁裏御料所率分の儀に付きて、様体を仰せ蒙り候。
何れも各談合せしめ、有様才覚申すべく候。
油断有るべからず候。
この由宜しく披露せしめ給い候。恐々謹言。」
(中略)
今夜南都の儀に就きて、京中終夜馳走なり。
明日敵出張(奉公衆)と云々。
10月3日
信長奉行人の坂井政尚と森可成、武儀郡の武芸八幡宮へ所領を安堵する旨の書状を発給。『武芸八幡宮文書』永禄十年十月三日付坂井政尚・森可成連署状
当寺領之儀ニ付て、西方より違乱之旨候、御制札之上者、不可有异儀候、前々より不相替候条、弥被仰出候、尤存候、重而違乱におゐて者、両人可申届候、恐惶謹言、
十月三日 森三左衛門尉可成(花押)
坂井右近尉政尚(花押)
武芸八幡寺
御坊中
(書き下し文)
当寺領の儀に付きて、西方より違乱の旨に候。
御制札の上は、異儀有るべからず候。
前々より相替わられず候の条、いよいよ仰せ出され候。
尤もに存じ候。
重ねて違乱においては、両人に申し届くべく候。恐惶謹言。(以下略)
語訳)当寺領について西方から違乱があるとのことである。しかし、信長からの御制札がある上は異儀がない。
織田が新たにこの地を統治することになったが、前々からの決まりで相違無い旨を信長が仰せになった。これはもっともなことである。従って、重ねて違乱する者があれば、坂井と森の両人に届け出るように。
(備考)
文書内に見える「御制札之上者」とは、同年10月日付で発給された織田信長制札『武芸八幡宮文書』(※詳細は下記参照)であろう。
ここにも戦乱の混乱に乗じて押領をする者がいたことが窺える。
10月10日
松永久秀、東大寺に陣する三人衆に夜襲。
中村新兵衛らが討死するも、池田勢らが持ち堪える。
東大寺の大仏殿は消失。 『言継卿記』永禄十年十月十一日条 『細川両家記』など
去夜南都東大寺大佛殿炎上云々、三國一之伽藍、歎入之儀也、不可說、鑓中村以下數十人討死、東大寺之内之衆敗軍、其外之衆堅固也云々、松永弾正少弼久秀朝大理云々、
『言継卿記』永禄十年十月十一日条
(書き下し文)
去夜、南都東大寺大仏殿が炎上と云々。
三国一の伽藍、嘆き入るの儀なり。
不可説。
槍中村以下数十人討死。
東大寺の内の衆敗軍、そのほかの衆は堅固なりと云々。
松永弾正少弼久秀朝大理云々、
一、同十月十日夜半に、三人衆陣所東大寺内へ多門衆夜討して打破、中村新兵衛をはじめうち取、因慈大佛殿を焼崩と風聞也、然といへ共池田勝政陣所無異儀、然ば則三人衆より加勢候て、又所々へ陣取共候也、
『細川両家記』
(書き下し文)
同十月十日夜半に、三人衆(三好三人衆)陣所東大寺内へ、多聞衆(松永勢)が夜討ちして打ち破る。
中村新兵衛をはじめ(としてその他の者も)討取る。
これにより大仏殿を焼き崩すと風聞なり。
然りといえども、池田勝正の陣所は異儀無し。
然らば則ち三人衆より加勢候て、また、所々へ陣取るとも候なり。
この頃
三好三人衆らに属す松山彦十郎、松永方に寝返るも数日後に降伏。『細川両家記』
松山彦十郎、松浦孫五郎於奈良陣所、興福寺三人衆へ一味候處に、松山安藝守吾に無案内由にて立腹して、多門がたへ被成候、則三人衆より飯盛城内味方衆被居家内へ人數加之、則安藝守方を取巻被責候間難相叶、噯に成て同十五日堺へ退也、味方になり前々の知行無相違也、
(書き下し文)
松山彦十郎、奈良陣所の松浦孫五郎(の陣)に於いて、興福寺・三人衆へ一味し候ところに、松山安芸守、吾(松山彦十郎)に案内無きの由にて立腹して、多聞(松永久秀)がたへ成られ候。
則ち三人衆より飯盛城内の味方衆居られ、家内へ人数これを加う。
則ち安芸守方を取り巻き、攻められ候間、相叶い難く扱いに成りて、同十五日堺へ退くなり。
(以降は)味方になり前々の知行は相違無しなり(安堵されたの意)。
10月12日
[参考]『古証文』二
今度同名新三郎・九里三郎左衛門尉景雄企謀反、既木村五兵衛尉を初右両人仁令一味、土田・中村・宇津呂・一井・西庄・籠屋場等道、相構要害、国□屋敷取巻、通路無合期、以無二御覚悟御忠節、於家御芳恩不可相忘候、殊右両人相催人数、及行、数度切崩、被討人、無比類御働共候、悉皆以御入魂施面目候、外聞実儀万々満足不可過之候、然者一謙令配当度儀候へとも、御存知之通候間、不及了簡候、何時も新知於拝領者、不混自余一謙可令支配候、就其島郷令持名士・馬飼一円幷相原小□中跡、一円永代遣之候、向後御知行不可有相違候、次深尾七郎左衛門尉跡与力・被官事、以目録預ヶ置候、但彼跡目於申付者、各別候、猶木村三郎右衛門尉・梅原対馬守・北川又三郎、紙面可令申候、恐々謹言、
永禄十年
十月十二日 池田
景雄(花押)
真光寺
周揚(花押)
杉山右兵衛尉殿
御宿所
(書き下し文)
この度同名新三郎・九里三郎左衛門尉景雄謀反を企て、既に木村五兵衛尉を初め右両人に一味せしめ、土田・中村・宇津呂・一井・西庄・籠屋場等の道に要害を相構え、国□屋敷を取り巻き、通路無合期、無二の御覚悟・御忠節を以て、家、御芳恩に於いては相忘るべからずに候。
殊に右両人、人数を相催してだてに及び、数度切り崩し、人を討たれ、御働き共に比類無く候。
悉く皆以て御入魂面目を施し候。
外聞実儀万々満足これに過ぐべからず候。
然らば一謙配当せしめたく儀に候へども、御存知の通りに候間、了簡に及ばず候。
何時も新知拝領に於いては、自余に混せず一謙支配せしむべく候。
それにつきて島郷の名士を持ちせしめ・馬飼一円並びに相原小□中跡、一円永代これを遣わし候。
向後は御知行相違有るべからず候。
次いで深尾七郎左衛門尉跡与力・被官の事、目録を以て預け置き候。
但しかの跡目を申し付くるに於いては、各々別に候。
なお木村三郎右衛門尉・梅原対馬守・北川又三郎が紙面で申せしむべく候。恐々謹言(以下略)
(備考)
土田・中村・宇津呂・一井・西庄・籠屋場・島郷はいずれも蒲生郡にある地名。
特に島郷は浜街道上に嶋郷市があり、近江指折りの商業地であった。
配当(はいとう)は割り当てること、配分することを指す。
観音寺騒動や安国寺質流相論の余波だろう。
六角氏は式目制定後も国内の秩序を保てていなかった。
本記事の主旨とは異なるので、詳しくは述べない。
10月20日
[参考]『言継卿記』永禄十年十月二十日条
炭山へ奉公衆三淵弾正左衛門大将出張、三好兵庫助大将播州衆、西岡衆、小泉、山本以下罷向、三淵敗軍討死云々、首卅六捕之云々、山名又五郎、布施彌太郎、
10月
信長、稲葉山城下で加納市場に還住する者を優遇する旨の制札を発給。『円徳寺文書』永禄十年十月日付織田信長制札
定 楽市場
一、當市場越居之者、分国往還不可有煩、幷借銭・借米・地子・諸伇令免除訖、雖為譜代相伝之者、不可有違乱之事、
一、不可押買・狼藉・喧嘩・口論事、
一、不可理不尽之使入、執宿非分不可懸申事、
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍下知如件、
永禄十年十月日 (織田信長花押)
(書き下し文)
定め
一、当市場に越居の者、分国の往還に煩い有るべからず。
並びに借銭・借米・地子・諸役を免許せしめおわんぬ。
譜代相伝の者たりといえども、違乱有るべからざるの事。
一、押買・狼藉・喧嘩・口論すべからざるの事。
一、理不尽の使を入るるべからず。
宿を取り、非分を申し懸くべからざるの事。
右の条々、違犯の輩に於いては、速やかに厳科に処すべきものなり。仍って下知くだんの如し。
永禄十年十月日 (織田信長花押)
語訳)定め。①加納市場に移住する者は、織田分国内での往来の自由を保証する。また、借銭・借米・地子銭(借地料)などの諸役(いろいろな雑役)を免除する。たとえ織田の譜代からの臣であっても、秩序をみだしてはならない。②不法(強引)な買い入れを行ったり、狼藉・喧嘩・口論をしてはならない。③理不尽なことを要求する使者を入れてはならない。また、宿をとり、秩序を乱すようなことを要求してはならない。(以下略)
(備考)
これは信長が稲葉山城下に発布した還住を呼びかける制札である。
円徳寺が所蔵するこの檜板に記された制札は36.5cm×33cm、厚さ1.0cmであり、近年まで信長がいわゆる「楽市・楽座」をよびかけたとする根拠となっていた。
翌永禄11年(1568)9月に加納市場へ出した制札『円徳寺文書』には、「一、楽市・楽座之上、諸商買すへ畿事」との文言が入っており、多くの書籍で取り上げられてきた。
これまでの常識では「この地に座席を持つ商人でなければ、自由に商買をすることができない」という制約を取り払い、「一定の税を納めさえすれば、誰でも商買ができるようにする」ことを示すものとされてきた。
しかし、近年の研究では、これは戦乱によって離散した住民たちを呼び戻し、速やかに平時の状態に戻す政策ではないかとの見解が主流となりつつある。
というのは、これ以降、信長は同地に対して複数回制札を出しているが、次第に借銭・借米などを免除する要素が減っていき、逆に権利者(債権者)の権利を保障する内容が増えていくのである。
確かに、先入観を捨てて素直に文書を読んでみると、還住政策の一環と見るのが自然なのかもしれない。(※以後の加納市場の制札についても追記予定)
10月
信長、稲葉山城下の美江寺へ禁制を発給。『美江寺文書』永禄十年十月日付織田信長禁制
禁制 美江寺十弐坊
一、甲乙人等執宿、附、新儀之諸伇免許之処、無謂子細申懸之事、
一、寺領諸奇進幷新堂地・坊地年貢及違乱之事、
一、相破先例之寺法事、
右条々、於違反之輩者、速可処厳科者也、仍下知如件、
永禄十年十月日 (信長花押)
(書き下し文)
禁制 美江寺十二坊
一、甲乙人等宿を取ること。
附けたり、新儀の諸役免許のところ、謂われ無き子細を申し懸くるの事。
一、寺領諸寄進並びに新堂地・坊地の年貢を違乱に及ぶの事。
一、先例の寺法を相破るの事。
右の条々、違反の輩に於いては、速やかに厳科に処すべきものなり。仍って下知くだんの如し。(以下略)
(備考)
美江寺は城下にある天台宗の寺院で、現在も美江観音として知られている。
もとは本巣郡十六条村にあったが、戦国時代にこの地に移転。
その経緯は諸説あるそうだが、美江寺は天文8年(1539)12月日付の斎藤左近大夫(利政・道三)発給の禁制を所蔵している。
文書内に見える「十二坊」は門前の両側にあったとみられ、かつては正覚院・観昌院などの子院を持つ大きな寺院だったのだろう。
10月
信長、武儀郡の武芸八幡宮へ制札を発給。『武芸八幡宮文書』永禄十年十月日付織田信長制札
寺社領幷門前之諸伇、如前々不可有相違、若於違犯之族在之者、可加成敗之状如件、
永禄十
十月日 (信長花押)
武芸八幡
衆僧中
(書き下し文)
寺社領並びに門前の諸役、前々の如くに相違有るべからず。
もし違犯の族(やから)これ有らば、成敗を加うるべきの状くだんの如し。(以下略)
(備考)
本制札は、同年10月3日付で同地へ発給された坂井政尚と森可成の連署状『武芸八幡宮文書』を裏付けるものであろう。
11月3日
勧修寺晴秀(黄門)・山科言継ら、摂州富田の足利義栄(左馬頭殿)と対面。『言継卿記』永禄十年十一月三日条
(3日)
佛暁出立、誘引勧修寺黄門、倉部等攝州富田へ罷下、供者大澤右兵衛大夫、澤路隼人佑、雑色與右衛門、孫左衛門、隼人小者兩人、人夫孫右衛門等也、勧之供侍雑色人夫等三人計也、於廣瀬畫休申付了、未下刻攝州富田へ下着、則畠山式部少輔入道安枕齋守肱、所へ以使者澤路、爲御禮下向仕候間、可然之様御披露之由申遣之、他行之由返答、重使有之、則令披露之處、軈可有御對面、時分可案内申云々、勧修寺黄門は別之宿程遠云々、暮々可参之由被申送之間則参、先予、勧中被参、軈左馬頭殿御對面、予、勧、内蔵頭次第御禮申之、太刀、金、申次畠山伊豆守、安枕之息也、安枕馳走也、次入道御所へ申入、御咳氣之由有之無御對面、以同申次各太刀金、進上之、次田宮御局へ以申次申了、御外奉公衆伊勢伊賀守、西郡三川守、同息龍千世、其外十一二三之若衆三人計也、次退出了、次軈西郡三州禮に被來云々、
(書き下し文)
佛暁に出立。
勧修寺黄門(勧修寺晴秀)・倉部等を誘引し、摂州富田へ罷り下る。
供者は大澤右兵衛大夫(大澤重延)・澤路隼人佑・雑色の与右衛門・孫左衛門・隼人小者両人、人夫の孫右衛門等なり。
勧(勧修寺氏)の供侍雑色人夫等三人ばかりなり。
広瀬に於いて書休を申し付けおわんぬ。
未の下刻に摂州富田へ下着。
則ち畠山式部少輔入道(安枕斎守肱)、所へ使者澤路を以て、御礼のため下向仕り候間、然るべきのよう、御披露の由、これを申し遣す。
他行の由の返答。
重ねての使いこれ有り。
則ち披露せしむるのところ、やがて御対面有るべきの時分を案内すべしと申し云々。
勧修寺黄門は別の宿で程遠しと云々。
暮ぐれに参るべきの由、申し送らるるの間、則ち参る。
まず予、勧中(勧修寺中納言)参らる。
やがて左馬頭殿(足利義栄)と御対面。
予、勧、内蔵頭と次第を御礼申す。
太刀(金)、申次に畠山伊豆守(安枕の息なり)安枕が馳走なり。
次いで入道が御所へ申し入る。
御咳気の由これ有り御対面無く、同じく申次を以て、おのおの太刀(金)これを進上す。
次いで田宮御局へ申次を以て申しおわんぬ。
御外に奉公衆の伊勢伊賀守・西郡三河守・同息の龍千世、そのほか十一・二・三の若衆三人ばかりなり。
次いで退出しおわんぬ。
次、やがて西郡三州(三河守)が礼に来られ云々。
※「黄門(こうもん)」は中納言の唐名。
※「雑色(ぞうしき)」は蔵人所の下級職員。
公卿の子弟などが任ぜられることが多い。
※大澤重延(右兵衛大夫)と澤路隼人佑は言継の側近。
※「畫休(かきやすらう)」は「書き休らう」。
休憩がてらに筆を執ったのだろうか。
※畠山式部少輔入道は足利義栄側近の人物か。
※他行(たぎょう)はよそへ出かけていること。
※進物の太刀は太刀代としての金銭を表しているのだろうか。
(4日)
早旦安枕齋へ予、倉部等禮に罷向、倉部兩人へ太刀絲卷、遣之、則安枕、伊豆守等見参、酒有之、次西郡三州へ禮申之、他行云々、勧黄門被來、雖然倉部令勞之間同道不可叶之間、先へ可被上洛之由示之、
倉部馬雖令調法不調之間、従巳刻閑に發足、かぢをりにて馬令調法、山崎迄令乗之、於山崎竹内左兵衛佐長治朝臣所へ罷向、馬之事申之、先吸物にて一盞有之、頻に留之間今日逗留了、晩飡上下申付了、雑談移刻、音曲等有之、湯積にて又一盞有之、
(書き下し文)
早旦に安枕斎(畠山守肱)へ予・倉部等礼に罷り向かう。
倉部両人へ太刀(糸巻)これを遣す。
則ち安枕・伊豆守等見参。
酒これ有り。
次いで西郡三州へ礼を申す。
他行に云々。
勧黄門(勧修寺晴秀)来たる。
然れども倉部労をせしむるの間、同道叶うべからずの間、先へ上洛せらるべきの由これを示す。
倉部の馬調法せしむるといえども、調わずの間、巳刻より閑に発足。
かぢをりにて馬を調法せしめ、山崎までこれを乗りせしめ、山崎に於いて竹内左兵衛佐長治朝臣所へ罷り向かう。
馬の事これを申す。
先ず吸物にて一盞これ有り。
頻りに留むの間、今日逗留しおわんぬ。
晩飡上下を申し付けおわんぬ。
雑談し刻を移す。
音曲等これ有り。
湯積にてまた一盞これ有り。
※絲卷(いとまき)・・・太刀の糸巻きは、柄や鞘の部分を組糸で巻いた部分。
※発足(ほっそく)・・・出立すること。
※一盞(いっさん)・・・1つのさかずき。1杯の酒を呑むこと。
※晩飡(ばんそん)・・・夕食。夕餉。晩餐のこと。
(備考)
山科言継は前日の11月2日に、勧修寺黄門(勧修寺晴秀)から同道するように誘われていた。『言継卿記』十一月二日条
同文書によると、3日に義栄らと対面。
4日に義栄側近らに礼を述べ、そのまま帰路についた。
その途中、山崎の竹内長治宅へ立ち寄り、もてなしを受ける。
翌5日、竹内宅を発ち暮れに帰宅。
6日に御所等に赴き報告を終えたようだ。
11月7日
石山本願寺の門跡顕如、織田信長へ美濃・伊勢平定を祝す旨の書状を発給。『顕如上人御書札案留』
今度濃州勢州平均事、無比類次第候、仍可有御上洛之由尤珍重候、就中太刀一腰一文字、赤熊□唐衣裳三、虎草(革カ)二枚、馬一疋青毛推進之候、猶上野法橋可令演說候、穴賢々々、
十一月七日 — —
織田尾張守殿
(書き下し文)
この度濃州・勢州を平均の事、比類無き次第に候。
仍って御上洛有るべくの由、尤も珍重に候。
就中太刀一腰(一文字)・赤熊□唐衣裳三・虎草(革カ)二枚・馬一疋青毛、これを推しまいらせ候。
猶上野法橋(下間頼充カ)演説せしむべく候。穴賢穴賢(以下略)
11月9日
正親町天皇、御倉職の立入宗継を織田信長に遣わし、美濃・尾張の御料所回復を命ず。(正親町天皇綸旨案)『道家祖看記』『立入宗継文書』
今度国々属本意由、尤武勇之長上、天道之感応、古今無双之名将、弥可被乗勝之□(条カ)為勿論、就中両国御料□(所カ)□(且カ)被出御目録之条、厳重被申付者、可為神妙旨、綸命如此、悉之以状、
永禄十年十一月九日 左中弁晴豊(花押)
織田尾張守殿
(書き下し文)
この度国々本意に属するの由、尤も武勇の長上、天道の感応、古今無双の名将、いよいよ勝に乗ぜらるべきの条もちろんたり。
就中両国の御料所且つは御目録を出さるるの条、厳重に申し付けらるれば、神妙たるべきの旨、綸命かくの如し。これを悉(つく)せ、以て状す。(以下略)
(備考)
これとは別に同日付で万里小路惟房が信長に宛てた書状案(『経元卿御教書案』)には
「今般隣国早速属御理運、諸人崇仰之由奇特、誠以漢家・本朝当代無弐之壽策、武運長久之基、併御幸名無隠候、就其被成勅裁之上者、被存別忠、毎端御馳走肝要候、・・・」とあり、上記の書状と同じく最大限の賛辞を送っている。
私はまだ未確認であるが、この万里小路惟房の案文は『立入宗継文書』に所載されているそうだ。
同日
若狭武田家の当主義統没。享年32。
家督は嫡子元明が継ぐ。(出展不明)
(備考)
若狭国は遠敷・大飯・三方の三郡で構成されている。
武田氏の本拠である小浜は遠敷郡にある。
それに従う有力国衆は西の大飯郡高浜の逸見氏、東の三方郡の佐柿氏・粟屋氏である。
11月21日
足利義秋、敦賀郡司朝倉景恒(中務大輔)を案内役として越前一乗谷に入る。(出展不明)
(備考)
朝倉義景は義昭を迎え入れるため、新築の将軍御座所を設備した。
しかしながら、越前では堀江氏の反乱の余波がまだ残っており、多事多難な時期であった。
11月27日
朝倉義景、義秋へ御礼のため参上。(出展不明)
(備考)
この時義景側近として朝倉出雲守、前波、山崎の馬上三騎が従った。
11月
信長、家臣の坂井利貞(文助)へ知行を安堵する旨の書状を発給。『坂井遺芳』永禄十年十一月日付織田信長朱印状
為扶助、旦嶋内弐拾貫文申付上、全知行、不可有相違之状如件、
永禄十
十一月日 信長(朱印)
坂井文助殿
(書き下し文)
扶助として、旦の嶋のうち、二十貫文を申し付くるの上は、全く知行し、相違有るべからざるの状くだんの如し。(以下略)
(備考)
「旦の嶋」は美濃国厚見郡にあり、現在も岐阜市内にその名がみえる。
かつては川と川に挟まれた輪中地区だったのかもしれない。
この文書が現存する中で、織田信長が発給した最古の朱印状である。
楕円形で輪郭一重の形状で「天下布武」と記したものである。
以後、信長の権力が増大するにつれて朱印状の割合が増え、やがて朱印から黒印へ、書留も「~候也(そうろうなり)、」で締めるものが多くなる。

宛所の坂井利貞は、織田家古参の奉行衆で弘治元年(1555)12月28日付で知行を宛行われている。『坂井遺芳』
以後も織田の奉行人として活躍し続け、のちに織田信忠にも仕えた。
なお、公卿の山科言継との親交も深いとみえ、『言継卿記』にも信長上洛の永禄11年(1568)以降しばしば登場する。
11月
信長、家臣の高木貞久(彦左衛門)へ判物を発給。『高木文書』永禄十年十一月日付織田信長判物
其方当知行、不可有違乱候、非分以下申懸者於在之者、厳重可申付者也、謹言、
永禄十
十一月日 (信長花押)
高木彦左衛門とのへ
(奥裏書)
「信長公御直筆」
(書き下し文)
その方の当知行、違乱有るべからず候。
非分以下を申し懸くる者これ在るに於いては、厳重に申し付くるべきものなり。謹言。(以下略)
(備考)
高木貞久は美濃駒野城主として近年まで安藤守就に属していた『重修譜』。
弘治2年(1556)9月20日付で新九郎高政(斎藤道三嫡子)より庭田・西駒野等6ヶ所を安堵されている。『高木家文書』
谷口克広著『織田信長家臣人名辞典(吉川弘文館)』によると、安藤守就よりもいち早く信長に降っており、市橋長利の仲介で永禄6年(1563)には既に織田方となっていたとある。
なお、後年に長島一向一揆との戦いに際し、貞久の領する駒野は長島との国境近くであるため、高木家臣の中には一揆勢に同調する者も多かった。
信長は猪子高就に命じて貞久家臣の糺明と、場合によっては貞久本人の成敗を命じている。『猪子文書』
11月
信長、家臣の矢野弥右衛門に美濃河野の地20貫文を宛行う。『尊経閣文庫文書』保包四六四 永禄十年十一月日付織田信長朱印状
為扶助、河野内弐拾貫文申付上、全知行不可有相違之状如件、
永禄十
十一月日 信長(朱印)
矢野弥右衛門尉殿
(書き下し文)
扶助として、河野のうち二十貫文を申し付くるの上は、全く知行し、相違有るべからざるの状くだんの如し。(以下略)
(備考)
宛所の矢野弥右衛門は、美濃の地侍と思われる。
河野は羽島郡笠松町の木曾川沿いにある地だろう。
前年にあたる永禄9年(1566)閏8月8日にあったとされる河野島の戦いの舞台であるが、史料に乏しく実態は不明。
河野もかつては輪中地域だったのかもしれない。
11月
信長、家臣の兼松正吉(又四郎)に美濃河野の地10貫文を宛行う。『兼松文書』永禄十年十一月日付織田信長朱印状
為扶助、河野内拾貫文申付上、全知行不可有相違之状如件、
永禄十
十一月日 信長(朱印)
兼松又四郎とのへ
(書き下し文)
扶助として、河野のうち十貫文を申し付くるの上は、全く知行し、相違有るべからざるの状くだんの如し。(以下略)
(備考)
兼松正吉は信長の馬廻の一人。
兼松は以前、6月10日付で佐々平太とともに「河野之嶋」の地22貫文を含め都合30貫文を宛行われ、昨年の11月には兼松弥四郎の跡職を安堵されている。『兼松文書』
正吉は以後の戦いもたびたび参陣し、天正元年(1573)の朝倉氏追撃戦では朝倉の臣中村新兵衛を討ち取り、信長から称賛されている『信長公記』『兼松文書』。
その後も寛永4年(1627)まで活躍し、最終的には丹羽・羽栗両郡にて2600石を知行する大出世を遂げた。
戦国の立身出世は彼のためにあるのかもしれない。
11月
信長、丸毛不心斎宛で禁制を発給。『吉田文書』
禁制 多芸
丸毛不心斎
一、買得之田畠幷年記・当作・借銭・質物等違乱事、
一、非分要脚等申懸事、
一、理不尽之使不可入事、
右条々不可有相違、然上者徳政等申事候共、令免許上、若此旨於違背之輩者、可加成敗者也、仍状如件、
永禄十年十一月日 (信長朱印)
(書き下し文)
一、買得の田畠並びに年期・当作・借銭・質物等違乱の事。
一、非分の要脚等を申し懸くるの事。
一、理不尽の使を入るべからざるの事。
右の条々、相違有るべからず。
然る上は、徳政等を申す事候えども、免許せしむるの上、もしこの旨違背の輩に於いては、成敗を加うるべきものなり。仍って状くだんの如し。
語訳)①私的に買い入れた田畠並びに年月を限って買い入れた田畠・本年耕作して手に入った田畠・借銭・借米・質物等に違乱すること。②不当に金銭を要求すること。③不当に使者を送ること。右の条々に背いてはならない。この上は、徳政等が発布されたとしても、丸毛不心斎には無効とする。これらの掟に背いた者があれば、処罰を加えるものとする。
(備考)
宛所の丸毛不心斎の詳細は不詳。
谷口克広著『織田信長家臣人名辞典(吉川弘文館)』によると、美濃多芸郡の人であることは明らか。
丸毛光兼とは同族の可能性が高いが、同一人物である可能性は低いとある。
不心斎は丸毛長照『寛政重修譜家譜』の斎号である可能性もあるが、実否は不詳。
なお、光兼は稲葉一鉄の娘を正室としている。
12月1日
織田信長、大和の興福寺衆徒へ加勢する旨の朱印状を発給。『柳生文書』(永禄十)十二月一日付織田信長朱印状
御入洛之儀、不日可致供奉候、此刻御忠節肝要候、就其対多聞、弥御入魂専一候、久秀父子不可見放旨、以誓紙申合候条、急度可致加勢候、時宜和伊予可有演説、猶佐久間右衛門尉可申候、恐々謹言、
十二月一日 信長(朱印)
興福寺御在陣衆御中
(書き下し文)
御入洛の儀、不日に供奉致すべく候。
この刻み御忠節肝要に候。
それに就きて、多聞(松永久秀・久通父子)に対し、いよいよ御昵懇 専一に候。
久秀父子も見放すべからざるの旨、誓紙を以て申し合わせ候条、急度加勢を致すべく候。
時宜は和伊予(和田惟政)演説有るべし。
なお佐久間右衛門尉(佐久間信盛)申すべく候。恐々謹言。(以下略)
語訳)信長は、足利義秋を供奉して近日のうちに上洛する。その時、義秋に対して忠節を尽くすことが肝要である。それについて、松永父子とも連絡を密にし、昵懇となることを第一と考えてほしい。信長は松永父子を見捨てず、起請文を交換したからには、必ず加勢をする。時宜については義秋奉行人の和田惟政が申し述べる。佐久間信盛が副状を発給するゆえ、そちらも合わせてご覧されたし。
(備考)
信長は新たに支配することとなった美濃国で政務に忙殺される一方、将軍となることを目的とする足利義秋と連絡を密に取っていた。
和田惟政(伊予守)も義秋奉行人としてその任に当たっていたのだろう。
和田は少なくとも永禄8年(1565)12月には、すでに織田信長と接点を持っている。『東京大学史料編纂所所蔵文書』(永禄八)十二月五日付織田信長書状
同日
織田信長、松永久秀老臣の岡国高(因幡守)へ加勢する旨の朱印状を発給。『岡文書』『集古文書』711-712(永禄十)十二月一日付織田信長朱印状
御入洛之儀、不日可致供奉候、此刻御忠節肝要候、就其対多聞、弥御入魂専一候、久秀父子不可見放旨、以誓紙申合候条、急度可致加勢候、時宜和伊予可為演説、猶佐久間右衛門尉可申候、恐々謹言、
十二月一日 信長(朱印)
岡因幡守殿
御宿所
(備考)
文面は同日付の『柳生文書』とほぼ同じ。
「時宜和伊予可為演説」に唯一ささやかな違いがある。
この時期にはすでに佐久間信盛が、大和方面における取次役として副状を発給できる立場であることも注目に値する。
なお、脇付の「御宿所」であるが、久秀本人ではなく、その取次に宛てた上、「あなた様の御宿へ」として直接宛てることを避けた大変厚礼なものとなっている。
12月3日
公卿の山科言継、足利義栄側近の畠山守肱(畠山式部少輔入道)へ所領の返還を歎願する旨の書状を発給。『言継卿記』永禄十年十二月五日条
稱號之地之事に、澤路筑後入道富田へ可罷下之由申付了、畠山式部少輔入道江書状調遣之、如此、
先度祗候之刻、御馳走千萬畏入存候、就中稱號之地大宅郷・同散在四宮河原野村西山等之儀、被返渡候様、別而御入魂奉頼存候外無他候、尚々委細之段、澤路入道可申入候也、恐々謹言、
十二月三日 言継
安枕齋 床下
(書き下し文)
称号の地の事に、澤路筑後入道を富田へ罷り下るべきの由を申し付けおわんぬ。
畠山式部少輔入道(畠山守肱)へ書状これを調い遣す。
かくの如し。
「先度は祗候のきざみ、御馳走千万畏み入り存じ候。
就中、称号の地大宅郷・同じく散在の四宮河原野村西山等の儀、返し渡され候よう、別して御入魂存じ頼み奉り候ほか無く候。
尚々委細の段、澤路入道申し入るべく候なり。恐々謹言。
十二月三日 言継(山科言継)
安枕斎(畠山守肱) 床下」
12月5日
信長、正親町天皇に対し、綸旨と女房奉書、そし紅衫?を下賜されたことを謝し、さらに勅命の条々についても忝く拝受した旨を大納言万里小路惟房に伝え、その執奏を願った請文を発給する(熱田神宮所蔵文書)
(備考)
翻刻未確認。
後日見つけ次第に追記・修正したい。
12月11日
[参考]『言継卿記』永禄十年十二月十一日条より
伊勢備中入道被來、就富田武家御妹之儀、内々被申子細有之、一盞勧了、次堀川近江守來、保多加賀守御詫言之儀可申調頼入之由申之、次竹内右兵衛佐内小寺來、對面勧一盞、右大将之儀懇に雑談了、同袍之調料旦四十疋持來云々、
12月12日
朝倉氏と加賀一向一揆の和議の証として、加賀一向衆方の杉浦氏の子息らが一乗谷の阿波賀に送られる。(出展不明)
12月15日
朝倉氏と加賀一向一揆の和議の証として、加賀越前の国境にあった一揆方の柏野・松山の両城、朝倉方の黒谷・檜屋・大聖寺の三城が破却される。『越州軍記』
12月17日
和田惟政、六角氏からの書状の返書として浅井長政(浅井備前守)と織田信長(信長)の縁辺が後日に伸びることを報じ、今後とも昵懇に願う旨の書状を発給。『福田寺文書』
御書畏令拝見候、仍浅井備前守与信長縁変雖入眼候、先種々申延信長無別義候、猶以自心切々調略候条、無由断不存疎意候、急度罷上可得御意候、委細山岡美作守江申渡候際、此等之趣、宜預御披露候、恐々謹言、
十二月十七日 惟政(花押)
三雲新左衛門尉
三雲対馬守殿
(書き下し文)
御書畏まりて拝見せしめ候。
仍って浅井備前守と信長縁辺の入眼、まず種々に申し延び候といえども、信長別儀無く候。
なお以て心より切々と調略に候条、油断無く疎意に存ぜず候。
急度罷り上り御意を得るべく候。
委細山岡美作守(山岡景隆)が申し渡す候際、これらの趣き、宜しく御披露に預かり候。恐々謹言(以下略)
(備考)
この文書の翻刻は『戦国遺文 佐々木六角氏編』に所収されている。
この時期の六角氏の立ち位置について考えるのに興味深い史料である。
なお宛所の三雲成持(新左衛門尉)と三雲定持(対馬守)はともに六角氏の側近である。
12月18日
[参考]『言継卿記』永禄十年十二月十八日条より
安二位に借用之新暦終寫功了、本則旅宿へ令随身返之、暫雑談移刻了、
12月19日
[参考]『言継卿記』永禄十年十二月十九日条より
長橋局へ罷向、上に御脚氣事外被相煩云々、又御不食云々、次大典侍殿へ参、従富田公方内々被仰之儀在之申之、次内侍所へ立寄、
12月25日
足利義秋、朝倉義景の屋形を訪問。
盛大な式が催される。
義景、数々の進物を献じる。『朝倉始末記』『越州軍記』
12月
信長、美濃の阿願寺に引得(買い入れ地)分以下の所領を安堵。『阿願寺文書』永禄十年十二月日付織田信長朱印状
当寺引得分以下令免許上、如前々不可有相違之状如件、
永禄十
十二月日 (信長朱印)
嶋
阿願寺
(書き下し文)
当寺引得分以下、免許せしむるの上は、前々の如く相違有るべからざるの状くだんの如し。(以下略)
(備考)
嶋はもと島村、岐阜島といい、岐阜市西北の長良川の分流の中にある。
阿願寺は臨済宗妙心寺派の寺院で、現在も岐阜市東島に所在する。
阿願寺には織田信長発給文書のほか、土岐政房・同頼芸・斎藤利茂・同利政(道三)などの文書も所蔵している。
足利義栄、征夷大将軍となる
この頃
信長、妹の市を北近江の浅井長政へ嫁ぐ。『古文書慕』『総見記』など
(備考)
輿入れの時期は諸説あり判然としない。
永禄11年(1568)
35歳
1月1日
河内の津田衆らが松永方へ寝返り、河内国で三人衆方と交戦。『多聞院日記』『言継卿記』『細川両家記』
去朔日、津田城多聞山へ裏歸色立了、則河州出口にて及一戦、木澤ノ紀伊守討死了、則首ニ多聞山へ来了、マエサクマト云タル仁也ト、
『多聞院日記』永禄十一年正月五日条
(書き下し文)
去一日、津田城多聞山へ裏返る色を立ておわんぬ。
則ち河州出口にて一戦に及び、木澤の紀伊守討死しおわんぬ。
則ち首に多聞山へ来たりおわんぬ。
マエサクマト云うたる仁なりと。
烏丸へ罷向、極位珍重之由申之、宰弔之時分云々、申置了、次長橋局へ罷向、理性院、蔭亮等被來、吸物にて酒有之、次竹内殿へ参、暫御雑談有之、河州津田、城州田邊、松永方へ一味云々、仍河内路通路無之云々、
『言継卿記』永禄十一年正月八日条
同十一月日、伏見の津田、松永方へ一味して、多門より加勢之由也、
『細川両家記』
(備考)
津田は河内国交野郡(現枚方市)にある地で、中世期に新興土豪の津田氏が現れ、延徳2年(1490)頃、国見山に城を構えた。『三之宮日記』『津田史』
『角川日本地名大辞典 27 大阪府(1983)』によると、永禄2年(1559)8月20日の交野郡五ヶ郷惣侍中連名帳(三宮神社所蔵文書/枚方市史6)によれば,津田村・藤坂村・杉村・芝村・穂谷村の「侍中」の組織を「別当津田筑後守中原範長」が統制していたとある。
1月2日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年正月五日条より
去二日至堺津三好千鶴殿御渡海了、則従十市も使河権被越了ト、
1月9日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年正月九日条より
今井より多聞へ音信之荷來候間、翌日送て遣了、
1月17日
番替えのため三好長逸(三好日向)・池田衆らが奈良に出陣。『多聞院日記』永禄十一年正月十七日条
西の城番替ニ、三好日向・池田衆以下來了、
(備考)
同日条でほかに越前朝倉氏と加賀一向宗の和睦について記述がある。
越前より一切経承仕上了、加賀と越前と和談事、上意越州一乗へ被移、於御座被仰調悉以無事也云々、
1月
三好義継(左京大夫殿)多聞山城を出て河内津田城に入る。『細川両家記』
永禄十一年戊辰年正月日、三好左京大夫殿多門城より津田城へ御入候也、
(備考)
同文書には詳しい日付までは記述がない。
大きな戦闘が行われた同月1日の後詰として義継が出陣したのか、その後に津田城に入ったのかはわからない。
2月1日
公家の山科言継、宝鏡寺にて足利義栄の病状の噂を聞く。『言継卿記』永禄十一年二月一日条より
近衛殿へ御禮に参、御盃被下之、次寶鏡寺殿へ参、今御所尋申之、御腫物は御験氣、御氣煩御不食云々、
(書き下し文)
近衛殿へ御礼に参る。
御盃これを下さる。
次いで宝鏡寺殿へ参る。
今御所(足利義栄)これを尋ね申す。
御腫物は御験気。
御気煩い・御不食と云々。
2月2日
[参考]『言継卿記』永禄十一年二月二日条より
自頭中将将軍宣下之一通到、
追上啓
将軍宣下事候、同可得其御意候也、
來八日可有宣下事、可令参陣給、者依天氣上啓如件、
二月二日 右中将重通
謹上 師中納言殿
2月4日
足利義栄の将軍宣下が同年2月8日に行われることが決まり、宮中ではその準備で慌ただしくなる。『言継卿記』永禄十一年二月四日条
勧修寺黄門被來、富田之武家将軍宣下可爲來八日、上卿之事内々被示之、尚従奉行可被触之由有之、
烏丸へ罷向、見参、來八日袍借用之事申之、内々同心也、次勧修寺黄門へ罷向、八日之将軍宣下之下行以下之事申談了、雙六有之、次持明院へ罷向、表袴借用之事申之、同心也、次長橋内侍所臺所等へ立寄、次高辻へ罷向、一盞有之、來八日依體笠可借用之由申之、叉念珠之道明寺菩提子等約束之間遣之、次甘露寺へ罷向、來八日に裾之事申之、
(書き下し文)
勧修寺黄門(勧修寺晴右)来たる。
富田の武家(足利義栄)の将軍宣下は来たる八日たるべし。
上卿の事内々にこれを示さる。
尚奉行より触れらるべきの由これ有り。
烏丸(烏丸光康宅)へ罷り向かう。見参。
来たる八日袍借用の事これを申す。
内々に同心なり。
次いで勧修寺黄門(勧修寺晴右)へ罷り向かう。
八日の将軍宣下の下行以下の事申し談じおわんぬ。
雙六これ有り。
次いで持明院(持明院基孝宅)へ罷り向かう。
表袴借用の事これを申す。
同心なり。
次いで長橋内侍所台所等へ立ち寄る。
次いで高辻(高辻長雅宅)へ罷り向かう。
一盞これ有り。
来たる八日の体に依り笠を借用すべしの由これを申す。
また、念珠の道明寺菩提子等へ約束の間これを遣す。
次いで甘露寺(甘露寺経元宅)へ罷り向かう。
来たる八日へ裾の事これを申す。
※袍は束帯・衣冠の時に着る上着
※下行(げぎょう)は下賜する物品。
※一盞は(いっさん)は一杯の盃。
(備考)
他にも同書は、将軍宣下の日までの準備を克明に記している。
なお、勧修寺晴秀(黄門)は昨永禄10年(1567)12月に諱を晴右と改めている。
2月8日
信長、越後の上杉氏の重臣直江景綱(大和守)へ無音を詫び、進物を贈る旨の書状を発給。『上杉家文書』一 (永禄十一)二月八日付織田信長書状案
態以使者申達候、其以来者、路次無自由故無音、本意之外候、然者雖無見立候、糸毛之腹巻・同毛之甲進覧、誠御音信計ニ候、猶重而可申宣由、可得御意候、恐々謹言、
二月八日 尾張守信長
謹上 直江大和守殿
(書き下し文)
わざと使者を以て申し達し候。
それ以来は、路次自由無き故に無音、本意のほかに候。
然らば見立て無く候といえども、糸毛の腹巻・同じく毛の兜を進覧。
誠に御音信ばかりに候。
なお重ねて申し述ぶべきの由、御意を得るべく候。恐々謹言(以下略)
(備考)
織田信長が「尾張守」を名乗る数少ない文書の一つである。
「尾張守」が最初に見られるのは『多聞院日記』の永禄九年(1566)七月十七日条から。
上洛に向けての軍事行動を活発化させた永禄11年(1568)5月から、信長は「弾正忠」を称しはじめる。
なお、この文書は署名のみあり、花押や印判、脇付はないようである。
同日
足利義栄の将軍宣下の儀が執り行われる。『言継卿記』永禄十一年二月八日条など
今夜将軍宣下、上卿出立要脚、於傳奏三百疋請取之、澤路備前入道遣之、同請取後日遣之、
「請取申上卿出立要脚事、
合三貫文者
右所請取申如件、
永禄十一年十二月八日 重延 判
勧修寺殿御雑掌」
戌刻高倉へ罷向着束帯、衣文入道に申之、相公沈酔云云、裾石帯玉、布衣之白袴同刀太刀持、借用之、自彼宅参内、供布衣大澤右兵衛大夫、烏帽子着澤路隼人佑、太刀持之、小川與七郎、其外松夜叉丸、小雑色二本、白丁笠持、小物兩人等也、次先予着陣、於宣仁門外官人に刻限間之、午刻と答、不審、次入宣仁門着奥座、四度揖如例、大納言座之程思祝儀、次着端座、四度之揖同前、縿裾揚、次檜扇取出沓直之、次召官人令敷軾、次頭中将吉書持來、置笏取之、付板、次被覧之、如常氣色、次頭中将退入、次以官人召辨、其詞右少辨宣教來、乍持笏以左手付板吉書遣之、辨被覧之、氣色、次如元調之退入、次令撤軾、次起座退入、則又入宣仁門着奥座、中納言座、揖縿裾、重通朝臣來仰云、左馬頭源朝臣義栄宣爲征夷大将軍、兼又可聽着禁色、予微頌、次起座着端座、揖縿裾、次召官人令敷軾、次官人沓直之、次以官人召辨、同前、次宣教來、仰云、左馬頭ヽヽヽ、同前、次辨退入、次以官人召外記、外記召せ、大外記師廉朝臣來、仰云、左馬頭ヽヽヽ可聽着禁色、揖頌、次退入、次召官人令敷軾、次揖出宣仁門、四度之揖悉以如常、次於男末御祝有之、被参之輩中山前大納言、万里小路大納言、予、勧修寺中納言、源中納言、水無瀬宰相、右大辨宰相、重通朝臣、爲仲朝臣、晴豊、宣教、橘以繼等也、入麺有之、次各退出、今夜御警固伊勢守内衆百人計参、畠山安枕斎被見物、御酒被下之云々、見物之貴賤男女驚目者也、
(備考)
他にも同日条で、言継が諏訪右兵衛大夫と対面し、足利義栄や朝倉義景、飯川信堅らの書状を受け取ったことや、高倉永相の息千菊丸元服の様子も記されている。
早旦山形右衛門大夫來、従越州昨夕爲武家御使諏方神右兵衛尉上洛、忍之間可來之由申候間、則山形所へ罷向、則神右兵衛對顔、當月末早々可罷下之由有之、種々被仰下之様體有之、御内書以下如此、
「就元服之儀、至當國下向候者可悦入候、爲其差上俊郷、於巨細者申含候、猶義景可演説之状如件、
正月廿三日 御判
山科殿」
「就御元服之儀、至當國可有下向之由被成御内書候、於御下國者尤可被悦思食之旨、猶相心得可申入之由被仰出候、委細諏訪甚兵衛尉可被申候條不能詳候、恐々謹言、
正月廿三日 義景判 朝倉左衛門督
山科殿」
「就御元服之儀被成御内書候、仍義景御副状候、無異儀御下向尤可爲珍重候、爲其被差上俊郷候條委細可被申候、此等之趣可然様御取成所仰候、恐々謹言、
正月廿六日 信堅 飯川山城守
山科殿」
「改年吉兆彌可爲御満足候、仍御元服之事、來月可有御座候、就其御装束同御道具等尋申爲可被仰付、被差上同名神兵衛尉候、様體可被仰聞候、将又御下向之儀内々如申談候、奉期候、被成御内書以義景一札被申入候條、早々御下國可然存候、巨細者申含神兵候間、定可申入候、此旨宜預御取成候、恐々謹言、
正月廿七日 睛長判 諏方信濃守
澤路殿」
一盞有之、様體懇に被示之、次歸宅了、
従伊勢虎福使横川掃部入道來、對面、就将軍宣下、告使出納右京進御倉與奪云々、下向富田、御昇殿と計申之云々、奏者摂津守役也云々、不参之間伊勢守に被仰出之、幼少之間同名可召進之、告使束帯持笏、乍立御昇殿と申之、奏者可畏歟否之由被尋之、於庭上者立か禮也、可爲色立之由返答了、
2月12日
公家の山科言継、足利義秋の元服式に関する件で幕府奉公衆や朝倉義景らに返書を認める。『言継卿記』永禄十一年二月十二日条より
山形右衛門大夫所へ罷向、諏方神右兵衛尉に對顔、條々示合之、一盞有之、御内書以下御返事共手日記等渡之、
「御内書謹致拜見候、就御元服之儀可罷下之由承了、宜然之様可預御取合候、尚委曲神右兵衛尉可被申入候也、恐惶謹言、
二月十日 言繼
飯川山城守殿」
「就御元服之儀御内書致拜見候、同芳札委曲承了、宜然之様御取合所仰候、尚々巨細之段諏方神右兵衛尉可有演説候也、恐々謹言、
二月十日 言繼
朝倉左衛門督殿」
「就御元服之儀御内書謹承了、同督殿御副状委曲被見申候、軈罷下可申入候、尚々巨細之段神兵に申含候間、可有演説候、可然之様御取成所仰候、恐々謹言、
二月八日 言繼
飯川山城守殿」
「誠當年之嘉慶自他不可有休期候、抑就御元服之儀、御装束以下之事存分注付進候、同可罷下之由御内書、督殿御副状等承了、委曲神兵へ申渡候、尚以手日記令申候間、以御分別宜然之様御取成所仰候、何も罷下可申入候、謹言、
二月八日 言繼
諏方信濃守殿」
手日記如此、
一、用意之物二千疋、金銀之間歟、
一、自然之儀於有之者妻子可召下事、
一、地行分名字地四ヶ所、其外敷地等御墨付之事、
一、自坂本自一條路次之調、香取に可被仰付事、
一、召具之者七八人又者十餘人歟之事、
陽春院へ罷向、笋刀打亂筥櫛手巾請取之、伏見殿へ持参、持明院に相渡之、次高倉相公へ罷向、小袖一、借用、今日富田へ被下向云々、次長橋局へ罷向、一昨日安二位へ御祭料百疋被遣之、忝之由御返事申入了、次内侍所へ立寄了、晩飡急之葉室へ罷向、供大澤右兵衛大夫、小五郎兩人計也、明日富田へ宣下之御禮に可罷下之儀也、
(書き下し文)
山形右衛門大夫所へ罷り向かう。
諏方神右兵衛尉に対顔。
条々これを示し合わせ、一盞これ有り。
御内書以下御返事ともに手日記等これを渡す。
「御内書謹みて拝見致し候。
御元服の儀につきて、罷り下るべきの由を承りおわんぬ。
宜しく然のよう御取り合い預かるべく候。
なお委曲神右兵衛尉申し入らるべく候なり。恐惶謹言
二月十日 言継
飯川山城守殿(飯川信堅)」
「御元服の儀につきて御内書拝見致し候。
同芳札で委曲承りおわんぬ。
宜しく然のよう御取り合い仰すところに候。
尚々巨細の段、諏方神右兵衛尉演説有るべく候なり。恐々謹言
二月十日 言継
朝倉左衛門督(朝倉義景)殿」
「御元服の儀につきて御内書謹みて承りおわんぬ。
同督(朝倉義景)殿への御副状で委曲被見申し候。
やがて罷り下り申し入るべく候。
尚々巨細の段神兵に申し含め候間、演説有るべく候。
然るべきのよう御取り成し仰すところに候。恐々謹言
二月八日 言継
飯川山城守(飯川信堅)殿」
「誠に当年の嘉慶、自他休み有るべからず期に候。
そもそも御元服の儀につきて、御装束以下の事、存分を注付進せ候。
同じく罷り下るべきの由を、御内書・督殿(朝倉義景)御副状等で承りおわんぬ。
委曲神兵へ申し渡し候。
なお以って手日記で申せしめ候間、御分別を以って宜しく然るのよう、御取り成し仰すところに候。
何れも罷り下り申し入るべく候。謹言
二月八日 言継
諏方信濃守(諏方晴長)殿」
手日記かくの如し。
一、用意の物二千疋(金銀の間か)
一、自然の儀これ有るに於いては、妻子を召し下すべきの事
一、知行分名字地四ヶ所、そのほか敷地等御墨み付きの事
一、坂本より一条路次よりの調え、香取に仰せ付けらるべきの事
一、召し連れの者七・八人または十余人かの事
陽春院へ罷り向かう。
筍刀・打乱箱・櫛・手巾これを受け取る。
伏見殿へ持参。
持明院にこれを相渡す。
次いで高倉相公へ罷り向かう。
小袖(一)借用。
今日富田へ下向せらると云々。
次いで長橋局へ罷り向かう。
一昨日安二位へ御祭料百疋これを遣せらる。
忝きの由を御返事に申し入れおわんぬ。
次いで内侍所へ立ち寄りおわんぬ。
晩飡これを急ぎ葉室(葉室頼房宅)へ罷り向かう。
供は大澤右兵衛大夫(大澤重延)、小五郎両人ばかりなり。
明日富田へ宣下の御礼に罷り下るべきの儀なり。
※一盞(いっさん)は1つのさかずき。1杯の酒を呑むこと。
※名字地(みょうじのち)とは、その家の名字の由来となった土地のこと。伊達氏や三浦氏などが有名だろう。
※笋刀(たこうながたな)=筍刀とは、元服の際に用いる理髪用の小刀。たけのこ形に似ていることから、この名がついたのだろう。
※打亂筥(うちみだりのはこ)=打乱箱とは広蓋のような箱で、もとは櫛笥に添えた手拭い箱であったが、後には化粧道具や所持品なども入れた。
※富田は摂津国富田。足利義栄の在所である。
※晩飡(ばんそん)は夕餉の意。
(備考)
陽春院は足利義輝の乳母か。
2月17日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年二月十七日条
竹下對面、七堂陳取事申候處、可有馳走之由同心了、
2月20日
十市氏の森屋城が陥落。『多聞院日記』永禄十一年二月二十日条
今朝森屋之城十市より取了、首七十計討死之由、申剋之終ニ兵より注進状在之、田中蔵人佐手負死了、幷福作内喜右衛門尉死了、田中源一郎手負了、不可有殊儀と云々、先々秋山知行半分通ハ三人衆ニも依同心如此成下了、珍重々々、
(書き下し文)
今朝森屋の城十市より取りおわんぬ。
首七十ばかり討ち取るの由、申刻の終に兵より注進状これ在り。
田中蔵人佐手負いし死におわんぬ。
並びに福住内喜右衛門尉死におわんぬ。
田中源一郎も手負いおわんぬ。
殊有るべからざる儀と云々。
先々秋山知行半分通りは三人衆にも同心によりかくの如く成し下しおわんぬ。珍重珍重。
(備考)
大和国の森屋城は大和川沿いにあるところで、もとは秋山氏の拠点であった。
この時期は十市遠勝が支配していた。
十市遠勝が三好三人衆と手を結ぶ一方、秋山直国は松永久秀と結び、このたび攻勢に転じてこれを奪還したようだ。
2月
信長、藤八へ安堵状を発給。『中村林一氏所蔵文書』永禄十一年二月日付織田信長朱印状
吾分名田、如前々不可(「有」脱カ)相違之状如件、
永禄十一
二月日 (信長朱印)
藤八
(書き下し文)
吾分(あがぶん)の名田、前々の如く相違有るべからざるの状くだんの如し。(以下略)
(備考)
藤八が誰なのか、どこの領地なのか全くの不明。
本能寺の変の際に討死した信長の中間衆に藤八の名がみえるが『信長公記』、それだけでは何とも言えない。
2月
織田信長、伊勢へ出陣。(出展不明)
2月
三男の三七を神戸友盛の養嗣子とし、弟の織田信包を長野家へ、さらに一族の織田(津田)掃部助一安を安濃津の守将として送り込む。
(備考)
・津田一安
津田一安(掃部助)は織田一族ではあるが、遠い親戚のような扱いである。
信長とどの程度縁遠なのか詳細は不明。
『張州府志』には、日置村の住人織田丹波守の子とある。
「織田丹波守」の名は『言継卿記』や谷宗牧の『東国紀行』に見える。
身分や状況からして一安本人の可能性を感じるが、断定はできない。
また、『織田系図』の中に寛貞の子「掃部助忠寛」の名がある。
事蹟は載っていないので、同一人物なのかは不明。
のちに一安は、北畠具豊(織田信雄)の奉行人として織田家の南伊勢や大湊支配に大きく貢献することになる。
・長野家
長野具藤は北畠具教の次男として生まれ、長野藤定の養嗣子となる。
永禄5年(1562)5月、藤定の死去により家督を継ぐ『勢州軍記』。
六角氏の陣営に与した関氏と三重郡塩浜で戦い、敗北したこともあった『勢州軍記』。
このたびの織田信長の侵攻に際し、一族の細野藤敦は徹底抗戦の姿勢を取り信長と戦うが、その弟の分部光嘉らは降る。
長野家中は、具藤を実家へ逐い、信長の弟である信包を当主として迎え入れた。
そこで故長野藤定の娘を娶り、名を長野信良と改めた『勢州軍記』。
クーデターに近い形での追放劇だったのかもしれないが、南北朝の頃より北畠・長野の両家は長年の宿敵であったため、北畠氏に従属していたとはいえ、長野家中の胸中は穏やかではなかったのかもしれない。
長野氏代々の有力な被官衆は工藤・雲林院・分部・細野・中尾・川北氏らである。
長野氏のもともとの出自が藤原の流れを汲む工藤氏であるため、長野工藤と呼ばれることも多い。
以後、長野信良は、少しずつ被官衆を粛清していき、家中を完全に織田色に染め上げてから名を織田に戻すこととなる。
・神戸家
神戸家は南近江の六角氏に従う関氏の一族で、ほかに国府・鹿伏兎・峯氏などが有力な被官として存在する。
応永22年(1415)の足利義持執政期には、六角・長野・雲林院・関・峯・千草家らが共同して挙兵した北畠満雅と戦っている。『木造記(聞書集本)』など
その後、神戸氏は北畠政郷の子である具盛(楽三)が家督を継ぎ、中勢~北勢にかけて北畠氏が影響力を伸ばした時期もあった。『勢州軍記』巻上
このたびの織田信長の侵攻当時、神戸家の当主は具盛(友盛)であった。
彼は六角氏の臣である蒲生定秀の娘を娶っており、将来的に神戸家の当主の座を関盛信の子に譲り渡す約束があったらしい『勢州軍記』『高野家譜』。
(これは具盛が永禄2年(1559)5月に亡くなった兄利盛の家督を継承していたことが関係しているのかもしれない。)
しかしながら、神戸家が織田に降る際、信長の三男である三七を養嗣子として迎え入れることとなった。
高岡城に拠って頑強に織田氏に抵抗したとされる山路弾正は、『勢州兵乱記』に見える神戸氏の重臣である。
永禄10年(1567)に滝川一益を先陣とする大軍の織田勢を追い払ったとする逸話には疑問が残る。
『伊勢国司御一族家諸侍幷寺社記』という文書には、山路玄蕃允という人物が、山路弾正少弼の弟とあるらしい。
『勢州兵乱記』には山路弾正とともに神戸四百八十人衆の大将の1人としてその名がみえる。
その後、養父神戸具盛と三七は不和となり、元亀2年(1571)正月、信長の命により具盛は隠居させられ、三七が新たな当主となった。『勢州軍記』『神戸録』
この際、大幅な家中粛清が行われ、山路弾正忠は切腹。
その他120人におよぶ臣が追放された。
引き続き神戸家に仕えた者は480人と『高野家譜』には記されている。
元亀二辛未年正月、神戸蔵人友盛公隠居し玉ふ、其子細ハ初神戸家男子なき故、兼而関盛信の子息勝蔵殿を養子にせんと約有しに、引替て三七君を名跡ニ居玉ひ候程に、関も神戸も其趣意有て三七君心よかざる仕方等相聞へける故、信長公憤り、蔵人友盛公年賀を申上ん為安土江参勤有しを留置、国へ帰らしめず、日野蒲生左京太夫秀賢に預らる、則三七君を継目ニ立られ、神戸三七信孝と号す、此節可夕入道に可奉仕よし進メ給へども、年老たりと称じて不奉仕、嫡子五郎右衛門甥の次右衛門を召出されん事を乞ひ、奉仕して使番と成、黄母衣七騎の列と成る、又信孝公は高岡の城を守りし山路弾正に腹切らせ、高岡の城を三七君同母の舎弟小嶋兵部少輔に渡さる、夫によりて神戸の諸士、信長公を恨て信孝公に帰服せす、百弐拾人浪人せし也、残りし侍四百八十人衆と言て信孝公へ仕へ諸事一味せり、其侍ニ者城治郎左衛門・川北喜兵衛・太田丹後・太田監物・矢田部掃部・高野五郎右衛門・佐々木隼人・片岡平兵衛・正田助右衛門等なり、
この『高野家譜』の記述には元亀2年(1571)の話なのに、年賀を申上げんと安土へ参勤など疑問がないわけではない。
この史料は家譜として書かれたものではあるが、他書にない事情も述べているので無視できない。
ここにある高野可夕入道は神戸具盛の三男である。
彼は次男の高島政光とともに分家した。
のち、政光の孫が神戸友盛(具盛)の養子となって神戸外記政房と称し、蒲生氏郷に仕える。
そして後年、神戸政房・良政父子は『勢州四家記』『勢州軍記』を編述している。
3月6日
足利義秋、上杉輝虎(上杉弾正少弼との)へ甲斐武田・相模北条氏と和睦し、上洛を促す旨の書状を発給。『上杉家文書』
(備考)
翻刻は後日に載せるが、本文書の分末尾には「猶義景申すべく候也」としている。
3月8日
足利義秋、朝倉義景生母の光徳院を従二位に任ず。
その御礼として義秋を光徳院の屋敷へ招き終夜まで盛大な酒宴が催される。(出展不明)
3月11日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年三月十一日条より
十市ト三好山城幷篠原弾正ト制帋令取替、則明日十二日兵少筆元見ニ兩三人使衆越由被申了、
3月21日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年三月二十一日条より
西陳へ番替ニ高屋衆三好備中守・遊佐安藝守・大嶋助兵衛・加地六郎兵衛、三鬼鎰助・カヰノ庄助丞・木村宗也以下人數千五百ほと越了、
上洛に際しての根回しと懐柔
3月25日
公家の山科言継、清水太郎左衛門に違乱された山城国宇治郡の木幡率分所の返還を、三好長逸(三好日向守殿)、石成友通(石成主税助殿)、坂本大炊助に要求する。『言継卿記』永禄十一年三月二十五日条
澤路筑後入道來、明日南方へ可罷下、木幡口之率分違亂有之云々、乃書状共調遣之、
「就御料所内蔵寮領率分木幡口役所之儀、御折紙被見候、此儀者至天文十八年於石田立置候、然者今度以御馳走木幡に申付候處、清水太郎左衛門令違亂、於先年之所可取之由申候條於石田申付候、然處只今又新儀之由申掠候段沙汰限候、如有来無別儀様被仰付候者可為祝着候、尚委曲筑後入道可申候、恐恐謹言、
三月廿三日 言繼
三好日向守殿」
「當年御慶珍重候、早々可申候處、御在陣之由候間、于今延引慮外候、仍雖軽微至候、表祝儀計百疋進入候、尚委曲澤路入道可申候、恐々謹言、
三月廿三日 言繼
石成主税助殿」
「就御料所内蔵寮領率分役所之儀、種々以御馳走被相調、祝着至候、以面御禮可申心中候處、于今延引背本意候、仍木幡口之儀、清水太郎左衛門尉及度々違亂、失面目候、於此儀者是非共に彌以御馳走、向州無別儀様可被仰調候、千萬頼入候、謹言、
三月廿三日 言繼
坂本大炊助殿」
(書き下し文)
澤路筑後入道来たる。
明日南方へ罷り下るべく、木幡口の率分違乱これ有り云々。
則ち書状ともにこれを調え遣す。
「御料所内蔵寮領率分木幡口役所の儀につきて、御折紙を被見し候。
この儀は天文十八年(1549)に至りて石田を於いて立て置き候。
然らばこの度御馳走を以て木幡に申し付け候ところ、清水太郎左衛門違乱せしめ、先年の所に於いて取るべきの由を申し候条、石田に於いて申し付け候。
然るところ、ただ今また新儀の由を掠め申し候段、沙汰の限りに候。
有り来たりの如く別儀無きの様、仰せ付けられ候はば祝着たるべく候。
なお委曲筑後入道申すべく候。恐恐謹言
三月二十三日 言継
三好日向守(三好長逸)殿」
「当年の御慶珍重に候。
早々に申すべきに候ところ、御在陣の由に候間、今に延引、慮外し候。
仍って軽微の至りに候といえども、祝儀を表すばかり百疋を進せ入り候。
なお委曲は澤路入道申すべく候。恐々謹言
三月二十三日 言継
石成主税助(石成友通)殿」
「御料所内蔵寮領率分役所の儀につきて、種々御馳走を以て相調えられ、祝着の至りに候。
面を以て御礼申すべき心中に候ところ、今に延引、本意に背き候。
仍って木幡口の儀、清水太郎左衛門尉たびたび違乱に及び、面目を失い候。
この儀に於いては、是非共にいよいよ御馳走を以って、向州(三好長逸)に別儀無きのよう、仰せ調えらるべく候。
千万頼み入り候。謹言
三月二十三日 言継
坂本大炊助殿」
(備考)
このうち、石成友通へ宛てた書状の返書が、同年四月一日付で言継のもとに届いている。『言継卿記』永禄十一年四月五日条
同日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年三月二十五日条より
今晩刁ノ初點ニ氷室城自焼了、寺内悉以開了、一宇モ不焼、無比類仕合也、寺僧衆社頭ニ心懸テ内々少々在之衆一番ニ入了、河州衆・筒衆一人も不入、内々此間申噯故也、珍重々々、上下万人歓喜無類也、朱雀院以下ハシロノ分ハ皆以自焼了、左京大夫令同道、金吾・竹下伴田へ被越了ト云々、定説ハ不知者也、火難必定ノ處、先段立願故歟、併神慮御計迄也、軈而果遂ノ催可在之、日中後大雨下、キヨメノ雨ト見タリ、
(備考)
難読のため読み下しは先送り。
3月30日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年四月一日条より
昨日超昇寺西陳へ礼ニ出了、人數二百五十ほと在之、筒井ヘハ不出と、
3月
越前一乗谷に逗留中の足利義秋、上杉輝虎に対し、武田信玄と北条氏康が輝虎と講和する旨の請文が届いたことを報せ、急ぎ上洛の軍に参加するよう要請する。『上杉家文書』
(備考)
後日追記予定
3月下旬
朝倉義景、南陽寺に足利義秋とその供衆を招き、遊宴と歌会が催される。(出展不明)
(備考)
もろ共に月も忘るな糸桜年の緒長き契りと思はゞ(義秋)
君が代の時にあひあふ糸桜いともかしこきけふのことの葉(義景)
この時の連歌会で具体的に誰が集まったのかは調べていない。
時期的に賦物は糸桜だったのか。
南陽寺は現在も臨済宗相国寺派の寺として存在する。
当時は義景屋形の北東にあった。
応永12年(1405)以後に代々朝倉氏の子女が入寺する尼寺として機能し、多くの史料に登場する。
4月8日
信長、甲賀の土豪たちからの音信を謝し、今後とも昵懇に願う旨の書状を発給。『山中文書』七 (永禄十一)四月八日付織田信長朱印状
先度為使者被差上富野候、殊太刀・馬祝着候、猶和田伊賀守可有演説候、恐々謹言、
卯月八日 信長(朱印)
甲賀
諸侍御中
(書き下し文)
先度は使者として富野を差し上せられ候。
殊に太刀・馬祝着に候。
なお和田伊賀守(和田惟政)演説有るべく候。恐々謹言(以下略)
(備考)
和田惟政は近江甲賀郡和田村の出身である。
その人脈を生かして、甲賀地方の懐柔を行ったのだろう。
足利義輝の執政期にあたる『永禄六年諸役人付』には、御供衆の項に
大舘伊豫守晴忠・一色式部少輔藤長・細川兵部大輔藤孝・上野陸奥守信忠・上野大蔵大輔豪孝・武田刑部大輔信實・佐々木治部大輔信堅といった面々の中に和田伊賀守の名がある。
足利義秋が大和から脱出した際も、惟政は自領にこれを迎え入れている。
4月15日
越前一乗谷に逗留中の足利義秋の元服の儀が執り行われ、名を義昭と改める。
加冠役は朝倉義景。
京都からは前関白二条晴良が招かれた。『言継卿記』『越州軍記』
(備考)
公家の山科言継もこの式典に招かれている。
本年2月12日条の『言継卿記』に記されたものがこの件に関する内容である。
なお、言継も当初は前向きに検討していたものの、結局は参加を見送っている。
なお、この式の日程が予定より少し遅れた4月21日とする説もあるようだが、こちらは出典がわからない。後日確認次第追記する。
同日
三好三人衆方に捕らえられていた朝山日乗が、勅命によって釈放される。『言継卿記』永禄十一年三月二十五日条・『耶蘇通信』
朝山日乗上人去年以来攝州に籠者也、不慮之至也、依勅諚遁之、今日上洛云々、
(書き下し文)
朝山日乗上人、去年以来摂州に籠もるものなり。
不慮の至りなり。
勅諚によりこれを逃る。
今日上洛し云々。
(備考)
朝山日乗は昨永禄10年(1567)に毛利氏と松永久秀を繋ぐ工作をしていたところを捕らえられ、摂津の牢に捕らえられていたようだ。
彼の半生は定かではない。
『朝山系図』によると彼の諱は「善茂」。
後奈良天皇の信任厚く、「日乗上人」の号も後奈良天皇より与えられたとある。
『耶蘇通信』や『太閤記』には、もとは出雲尼子氏の臣で毛利元就を頼り、僧となって上洛。
禁裏と繋がりを持ち、荒廃した御所の修理に貢献があったとされている。
良質な史料でないにせよ、同年中に織田信長が上洛すると、さっそくこれと接点を持ち、内裏-足利義昭・織田信長-毛利元就との間を取り持つ懸け橋となっていたことは間違いないようだ。
なお「日」の名が付くところから、日蓮宗系の僧とされているが、京の妙顕寺に本山を置く法華宗との関係性は不明。
このたび政治的中立の立場を少し越えて、正親町天皇が勅諚を出した理由も不明である。
4月16日
朝山日乗、お礼のために参内。
朝廷に物を献上する。『御湯殿上日記』
(備考)
同日条の『言継卿記』には、言継が日乗の宿を訪れたが、留守であったと記されている。
以下がその記述である。
朝山日乗上人旅宿丹波屋判田入道所云々、錫携之罷向之處、他行云々、申置了、軈使僧正覺坊禮に來、出納右京進重弘相副了、
(書き下し文)
朝山日乗上人の旅宿は丹波屋判田入道所と云々。
錫これを携え罷り向かうのところ、他行と云々。
申し置きおわんぬ。
やがて使僧の正覚坊が礼に来たる。
出納右京進重弘を相添えおわんぬ。
また、同月19日条にも日乗本人が鵝眼銭二十疋を手に言継宅を訪れている。
4月27日
信長、甲賀の佐治為次(美作守)へ知行を与える旨の朱印状を発給。『佐治家乗』
扶助分之事
一、市子庄
一、羽田庄
一、河井跡職
一、馬淵源左衛門跡職
一、楢崎跡職
右分御知行不可有相違者也、仍状如件、
「(追筆)永禄十一」
四月廿七日 織田尾張守
信長(朱印)
佐治美作守殿
(書き下し文)
扶助分の事
一、市子庄
一、羽田庄
一、河井跡職
一、馬淵源左衛門跡職
一、楢崎跡職
右の分、御知行相違有るべからざるものなり。仍って状くだんの如し(以下略)
(備考)
佐治氏は甲賀郡小佐治郷を領する土豪。
南北朝期の康安元年(1361)5月、南近江の守護大名である六角氏頼は、小佐路(治)郷地頭職のうち、辻孫太郎跡地を料所として佐路弾正忠に預け置いた『蒲生文書』。
甲賀21家中北山9家の1つといわれる佐治氏は、もと小佐治氏あるいは大原小佐治氏と名乗り、六角氏や足利幕府にのために働いている。
この朱印状は、佐治秀寿氏が編した『佐治家乗』に東京市の佐治仲太郎氏所蔵の文書を写真版にして収めてある。
文中にある「市子庄」は蒲生郡蒲生町にかつてあった荘園。
文書によっては「市子本庄」としているものもあるが、同義のようである。『角川日本地名大辞典』25滋賀県
「羽田庄(荘)」は八日市市に存在し、戦国期には日吉社と広橋大納言家の所領があった。
ところが「文亀二壬戌年九月十六日」と記された東大寺領古絵図と大安寺古絵図によれば、羽田荘は興福寺領内官務殿惣領所とあり、興福寺政所があったようだ。『角川日本地名大辞典』25滋賀県
河井跡職(あとしき)は蒲生郡川合(現東近江市)を領していた河井氏の旧領、馬淵源左衛門跡職は蒲生郡馬淵町(現近江八幡市)を領していた馬渕源左衛門、楢崎跡職は犬上郡多賀町にあった楢崎である。
このうち、馬淵と楢崎の一族は、六角氏の重臣を勤めている。
詳しいことはわかりかねるが、信長はすでに六角氏と対決することを念頭に戦略を練っていたのかもしれない。
同日
信長、野洲郡の永原重康(越前守)へ3ヶ条からなる条書を発給。『教王護国寺文書』永禄十一年四月二十七日付織田信長条書
一、深重入魂之上、向後不可有表裏・抜公事之事、
一、知行方之儀、去年遣候如書付之、不可有相違事、
一、御進退之儀、向後見放申間敷事、
永禄十一年四月廿七日 織田尾張守
信長(花押)
永原越前守殿
(書き下し文)
一、深重に入魂の上、向後は表裏・抜け公事これ有るべからざる事。
一、知行方の儀、去年遣わし候書付の如く、相違有るべからざる事。
一、御進退の儀、向後見放し申す間敷き事。(以下略)
語訳)①深重に親しい関係になった上は、今後は命令に背いたり、欺いたりしないこと。②知行は去年遣わした目録の通りで相違ないこと。③そなたの身の上のことは、今後も見放さないことをここに約束する。
(備考)
永原氏は近江野洲郡永原を本拠とする。
重康(越前守)はその分家筋である。
両細川の乱時代から六角義賢の執政期にかけて、永原本家は六角氏の奉行人として活躍し、室町将軍から御判(花押)の御内書を与えられるほどの存在であった。『保坂潤治氏所蔵文書』『古簡雑纂』五 『筆陳』一・二
文中にある「去年遣わした書付」についてはわからない。
同年9月に足利義昭を奉じる織田信長が六角氏を攻撃した際、重康は約束の通りに主家を見限り、後藤氏らとともにこれに味方している『言継卿記』。
なお、『信長公記』には越前守も重康も見当たらず、永原筑前守の名が登場する。
ほかの文書では重康を筑前守としているものが見当たらないが、彼のことではないかと考える。
4月29日
山科七郷衆と醍醐衆が数日争い、この日に戦いが終わる。『言継卿記』永禄十一年四月二十九日条
山科七郷與醍醐數日取合云々、今日醍醐衆敗軍云々、十七八人討死、手負六七十人有之云々、生捕數多放之云々、山科郷衆も六七十人討死云々、手負廿人計有之云々、
(書き下し文)
山科七郷と醍醐数日取り合い云々。
今日醍醐衆(三千人ばかり)敗軍し云々。
十七~八人討死。
手負い六七十人これ有ると云々。
生け捕りは数多これを放つと云々。
山科郷衆も六七十人討死云々。
手負い二十人ばかりこれ有り云々。
(備考)
宇治郡醍醐村には真言宗醍醐派の総本山である醍醐寺がある。
山科盆地南東部に位置し、山科言継の名字地の隣にあたる。
醍醐寺三宝院は幕府との繋がりが強く、山科七郷にも強い影響力を持っていた。
山科郷民と醍醐郷民の争いは貞和二年(1346)にはすでに起きおり、以後も争いの絶えない地域であった。
5月8日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年五月八日条より
松浦方使衆ニ付、野田与理祢宜可遣、種々申分了、則松肥へ卅疋、使衆三人へ十疋ツヽ遣之、
(備考)
和泉国は代々、細川和泉上守護家が支配し、細川宗家を支える上で重要な役割を果たしていた。
しかし、相次ぐ戦乱により当主の元常・晴貞は力を落とし、代わって重臣の松浦氏が三好氏の後援を受けて実力をつけていった。
「松肥」とあるのは松浦肥前守のことで、松浦光あるいは松浦まんみつと呼ばれる人物である。
彼は十河一存の子として生まれ、松浦盛(周防守)の養嗣子となった。
十河一存、三好実休、三好義興さらには三好長慶が相次いで亡くなると、三好家中は大きな内紛に見舞われる。
この永禄11年(1568)時点では、松浦肥前守は実の兄弟である三好義継に味方しており、ともに足利義昭を支える松永久秀や織田信長と陣営をひとつにしていたと考えられるが、必ずしも松浦分国内の政情は安定していたわけではなかった。
なお、この時期の『多聞院日記』には「今井」の名がたびたび見えるが、今井宗及と松浦肥前守は昵懇の関係であったようだ。
5月17日
足利義昭、朝倉屋形を訪問。『朝倉亭御成記』
(備考)
義昭の御成りは午刻で、御剣を上野陸奥守が持ち、騎馬衆六人、御走衆六人、同朋・御小人百余人が近臣二十人ほどとともに一刻ばかり前に出立し、義昭は二条晴良に先導されて出御した。
この時の警固役が氏家・真柄・北村・千秋氏のようだ。
5月19日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年五月二十二日条より
去十九日、山城へ津田ヨリ篠原幷釣閑齋一万五千ほとにて打廻在之、狛・□八妻モ不仕居、木津噯も不調、無殊儀、今日西京表へ打越陳取了、奈良中ヘハ人數不入、
(備考)
津田に関しては本記事永禄11年(1568)1月1日項を参照のこと。
篠原と三好宗渭(釣閑斎)はともに足利義栄を支える有力武将で、この後織田信長や足利義昭と激しく争う人物である。
噯(あつかい)は和睦のことで、それが調わなかったのだろう。
5月24日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年五月二十四日条より
釣閑齋同道ニテ篠原右京進社参了、自是八幡へ被参了、
5月25日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年五月二十五日条より
篠原幷釣閑筒井へ召請、成身院へ被来、及晩被下了、雨不下、
5月29日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年五月二十九日条より
篠・釣河州へ引退了、少々人數残了、ナラ中家陳ヲ取了、言悟々々、
6月2日
三好長逸が上洛。『言継卿記』永禄十一年六月二日条
同日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年六月二日条より
喜多院家ノ北ノ方石切ノ町ニ、筒井ヨリ城拵了、ヤクラ屏一圓ナラ中へ申懸、人夫以下直カケラレ了、先代未聞之事、珍事ヽヽ、
(書き下し文)
喜多院家の北の方石切の町に、筒井より城拵えおわんぬ。
やぐら・塀一円を奈良中へ申し懸け、人夫以下直しかけられおわんぬ。
前代未聞の事。
珍事珍事。
(備考)
河内国河内郡の生駒山の麓に石切の町(現東大阪市)がある。
石切劔箭神社が有名。
6月6日
石成友通や南方衆らが上洛。『言継卿記』永禄十一年六月六日条
石成主税助上洛云々、其外南方衆悉上洛云々、何事可出來乎、不知其故也、
6月20日
足利義昭、紀伊粉河寺の惣分沙汰所に対し、畠山昭高と相談し、全山挙げて味方するように命じる旨の御内書を発給。『粉河寺文書』
(備考)
この御内書について一色藤長・細川藤孝が連署で副状を発給している。
翻刻未確認。
6月24日
甲賀の住人の山中蔵人、三好三人衆方として河内三屋に出陣。
辰の刻に松永久通(松永右衛門佐)がこれを攻め破る。
山中蔵人討死。『言継卿記』『多聞院日記』
(備考)
『多聞院日記』永禄十一年六月二十六日条
去廿三日、於津國表三人衆へへ甲賀衆三百計出テ討果了ト、
※津国は摂津国の古称
以下は同年6月23~26日までの『言継卿記』の記述を抜粋したものである。
『言継卿記』永禄十一年六月二十三日条
木幡口關之事、江州甲賀之山中蔵人に宇治郡十一ヶ郷自南方遣之間、可押領之由申、一昨日以人數雖打立、澤路筑後入道不承引于今堪忍之由、昨日注進之間、則三好日向守旅宿へ、以澤路隼人佑書状遣之、
「就木幡口役所之儀、先日對澤路入道、石主御兩所無別儀御折紙調給候處、夜前山中蔵人如此兩三人折紙相付、以人數令違亂候條、重而對蔵人御折紙調給候者、尤可為祝着候、尚可参申候、委曲澤路隼人佑可申入候、恐々謹言、
六月廿二日 言繼
三好日向守殿」
(書き下し文)
木幡口関の事、江州甲賀の山中蔵人に宇治郡十一ヶ郷南方よりこれを遣すの間、押領すべきの由を申す。
一昨日人数を以て打ち立つといえども、澤路筑後入道承引せず、今に堪忍の由、昨日注進の間、則ち三好日向守(三好長逸)の旅宿へ、澤路隼人佑を以て書状これを遣す。
「木幡口役所の儀につきて、先日澤路入道に対し、石主御両所別儀無く御折紙を調い給い候ところ、夜前に山中蔵人かくの如き両三人へ折紙を相付け、人数を以て違乱せしめ候条、重ねて蔵人に対し御折紙調え給い候はば、もっとも祝着たるべく候。
なお参り申すべく候。
委曲澤路隼人佑申し入るべく候。恐々謹言
六月二十二日 言継
三好日向守殿」
『言継卿記』永禄十一年六月二十六日条
山中蔵人廿三日和州へ陣立、河州三屋に陣取、廿四日辰刻松永右衛門佐自身三百計、搦手面は七百計、以上千計にて取懸、山中以下悉討捕云々、五十計逃云々、松尾之邊へ來、具足二両有之、腰刀以下悉捨之云々、
(書き下し文)
山中蔵人二十三日和州へ陣立つ。
河州三屋に陣取る。(三百五十人ばかりこれ有ると云々)
二十四日辰刻に松永右衛門佐(松永久通)自身三百計、搦手面は七百ばかり、以上千ばかりにて取り懸かり、山中以下を悉く討ち取り云々。
五十ばかりは逃げ云々。
松尾の辺へ来、具足二両これ有り。
腰刀以下は悉くこれを捨て云々。
6月25日
信長、上杉輝虎側近の直江景綱(大和守殿)に甲斐武田氏との和睦について書状を発給。『歴代古案』一 (永禄十一)六月二十五日付織田信長書状写
去比種々御懇慮不知所謝候、仍自甲州可有和親之旨、度々被申越候、雖然于今無入眼候、随而越・甲御間之儀、和談雖申噯度候、貴辺依難測令遠慮候、併賢意次第可致馳走事候、後御返事様子承届、自是可申入候、委曲佐々一兵衛可申候、恐々謹言、
六月廿五日 織田尾張守
信長
直江大和守殿
(書き下し文)
去る頃、種々の御懇慮謝すところを知らず候。
仍って甲州(武田信玄)より和親有るべきの旨、たびたび申し越され候。
然りといえども、今に入眼無く候。
従って越・甲御間の儀、和談を申し扱いたく候といえども、貴辺測り難きにより遠慮せしめ候。
しかし賢意次第で馳走致すべき事にて候。
後に御返事の様子を承り届け、これより申し入るべく候。
委曲佐々一兵衛長穐申すべく候。恐々謹言(以下略)
語訳)過日からいろいろと御懇ろな御心遣いをしてくださり、お礼の申しようもありません。さて、甲州の武田信玄から、和親(講和の仲介を)したい旨をたびたび申し入れてきました。しかしながら、貴方の御心中をお察しして、まだ返答できずにいます。もし、あなたがそのおつもりでしたら、私が然るべきように取り計らい、信玄にお伝えしましょう。委細は佐々長穐が申し述べます。
(備考)
写のため花押がない。
佐々長穐(さっさながあき)は永禄年間から天正にかけて、上杉氏との交渉を担当した人物である。
佐々成政との関係は不明。
諱は長秋、通称名は権左衛門尉と記されたものもある。
彼が上杉氏と関わった文書の初見は永禄7年(1564)で、信長が直江景綱へ書状を発した際に副状を発給している。『歴代古案』永禄七年九月九日付
北陸方面の外交経験を買われてなのか、のちに長穐は簗田広正や柴田勝家の与力として織田家を陰から支えた。
なお、上杉・武田両家の和平をもっとも実現させたがっていたのは、足利義昭であることは言うまでもないだろう。
6月26日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年七月二十六日条
一、去廿六日、珎藏院・吉祥院學侶使莭トシテ河州へ被越了、烏芋峯一向衆導場可有興行之儀付先段閇門、三好山城守依無別儀、于今不相立之間、 相了、幷寺門領押領之届彼是爲札入魂也、
一、廿七日入夜十兵平城へ被入移了、近日秋山可働之由沙汰之間此通歟、
6月27日
[参考] 『言継卿記』永禄十一年六月二十七日条
近衛殿近日雑説、三好日向守以下取懸可爲御生害之由風聞、仍今日爲御見舞参、公家衆以下悉被参云々、御見参、御盃賜之、坊城、祥壽院同参、昨日日向守、石成主税助参、一向不存之由以起請文申入云々、
同日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年六月二十八日条より
昨日天満山ノ城開け了、氷室幷マメ山へ人數入故歟、
6月29日
細川藤賢(典厩藤賢)の籠もる信貴山城が陥落。
石山本願寺(大坂院家)の調停により、この日城を三好康長(三好山城守)に明け渡す。『多聞院日記』『細川両家記』
成身院講問へ出了、講師鏡禅房、問ヽ延観ヽ、題不顯論宗、夕部爲因明講出仕、瓦屋へ成身院鈴被持被出、知足屋へ妙徳院引茶被持被出、水團にて御酒申了、雨下了、信貴城落了、
『多聞院日記』永禄十一年六月二十九日条
松永方信貴城、典厩藤賢御籠城候條、高屋より三好山城守調儀にて取巻、通路無之して、大坂院家より噯にて退城也、大坂へ送り被申候也、六月廿九日城高屋衆へ請取也、
『細川両家記』
(書き下し文)
松永方の信貴城、典厩藤賢(細川藤賢)御籠城に候条、高屋より三好山城守(三好康長)調儀にて取り巻き、通路これ無くして、大坂院家(石山本願寺)より扱いにて退城なり。
大坂へ送り申され候なり。
六月二十九日に城、高屋衆へ請け取りなり。
(備考)
細川本家(京兆家)の分家に細川典厩家がある。
京兆は左京職・右京職の唐名で、左京大夫・右京大夫を名乗る家の棟梁はこう呼ばれる。
同じように、典厩は左馬頭・右馬頭の唐名であり、この時代にそれを名乗る家の棟梁はこう呼ばれる。
細川藤賢はその典厩家の当主細川尹賢の子である。
兄の細川氏綱が細川高国の養子として家を出たため、典厩家当主となった。
この時期の細川藤賢は足利義昭を奉じる三好義継や松永久秀と行動をともにしているが、旗色は必ずしも良いわけではなかった。
(年次不明)6月
信長、近江栗太郡の芦浦観音寺に判物を発給。『蘆浦観音寺文書』(年次不詳)六月日付織田信長判物
あしき三郷欠所方幷給人はつれの事、糾明□□□年貢等可納所候、誰々違乱有間敷候、かしく
六月日 信長(花押)
(備考)
芦浦観音寺は栗太郡芦浦(現草津市)にあり、平安時代末期、天台宗の末寺として建立された。
琵琶湖上の水運管理権の一部を握っていた(志那渡船の支配権)ことから、信長が折衝してきたのかもしれない。
天正8年(1580)9月の『観音寺文書』の「近江蘆浦観音寺領指出目録」によれば、その寺領は近辺の欲賀・杉江・山賀・駒井・長束・出庭・(播カ)持磨田の各郷内に散在していたようだ。
この文書は、信長の花押から永禄9年(1566)~同11年(1568)のものと比定されている。
芦浦三郷の欠所方(没収地)と主から給地を与えられていない者を調査した上で、これを観音寺に与え、年貢などを納めるようにさせる。何人も違乱してはならないとの文意であろう。
未だ信長の影響力が及ばない時期であるが、可能性がもっとも高いのは永禄11年(1568)だろうか。
7月1日
[参考] 『言継卿記』永禄十一年七月一日条
早朝勧修寺内日下久右兵衛曲事有之生害、三好日向以下衆沙汰之、
7月5日
六角義治、黒川家からの書状を披見し、返書を認める。『黒川文書』
同名与次兵無出陣理之趣、対三新左両三人幷年寄衆折紙加披見候、其方之物言申披通、非偽候旨、得其心候、雖然既信長令上落候、火急至于此表可及行之由注進候、国家案否此刻候、在所之儀留守被申付出陣肝要候、只今□□越通迄候へハ、事不行様分別候、委曲与次兵被申聞候、猶三雲可申候、謹言、
七月五日 義治(花押)
黒川蔵人殿
黒川修理進殿
黒川甚右衛門尉殿
(書き下し文)
同名与次兵出陣無きことわりの趣き、三新左(三雲成持)に対し両三人ならびに年寄衆、折紙に披見を加え候。
その方の物言い・申し開きの通り、偽らざる候旨、その心を得候。
然れども既に信長上洛せしめ候。
火急この表に至り、てだてに及ぶべきの由の注進に候。
国家安否この刻みに候。
在所の儀、留守を申し付けられて出陣肝要に候。
「只今□□越通迄候へば、事不行様分別候、 (ここ分かりません)」
委曲与次兵申し聞かされ候。
なお三雲申すべく候。謹言(以下略)
(備考)
三雲新左衛門は三雲成持だろう。
年寄衆は老臣や家老衆の意で記されることが多い。
この信長進発の緊迫感が伝わる翻刻は『戦国遺文 佐々木六角氏編』に所収されている。
7月10日
公家の山科言継、自身の被官である早瀬彦二郎の遺領が不当に買得されたことについて、三好長逸(三好日向守殿)に伝えるも、行き違いが生ず。『言継卿記』永禄十一年七月十日条
就早瀬扶持之地之儀、三好日向守所へ調遣之、澤路隼人佑可持罷向之由申遣了、文言如此、
「先度以書状委申候處、不能御報候間重令啓候、拙者被官人早瀬民部丞去々年死去仕候、其子彦二郎去年叉於田舎罷過候、然者彼跡斷絶之事候間、扶持之地爲此方申付候處、玉井與申候者令買得之由申、點札之竹拔之切折、今日遣使者候處、尚々狼藉緩怠、沙汰之限候、其後以伊曾與右衛門尉申候間、様體委申分候、然者貴殿へ掠申預御折紙候間、立毛之儀者不及是非候了、彼玉井、自幼少之時早瀬被官分候、其後弟子に罷成、淵底之儀乍存知如此之儀、條々曲事候、總別貴殿諸事頼入存候事候に、不預御尋之條無曲次第候、雖聊之儀我等風情理不盡之儀可申付候哉、扶持之地私に沽却候段、其法可爲如何候哉、以憲法之儀被仰付候者可満足候、尚々委曲澤路隼人佑可申入候、恐々謹言、
七月十日 言繼
三好日向守殿」
(書き下し文)
早瀬扶持の地の儀に就きて、三好日向守(三好長逸)所へ(「書状」脱カ)これを調え遣す。
澤路隼人佑が罷り向かい持つべしの由を申し遣わしおわんぬ。
文言かくの如し。
「先度は書状を以って委ね申し候ところ、御報能わず候間重ねて啓せしめ候。
拙者(山科言継)の被官人早瀬民部丞が去々年死去仕り候。
その子彦二郎も去年また田舎に於いて罷り過ぎ候。
然らば、かの跡断絶の事に候間、扶持の地此方として申し付け候のところ、玉井と申し候ものが買得せしむるの由を申す。
点札の竹これを抜き切り折り、今日使者を遣わし候ところ、尚々狼藉・緩怠、沙汰の限りに候。
その後伊曽与右衛門尉を以って申し候間、様体を委ね申分に候。
然らば貴殿へ掠め申す御折紙を預かり候間、立毛の儀は是非に及ばず候おわんぬ。
かの玉井、幼少の時より早瀬の被官分に候。
その後弟子に罷り成り、淵底の儀を存じながらかくの如きの儀、条々曲事に候。
総別は貴殿に諸事を頼み入り存じ候事候に、御尋ね預らずの条、曲がり無きの次第に候。
いささかの儀といえども、我ら風情が理不尽の儀を申し付くるべきに候や。
扶持の地は私に沽却し候段、その法如何たるべきに候や。
憲法の儀を以って仰せ付けられ候はば満足すべく候。
尚々委曲は澤路隼人佑申し入るべく候。恐々謹言。
七月十日 言継
三好日向守殿」
※点札(てんさつ)は土地や農作物を差し押さえる旨を記した札のこと。点定(てんじょう)。田札(でんさつ)。
※淵底(えんてい)は物事の奥深いところ。深く。詳しく。語源は淵の底。深い水の底から。
今回の文脈では早瀬と旧知の中でありながら、玉井がこのような暴挙に出たことを指しているのだろう。
(備考)
この件に関する続報が8月24日条にある。
本記事の主旨とは異なるので、翻刻はタブ内に収めることにした。
橋本伊賀守爲小林入道使両度被来、大原竹座人之事、書状可調與之由被申候間則調遣之、
「又申候、被官人早瀬に扶持之地、玉井違亂之事、是又無別儀御折紙給候様、御取成所仰候、
岩崎越後守留申候大原座人竹之事、京座人訴訟申候由、驚存候、又岩崎澤路入道に相尋候處、本所之儀入候間敷候、澤路進退之様申候由、言語道斷曲事候、最前貴殿以御馳走補任遣候上者、聊以別儀有間敷候、總別在々所々悉以古今當家進退之事候間、如此間被申付候様、能々向州へ御入魂千萬所仰候、尚可参申候、恐々謹言、
八月廿四日 言繼
ト隱軒 床下 小林民部少輔入道之事也、」
澤路隼人佑所へ、畠之儀に向州方へ之書状調遣之、早早可申調之由申付了、
「先度申候被官人早瀬扶持之地、玉井違亂之事、於様體者度々申候間不能詳候、急度御折紙調給候者可爲本望候、恐々謹言、
八月廿四日 言繼
三好日向守殿」
※「能々向州へ御入魂」
恐らく向州は三好長逸を指すのだろう。
7月12日
足利義昭、越後の上杉輝虎(上杉弾正少弼との)に美濃へ移ることを伝え、馳走を頼む旨の御内書を発給。『上杉家文書』四 (永禄十一)七月十二日付足利義昭御内書
就入洛之儀、信長厳重言上、先至于濃州可被移御座之由申間、近日発足候、義景弥無別儀無二之覚悟候、各申談、馳走偏頼思召候、具智光院可申候也、
七月十二日 (義昭花押)
上杉弾正少弼とのへ
(書き下し文)
入洛の儀に就きて、信長(織田信長)厳重に言上。
まず濃州に至りて御座を移さるべきの由と申す間、近日発足し候。
義景(朝倉義景)いよいよ別儀無く、無二の覚悟に候。
おのおの申し談じ、馳走偏えに頼み思し召しに候。
つぶさに智光院(頼慶)申すべく候なり。(以下略)
(備考)
このあたりの政治的な動きは、京都や奈良の文化人の日記より、当事者が発給する一次史料や軍記物の方が詳しい。
主語がないので分かりにくいが、御座を移さるべきと言上したのが信長。
近日に出立するのが義昭である。
さらに、朝倉義景も無二の覚悟であるから、そなたも馳走せよといった文意である。
この頃
信長、不破光治(河内守)・村井貞勝(民部)・島田秀満(所之助)を足利義昭を迎える使者として越前へ派遣。『信長公記』巻之上(我自刊我本)
7月16日
信長の迎えを受けた足利義昭(公方様)、越前を発ち近江の浅井館に移る。『多聞院日記』永禄十一年七月二十七日条 『信長公記』
(備考)
日付については『信長公記』に誤りがある可能性が高い。
詳細は同月22日の項に記載。
この時期に、義昭が朝倉義景へ「この度、越前を退くこととなった。越前滞在中は、大変世話になった。今後とも、そなたの身上を捨てることはないであろう」との御内書を与えたとしているのは『足利季世記』の記述である。
7月22日
足利義昭(公方様)、浅井館を発ち美濃へ移る。『多聞院日記』永禄十一年七月二十七日条 『信長公記』『細川両家記』など
公方様去十六日ニ越前ヨリ江州浅井館へ御座ヲ被移、同廿ニ日ニ濃州へ御座被移了、尾張上總守御入洛御伴可申之由云々、
『多聞院日記』永禄十一年七月二十七日条
(書き下し文)
公方様(足利義昭)去十六日に越前より江州浅井館へ御座を移され、同二十ニ日に濃州へ御座を移されおわんぬ。
尾張上総守(織田信長)御入洛の御供申すべきの由と云々。
永禄十一年七月廿七日越前へ爲御迎和田伊賀守・不破河内守・村井民部・島田所之助被成進上濃州西庄立正寺尓至而公方様御成末席尓庁鳥目千貫積せられ御太刀・御鎧武具・御馬色々進上由され、其外諸侯之御衆是又御馳走不斜、此上者片時も御入洛可有御急と思食・・・
『信長公記』巻之上(我自刊我本)
(書き下し文)
永禄十一年(1568)七月二十七日越前へ御迎えとして和田伊賀守(和田惟政)・不破河内守(不破光治)・村井民部(村井貞勝)・島田所之助(島田秀満)を進上なさる。
濃州西庄立正寺に至りて、公方様(足利義昭)御成り。
末席に鳥目千貫を積せられ御太刀・御鎧武具・御馬と色々進上由され、その他諸侯の御衆これまた御馳走斜めならず。
この上は、片時も御入洛御急ぎ有るべしと思し召し・・・
※鳥目(ちょうもく)・・・銭の異称。
八月日御所様、一乗院殿を越前敦賀より美濃へ御出、朝倉太郎左衛門御供申候、織田上總介御迎に参、國堺にて請取被申由候、同頃近江北の郡へ被越、浅井方一味して被相談と風聞也、
『細川両家記』
(書き下し文)
八月日御所(足利義昭)様、一乗院殿を越前敦賀より美濃へ御出、朝倉太郎左衛門が御供申し候。
織田上総介御迎えに参る。
国境にて請け取り申さるるの由に候。
同じ頃、近江北の郡へ越され、浅井方一味して相談ぜらると風聞なり。
(備考)
日付については『信長公記』に誤りがある可能性が高い。
時差や噂の伝達精度を考えると『細川両家記』も同程度の正確さだろう。
『信長公記』にある和田惟政は足利義昭の側近。
不破は信長の馬廻。
村井と島田の両名は信長の文官である。
日付は太田牛一の記憶違いの可能性が高い。
ほかにも入京の日付に誤りがあるなど、この時期の公記の日付は信憑性が低い。
7月27日
[参考] 『言継卿記』永禄十一年七月二十七日条
烏丸へ罷向躍之用意、人數以上五十三人云々、笠、金銀四はかり、唐絲、四方に有之、各一様也、白帷、腰巻、まわりの衆綉□繪、織持五六人、中をとりは皆紅梅也、持白帽子、たすきは悉けかちの帯、扇、金銀、繪なし、三躍有之、門之内にて習禮有之、已下刻出門、一品以下公家十三人有之、先伏見殿、次近衛殿、予、冨小路入道令同道先へ参、躍之後各被召御酒賜之、三好日向守以下祗候、庭上以外之群集也、かうかい抜召捕之、事外物忩也、日向守内衆召取了、石成主税助内衆云々、次日向守、次伊勢守、次日野等にて有之、申刻歸宅了、
※唐糸(唐絲=からいと)は中国渡来の糸または織物。
※白帷(しろかたびら)は麻や絹などで織られた白地の単衣。
7月28日
足利義昭、服部同名中に対し、郡内通行の安全をはかるよう御内書を発給。『記録御用所本古文書』
(備考)
翻刻未確認。
服部氏は野洲郡服部(現守山市)の住人か。
7月29日
信長、越後の上杉輝虎(弾正少弼殿)に、畿内や濃尾地方の情勢を伝える旨の書状を発給。『志賀槇太郎氏所蔵文書』二
去六日芳問遂拝悦候、畿内幷此表之様子、其元□(PCで漢字出ず。「匚」はこがまえに「口」くち)風説之由候付而尋承候、御懇情候、然間始末有姿以一書申候、毛頭無越度之条、可被安賢意候、仍条々御入魂之趣、快然之至候、誠爾来疎遠之様候、所存之外候、甲刕与此方間之事、公方様御入洛供奉之儀肯申之条、隣国除其妨、一和之儀申合候、其以来者駿遠両国間、自他契約子細候、依之不寄除為躰候、雖然万貴辺前々相談族無別条候、度々如申旧候、越甲間属無事互被抛意趣、天下之儀、御馳走所希候、将又越中表一揆蜂起、其方御手前候歟、神保父子間、及鉾楯之旨候、如何之躰ニ候哉、彼父子事於信長も無疎略之条、痛入斗候、随而唐糸五斤紅・豹皮一枚進之候、猶重而可申述候、恐々謹言、
七月廿九日 信長(花押)
上杉弾正少弼殿
進覧之候、
(書き下し文)
去六日の芳問、拝悦を遂げ候。
畿内並びにこの表の様子、其元風説かたきの由候につきて尋ね承り候。
御懇情に候。
然る間、始末の有る姿、一書を以て申し候。
毛頭落ち度無きの条、賢意を安んぜらるべく候。
仍って条々御昵懇の趣き、快然の至りに候。
誠に爾来疎遠の様に候。
所存のほかに候。
甲州(武田信玄)と此方(織田信長)間の事、公方様(足利義昭)御入洛の供奉の儀、うけかい申すの条、隣国その妨げを除き、一和の儀申し合わせ候。
それ以来は駿遠両国の間、自他の契約の子細に候。
これにより、寄り除かざる体たらくに候。
然りといえども、よろず貴辺と前々相談の族は、別条無く候。
たびたび申しふり候如く、越(上杉輝虎)甲(武田信玄)の間、無事に属し、互いに意趣を抛れ、天下の儀、御馳走乞い願うところに候。
はたまた、越中表で一揆蜂起、その方御手前に候か。
神保(神保長職・長住)父子の間、鉾楯に及ぶの旨に候。
いかがの体に候や。
かの父子の事、信長に於いても疎略無きの条、痛み入るばかりに候。
従って唐糸五斤(紅)・豹皮一枚これを進せ候。
なお、重ねて申し述ぶべく候。恐々謹言(以下略)
語訳)去六日に届いたあなたの書状を拝見しました。畿内やこちらの様子は、貴国では風説がないようなので、一部始終をくまなくお伝えしましょう。決して誤った情報ではありませんので、ご安心ください。いろいろと御懇ろな御心遣い、感謝いたします。久しく無音無沙汰にしてしまいましたが、本意ではありません。さて、甲斐の武田信玄と私との間ですが、足利義昭様を奉じるという一致点がありますので、隣国(国境)などその妨げを除くために和睦しました。駿河・遠江のことは、武田信玄・徳川家康の間で相互に侵略しない(自他の契約)ことを申し合わせているそうです。これにより、両国の間では大きな動きはみせないでしょう。万事、貴方と前々から親交のある者たちも、大きな変わりは見せないでしょう。たびたび申し入れました通り、上杉殿と武田信玄が互いに遺恨を忘れ、和睦をなさることが天下ために何より重要なことです。また、越中国で一揆が蜂起し、神保父子が争っているらしいですが、あなたの御味方でしょうか。どのような様子なのか気になります。かの父子の事は、信長も疎略に考えてはいないので、心を痛めております。従って、唐糸五斤(紅)・豹皮一枚を上杉殿へ贈ります。(詳細は副状発給者が)重ねて申し述べます。
(備考)
信長の花押の形状と内容から、永禄11年(1568)のものと比定されている。
この文書は写真を見たわけではなく、翻刻のみの確認のため、料紙の質や形状等はわからない。
「其元風説かたきの由候につきて尋ね承り候」など、信長発給の文書にしては他に見ない表現がある。
これまでは直江景綱に宛て、さらに日付よりも上に「謹上 直江大和守殿」としたものが多かったのに、これは直接輝虎に宛て、さらに日付よりも下にしているのが少し気になるところだ。
足利義昭を美濃に招き入れたことが関係しているのだろうか。
なお、文中にある通り、織田-武田間の一和(和睦)は、国境の遠山氏の仲立ちで、信長の養女を信玄子息の武田勝頼に嫁ぐ約束をしたことで成立している。
正確な輿入れの時期は不明。
その間にできた子が、のちの武田信勝である。
8月2日
信長、近江甲賀の土豪たち(甲賀諸侍中)に対し、近江に進発する予定日を告げる旨の書状を発給。『大野与右衛門氏所蔵文書』「近江蒲生郡志」巻十(所収) (永禄十一)八月二日付織田信長判物写
至当国被移御座、入洛之儀被仰出候之処、則信長可供奉旨候、雖然江州依難叶通路、来ル五日先於彼国可進発候、先々任請状旨、信長令入魂、此刻各抽忠節者、可為神妙候、為其差越惟政・公広候、猶両三人可申入候也、
八月二日 信長御判
甲賀諸侍中
(書き下し文)
当国に至りて御座を移され、入洛の儀を仰せ出され候のところ、則ち信長に供奉すべきの旨に候。
然りといえども、江州の通路叶い難きにより、来たる五日、まずかの国に於いて進発すべく候。
先々の請状の旨に任せ、信長に入魂せしめ、このきざみ、各々忠節を抜きんでば、神妙たるべく候。
その為に惟政(和田惟政)・公広(大草公広)を差し越し候。
なお両三人申し入るべく候なり。(以下略)
(備考)
写のため花押や印判はない。
文中の「当国に至りて御座を移され、入洛の儀を仰せになった」とは、言うまでもなく足利義昭のことである。
また、「江州の通路叶い難きにより」は六角氏が敵方であることを意味する。
「請状」は、この文脈では承諾書と解釈して良いだろう。
足利義昭は美濃に移る直前の7月12日、越後の上杉輝虎に馳走せよとの御内書を発給している。『上杉家文書』四
『信長公記』によると、これより信長は近江佐和山に赴き、六角氏へ最後の説得を試みる。
8月7日~13日
信長、足利義昭の上意を受けて近江佐和山に赴き、六角承禎を天下所司代に任じて協力を要請。『信長公記』巻之上(我自刊我本)
同書の「巻之一 (永禄十一戊辰以来織田弾正忠信長公之御在世且記之)」の項より抜粋
八月七日 江州佐和山へ信長被成御出上意之御使尓使者を被相副、佐々木左京太夫承禎御入洛之路次、人質を出し馳走候へ之旨、七ヶ日御逗留候て、様々被仰含、御本意一途之上、天下所司代可被申付雖御堅約候、不能許容不及是非、此上者江州へ可被御行之御造意頻尓て・・・
(書き下し文)
(永禄11年)八月七日 江州佐和山へ信長御出に成られ、上意の御使に使者を相添えらる。
佐々木左京太夫承禎へ御入洛の路次、人質を出し馳走候えの旨を、七ヶ日御逗留候て、様々に仰せ含めらる。
御本意一途の上、天下所司代の御堅約を申し付けられ候といえども、許容能わず、是非に及ばざる。
この上は、江州へ御行(てだて)を成さるべしの御造意頻りにて・・・
(備考)
『浅井三代記』には信長がこの帰路の途中、美濃へ帰る最後の夜を近江柏原の常菩提院で宿泊し、浅井氏の面々と名残の酒宴を開いたとある。
この時、信長の不用心を見た馳走役の遠藤喜右衛門尉(遠藤直経)は小谷山へ取って返し、浅井長政に暗殺を言上するも受け入れられなかったとする一説がある。
事実であれば面白いが、それを裏付けるものは一切なく、信憑性に乏しい。
この文書には他にも整合性が取れない記述がいくつもある。
昭和6年(1931)に発表された谷崎潤一郎の「盲目物語」にもこの一節があるが、恐らく同書を元ネタにしているのだろう。
8月8日
足利義昭、服部同名中に対し、昨永禄10年(1567)に請状を差出した趣旨により、味方して出兵せよとの御内書を発給。『記録御用所本古文書』
(備考)
翻刻未確認。
足利義昭は同地に同年7月28日付で御内書を発給している。
8月11日
京都日蓮宗系の本国寺、使者を美濃へ派遣。
上野秀政らが取次いで足利義昭と対面。『本国寺文書』二
(備考)
翻刻未確認。
本国寺は京都妙顕寺を本山とする所謂法華宗の寺である。
のちに足利義昭はここを仮御所と定め、永禄12年(1569)正月に三好勢と激しく交戦している。
8月12日
三好宗渭(三好下野入道釣閑斎宗渭)が上洛。『言継卿記』永禄十一年八月十二日条
8月15日
[参考] 『言継卿記』永禄十一年八月十五日条
局務師廉朝臣所へ罷向、補歴古本一覧了、次庭田へ罷向、黄門長谷郷祭見物に被行云々、頭中将見参、先日伊勢國岩内官位之事被尋之間勘申之、・・・
(備考)
「岩内」は伊勢国飯野郡または多気郡に所領を持つ北畠氏の準一門。
8月16日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年八月十六日条より
従河州珎藏院・吉祥院歸寺了、寺訴悉属本意了、
織田信長、足利義昭を奉じて上洛
8月17日
三好長逸(三好日向守)・同宗渭(下野入道釣竿)・石成友通(石成主税助)ら、近江へ下向し六角氏と会談か。『言継卿記』『細川両家記』
早旦三好日向守、同下野入道釣竿、石成主税助等江州へ下向、天下之儀談合云々、不知其故也、
『言継卿記』永禄十一年八月十七日条
(書き下し文)
早旦に三好日向守、同下野入道釣竿、石成主税助ら、江州へ下向。
天下の儀を談合と云々。
その故は知らずなり。
同八月日、三好方三人衆、江州へ被越、六角方直談之由候、
『細川両家記』
8月18日
松永方(松弾)の富野城が落城か。『多聞院日記』永禄十一年八月二十一日条
去十八日夜、城州富野城ヲ宇治田原ノ衛門兵衛打入、則時討果了、十川ヨリ調儀云々、松弾方弥相果者也、
(書き下し文)
去十八日夜、城州富野城を宇治田原ノ衛門兵衛打ち入り、則時に討ち果たしおわんぬ。
十川より調儀云々。
松弾(松永久秀)方いよいよ相果つるものなり。
(備考)
富野は山城国久世郡(現城陽市)の谷あいにあり、京街道からは少し離れた位置にある。
8月
信長、岐阜城下の瑞龍寺に全五ヶ条からなる禁制を発給。『瑞龍寺文書』(永禄十一年八月日付織田信長禁制)
禁制 瑞竜寺
一、当寺幷門前伐採竹木、放飼牛馬之事、
一、寺家幷門前諸伇、取陣、借宿事、
一、祠堂方先規相定年貢・諸伇之外、臨時之課伇之事、
一、外山苅取㕝、雖為一切停止、衆僧之儀、如先々受用其意事、
一、背寺家之法度輩、檀方許容之事、
右条々、於違背之輩者、速可処厳科者也、仍下知如件、
永禄十一年八月 日 信長(朱印)
(書き下し文)
禁制 瑞竜寺
一、当寺並びに門前の竹木を伐採し、牛馬これを放ち飼う事。
一、寺家並びに門前の諸役、陣取り、宿を借りる事。
一、祠堂方先規に相定むる年貢・諸役のほか、臨時の課役の事。
一、外山を刈り取る事、一切停止たりといえども、衆僧の儀、先々の如く受用するは、その意を得る事。
一、寺家の法度に背く輩、檀方(檀家)許容の事。
右の条々、違背の輩に於いては、速やかに厳科に処すべきものなり。仍って下知くだんの如し。(以下略)
(備考)
瑞龍寺は美濃国厚見郡(現岐阜市寺町)にあった臨済宗妙心寺派の寺院。
2条目は寺院関係者から課税をしたり、矢銭を要求したり、兵粮米や人足を徴発してはならない。
陣を取ったり、寄宿することを禁じたものである。
3条目は祠堂方に対して、先例で定めた年貢や諸役以外に、臨時で課役を申し付けることを禁じたもの。
祠堂は死者の霊をまつる所。位牌をまつる堂のことで、ここでは檀家から寄進された堂を指すのだろう。
4条目は寺周辺の山林を刈り取ることを禁止しているが、衆僧がこれを行うことは、寺家の許可があれば認めている。
信長が大規模な軍事行動を起こすことが世上の噂になっていたのだろう。
瑞龍寺は岐阜城下の南に連なる丘一帯を寺領として持ち、美濃を代表する大規模な寺院であった。
しかし、昨年にあたる永禄10年(1567)9月の織田信長の美濃攻めを受け、大きな被害を受けたのだろうか。
その反省があってなのか、同寺院はいち早く禁制の発給を求めている。
8月
信長、近江国坂田郡の成菩提院に全三ヶ条からなる禁制を発給。『成菩提院文書』(永禄十一年八月日付織田信長禁制)「改訂近江国坂田郡志」四(所収)
禁制 柏原
成菩提院
一、陣取、放火之事、
一、濫妨・狼藉之事、
一、伐採山林・竹木事、
右条々、堅令停止訖、若於違乱之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
永禄十一年八月日 弾正忠(花押)
(書き下し文)
禁制 柏原 成菩提院
一、陣取り、放火の事。
一、濫妨・狼藉の事。
一、山林・竹木を伐採の事。
右の条々、堅く停止せしめおわんぬ。
もし違乱の輩に於いては、速やかに厳科に処すべきものなり。仍って執達くだんの如し。(以下略)
(備考)
寂照山成菩提院円乗寺は美濃との国境に近い柏原に所在する天台宗の寺院。
現存する中で、信長が自らを「弾正忠」と称する最古のものである。
先述の『瑞龍寺文書』(永禄十一年八月日付織田信長禁制)にはこれがないのが興味深い。
8月
信長、近江国犬上郡の多賀社に全三ヶ条からなる禁制を発給。『多賀神社文書』二
禁制 多賀大社幷町
一、当手軍勢濫妨・狼藉之事、
一、陣取、放火之事、
一、伐採竹木、相懸非分課伇事、
右条々、堅令停止訖、若於違乱之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
「信長公」
永禄十一年八月日 弾正忠(朱印)
(書き下し文)
一、当手の軍勢、乱妨・狼藉の事。
一、陣取り、放火の事。
一、竹木を伐採し、非分の課役を相懸くるの事。
右の条々、堅く停止せしめおわんぬ。
もし違乱の輩(ともがら)に於いては、速やかに厳科に処すべきものなり。仍って執達くだんの如し(以下略)
(備考)
多賀社は近江犬上郡に所在する大社。
その歴史は古く、多くの古文書を所蔵する。
天文14年(1545)に甲斐の武田信玄が、自らの誕生年を記した願文を奉納したことでも知られている。『多賀神社文書』
8月
朝倉義景、亡武田義統との盟約のもと、若狭に兵を進めて武田元明を救出。
越前へ迎え入れる。(出展不明)
(備考)
若狭国を支配する武田氏は、室町将軍家の奉公衆として代々幕府と深い繋がりもっていた。
幕府や朝廷からの軍勢催促や財政的負担にも応じなければならず、次第に家臣や民衆の不満が増大していた。
天文年間からはじまる武田元光・信豊父子の内紛は、次世代の武田信豊・義元(義統)父子との争いへと移り、家臣団も巻き込んで深い禍根を残す。
弘治・永禄年中には、家督を継いだ義統を支える譜代の山県・上原氏と、信豊を支持する逸見氏が激しく対立する。
さらに、三好党の丹波八木城主内藤宗勝(松永長頼)が逸見氏を支えた。
永禄4年(1561)正月に逸見氏が武田義統に対し反乱を起こす。
義統は越前の朝倉義景(義景の生母は武田家出身。妻は細川晴元娘)に救援を求める。
これに応じた義景は、5月28日に敦賀郡司の朝倉景紀に出陣を命じる。
この戦いで逸見氏の高浜城は攻略され、義統を支持する朝倉氏が勝利したのだった。『当国御陳之次第』『厳助往年記』『御湯殿上日記』
一方、永禄6年(1563)から永禄11年(1568)まで毎年のように若狭へ侵攻する朝倉氏を相手に佐柿城に籠城したのが粟屋勝久であると『若州国吉籠城記』は記す。
真偽のほどはわかりかねるが、逸見氏を支持する内藤宗勝が丹波の合戦で討死を遂げ、さらに三好長慶が没すると、時代は新たな局面を迎える。
それが将軍足利義輝の横死である。
以後は国内外で足利義栄を支援する陣営と、足利義昭を支援する陣営が争うようになった。
そのような情勢の中、永禄10年(1567)11月9日に武田義統は没する。
このたび朝倉氏がこのような行動に出たのは、政情不安定な若狭へたびたび援軍を送るよりも、元明を国元に置いておく方が合理的だと考えたのかもしれない。
9月1日
公家の山科言継、信濃国を逐われ三好氏の庇護を受ける小笠原氏と参会。 『言継卿記』永禄十一年九月一日条
今日禮に罷出、路次次第、寶鏡寺殿、新御所御盃賜之、次入江殿御盃賜之、次近衛殿御盃賜之、次武者小路廣大妾かヽ所へ罷向、酒有之、信乃國小笠原牢人、三好方賴之住芥川、子源三郎参會、次岡殿、次竹内殿、次伏見殿、次大祥寺殿、次内侍所等へ参了、
(書き下し文)
今日礼に罷り出る。
路次次第に宝鏡寺殿、新御所の御盃これを賜る。
次いで入江殿の御盃これを賜る。
次いで近衛殿の御盃これを賜る。
次いで武者小路広大妾かか所へ罷り向かう。
酒これ有り。
信濃国小笠原牢人、三好方これを頼り芥川に住む子源三郎と参会。
次いで岡殿、次いで竹内殿、次いで伏見殿、次いで大祥寺殿、次いで内侍所等へ参りおわんぬ。
同日
[参考]『言継卿記』永禄十一年九月一日条
橋本伊賀守被来、小林使也、就大原竹之事に、書状可書與之由被申、則調遣之、
「度々申候大原竹座人之事、三向貴所迄一札可被参旨何共無分別候、京座人申掠候被賞、本所之申分御疑與相聞候、如何候哉、併貴殿懇に不被仰分與推量申候、今日明日之内三向下向之由承及候條、急度折紙被仰調可給候、澤路に相尋候處に、本所之補任口入旨、且以不申由候間、能々御分別候而御調干要候、恐々謹言、
八月廿九日 言繼
ト隱軒 床下」
(備考)
翻刻難読により読み下しは先送り。
「三向」は三好長逸だろう。
「與」は与。~と。
宛所は小林ト隠斎か。
9月2日
三好康長(三好山城)、3000余の兵で西京辺りへ移動し、各所に布陣。『多聞院日記』永禄十一年九月二日条
三好山城人數三千余、西京邊へ打越了、何事共シレス、奈良中陳取ハ寺門ヨリ届ニテ無之、
(書き下し文)
三好山城人数三千余、西京辺りへ打ち越しおわんぬ。
何事とも知れず。
奈良中陣取りは寺門より届けにてこれ無し。
9月3日
三好康長、奈良宿を放火。
これに呼応して筒井勢(筒衆)は多聞山の東側に布陣する。『多聞院日記』永禄十一年九月三日条
人數多聞山西北へ打寄、ナラ宿放火了、筒衆ハ東へ寄了、無殊儀打入了、仙學房上之間条々申遣之、
(書き下し文)
人数多聞山の西北へ打ち寄せ、奈良宿を放火しおわんぬ。
筒(筒井)衆は東へ寄せおわんぬ。
事無きの儀打ち入れおわんぬ。
仙学房上の間へ条々これを申し遣す。
同日
公家の山科言継、三好長逸(三好日向守所)へ書状を発給か。『言継卿記』永禄十一年九月三日条
三好日向守所へ書状遣之、關之儀申事有之、
(書き下し文)
三好日向守所へ書状を遣わす。
関の儀申す事これ有り。
9月4日
三好康長に呼応して河内勢も東大寺近辺に出陣。
午後7時~午後11時頃にカヰノツサカ郷を焼き払い、さらに西京を攻める。
多聞院、陣中の見舞いとして三好康長・筒井氏・河内勢に樽代20疋を贈る。『多聞院日記』永禄十一年九月四日条
河州衆東大寺邊ニ打寄、戌亥・カヰノツサカ郷焼沸、無殊儀、叉西京へ打入了、三備へ樽代廿疋遣之、
(書き下し文)
河州衆東大寺辺に打ち寄せ、戌亥・カヰノツサカ郷を焼き払う。
殊無きの儀。
また西京へ打ち入れおわんぬ。
三備へ樽代二十疋を遣す。
(備考)
東大寺は昨年10月10日の戦いで、既に大仏殿以下が灰燼に帰している。
樽代は酒肴代のことで、進物や祝儀の進物として定番の品。
「〇種〇荷」(〇に数字が入る)なども同じ意。
9月5日
禁裏で日月不蝕が問題化か。
陰陽師の土御門有脩・在高の責任が追及される。『言継卿記』永禄十一年九月五日条
一昨日従禁裏被仰下日月不蝕候儀、如何之由御尋也、算勘之面相違之段、致蝕書之本書不所持之間、有脩朝臣、在高等に被仰出令拜見校合仕度候、不然者来年之蝕之有無可被御覧候、若於相違暦道令斟酌、一身可相果覚悟之由、可然之様可申入之由有之、
(書き下し文)
一昨日禁裏より仰せ下さる日月不蝕の候儀、いかがの由かの御尋ねなり。
算勘の面相違の段、これを書き蝕み致す本書を所持せざるの間、有脩朝臣、在高等に仰せ出され拝見せしめ校合を仕りたく候。
然らずんば、来年の蝕の有無を御覧せらるべく候。
もし相違に於いては暦道を斟酌せしめ、一身を相果たすべきの覚悟の由、然るべきのようを申し入るべきの由これ有り。
※算勘(さんかん)は占いなどをして勘定すること。数を数えること。
※校合(きょうごう)は基準とする本文に照らして、本文の異同を確かめること。
※不然者(しからずは)はそうでなければ。促音化して「しからずば」や「しからずんば」と発音されることもある。
※斟酌(しんしゃく)は相手の事情や心情を汲み取り、手心を加えること。遠慮すること。言動を控えること。
同日
河内勢帰陣。『多聞院日記』永禄十一年九月五日条
河州人數歸陣了、長賢房神事トテ下了、
9月7日
信長、足利義昭と会見し、上洛の決意を述べる。『信長公記』
9月8日
信長、美濃・尾張・伊勢3ヶ国の兵を率いて近江国高宮に着陣。
先陣は平尾付近に陣を敷く。『信長公記』
9月9日
信長、同地に滞在。『信長公記』
9月10日
石成友通、近江国坂本へ出陣。『言継卿記』永禄十一年九月十日条
自尾州織田上總介、江州中郡へ出張云々、仍今朝石成主税助坂本迄罷下了、
(書き下し文)
尾州より織田上総介(織田信長)、江州中郡へ出張し云々。
仍って今朝石成主税助(石成友通)坂本まで罷り下りおわんぬ。
9月11日
信長、愛知川付近を放火し、同地で野営を張る。『信長公記』
同日
近江国で両軍が交戦か。
石成友通(石成主税助)は帰京する。『言継卿記』永禄十一年九月十一日条
於江州合戦有之云々、左右方討死云々、但上總介先國へ打歸云々如何、申刻石成主税助先打歸了、
(書き下し文)
江州に於いて合戦これ有ると云々。
左右方討死と云々。
但上総介(織田信長)先国へ打帰り云々如何。
申刻石成主税助(石成友通)先に打帰りおわんぬ。
9月12日
織田の臣森可成(森三左衛門尉)・坂井政尚(坂井右近将監)ら、威力偵察のため箕作山城へ兵を出す。
六角勢と城外で交戦し、敵80余りを討ちこれを破る。
浅井勢の力を借りるために佐々成政(佐々内蔵助)・福富秀勝(平左衛門尉)を遣わすが、浅井長政(浅井備前守)はこれを拒否。
坂井久蔵(坂井政尚嫡子)が武功を立て、足利義昭から感状を賜る。『信長公記』『言継卿記』永禄十一年九月十三日条
(備考)
以下は『信長公記』巻一 信長卿御入洛幷坂井久蔵感状事の記述である。
同年9月7日の足利義昭への謁見から12日箕作山夜戦前までの様子をまとめて引用した。
信長卿御入洛幷坂井久蔵感状事
永禄戊辰九月七日、義昭公へ御暇申給ひて近江國攻傾、やがて御迎を奉るべしと被仰上、翌日美濃・尾張・伊勢三箇國之軍勢を相具し打立給ふ、先陣は早江州平尾近邊に充満せしかば、後陣は垂井・赤坂邊に控たり、信長卿も高宮に著給ひて、両日人馬の息をやすめ、同日十一日愛智川近邊を放火し、其夜は野陣をかけらる、片邊の小城ともをば屑もし給はずして、同十二日佐々木左京太夫入道抜關齋承禎が居城観音寺並に箕作山の城へ押寄んとて手分を定めて、其朝先信長卿箕作山の様體見渡さるべしとて森三左衛門尉・坂井右近将監其外小姓馬廻五百騎計にて打出らるゝ處に、敵よりも足軽少々出しけるに、森・坂井手勢引分馬を懸入、東西北南に懸やぶり、追散し城中へ追こみ、敵八十餘討捕時を噇と上たりけり、角て宣ひけるは道途はよし先懸の勢をば悉愛知河表へ引取、観音寺に向て鶴翼に陣を取せ候へと柴田に被仰付けるが、各衆徒人々を被召て何様出張の験なくしては不可叶、箕作城を責べしと思ふは如何に皆々計ひ可申と仰ければ、坂井右近将監進出て、箕作と観音寺の間は少計のやうに見江て候、佐々木父子於目前て争か見捨候べき、先観音寺を押候はん御行候うてこそと申ければ、信長卿幸に浅井備前守自國の事也さぞ案内をも知つらん彼兩城の夾にわり入て押候へ箕作を責られ候はんと使者を遣し候ばやと仰ければ、各尤とこそ申けれ、さらば佐々内蔵助・福富平左衛門尉参て其由申候へと有しかば、兩人急馳向て其旨かくと申ければ、浅井も家老の者共召寄せ評諚ありけるが、何とやらんとかう御返事申煩うたる氣色ならば、兩人頓て心得定て罷成候まじとて馳歸て其旨申上けるに、信長卿もさぞ不快には思召けんなれども、今度浅井と初めての御見参、殊君臣の睦も未うひヽヽしき事なれば、打笑せ給ひて、然らば我勢を以両城の夾へわり入せ、承禎父子を押させ候べし、備前守に箕作を攻候へかしとて重て兩人被遣て云にて宣ひけるは、彼大ぬる者の浅井が所存にては兩條何もやは請候べし、其に究て疾々評議せよと仰けるに、只今せめられ候へと申者もあり、いやヽヽ夜に入責られ可然候はんやと申者もありけり、信長卿内々夜に入ば、責らるべしと思召けるにや日中に責候はゞ城中の兵ども多はもらさしなれど、坂井が申通に同じ候べし、皆々支度を致し、夜に入なば責候べしと軍中へ触させ玉ひけり、斯りける處に、佐々・福冨馳歸て、中々申上るまでも候はず、美濃・尾張の者より外には勇猛の者はいざしらず候と怒て申より外はなければ、信長卿却て兩人が氣色痛り思しけるにや、予亦かく察して早軍伍をば定たるぞ、心安思候へと御心よげにぞ仰ける、斯處に敵足軽を出しけるに、右近が嫡男坂井久藏少年未十三歳なりしが、城の山下掘際まで追詰、鑓を合せ散々につき合しが、遂に頸を捕て信長卿の見参に入ければ、大に感じ玉ひけり、角て其日の様子、義昭公へ注進有し時、久藏が働殊更に申上られければ、義昭公も類なき事なりとや思召けん感状をぞ被下ける、誠に馬に乗る姿さへあやうき程の者として、将軍の御感状に預る事は古き例にも有難かるべしと老若ほめぬ人こそ無りけれ、
同日 夜半
佐久間信盛(右衛門尉)・丹羽長秀(五郎左衛門尉)・木下秀吉(藤吉郎)・浅井新八が箕作山城を夜襲し攻め降す。
和田山城も開城。
これを見た六角父子、夜陰に紛れて観音寺を去る。『信長公記』『言継卿記』永禄十一年九月十三日条 『多聞院日記』永禄十一年九月十四日・十九日条
江州へ尾州之織田上總介入、昨日美作之城責落、同觀音寺之城夜半計落云々、自燒云々、同長光寺之城以下十一二落云々、
『言継卿記』永禄十一年九月十三日条
(書き下し文)
江州へ尾州の織田上総介(織田信長)が入り、昨日箕作の城を攻め落とす。
同じく観音寺の城が夜半ばかりに落ちたと云々。
自焼と云々。
同じく長光寺の城以下十一・二が落ち云々。
(備考)
以下は『信長公記』巻一 箕作城攻落事付観音寺城開退事の記述である。
同月12日の箕作山夜襲から1~2日間に六角の臣18ヶ城が降るところまでの様子をまとめて引用した。
箕作城攻落事 付観音寺城開退事
去程に抜關斎承禎子息右衛門督義弼も兼て家老の共召寄信長當國發向せば、定て街道筋の城々を先攻むべし、然は和田山城は此度の手宛として内々拵置たり、此幸にとて、南都にても事にあうたる兵共をすぐり勝て籠置たり、信長卿當國の繪圖を委細にしつらへ、山野溝洫難易等幷敵の謀所をも賂を入こまゝゝしく間尋られしかば、観音寺和田山へ押寄する様にして和田山には美濃三人衆を押として差向られ、和田山よりは奥なる箕作の方へ勢を押廻し玉へば、佐々木案に相違してぞ見江たる、佐久間右衛門尉・木下藤吉郎・丹羽五郎左衛門尉・浅井新八は、兼て箕作の責手に定られたる事なれば、時を作かけゝゝ攻寄けるに、城の内にも吉田の某建部源八など籠たれば、山下へ人數を下し、一支へ支へんとしけるに、態弱々と會釋て人數をくりよせ、息をも不繼喚叫で攻ける間、不叶して城内へ引取んとしけるを追つめ山の半にしてはや能兵共二百騎計討捕、勇みにいさんだる事なれば、此勢ひをぬかすな懸れや者どもと、四人の大将々々下知しければ、元より望む所なりなじがは少もたゆむべき、皆ひたヽヽと堀際へ付て、旗さし物なんどを投入打入面もふらず込入んとしければ、敵難怺や思けん笠を出して其に詰められたるは誰々やらんと云ければ、佐久間が手に與せし佐久間久六・原田與助、木下が手に與せし竹中半兵衛尉・峰次賀彦右衛門尉・木村隼人正、丹羽が手に與せし林志島などゝ答へければ、是までは持は持て候へども、一命を被助候はゞ、旗を巻鉾を逆にして降るべきと申ける間、即此由四人の大将へ注進しけるに、信長卿も幸彼が手に御座しける間、佐久間進出先城中の者ども一命を助け城を請取可申と存ずるはいかゞ候べきと窺申ければ、兎も角も事の能様に計候へと宜ひし間、箕作を請て勝時を噇とぞ上たりける、佐々木案に相違してこと見江たりけれ、箕作城落去せしに依て、和田山城も其夜開退く、観音寺にも兎やせん角やあらまじ、なんどひしめき騒ぎけるに、三雲新左衛門尉・同三郎左衛門尉申しけるは、是にこたへさせ給ふとも詰ては叶べからず、一先落させ玉ひ、身を全して時莭を待、一度會稽の恥を雪かんと思召さば、疾々我等が居城へ退せられ候へ、乍去家老の面々如何計被存候と聲を放て申ければ、各も内々退たくは有尤をこそ申されけるもの哉、あの鬼がみの様なる信長に、加様に成果中々敵對申事思ひも寄らず候とかうせば、夜も明なんず早とくヽヽと同じければ、數年住馴し所なれば名残をしくはあんなれども、上下共に唯命を助かり度思ければ、自ら執着は切てけり、何の御曹司をば誰圍申ぞ尊丈其は何としたなど云計にて、君臣上下の分もなく上を下へと観音寺坂を下り立て、女子供は聲をばかりに悲みあひて誰かれと呼ふ聲々餘りに分もさだからぬば、聞得て答る人もなし、寔に一年平家の人々都を落させ給ひし形勢も、角やと知れて哀なり、角て観音寺の城落去しければ、所々に楯籠し城々共一日二日の内に十八箇所まで開退、其外味方に降る輩をば人質を取、其まゝ己が居城に置せ給ふもあり、退散したる城々には、宗徒の人々入置けれり、爰に氏家常陸介入道ト全・稲葉伊豫守・伊賀伊賀守彼等三人は元来美濃國守護齋藤右兵衛大夫龍興が家子なりしが、近年は信長卿の幕下に属しぬ、然ば城攻等の先駈をば定て我々にこそ被仰付候はんと兼ては思ひまうけたる處に、御手の衆に攻させら候事事外なる御行哉と思ければ、今夜は先陣を申請て忠勤を抽べしとぞ励ける、誠大将たる人は無親疎遠近之間、慈仁を以先とすべき事樞要也、皆此君の御爲ならば一命をも顧みず忠功を励むべしと其氣日々新た也、抑近江國中の城々将碁倒しをする様に、波羅々々と落去したる事は信長卿の一胸襟より出たる智謀ぞ、和田山なんどに攻懸り玉はゞ、能兵をば失ひながら、加様にはかは行まじきか、兼て敵の謀を能聞召たればこそ角はなりけれ、嗚呼謀略の益たる事挙て申さんもいか計ぞと、浅井が家老に赤尾美作守申たりければ、傍の人聞て未智謀の深事知り給はずや、漢の高祖の終を有しも、臣等には張良三寸の舌を以王者の師と成し事も何故ぞや、全深慮の外あらばこそとてあざ笑て立たりければ、各目ひき鼻ひきいしくも申たる物哉と思入たる氣色は最もかしうぞ見江たりける、
※洫(みぞ)
※怺(こらえる)「堪」に同じ。「敵堪え難き」
※與(くみす・よ)「与」の旧字。「与せし」「原田与助」
※圍(かこむ)「囲」の旧字。
※樞(すう) 「枢」の旧字。
(書き下し文)
「箕作城攻め落とす事 付けたり、観音寺城開退の事」
去程に抜関斎承禎(六角承禎)の子息右衛門督義弼も、かねて家老の共召し寄せ、信長当国へ発向せば、定めて街道筋の城々を先に攻むべし。
然らば和田山城はこたびの手当たりとして内々に拵え置きたり。
この幸いにとて、南都(奈良)にても事にあうたる兵どもをすぐり勝て籠め置きたり。
信長卿当国の絵図を委細に設え、山野溝々の難易等並びに敵の謀所をも賂いを入れ、細々しく間尋ねられしかば、観音寺・和田山へ押し寄せする様にして、和田山には美濃三人衆を抑えとして差し向けられ、和田山よりは奥なる箕作の方へ、勢を押し廻し給へば、佐々木(六角父子)案に相違してぞ見えたる。
佐久間右衛門尉(佐久間信盛)・木下藤吉郎(木下秀吉)・丹羽五郎左衛門尉(丹羽長秀)・浅井新八は、かねて箕作の攻め手に定められたる事なれば、時を作かけかけ攻め寄せけるに、城の内にも吉田の某建部源八など籠もりたれば、山下へ人数を下し、一支へ支えんとしけるに、わざと弱々と会釈(解釈)して、人数をくりよせ、息をも継がず喚き叫びて攻めける間、叶わずして城内へ引き取らんとしけるを追いつめ、山の半ばにして、はや能兵ども二百騎ばかりを討ち捕り、勇みにいさんだる事なれば、「この勢いをぬかすな。懸かれや者ども」と、四人の大将大将下知しければ、元より望む所なり。なじがは少しもたゆむべき。皆ひたひたと堀際へ付きて、旗さし物などを投げ入れ、打ち入る面もふらず込み入らんとしければ、敵堪え難きや思けん笠を出して、それに詰められたるは誰々やらんと云いければ、佐久間が手に与せし佐久間久六・原田与助、木下が手に与せし竹中半兵衛尉(竹中重治)・蜂須賀彦右衛門尉(蜂須賀正勝)・木村隼人正、丹羽が手に与せし林志島などと答へければ、是までは持は持て候へども、一命を助けられ候はば、旗を巻鉾を逆にして降るべきと申しける間、即ちこの由四人の大将へ注進しけるに、信長卿も幸い彼が手に御座しける間、佐久間が先ず進み出て、「城中の者ども、一命を助け城を請け取り申すべしと存ずるはいかがに候べき」と窺い申しければ、「兎も角も事の良きように計らい候へ」と宜ひし間、箕作を請て勝鬨を「どう」とぞ上げたりける。
佐々木案に相違してこと見えたりけれ、箕作城落居せしによりて、和田山城もその夜開け退く。
「観音寺にも兎やせん斯くやあらまじ」などひしめき騒ぎけるに、三雲新左衛門尉(三雲成持)・同三郎左衛門尉(三雲定持)申しけるは、「これに堪えさせ給うとも、詰めては(籠城したままでは)叶うべからず。ひとまずは落させ給い、身を全うして時節を待ち、一度会稽の恥をそそがんと思し召さば、早々と我らが居城(三雲城)へ退かせられ候へ」
去りながら、家老の面々いかばかり存ぜられ候と声を放ちて申しければ、「各々も内々退たくば、尤も有をこそ申されけるものかな。あの鬼神の様なる信長に、斯様に成り果て中々敵対申す事思いも寄らず候と抗せば、「夜も明けなんず早とくとくと同じければ、数年住み馴れし所なれば、名残り惜しくはあんなれども、上下共に唯命を助かりたく思いければ、自ら執着は切りてけり。何の御曹司をば誰囲み申すぞ尊丈(そんじょう)其は何とした」
など云うばかりにて、君臣上下の分もなく、上を下へと観音寺の坂を下り立て、女子供は声をばかりに悲しみ哀いて誰かれと呼ぶ声々余りに分もさだからぬば、聞き得て答える人もなし。
誠に一年平家の人々、都を落させ給ひし形勢も、斯やと知れて哀れなり。
斯くて観音寺の城落去しければ、所々に立て籠もりし城々ども、一日~二日の内に十八箇所まで開き退く。
そのほか味方に降るともがらをば人質を取り、そのまま己が居城(岐阜)に置かせ給うもあり。
退散したる城々には、宗徒の人々入れ置けれり。
ここに氏家常陸介入道ト全・稲葉伊予守(稲葉良通)・伊賀伊賀守(安藤守就)彼等三人は、元来美濃国守護斎藤右兵衛大夫龍興が家子なりしが、近年は信長卿の幕下に属しぬ。
然らば城攻ぜ等の先駆けをば、定めて「我々にこそ仰せ付けられ候はん」とかねては思いもうけたるところに、御手の衆に攻めさせら候事、殊のほかなる御てだてかなと思いければ、今夜は先陣を申し請けて、忠勤を抜きんでるべしとぞ励みける。
まこと大将たる人は親疎無く遠近の間、慈仁を以って先とすべき事枢要なり。(以下割愛)
9月13日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年九月十三日条
一、一坂へ毛見ニ等春ヲ雇、少太郎付下了、近日ニ木津へ給人松浦可有働之由雑説半也、いかゝ、及晩三千ほとにて入了、兩人カセ山へニケ入了、
一、上意御入洛近々相調之由、諸方より多聞山へ注進在之云々、
(備考)
松浦氏の大方の説明は本年5月8日の項に記載。
9月13~14日
南近江に籠城する六角氏の臣、開城して降伏。
合わせて18ヶ城が降り、信長に人質を差し出す。
これらの城々に氏家ト全(常陸介入道ト全)・稲葉良通(伊豫守)・安藤守就(伊賀伊賀守)を入れ置く。『信長公記』
(備考)
日野城主蒲生賢秀もこの時信長に降った一人。
賢秀は徹底抗戦を貫く決意であったが、すでに信長に降っていた妹婿の神戸具盛(神戸蔵人)の説得により、城を明け渡して降伏。
嫡子の鶴千代を質に出した。
(後日『蒲生氏郷記』か『勢州四家記』あるいは『勢州兵乱記』の記述を抜粋する予定)
9月14日
信長、観音寺山に登り陣を敷く。
不破光治(不破河内)を迎えの使者として立正寺にある足利義昭のもとへ派遣。『信長公記』巻之上(我自刊我本)
(備考)
この様子は同年9月23日の足利義昭、観音寺城下の桑実寺に到着の備考にまとめて載せた。
同日
正親町天皇、信長に禁中の警護と、京都市中における軍勢の乱暴狼藉の禁止を命じる。『経元卿御教書案』
入洛之由既達叡聞、就其京都之儀、諸勢無乱逆之様可被加下知、於禁中陣下者、可令召進警固之旨、依天気執達如件、
九月十四日 左中弁経元
織田弾正忠殿
(書き下し文)
入洛の由すでに叡聞に達す。
それに就きて京都の儀、諸勢乱逆無きの様に下知を加えらるべし。
禁中陣下に於いては、警固を召し進らしむべきの旨、天気に依って執達くだんの如し。(以下略)
(備考)
綸旨の発給者は甘露寺経元。
叡聞(えいぶん)は天皇がお聞きになることを指す。
禁中は皇居のこと。
陣下(じんげ)は政務を執る場所のこと。
甘露寺経元は勧修寺流に属す公家で中御門・万里小路家と同門の家格で、正二位・権大納言を極位極官とする。
同日
大納言の万里小路惟房、織田信長と明院良政に禁中の警固を求める旨の書状を発給。『立入宗継文書』
御出張珍重候、就其被成綸旨、京都之儀、禁中御警固以下堅固被申付候者、可被悦思食之旨被仰下候、猶明院可被申候、巨細磯谷両人仰含候也、謹言、
九月十四日 惟房
織田弾正忠殿
(書き下し文)
御出張珍重に候。
それに就きて綸旨を成され、京都の儀、禁中御警固以下を堅固に申し付けられ候はば、悦び思し食さるべきの旨を仰せ下され候。
なお明院(明院良政)申さるべく候。
巨細は磯谷(磯谷久次)両人に仰せ含め候なり。謹言。(以下略)
就霜台出張之儀、被成綸旨候、諸勢堅被申付、京都之儀、無別儀之様肝要候、禁中可被召進御堅固候者、可然之旨被仰進、御馳走所仰候、猶磯谷両人可申候也、謹言、
九月十四日 惟房
明院御房
(書き下し文)
霜台出張の儀に就きて、綸旨を成され候。
諸勢に堅く申し付けられ、京都の儀、別儀無きのように肝要に候。
禁中に御堅固を召し進らせらるべく候はば、然るべきの旨を仰せ進らせられ、御馳走仰す所に候。
なお磯谷(磯谷久次)両人申すべく候なり。謹言。(以下略)
(備考)
明院とは信長側近の一人である明院良政。
磯谷氏は近江甲賀郡の山中の領主で、久次の女が宮中を出入りする御倉職の立入宗継に嫁している。
磯谷両人とは久次・宗継のことだろう。
霜台(そうたい)は 弾正台の唐名で織田信長を指すのだろう。
万里小路家は藤原北家の流れをくむ公家で、極官を大納言とする家格であったが、稀に内大臣まで昇進を遂げる者もいた。
なお、惟房は正親町天皇と従兄弟同士である。
同日
京中大騒動となる。『言継卿記』永禄十一年九月十四日条
六角入道紹貞城落云云、江州悉焼云々、後藤、長田、進藤、永原、池田、平井、久里七人、敵同心云々、京中邊大騒動也、此方大概之物内侍所へ遣之、
自禁裏御庚申に可参之由有之間暮々参内、然處從方々注進、尾州衆明曉出京必定云云、倉部、薄等遣、相殘雑具内侍所臺所等へ巳刻取寄了、今夜於御三間御碁、若宮御方、晴豐被遊之、出御、伏見院宸筆往来講私記被一覽、予讀之、今夜當番持明院宰相、橘以繼雅英代、其外予、晴豐計也、臺物又柿栗被出御酒賜之、音曲有之、夜半鐘以後退出了、晴豊御添番云々、終夜京中騒動、不可說々々々、江州悉落居故云々、
(書き下し文)
六角入道承禎の城が落ち云々。
江州悉く焼けると云々。
後藤、長田、進藤、永原、池田、平井、久里の七人、敵へ同心と云々。
京中辺り大騒動なり。
こなた大概の物、内侍所へこれを遣る。
禁裏より御庚申に参るべきの由これ有る間、暮々に参内。
然るところ方々の注進より、尾州衆明暁に出京は必定と云云。
倉部、薄等を遣わし、相残る雑具を内侍所・台所等へ巳刻に取り寄せおわんぬ。
今夜御三間に於いて御碁を若宮御方(誠仁親王)、晴豊(勧修寺晴豊)が遊ばる。
御を出、伏見院、宸筆の往来講私記を一覧せらる。
予もこれを読む。
今夜の当番は持明院宰相(持明院基孝カ)、橘以継(雅英の代わり)、そのほか予、晴豊ばかりなり。
台の物はまた柿栗を出され御酒を賜る。
音曲これ有り。
夜半の鐘以後に退出しおわんぬ。
晴豊は御添番し云々。
終夜京中騒動。
不可説不可説。
江州悉く落居ゆえに云々。
(備考)
当時の庚申日は、当番の公家が宮中に呼ばれ、一夜を宿直するのが習わしであった。
本年の9月14日は、その庚申日にあたる。
倉部は言継側近として同文書で頻繁に登場する人物。
薄は橘以継のことで、言継の次男として薄家の養子となった人物。
宸筆は天皇御自らが記したものである。
同日
奈良では三好宗渭(釣閑斎)と香西氏が3000の兵で木津ノ平城に入城。
鹿背山城下の里で田畠の薙ぎ払いが行われる。『多聞院日記』永禄十一年九月十四日条
今日於江州合戦在之云々、兩方勝負は不聞、
一、昨日釣閑齋・香西以下三千ほとにて木津ノ平城へ入候、毛見ニ下處やうゝゝ鹿山城へ迯入了、里ノ近邊ハ苅田沙汰之、今日雨下、
※「迯」は逃の異体字。
(書き下し文)
今日江州に於いて合戦これ在り云々。両方勝ち負けは聞かず。
一、昨日釣閑斎・香西以下三千ほどにて木津の平城へ入り候。
毛見ニ下るところ、ようよう鹿山城へ逃げ入りおわんぬ。
里の近辺は刈り田これに沙汰す。今日雨下る。
(備考)
江州合戦の記述は、伝聞と時差の点を考慮しなければならない。
木津の平城の詳細は不明。
市街地に埋没しているためか、遺構はほとんど遺っていないそうだ。
鹿背山城は木津近辺にあった城で、当時は松永方であった。
戦況が不利にも関わらず、久秀がここまで持ち堪えたのは、多聞山・信貴山・鹿背山など強固な城郭をいくつも拵えていた点もあったのかもしれない。
なお、信貴山は同年6月29日にすでに陥落している。『多聞院日記』永禄十一年六月二十九日条
9月16日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年九月十六日条
及晩木津へ立衆引退、西京へ陳取了、
9月17日
織田勢、蒲生郡鏡山村の薬師勝手神社を襲う。『鏡山村薬師勝手神社棟札』
右前之御本者、尾張國織田信長、當國亂入時、彼黨輩、永禄十一年丁辰九月十七日當所亂入、僧坊在家放火之餘炎、當社吹懸、七社之御寶殿、並拜殿、七間御供所、寶藏、鐘樓、如法經堂、庵室、藥師堂悉燒失畢、
(書き下し文)
右前の御本者、尾張国織田信長、當国乱入時、かの党輩、永禄十一年丁辰(1568)九月十七日に当所へ乱入。
僧坊在家放火の余炎、当社に吹き懸かり、七社の御宝殿、並びに拝殿・七間御供所・宝蔵・鐘楼・如法経堂・庵室・薬師堂が悉く焼失しおわんぬ。
(備考)
鏡山村薬師(くずし)村は竜王町にある。
集落の東寄りを県道春日竜王線が南北に通り、祖父川が南北に流れている。
『角川日本地名大辞典25滋賀(1979)』によると、他にも
“当時延暦寺の支配下にあった箱石山雲冠寺・星宿山西光寺の壮大な堂舎伽藍が焼滅され廃墟と化したが,今日その跡がしのばれる。”
とあるが詳細は不明。
同日
観音寺を落ち延びた六角父子、甲賀に移って望月氏の庇護をうけるも、信長の追撃を警戒し伊賀へ移動を開始。『甲賀郡南杣村木村政延氏文書』
今度宿之儀頼入候處、別而入魂難忘候、仍郡内之儀、織田可有行之由候而物忩之間、至于伊賀打越候、雖勿論之儀候、出張之刻、必當屋敷え可入城候間、不相易馳走可爲喜悦候、猶高野瀬備前守、狛修理亮可申候、恐々謹言、
九月十七日 義治(花押)
望月吉棟殿
(書き下し文)
この度宿の儀を頼み入り候ところ、別して昵懇忘れ難く候。
仍って郡内の儀、織田のてだて有るべくの由候て物騒の間、伊賀に至りて打ち越し候。
勿論の儀に候えども、出張の刻み、必ず当屋敷へ入城すべきに候間、相易しからず馳走喜悦たるべく候。
なお高野瀬備前守・狛修理亮申すべく候。恐々謹言(以下略)
同日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年九月十七日条
少太郎一坂へ下了、坊領一本も不苅取、先以珍重々々、併神力也、
9月18日
信長、勅使を観音寺城に迎え、正親町天皇の綸旨と万里小路惟房からの副状を受け取る。
さらに正親町天皇と夫人御作の台物と唐墨を拝領し、勧修寺大納言に返書を認める。『安土村総見寺所蔵文書』『近江蒲生郡志』巻十
就當國在陣被立勅使候、殊 (闕字)御作臺物、幷唐墨従御兩所様拜領、即頂戴忝存候、此表之趣、自是雖可致言上候上揆之類還如何遠慮仕候、然而被仰下之條、無冥加之次第ニ候、此等之旨、宜被達叡聞事、可爲大慶候、恐々謹言、
九月十八日 信長(朱印)
勧修寺大納言殿
(書き下し文)
当国在陣に就きて勅使を立てられ候。
殊に (闕字)御作の台物、並びに唐墨を御両所様より拝領。
即ち頂戴忝く存じ候。
この表の趣き、これより言上致すべき候といえども、上揆の類還如何遠慮仕り候。
然して仰せ下さるるの条、冥加無きの次第に候。
これらの旨、宜しく叡聞に達せらるる事、大慶たるべく候。恐々謹言(以下略)
(備考)
勧修寺大納言は晴右のことでよいのだろうか。
『近江蒲生郡志』は大正11年(1922)に初版が出され、昭和47(1972)年と同55年(1980)に復刻版が出版されている。
同日
足利義昭奉公衆の細川藤孝、西養坊に先規の通りに参陣するよう要請。『富田仙助氏所蔵文書』二
来廿四日御入洛候、如先規御参陣、不可有御断之由、被仰出候、恐々謹言、
□月十八日 細川兵部大輔
藤孝(花押)
西養坊
(書き下し文)
来たる二十四日御入洛候。
先規の如くに御参陣、御油断有るべからざるの由を仰せ出され候。恐々謹言(以下略)
(備考)
宛所の西養坊は不明。
文脈から本年9月18日付と見て間違いはないだろう。
9月19日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年九月十九日条
江州之様篇々沙汰之大略六角方負歟、
9月20日
[参考]『言継卿記』永禄十一年九月二十日条
織田明朝出張必定之由有之、騒動以外及暁天也、
9月21日
信長、越後の上杉輝虎への返書として、近況を伝える旨の書状を発給。『蕪木文書』『越佐史料』四
芳翰之趣本望存候、仍去七日御入洛、至江南令着陣候、国々之儀平均ニ申付候、然者来廿四日可為御渡海候、弥被任御本意候、此等之通可得御意候、恐々謹言、
九月廿一日
直江大和守殿 信長
(書き下し文)
芳翰の趣き本望に存じ候。
仍って去七日御入洛、江南に至りて着陣せしめ候。
国々の儀平均に申し付け候。
然らば来たる二十四日に御渡海たるべく候。
いよいよ御本意に任せられ候。
これらの通り御意を得べく候。恐々謹言(以下略)
同日
伊賀に逃れた六角父子、伊賀国武士の友田氏の庇護を受け、音羽郷(音波)に移る。
承禎は友田氏(友田山内殿)に気遣いを謝する書状を発給。『川合文書』『三国地志』
今度於音波相越候之處、路次送幷種々機遣、其懇意段不可忘候、殊更切々見舞尤祝着候、彌入魂肝要候、猶繁岡可申候、恐々謹言、
九月廿一日 承禎(花押)
友田山内殿
(書き下し文)
この度音波に於いて相越し候のところ、路次の送りならびに種々の気遣い、その懇意の段忘るべからず候。
殊さら切々に見舞もっとも祝着に候。
いよいよ昵懇肝要に候。
なお繁岡申すべく候。恐々謹言(以下略)
(備考)
『戦国遺文 佐々木六角氏編』によると、この文書は写のようだ。
上記の翻刻は『近江蒲生郡志』巻十によるもの。
『戦国遺文』は「路次送幷種々機遣、其懇意段不可忘候、」のところを「路次送幷種々機遣共懇意段、可可相忘候、」としている。
同日
足利義昭、西庄を立ち、近江国坂田郡柏原の成菩提院に泊まる。『信長公記』巻之上(我自刊我本)『近江蒲生郡志』巻十
(備考)
この時期の『信長公記』の日付については慎重に扱う必要がある。
同日
[参考]『言継卿記』永禄十一年九月二十一日条
今日之出張延引云々、來廿四日必定云々、
9月22日
信長、百済寺に3ヶ条からなる条書を発給。『百済寺文書』
条々 百済寺
一、当寺諸事寺法之儀、可為如前々、寺領之内へ臨時之課伇等、一切不可申懸之事、
一、惣寺物、所務以下散在ニ有之諸知行分、如前々不可相違、尚以当寺知行方不可付給人、幷山林・竹木伐採儀、不可有之事、
一、当寺之儀、此方為祈願所之条、自何方も非分族雖申懸輩、不可有承引事、
永禄十一
九月廿ニ日 弾正忠(朱印)
(書き下し文)
条々 百済寺
一、当寺の諸事寺法の儀、前々の如くたるべし。
寺領の内へ臨時の課役等、一切申し懸くべからざるの事。
一、総寺の物、所務以下散在にこれ有る諸知行分、前々の如くに相違すべからず。
なお以って当寺の知行方は、給人を付すべからず。
並びに山林・竹木伐採の儀これ有るべからざるの事。
一、当寺の儀、此方祈願所たるの条、何れ方よりも非分のやから申し懸くるともがらといえども、承引有るべからざるの事。(以下略)
(備考)
百済寺(ひゃくさいじ)は愛知郡(現東近江市百済寺町)に存在する天台宗の寺。
現在も湖東三山の一として有名である。
寺伝によれば、推古天皇14年(606)に聖徳太子が建立し、百済の僧恵聡・道欣・勧勒らが来住したことが名の由来とある。
勅願所となり、一山僧坊600を数えるほど栄えるも、明応7年(1498)の火災で本堂などが焼け、文亀3年(1503)には六角氏とその有力被官である伊庭貞隆の争いで多くが焼失した。
信長の祈願所とあるのが意外である。
というのは、この後六角氏が近辺の鯰江城に立て籠もった際、同寺は六角氏に味方して織田信長の焼き討ちを受けて灰燼に帰したからだ。
大方の語訳は以下の通り。
1.百済寺の諸事に関する寺法はこれまで通り認めるものであり、臨時の課役等は一切求めない。
2.百済寺の雑具や各地に散在している知行地、年貢の徴収権等は、これまで通り保証する。
なお、百済寺所有の知行地を、給人(知行人)につけてはならない。
並びに竹木や山林を伐採してはならない。
3.百済寺は信長の祈願所であるため、例え誰からの圧力があっても不当な要求を受け入れてはならない。
同日
足利義昭、観音寺城下の桑実寺に到着。
正覚院を陣所とし、信長の戦功を労う。
さらに、正覚院へ寺領を安堵する旨の書状を発給。『安土村豊浦東南寺文書』『信長公記』巻之上(我自刊我本)『近江蒲生郡志』巻十
就今度出張當寺
被居御座訖、然者
寺領等之儀、彌不可
有異儀候、猶藤孝
可申者也、
九月廿二日 (足利義昭花押)
正覺院
(書き下し文)
この度出張に就きて当寺に御座を居られおわんぬ。
然らば寺領等の儀、いよいよ異儀有るべからず候。
なお藤孝(細川藤孝)申すべきものなり。(以下略)
(備考)
蒲生郡の桑実寺(現近江八幡市安土町)は現在も当地に存在する天台宗の寺院。
天智天皇の勅願寺として開山し、日本で初めて桑の木が生えたことが名の由来である。
中世では佐々木六角氏の手厚い保護を受け、のちに織田信長が天正4年(1576)に安土に入った時期に堂舎が再建され、山林8町・寺領415石の寄進を受けている。
子院に正寿院・千光院・宝泉寺がある。
この文書の写真が『近江蒲生郡志』巻十に所収されている。
現在は国立国会図書館デジタルコレクションから閲覧が可能である。
『信長公記』巻之上(我自刊我本)より抜粋
観音寺山乗取御上り候、依之残黨致降参候之間、人質を執固、元の如く被立置、一國平均候者、公方様へ御堅約之爲御迎不破河内十四日尓濃州西庄立正寺へさしつかハされ、廿一日既被進御馬柏原上菩提院御着座、廿二日桑實寺へ御成、廿四日信長守山まて御働、翌日志那勢田之舟さし相御逗留被成、
(書き下し文)
(信長が)観音寺山乗取り御上り候、これにより残党降参致し候の間、人質を取り固め、元の如く立て置かれ、一国平均に候はば、公方様(足利義昭)へ御堅約の御迎えとして、不破河内(不破光治)十四日に濃州西庄立正寺へさしつかわされ、二十一日既に御馬を進められ柏原上菩提院に御着座。
二十二日桑実寺へ御成り、二十四日信長守山まで御働き、翌日志那勢田の舟さし相御逗留成され・・・
(備考)
この時期の『信長公記』の日付は他の文書と整合性の取れない箇所が多い。
同日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年九月二十二日条
木津迄南花院送下了、以次御なへ見廻處、今日既迯歸了、先々珍重々々、
9月23日
織田勢と足利義昭勢、京都山科七郷に布陣。
信長は近江三井寺で陣を張る。『言継卿記』永禄十一年九月二十三日条 『多聞院日記』永禄十一年九月二十三日条 『信長公記』
織田弾正忠今日三井寺へ出張云々、先勢山科七郷へ陣取云々、
深草之寺本成戌刻自焼也、
『言継卿記』永禄十一年九月二十三日条
(書き下し文)
織田弾正忠今日三井寺へ出張し云々。
先勢は山科七郷へ陣取り云々。
深草の寺本成戌刻に自焼なり。
今日京邊土へ細川兵部大輔、和多伊賀守大将にて江州裏歸衆召具、一万余にて上洛了、
『多聞院日記』永禄十一年九月二十三日条
(書き下し文)
今日京辺土へ、細川兵部大輔(細川藤孝)、和田伊賀守(和田惟政)大将にて江州裏帰衆を召し連れ、一万余にて上洛おわんぬ。
(備考)
深草は伏見近くの鳥羽街道にあり、山科からはわずか山一つ隔てた位置にある。
『信長公記』はこの日を9月26日としているが誤りであろう。
『多聞院日記』には「上洛」とあるが、恐らく山科あたりで一夜を明かしたのだろう。
奈良であるという情報伝達の精度を考慮しなければならない。
同日
足利義昭側近の飯尾貞遙・諏訪晴長が、連署で賀茂荘の地侍らを懐柔する旨の奉書を発給。『山城加茂郷文書』永禄十一年九月二十三日付足利義昭奉行人奉書
就今度御入洛各可致忠節云々、被思食神妙訖、早存其旨可被抽戦功之由、被仰出候也、仍執達如件、
永禄十一
九月廿三日 貞遙(花押)
晴長(花押)
城州
賀茂郷諸侍中
(書き下し文)
この度の御入洛に就きて、各々忠節致すべき云々を思し食され神妙におわんぬ。
早くその旨を存じ、戦功抜きんでらるべきの由を仰せ出され候なり。
仍って執達くだんの如し。(以下略)
(備考)
当地は京都南部にあたる相楽郡の賀茂。
山城国賀茂荘は賀茂郷の故地である。
ここには春日社領も存在する。
地名辞典京都版が手に入り次第追記したい。
9月24日
西院の小泉島介・九條和久・壱岐守らが居城を焼き南方へ落ち延びる。
丹波から足利義昭の味方として柳本氏が出陣し、嵯峨・川端・太秦を放火し、大将軍に布陣。『言継卿記』永禄十一年九月二十四日条
西院之小泉島介、九條和久壹岐守等城早旦自焼、南方へ加云々、自丹州柳本出張、嵯峨川端太秦等放火、大将軍迄來云々、
(書き下し文)
西院の小泉島介、九條和久壹岐守等、城を早旦に自焼。
南方へ加わり云々。
丹州より柳本出張。
嵯峨・川端・太秦等を放火。
大将軍まで来たり云々。
(備考)
西院の小泉氏や九條氏についてはよくわからない。
嵯峨・川端・太秦の地はいずれも丹波街道にある西京都の地。
大将軍は北野天満宮あたりにあり、御所は目と鼻の先である。
また、西院も近い。
同日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年九月二十四日条
尾張ノ上總守大津迄出了、藤六上了、
9月25日
織田勢の先陣が上洛か。『言継卿記』永禄十一年九月二十五日条
尾州之足軽二三騎近所迄來、禁裏御近所之儀堅申付之由申理云々、東之田中之在所少放火云々、
(書き下し文)
尾州の足軽二・三騎近所まで来たる。
禁裏御近所の儀を堅く申し付くるの由をことわり申し云々。
東の田中の在所を少し放火し云々。
(備考)
田中は北白川や東山慈照寺付近で、現在の出町柳の近くにあたる。
同日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年九月二十五日条
一日雨下了、上意大津迄御出張、上總ハ清水寺迄出了、爰元物忩、
9月26日
織田勢、山科郷より軍を分ける。
織田信長は東寺に陣を敷く。
足利義昭(武家)は清水寺に布陣。
山科郷から直進して北白川へ向かう街道では栗田口を放火。
細川藤孝(細川兵部大輔)・明院良政(明院)は御所の北門へ向かい、禁裏と折衝を行う。『言継卿記』永禄十一年九月二十六日条
同日
久我で両軍が衝突。
激しい戦いの末、石成友通が勝龍寺城へ退却か。『言継卿記』永禄十一年九月二十六日条
自早旦尾州衆出張、自山科郷南方へ通了、従北白川同出人數有之、細川兵部大輔、明院等北門迄参、今日武家清水寺迄被移御座云々、織田弾正忠信長東寺迄進發云々、山科郷栗田口西院方々放火、於久我軍有之云々、左右方多討死云々、石成主税助友通城於勝龍寺同合戦有之云々、
(書き下し文)
早旦より尾州衆出張。
山科郷より南方へ通りおわんぬ。
北白川より同じく人数を出しこれ有り。
細川兵部大輔、明院等北門まで参る。
今日武家清水寺まで御座を移られ云々。
織田弾正忠信長は東寺まで進発し云々。
山科郷栗田口西院方々を放火。
久我に於いていくさこれ有り云々。
左右方多く討死云々。
石成主税助友通城勝龍寺に於いて同じく合戦これ有り云々。
(備考)
栗田口は御所から鴨川を挟んだ二条通り沿いにある。
清水寺の北。吉田社の南にあたる。
御所へ向かった細川藤孝は義昭の奉公衆、明院良政は信長の文官である。
信長が布陣した東寺は現在の京都駅すぐ南にある寺で、信長発給禁制をはじめ、現在でも多くの権力者からの文書を所蔵している。
足利義昭が陣した清水寺は東山にあり、まだ山科から一山越えたに過ぎない。
久我は京都から大坂に向かう桂川沿いにある地で、川沿いを少し下った先に勝龍寺城がある。
なお、『信長公記』はこの日を9月28日としており、陣を敷いた場所も「東寺」ではなく「東福寺」としている。
牛一の記録ミス、記憶違いだろうか。
同日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年九月二十六日条
筒井順慶・マメ山三好新丞各引退了、多聞山ヨリ奈良中・寺門厳重ニ亂妨停止了、先代未聞ノ事、右往左往之處各々安堵了、南花院被歸了、
一、昨日箸尾ヨリ出、十市郷五ヶ所焼了、井戸堂・吉田・九條・備前・長柄、
一、成身院・常如院・吉祥院・蓮成院各々法隆寺邊へ離了、先段多聞山ヨリ懸銭以下彼是氣遣之故也、
9月27日
北近江の高島衆ら、約8000の兵で神楽岡に陣取る。
淀・勝龍寺・西岡あたりで両軍が激しく衝突。
足利義昭は清水寺から東寺に移陣。
織田勢は柴田勝家(日向守?)、蜂屋頼隆(兵庫頭)・森可成(三左衛門)・坂井政尚(右近)を先陣として石成友通(岩成主税頭)の籠もる勝龍寺城を攻める。『言継卿記』永禄十一年九月二十七日条 『多聞院日記』永禄十一年九月二十七日条 『信長公記』『細川両家記』など
同九月日、一乗院殿御供申、織田上總介江州北の郡浅井方と相談一味して同國南郡六角方へ切懸候處に、彼方の衆過半一乗院殿へ参る上は、六角方難堪して、則伊賀國へ被引退也、然ば江州を切取、一乗院殿御供申則御入洛候也、御大慶無申計候、
『細川両家記』
(書き下し文)
同九月日、一乗院殿(足利義昭)に御供申し、織田上総介、江州北の郡浅井方と相談じ、一味して同国南郡の六角方へ切り懸け候ところに、彼方の衆過半は一乗院殿へ参る上は、六角方堪え難くして、則ち伊賀国へ引き退かるなり。
然らば江州を切り取り、一乗院殿御供申し則ち御入洛に候なり。
御大慶は申すばかりに無し候。
(備考)
この時期の『信長公記』は日付に誤りがある可能性が高い。
勝龍寺を攻めた織田勢の中で、ほかの3大将の面子を見る限り、柴田日向守とあるのは勝家であろう。
同月29日条に詳述する。
同日夜
足利義昭、西岡の寂勝院に陣を移す。
諸勢は山崎天神馬場付近に陣を構える。『言継卿記』永禄十一年九月二十七日条
早旦禁中参、御見舞如日々、江州北郡衆高島衆八千計神樂岡陣取、叉南方へ越了、武家御所自清水寺東寺江被移御座、叉西岡向へ被移御座云々、西岡方々所々、吉祥院、淀、鳥羽、河州、樟葉以下放火也、今夜武家西岡寺土之寂勝院に陣取云々、諸勢山崎天神馬場迄陣取云々、勝隆寺之城堅固云々、但和睦之調有之云々、
『言継卿記』永禄十一年九月二十七日条
(書き下し文)
早旦に禁中へ参る。
御見舞は日々の如し。
江州北郡衆高島衆八千ばかり神楽岡に陣取る。
また南方へ越しおわんぬ。
武家御所(足利義昭)清水寺より東寺へ御座を移さる。
また西岡向へ御座を移られ云々。
西岡の方々所々、吉祥院・淀・鳥羽・河州・樟葉以下を放火なり。
今夜、武家西岡寺土の寂勝院に陣取り云々。
諸勢山崎天神馬場まで陣取り云々。
勝龍寺の城堅固に云々。
但し和睦の調いこれ有りと云々。
(備考)
神楽岡は吉田社の北。慈照寺の近くにある。
西岡(にしのおか)は長岡や勝龍寺の辺り。
方々所々は所々方々と同義で、あちらこちらという意味。
所々方々の方が一般的。
在々所々を所々在々と書くのとさほど変わらないだろう。
「鳥羽・河州・樟葉以下放火」とあるのは、淀川の南を走る街道で、今日の伏見から石清水八幡宮を経由し、大坂へ下るルートが焼かれたのだろう。
現在は京阪電鉄の沿線となっている。
公家や僧侶の日記等では「武家」は将軍その人を指すことが多い。
従って本来なら「武家」と記されるべきは足利義栄である。
しかし、この日の夜に寂勝院に陣取ったのは足利義昭だろう。
『言継卿記』は義昭が出陣以来、足利義昭のことを「武家」や「公方様」と一貫して記している。
この時期の足利義栄が病により臥せっている様子は『言継卿記』をはじめ、様々な史料から判然としている。
数日後に彼が没した事実を考えると、とても出陣できる状態ではなかっただろう。
[参考]『多聞院日記』永禄十一年九月二十七日条
十七日、京都西岡勝龍寺城石成大将ニて五百余たて籠了、責切悉以討死了ト、實否ハ慥ニ不知、ウソ也、十市郷ヘハ箸尾ヨリ秋山龍王より出、散々ニ苅田放火果切了、
9月28日
阿波三好勢ら、山崎で敗れて退却。
西岡あたりで放火・略奪が続く。
織田勢らは芥川城下の市場を放火。
足利義昭は竹内邸に宿泊。『言継卿記』永禄十一年九月二十八日条
自早旦度々禁中見舞申、油小路迄中山以下七八人見物に罷出、二條迄下、山崎破之由申、取物共繁多也、西岡邊悉尚放火、武家御所山崎竹内左兵衛亭江被移御座云々、先勢芥川之市場放火云々、
(書き下し文)
早旦よりたびたび禁中を見舞申す。
油小路まで中山以下七八人見物に罷り出で、二条まで下る。
山崎破れるの由を申す。
取る者ども繁多なり。
西岡辺り悉くなお放火。
武家御所(足利義昭)山崎竹内左兵衛(竹内長治)亭へ御座を移られ云々。
先勢芥川の市場放火し云々。
(備考)
『信長公記』『永禄記』によると、この時芥川山城に籠城したのが細川六郎(のちの昭元)・三好長逸(三好日向守)のようだ。
山崎竹内左兵衛亭とあるのは、山崎に居住する竹内長治邸のことだろう。
山科言継とは親しく交際している様子が彼の日記から散見される。
竹内氏は公卿久我家の家司であったが、竹内季治の代から昇殿を許されるほどに家名を挙げた。
永禄10年(1567)11月4日条の『言継卿記』には「山崎に於いて竹内左兵衛佐長治朝臣所」に一泊したとある。
永禄11年(1567)10月4日条の『多聞院日記』で松永久通(松右)とともに上洛した竹内秀勝(竹下)は一族親類だろうか。
なお主家にあたる久我通俊はこの永禄11年(1568)に正親町天皇の勘気を蒙り失脚する。
9月29日
織田勢、芥川山城を焼き討ちにし攻め降す。
石成友通籠もる勝龍寺城が降伏。
河内国でも各所で放火。
足利義昭(武家御所)は天神之馬場に兵を進める。『言継卿記』永禄十一年九月二十九日条・三十日条 『細川両家記』
今日武家御所天神之馬場迄御進發云々、先勢芥川之麓焼之責云々、其外河州方々放火云々、
『言継卿記』永禄十一年九月二十九日条
(書き下し文)
今日武家御所天神の馬場まで御進発し云々。
先勢芥川の麓を焼き攻め云々。
そのほか河州方々を放火し云々。
三好三人衆方石成主税助は、山城國西岡勝蔵寺と云處に籠城候、然に則九月廿六日猛勢を以て押よせ、一責攻てくつろげ、噯に成て石成方退城候也、
『細川両家記』
(書き下し文)
三好三人衆方石成主税助(石成友通)は、山城国西岡勝蔵寺(勝龍寺カ)と云うところに籠城し候。
然るに則ち九月二十六日、猛勢を以て押よせ、一攻めに攻めてくつろげ、扱いに成りて石成方退城し候なり。
(備考)
両家記にはそれ以上の記述がない。
この文脈だと同月26日に石成友通が開城を受け入れたように見える。
しかしながら、猛攻を受けたのが26日で、その数日後に城を明け渡したとも読めなくはない。
『信長公記』による芥川城攻略の様子は同年10月2日の項を参照のこと。
同日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年九月二十九日条
新二郎于キ・七上了、十市郷ノ式悉はて切了、無足迄也、
一、昨今攝州之方大焼也ト申、いかゝ、
一、昨日松少より人質ニ、廣橋殿ノムスメ號祝言京へ被上了、尾張守へ被遣之了、
一、常如院・吉祥院へ敵へ同心〆寺門ヲ被開間、坊領可有闕所由、松少より被申遣了云々、咲止々々、
一、松右より銀屋与三郎使トシテ俵十一半預リ了、和喜坊方地子也、
(備考)
『多聞院日記』の常如院・吉祥院はともに興福寺の子院である。
過去に三好三人衆ら(敵)に同心し、寺門を開いたことが咎められたのだろう。
情勢が一変した今、興福寺でも関係者の仕置きが行われたのだろう。
両院の坊領は闕所とされたようだ。
広橋娘についてはよくわからない。
『信長公記』巻之上(我自刊我本)の本年9月27日~石成友通が降伏する29日までの記述は以下の通りである。
なお、このあたりの太田牛一の日付は、記憶違いの可能性がある。
ほかの3大将の面子を見る限り、柴田日向守とあるのは勝家であろう。
三井寺極樂院尓被懸御陣諸勢大津馬場松本陣取、廿七日公方様御渡海尓て同三井寺光浄院御陣宿、廿八日信長東福寺へ被移御陣、柴田日向守・蜂屋兵庫頭・森三左衛門・坂井右近此四人尓先陣被仰付、則か徒ら川打越御敵城岩成主税頭(ママ)楯籠正立表手遣御敵も足軽を出し候、右四人之衆見合馬を乗込、頸五十余討捕、東福寺尓て信長へ被懸御目、公方様同日に清水御動座、廿九日靑龍寺表被寄御馬、寺戸寂照御陣取、依之岩成主税頭降参仕・・・
※「見合馬」は見栄えのする名馬か
(書き下し文)
(足利義昭は)三井寺極樂院に御陣を懸けられ、諸勢は大津・馬場・松本を陣取る。
二十七日公方様(足利義昭)御渡海にて同三井寺光浄院に御陣宿とす。
二十八日信長東福寺へ御陣を移され、柴田日向守(柴田勝家カ)・蜂屋兵庫頭(蜂屋頼隆)・森三左衛門(森可成)・坂井右近(坂井政尚)この四人に先陣を仰せ付けられ、すなわち、桂川へ打ち越し、御敵城岩成主税頭(石成友通)の立て籠もる正立表手遣い、御敵も足軽を出し候。
右四人の衆見合馬を乗り込め、首五十余を討ち取る。
東福寺にて信長へ御目に懸けられ、公方様も同日に清水に御動座。
二十九日勝龍寺表へ御馬を寄せられ、寺戸寂照に御陣取る。
これにより岩成主税頭降参仕る・・・
この時期
摂津の伊丹衆、足利義昭(一乗院殿)に降る。『細川両家記』
攝州伊丹方は一乗院殿越前敦賀に御座の時より連々調儀共有、所領三万石給、此時色を立、攝州河邊武庫両郡、同廿九日に放火の條、阿州方城々攝州芥川城、河内の飯盛の城、同高屋城悉被明候上は、是非なき次第也、
『細川両家記』
(書き下し文)
摂州伊丹方は一乗院殿(足利義昭)越前敦賀に御座の時より連々調儀とも有り。
所領三万石を給わり、この時色を立つ。
摂州の河辺武庫両郡、同二十九日に放火の条、阿州方の城々、摂州芥川城・河内の飯盛の城、同じく高屋城は悉く明けられ候上は、是非なき次第なり。
(備考)
伊丹を根城とする伊丹親興は元々足利義昭を奉じる松永久秀方であった。
永禄9年(1566)5月末に堺起きた戦いでも、伊丹は松永方として参陣し、池田勝正に所領を焼かれている。
しかしながら、周辺の味方勢力が次々と降伏。
伊丹も同年8月17日頃に阿波勢に降っている。『細川両家記』
なお、この永禄11年(1568)9月あたりから、伊丹の棟梁は親興から忠親へと転換する。
9月30日
三好三人衆方の城々が降伏。
郡山道場が落ち、富田寺(普門寺カ)も降伏寸前となる。
織田勢、池田城を攻撃。『言継卿記』永禄十一年九月三十日条 『細川両家記』など
同日
戦乱により河内高屋城周辺が焼ける。
超昇寺が足利義昭に付き西京を放火。
箸尾氏らも足利義昭に付き、筒井氏の七条を焼く。『多聞院日記』永禄十一年九月三十日条
今日武家芥川へ被移御座云々、勝隆寺・芥川等之城昨夕渡之、郡山道場今日破之、富田寺外破之、寺内調有之、池田へ取懸云々、
『言継卿記』永禄十一年九月三十日条
(書き下し文)
今日武家芥川へ御座を移られ云々。
勝龍寺・芥川等の城昨夕これを渡す。
郡山道場今日これを破る。
富田寺外も破る。
寺内にて調いこれ有り。
池田へ取り懸かり云々。
今井道具彼是之用長賢房南へ下了、神人掃部・新二郎付下、神人ハ夕部上了、
一、摂州悉焼沸、河州高屋迄今日ハ焼了、藉?八妻昨夜退城了、城州・摂州・河州開隙、急度當國へ人數可越歟、安否之巷也、今日超昇寺ハ上意へ色立トテ西京少々焼了、
スカタハ箸尾へ一味、則色立ニ筒井ノ七条ヲ焼了ト、萬一一時亂了、抑寺社頓滅之基、いかゝ、面々殊惡行浅猿々々、眼前相果迄也、今生如此、來世弥々無所憑、アヽ、
『多聞院日記』永禄十一年九月三十日条
(書き下し文)
今井の道具かれこれの用長賢房南へ下しおわんぬ。
神人掃部・新二郎を付け下し、神人は夕部上げおわんぬ。
一、摂州悉く焼き払い、河州高屋まで今日は焼きおわんぬ。
藉?八妻昨夜退城おわんぬ。
城州・摂州・河州がひま開くと、急度当国へ人数を越すべくか。
安否の巷(巷説)なり。
今日超昇寺は上意へ色立とて西京を少々焼きおわんぬ。
スカタハ箸尾へ一味、則ち色立に筒井の七条を焼きおわんぬと、万一一時乱了。
そも寺社頓滅の基、いかが。
面々殊に悪行浅まし浅まし。
眼前相果つるまでなり。
今生はかくの如し。
来世はいよいよ頼みどころ無し。嗚呼。
(備考)
『言継卿記』に見える郡山道場は、恐らく摂津国島下郡(現茨木市)だろう。
普門寺城は数日前まで足利義栄がいた場所である。
『多聞院日記』に見える超昇寺は興福寺系の寺院。
「上意へ色立」とは足利義昭方へ付くと旗幟を鮮明にしたと解釈してよいだろう。
「スカタハ」については分かり次第後日に加筆したい。
同日
大和高田城を攻撃していた十市・箸尾ら、足利義昭の調停により兵を布方まで退く。『多聞院日記』
昨日高田城ノ責衆、布方悉以退散了、従上意様十市・箸尾へ被成御下知被追拂了、十□之儀将軍付、近日噯ニ新縫助参之間其調歟、大慶不及是非者也、但雑説ハ不知、
『多聞院日記』永禄十一年十月一日条
(書き下し文)
昨日高田城の攻め衆、布方へ悉く以て退散しおわんぬ。
上意様(足利義昭)より十市・箸尾へ御下知を成され追い払われおわんぬ。
十兵?の儀、将軍に付き、近日扱いに新縫助参るの間、その調べか。
大慶是非に及ばずものなり。
但し雑説は知れず。
(備考)
籠城の衆は恐らく筒井方だろうが、この時誰が籠もっていたのかわからない。
この時扱いが入り、恐らく開城したのだろう。
十市は十市常陸介のことか。
箸尾は箸尾宮内少輔(為綱)のことか。
『重修譜』によると、箸尾為綱は筒井順昭の娘を娶っているため、心中は複雑だったのかもしれない。
(推定永禄11)同日
六角義治、山中新三郎へ書状を発給。『山中文書』
就当国江相越、毎事可令馳走之由、以岡本申候、尤祝着候、仍進藤配当分如当知行為給恩申付候条、領地不可有相違候、猶狛修理亮可申候、謹言、
九月晦日 義治(花押)
山中新三郎殿
(書き下し文)
当国へ相越すに就きて、毎事馳走せしむべきの由、岡本を以て申し候。
もっとも祝着に候。
仍って進藤配当分、当知行の如く給恩として申し付け候条、領地相違有るべからず候。
なお狛修理亮申すべく候。謹言(以下略)
(備考)
『戦国遺文 佐々木六角氏編』は、年次を(永禄十一年カ)としている。
9月
信長、岐阜城下の加納市場に3ヶ条からなる制札を発給。『円徳寺文書』永禄十一年九月日付織田信長制札
定 加納
一、當市場越居之輩、分国往還煩有へ
から須、幷借銭・借米・さ可り銭・敷地年貢、
門奈ミ諸伇免許せしめ訖、譜代相傳能
者たりといふと毛、違亂春へ可ら佐流事、
一、楽市・楽座之上、諸商買すへ畿事、
一、をしかひ・狼藉・喧□(くちへんに花)・口論、使入邊可ら須、幷
宿をとり、非分申かくへ可らさ流事、
右条々、於違背之族者、可加成敗者也、仍下知如件、
永禄十一年九月 日 (信長花押)
(書き下し文)
定め 加納
一、当市場に越居(おっきょ)のともがら、分国往還の煩い有るべからず。
並びに借銭・借米・さがり銭・敷地年貢、門なみ諸役免許せしめおわんぬ。
譜代相伝の者たりというとも、違乱すべからざるの事。
一、楽市・楽座の上、諸商買すべき事。
一、おしかい・狼藉・喧嘩・口論、使入るべからず。
並びに宿をとり、非分を申しかくべからざる事。
右の条々、違背のやからに於いては、成敗を加うるべきものなり。
仍って下知くだんの如し。(以下略)
(備考)
語訳)①加納市場への移住者は、織田領内での往還の自由を保証する。並びに借銭・借米・悪銭・敷地の年貢、門ごとにかける諸役を免除する。例え織田の古くからの家臣であっても、違乱してはならない。②楽市・楽座であるから、これを承知のうえで商売せよ。③不法(強引)な買い入れを行ったり、狼藉・喧嘩・口論を行ったり、使者を遣わしてはならない。加えて、宿を取り、不当な要求をしてはならない。(以下略)
1条目のさがり銭は下落銭のことであり、本来ならば自然に排除されるべき悪幣である。(詳しくは当サイトの「撰銭(えりぜに)」の項を参照のこと)
同じく1条目の「使入るべからず」は、使を派遣し不当な要求をする者がいたからであろう。
そのため、使を出すこと自体を禁じたのかもしれない。
これは、信長が岐阜城下の加納市場に発布した還住を呼びかける制札である。
加納市に出した現存する信長発給制札の中では、2番目に古いものとなる。
円徳寺が所蔵するこの檜板に記された制札は35.9cm×33.9cm、厚さ1.0cmであり、さまざまな議論を呼ぶ「楽市・楽座」が明記されたものである。
現存する中で、前回発給された永禄10年(1567)10月日付の制札と内容的にはほぼ変わりはない。
しかしながら、前回分には「楽市場」とあったものが、このたび発給された制札には楽市に加えて「楽座」の語彙が追加されている。
これにはどのような意図があったのだろうか。
邪推をすれば、地下人の還住が進んでおらず、税収が安定しなかった。
秩序は乱れ、治安もさほど良いわけではなかったため、たびたび制札を出さねばならなかった。
案外信長が行った楽市・楽座政策は、借銭や借米を棄破することにより、速やかに戦乱前の状態に戻すことが主眼だったのかもしれない。
そのため”楽市・楽座”も場当たり的な政策に過ぎない。
というのは、これ以降、信長は同地に対して複数回制札を出しているが、次第に借銭・借米などを免除する要素が減っていき、逆に権利者(債権者)の権利を保障する内容が増えていくからだ。
9月
信長、蒲生郡沖島(冲嶋)に3ヶ条からなる禁制を発給。『沖島共有文書』『近江蒲生郡志』巻十(所収)
禁制 冲嶋
一、當手軍勢濫妨・狼藉之事、
一、放火之事、
一、廻船令違亂之事、
右條々於違犯之輩者、速可處厳科者也、仍執達如件、
永禄十一年九月 日 弾正忠(花押)
(書き下し文)
禁制 沖島
一、当手軍勢乱妨・狼藉の事
一、放火の事
一、廻船に違乱せしむるの事
右条々違犯のともがらに於いては、速やかに厳科に処すべきものなり。
仍って執達くだんの如し。(以下略)
(備考)
沖島はJR近江八幡駅から北へ進んだ先の琵琶湖上に浮かぶ小さな島。
かつては奥津島ともいい、琵琶湖の水運を利用した廻船業がさかんであった。
このたび信長に禁制の発給を依頼したのは、こうした経済的な側面もあったのだろう。
なお、この文書の写真が『近江蒲生郡志』巻十に所収されている。
9月
信長、永源寺(飯高)に3ヶ条からなる禁制を発給。『永源寺文書』四 『近江蒲生郡志』巻十(所収)
禁制 飯高
一、當手軍勢濫妨・狼藉之事、
一、陣取・放火之事、
一、伐採竹木之事、
右條々於違犯輩者、可處厳科者也、仍執達如件、
永禄十一年九月 日 弾正忠
(書き下し文)
禁制 飯高
一、当手軍勢乱妨・狼藉の事
一、陣取り・放火の事
一、竹木伐採の事
右条々違犯のともがらに於いては、厳科に処すべきものなり。
仍って執達くだんの如し。(以下略)
(備考)
神崎郡の愛知川沿いにある永源寺(現東近江市)は臨済宗永源寺派の本山である。
山号は瑞石山、別名として飯高山山上寺とも称される。
中世期の永源寺は瑞石山永源寺を第1に、飯高山含空院・瑞雲山永安寺・大雲山興源寺・集雲山曹源寺・仏日山退蔵寺の堂宇と塔頭により永源寺が構成されていた。
寺領は同地のほかに、神崎郡・蒲生郡・愛知郡・栗太郡にもあり、六角氏から手厚い保護を受けてきた。
このたびは信長からの禁制により兵火を免れたと推察されるが、元亀2年(1571)の織田勢による焼き討ちに遭い、一山が灰燼に帰した。
この文書は料紙の摩耗が激しいためか読みづらい箇所が多い。
花押影が見えないのはそのためなのか不明。
9月
信長、上京に3ヶ条からなる禁制を発給。『京都上京文書』一
(前文欠ク)
一、当手軍勢濫妨・狼藉之事、
一、陣執・放火之事、
一、非分之族申懸之事、
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
永禄拾一年九月日 弾正忠(朱印)
(書き下し文)
(前文欠ク)
一、当手軍勢乱妨・狼藉の事
一、陣取り・放火の事
一、非分のやから申し懸くるの事
右条々、違犯のともがらに於いては、速やかに厳科に処すべきものなり。
仍って執達くだんの如し。(以下略)
(備考)
上京について奥野高廣著『織田信長文書の研究(吉川弘文館)』には興味深いことが記されている。
少し長くなるが、以下はその抜粋である。
「(この文書は信長が)上京にあてたと推定される。京都の三条通以北を上京(かみぎょう)という。平安京の東北部と愛宕郡錦部郷(にしごり)・出雲郷の地をふくんでいる。上京区を定めたときに、賀茂川東の栗太郷も編入した。
京都は古い政治都市だが、十四世紀南北朝時代に、いまの新町通りを中心に東は室町、西は西洞院あたりまでが商工業の中心になっており、町座という商店街ができていた。この商業地区の「町」の周辺に都市生活としての「町」が十五世紀ころから見られる。市民生活の単位としての町が発達し、その町人によって自治の機能が果たされていた。
応仁乱から町は発展し、その町々を連合した親町組ができた。天文(一五三二-五四)のころになると上京・下京と行政的に区別されるようになる。上京では親八組・親九組という番号でよぶ親町であった。新町組の組織の発展とともに町衆という市民があらわれる。親町を中心とした自治的生活を営む市民である。この町衆は月行事などの役につき、一か月づゝの輪番で町の事務を処理し、町組の自治的な運営をはかった。
京都の町組は、さらに大きく上京・下京に統一され、おのおのに十人づつの宿老があった。天文八年(一五三九)酒屋・土倉の役銭の収納について上京・下京二十人が連署して幕府と交渉している。このような上京・下京を代表する宿老は土倉・酒屋のような富福な前期的資本家らしい。上京・下京という大組織の実際的な事務処理は、その単位となった親町に輪番にまわして行ない、これを月行事町とした。
このように京都では町々が発達し、町衆の自治的な親町組が形成され、これらの親町組が上京・下京に大きく組織され、両京の宿老が合議支配する都市自治の制度が発展した。
京都の人口は二〇万ほどと考えられる。上京は内裏とその附近に貴族の集団をもち、室町の幕府附近に武士団を居住させていた。下京は庶民層のものが多く、なかでも三条・四条は繁華な商業街になっていた。その商工業者も同一商品の販売者は同一箇所に密集しているのが特徴であった。」
これは30年以上前に著されたものである。
現在は研究がさらに進み、河内将芳氏などが当時の京都の民俗・風俗情勢に明るい。
9月
信長、吉田郷に3ヶ条からなる禁制を発給。『吉田文書』二
(包紙)
「永禄拾一年 当所 制札」
禁制 吉田郷
一、当手軍勢濫妨・狼藉事、
一、陣執、放火之事、
一、非分之輩申懸之事、
右条々、於違犯之輩者、速処厳科者也、仍執達如件、
永禄拾一年九月日 弾正忠(朱印)
(備考)
前述の禁制と内容が同じなので、読み下しは割愛する。
吉田郷は吉田社が存在する地である。
卜部家の血筋をひく吉田兼倶が、唯一神道を謳う一大勢力を築いたことで有名。
兼倶の孫が兼右である。
文中の「執達くだんの如し」は、発給の主体に信長よりも上位の存在があり、その意を汲んで発給していることを指す。
他ならぬ足利義昭である。
9月
信長、八瀬荘に3ヶ条からなる禁制を発給。『八瀬童子会所蔵文書』
禁制 八瀬
一、当手軍勢濫妨・狼藉之事、
一、陣取・放火之事、
一、伐採竹木之事、
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
永禄十一年九月日 弾正忠(朱印)
(備考)
読み下しは割愛。
京から比叡山へ登る際の入口に八瀬がある。
現在ではケーブル八瀬駅からロープウェイで比叡山山頂まで登ることができ、四季折々の風景が観光客の心を慰めてくれる。
中世期の八瀬は八瀬荘があり、谷に沿って流れる高野川の瀬が多いことが地名の起こりだといわれている。
南北朝の争乱の際には後醍醐天皇に従い、以来明治に至るまで租税を免除される特権を得ていた。
そして、宮廷の即位・大葬の際は、八瀬童子とよばれる特定の家柄が駕輿丁を奉仕した。
なお、同年10月7日に幕府が同所へ禁制を発給しているようだが、こちらは未確認。
9月
信長、洛中の余部へ3ヶ条からなる禁制を発給。『余部文書』
禁制 四条
あまへ
一、当手軍勢濫妨・狼藉事、
一、陣執・放火之事、
一、伐採竹木幷非分之族申懸事、
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
永禄拾一年九月日 弾正忠(朱印)
(書き下し文)
一、当手軍勢乱妨・狼藉の事
一、陣取り・放火の事
一、竹木の伐採並びに非分のやからへ申し懸くるの事
右条々、違犯のともがらに於いては、速やかに厳科に処すべきものなり。仍って執達くだんの如し(以下略)
(備考)
余部は地名ではないようだ。
四条で営業した商工業者か。
9月
信長、賀茂社領の六郷へ3ヶ条からなる禁制を発給。『賀茂別雷神社文書』四
禁制 賀茂社領境内六郷
一、当手軍勢濫妨・狼藉之事、
一、陣取・放火・付非分課伇之事、
一、伐採山林・竹木之事、
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
永禄十一年九月日 弾正忠(朱印)
(書き下し文)
一、当手軍勢乱妨・狼藉の事
一、陣取り・放火、付けたり、非分へ課役の事
一、山林・竹木伐採の事
右条々、違犯のともがらに於いては、速やかに厳科に処すべきものなり。仍って執達くだんの如し(以下略)
(備考)
賀茂社とは賀茂別雷社(上賀茂社)と賀茂御祖社(下鴨社)の総称である。
下賀茂の祭神である玉依姫命は、別雷社の母にあたるので、御祖(みおや)とよばれている。
文中の賀茂社領境内六郷とは、河上・岡本・小野・大宮・小山・中村の各郷である。
内外から神戸の地として特別視されていたのか、他所に比べて守護・地頭などの押妨にはあまり遭わなかったようである。
なお、賀茂社に関しては今後織田氏との関りが深くなる。
特に元亀年間は、徳政の対象外となったことに腹を立てた郷民が一揆をやめないことで、奉行に当たった木下秀吉・塙直政らは手を焼いている。『賀茂別雷神社文書』『真珠庵文書』など
9月
信長、若王子社へ3ヶ条からなる禁制を発給。『若王子神社文書』二
禁制 若王子幷(□□□ 文字数不明)
一、当手軍勢濫妨・狼藉之事、
一、陣取・放火之事、
一、伐採竹木幷非分申懸之事、
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
永禄十一年九月日 弾正忠(朱印)
(備考)
内容はほぼ同じため読み下しは割愛。
若王子は今日も左京区若王子町に存在する神社。
若一王子は紀州熊野神社の祭神である。
9月
信長、離宮八幡宮へ3ヶ条からなる禁制を発給。『離宮八幡宮文書』三
禁制 大山崎
一、当手軍勢濫妨・狼藉之事、
一、伐採山林・竹木事、付、放火事、
一、為私相懸矢銭・兵粮米事、
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
永禄十一年九月日 弾正忠(朱印)
(書き下し文)
一、当手軍勢乱妨・狼藉の事
一、山林・竹木を伐採の事。付けたり、放火の事
一、私(わたしく)として矢銭・兵粮米を相懸くるの事
右条々、違犯のともがらに於いては、速やかに厳科に処すべきものなり。仍って執達くだんの如し(以下略)
(備考)
離宮八幡宮は今日も乙訓郡大山崎にあり、古来から交通の要衝として繁栄した。
北に天王山が聳え、淀川を挟んだ南には石清水八幡宮が鎮座する。
山崎の合戦の主戦場として名高い地域だが、古来からたびたび戦場の舞台となっている。
このたびの足利義昭軍と、足利義栄奉じる三好三人衆らが衝突したのもこの地域である。
9月29日には芥川山城や石成友通籠もる勝龍寺城が落ち、翌30日には富田城が落ち、10月に入ると池田城が落ちている。
この付近の狭い戦場を破られた後の勢いは、すさまじいものがあったであろう。
なお、足利義昭奉行人の和田惟政が11月21日付で大山崎惣中へ副状を発給している。『離宮八幡宮文書』三
当所事、任信長判形旨、陣取・乱妨在之間敷候、若狼藉仕者候者、為在所被搦取、可有注進候、恐々謹言、
十一月廿一日 和田伊賀守
惟政(花押)
大山崎惣中
(書き下し文)
当所の事、信長判形の旨に任せて、陣取り・乱妨これ在る間敷く候。
もし狼藉仕る者候はば、在所として搦め取られ、注進有るべく候。恐々謹言(以下略)
9月
信長、大徳寺へ3ヶ条からなる禁制を発給。『大徳寺文書』二
禁制 紫野
大徳寺同門前
一、当手軍勢濫妨・狼藉之事、
一、陣取、放火之事、
一、伐採竹木之事、
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
永禄十一年九月日 弾正忠(朱印)
(備考)
文章はほぼ同じため読み下しは割愛。
臨済宗大徳寺派の本山である大徳寺は、今日も北区紫野大徳寺町に存在する。
開基は大燈国師(宗峰妙超)は元応元年(1319)赤松則村(円心)の草創。
本能寺の変後、大徳寺の塔頭が羽柴秀吉によって創建された。
それが総見院である。
ここは信長の菩提寺として知られている。
9月
信長、妙心寺へ3ヶ条からなる禁制を発給。『妙心寺文書』六
禁制 妙心寺
一、当手軍勢濫妨・狼藉之事、
一、陣執、放火之事、
一、伐採竹木、幷非分申懸之事、
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
永禄拾一年九月日 弾正忠(朱印)
(書き下し文)
一、当手軍勢乱妨・狼藉の事
一、陣取り、放火の事
一、竹木を伐採、並びに非分へ申し懸くるの事
右条々、違犯のともがらに於いては、速やかに厳科に処すべきものなり。仍って執達くだんの如し(以下略)
(備考)
臨済宗妙心寺派の大本山である妙心寺は、右京区花園妙心寺町に所在。
「並びに非分へ申し懸くるの事」は非分の者へ課役等を申し懸くるの事の略。
妙心寺ものちに織田家と深いつながりを持つこととなる寺である。
9月
信長、南禅寺へ3ヶ条からなる禁制を発給。『南禅寺文書』九 (京都帝国大学国史研究室史料集)
(端裏書)
「信長公御朱印御制札」
禁制 南禅寺同門前
一、当手軍勢濫妨・狼藉之事、
一、陣取、放火之事、
一、伐採竹木、非分申懸之事、
右条々、違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
永禄十一年九月日 弾正忠(朱印)
(書き下し文)
禁制 南禅寺 同門前
一、当手軍勢濫妨・狼藉の事
一、陣取、放火の事
一、竹木の伐採、非分を申し懸くるの事
右条々、違犯のともがらは、速やかに厳科に処すべきものなり。仍って執達くだんの如し(以下略)
(備考)
東山にある南禅寺は、臨済宗南禅寺派の本山で、瑞龍山太平興国南禅寺ともいう。
最盛期には大小の子院も含め62を数える規模を誇ったが、応仁・文明の乱以後は荒廃の一途を辿った。
この永禄年中は、どの程度の規模であったかはよくわからない。
なお、少し南に下ると青蓮院や知恩院、清水寺がある。
これらの寺々も同じように信長に禁制の発給を求めている。『新知恩院文書』『成就院文書』など
9月
信長、知恩院へ3ヶ条からなる禁制を発給。『新知恩院文書』
禁制
一、当手軍勢濫妨・狼藉事、
一、陣執、放火之事、
一、伐採竹木、幷非分之族申懸事、
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
永禄拾一年九月日 弾正忠(朱印)
(備考)
ほぼ同じ内容のため、読み下しは割愛する。
この地は浄土宗の祖である法然ゆかりの地である。
浄土宗の総本山として知られ、華頂山知恩教院大谷寺ともいわれる。
応仁・文明の乱の際、近江の伊香立に本山を移すが、文明11年(1479)に帰洛。
この庵を新知恩院として戦国時代に至る。
奥野高廣著『織田信長文書の研究(吉川弘文館)』はこう記す。
“ここに現蔵の永禄十一年九月日付信長の禁制は、もと「東山知恩院」とあったのが「新知恩院」と抹消して書き変えられた。知恩院でも必要なこの禁制が、なぜ新知恩院に移ったのだろうか。新知恩院でも信長に申請すればよいのではないか(鈴木成元氏「新知恩院の禁制」『日本歴史』第二二一号)。”
9月
信長、清水寺へ3ヶ条からなる禁制を発給。『成就院文書』
禁制 清水寺同門前
一、当手軍勢濫妨・狼藉之事、
一、放火、付殺生之事、
一、伐採山林・竹木事、
右条々、違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
永禄十一年九月日 弾正忠(朱印)
(書き下し文)
禁制 清水寺同門前
一、当手軍勢濫妨・狼藉の事
一、放火、付けたり、殺生の事
一、山林・竹木伐採の事
右条々、違犯のともがらは、速やかに厳科に処すべきものなり。仍って執達くだんの如し(以下略)
(備考)
東山にある清水寺は法相宗の中本山で、音羽山清水寺と号す。
文書名にある成就院は本堂後方の谷の北方にあり、清水寺の住坊のようだ。
この時期、9月26日に足利義昭が清水寺に陣を敷き、芥川城を攻め落とした数日後の10月14日に、織田信長が同地を宿所としている。『言継卿記』『信長公記』など
9月
信長、東寺へ3ヶ条からなる禁制を発給。『東寺百合文書』せ六十五-九十七
禁制 東寺同境内
一、当手軍勢濫妨・狼藉之事、
一、陣執、放火之事、付、寄宿、
一、伐採竹木之事、
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
永禄十一年九月日 弾正忠(朱印)
(備考)
内容はほぼ同じなため読み下しは割愛する。
真言宗東寺派の総本山である東寺(教王護国寺)は、今日も京都駅すぐ南に存在する。
かつて桓武天皇が平安京へ遷宮した際、東寺の対を為す形で西寺もあった。
のちに嵯峨天皇が空海(弘法大師)にこの寺を与え、以後は真言密教の根本道場として栄えた。
平安から明治に至るまで、東寺は多くの文書を保存してきた。
東寺の子院によっても文書の保管先が異なるため、文書名も多岐にわたる。
その中でも特に有名なものが『東寺百合文書(とうじひゃくごうもんじょ)』・『教王護国寺文書』か。
出典元を記す際、あまり自信がない場合は『東寺文書』とするのが無難。
なお、同年9月26日に織田信長が東寺に陣を敷き、久我や山崎・勝龍寺近辺で阿波三好勢らと戦っている。
翌日には足利義昭が清水寺から東寺に移陣し、勝龍寺攻めの支度を整えている。『言継卿記』
9月
信長、清涼寺へ3ヶ条からなる禁制を発給。『清凉寺文書』
禁制 嵯峨郷清凉寺
一、当手軍勢濫妨・狼藉事、
一、陣執、放火、付、伐採竹木事、
一、為私矢銭・兵粮米申懸之事、
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
永禄拾一年九月日 弾正忠(朱印)
(書き下し文)
禁制 嵯峨郷清凉寺
一、当手軍勢乱妨・狼藉事
一、陣取り、放火、付けたり、竹木伐採の事
一、私として矢銭・兵粮米を申し懸くるの事
右条々、違犯のともがらに於いては、速やかに厳科に処すべきものなり。仍って執達くだんの如し(以下略)
(備考)
清凉寺は嵯峨嵐山のあたりに存在する浄土宗の寺院。
古くは嵯峨天皇の離宮があったところに皇子の左大臣源融が栖霞観(せいかかん)という山荘をつくり、のちにこれを寺としたことから棲霞寺(せいかじ)と号した。
この永禄年中は子院も含めてどの程度の規模があったのかはよくわからない。
9月
信長、遍照心院へ3ヶ条からなる禁制を発給。『大通寺文書』
禁制 西八条遍昭心院幷境内
一、当手軍勢濫妨・狼藉之事、
一、為私相懸矢銭・兵粮・非分之事、
一、陣取、放火、伐採竹木、田畠荒事、
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
永禄十一年九月日 弾正忠(朱印)
(書き下し文)
禁制 西八条遍照心院並びに境内
一、当手軍勢乱妨・狼藉の事
一、私として矢銭・兵粮を相懸け、非分の事
一、陣取り、放火、竹木の伐採、田畠を荒らす事
右条々、違犯のともがらに於いては、速やかに厳科に処すべきものなり。仍って執達くだんの如し(以下略)
(備考)
JR京都駅近くにある八条の大通寺は、真言宗の寺である。
源実朝の御台所が夫の死後、真言宗の僧を招いて髪をおろし、ここに菩提寺を建立した。
遍照心院という別名がつくのはそのためである。
9月
信長、本能寺へ3ヶ条からなる禁制を発給。『本能寺文書』二
禁制 本能寺
一、当手軍勢濫妨・狼藉之事、
一、陣取、寄宿、放火之事、
一、非分之輩申懸之事、
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
永禄十一年九月日 弾正忠(朱印)
(備考)
内容が同じであるため読み下しは割愛する。
いわゆる法華宗の京都における総本山が妙顕寺で、それを支える寺の一つに本能寺がある。
本能寺はもと本応寺といい、六角室町玉蔵町小袖屋宗句が300貫文を日隆に提供し、永享5年(1433)に六角以南、四条坊門北、櫛笥東、大宮西の地に建立された。
今はどうなのか分からないが、毎年6月2日に本能寺で開催される信長まつりの際、境内にある大寶殿宝物館の受付に無理を言って信長まつりのポスターがほしいと頼み込んで毎年のようにもらっていた。
そのポスターのデザインは毎年変わるのだが、ある年にそのデザインが上記の信長発給禁制があった。
私は子どもながらに大興奮したことを覚えている。
9月
信長、妙伝寺へ3ヶ条からなる禁制を発給。『妙伝寺文書』
禁制 妙伝寺
一、当手軍勢濫妨・狼藉之事、
一、陣取、放火之事、
一、伐採竹木、非分申懸之事、
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
永禄十一年九月日 弾正忠(朱印)
(備考)
内容が同じであるため読み下しは割愛する。
いわゆる法華宗の京都における総本山が妙顕寺で、それを支える寺の一つに妙伝寺がある。
この寺は文明9年(1477)に円教院日意によって京都一条尻切屋町の地に建立されたものである。
天正7年(1579)の安土宗論で法華宗が敗れた際、妙伝寺もほかの日蓮宗の寺々に名を連ねて、起請文を書かされている。
この時の妙伝寺は名代として日請が花押を据えている。
9月
信長、妙顕寺へ3ヶ条からなる禁制を発給。『妙顕寺文書』一
禁制 妙顕寺
一、当手軍勢濫妨・狼藉之事、
一、陣取、寄宿、幷伐採竹木之事、
一、放火、相懸矢銭・兵粮等非分之事、
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
永禄十一年九月日 弾正忠(朱印)
(備考)
内容が同じであるため読み下しは割愛する。
妙顕寺は京都における日蓮宗最初の道場である。
建立したのは日像という僧で、彼は日蓮の六弟子の中の1人である日朗の系統となる。
日像は京都に乗り込み、辻説法を行うが、他宗がこれを嫌い朝廷に訴える。
その結果、日像は追放に処されるが、赦免されると再び京都に戻り辻説法を繰り返した。
日像は追放・赦免を徳治2年(1307)・延慶3年(1310)・元亨3年(1321)の3度繰り返し、ついに妙顕寺を建立するに至った。
ここから京都を中心としたいわゆる法華宗の繁栄が始まる。
建武元年(1334)4月14日付の後醍醐天皇の綸旨を以て、妙顕寺は勅願寺となった。
さらに、日像の弟子たちが四条門流という門流を展開し、全盛期には京都に21ヶ寺の本山寺院が建立される。
このような経緯を経たことにより、南北朝時代以降、急速に信者を獲得したものの、他宗派とはしばしば軋轢を生み、訴訟へと発展したことも少なくない。
特に戦国時代は天文法華の乱の当事者となり、一時は朝敵とされて京都の出入りを禁じられたこともあった。
そのため、堺にも似た名前の寺がある。
6年間の朝敵期間を経て、天文11年(1542)に後奈良天皇の綸旨により、ようやく帰洛を許されることとなった。
しかしながら、その後も他宗派との関係は悪く、訴訟沙汰・武力衝突へと発展したことも少なくなかった。
信長や義昭が上洛戦を展開した永禄年中は、そのような情勢である。
9月
信長、摂津の本興寺へ3ヶ条からなる禁制を発給。『本興寺文書』
禁制 尼崎本興寺幷寺中
一、当手軍勢濫妨・狼藉之事、
一、陣執、放火之事、
一、伐採竹木之事、
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
永禄十一年九月日 弾正忠(朱印)
(備考)
内容が同じであるため読み下しは割愛する。
本興寺も法華宗本門流の大本山である。
尼崎の中心地に建立された細川京兆家ゆかりの寺である。
10月1日
足利義栄(阿州公方様)・細川真之(讃州御曹司)ら、篠原長房とともに阿波国へ落ち延びる。『細川両家記』
一、十月一日に阿州公方様、讃州御曹司様、三好彦十郎殿皆々篠原右京進調儀して阿州へ先々御下向也、
(書き下し文)
十月一日に阿州公方様(足利義栄)、讃州御曹司(細川真之)様、三好彦十郎(実休子息)殿皆々篠原右京進(篠原長房)と調儀して阿州へ先々御下向なり。
同日
山科言継、摂津郡山で織田勢(尾州衆)に捕らえた広橋兼勝娘(かか女一之采女)、小笠原貞慶妻を預かる。『言継卿記』永禄十一年十月一日条
廣橋妾かか女一之采女、信州小笠原妻、一昨日於攝州郡山尾州衆取之、今日内侍所へ預置之、予に可預之由申云々、思案之儀也、罷向尋之、先無事殊事、遂可及其沙汰事也、
(書き下し文)
広橋(広橋兼勝)妾のかか女一之采女、信州小笠原(小笠原貞慶)妻、一昨日摂州郡山において尾州衆これを捕らえる。
今日内侍所へ預け置く。
予に預けるべき由を申し云々。
思案の儀なり。
罷り向かいこれを尋ねる。
まずは無事こと無きの事、その沙汰を遂げ及ぶべきの事なり。
(備考)
「摂州郡山」は三島郡(現茨木市)の城か。
この頃
足利義昭と織田信長、堺南北惣中へ2万貫文の供出を命じるも、堺衆はこれを拒否。『細川両家記』
(備考)
文中にある(下記石山本願寺が5000貫文献上の項に記載)「堺南北」というのは、それぞれ北と南に荘が置かれていたことを意味する。
堺は摂津・和泉・河内の三国の境目にあることに由来する。
『堺市史』第三巻によると堺の南北二荘のうち、北荘は摂津国に属し、南荘は和泉国に属しているが、繁栄の中心地は南荘であったとある。
さらに、政所も南荘に置かれたことで、堺はもっぱら「和泉堺」「泉州堺南北」と記されるようになる。
この時から元亀年間にかけて、堺と織田氏は険悪な関係となり、やがて力を落とすに至る。
この頃
石山本願寺、足利義昭へ5000貫文を献上。『細川両家記』
一、今度東國衆攝州入之時、大勢山崎家々居取に亂妨之由候、此外國中郡山所々被相破候寺寺、吉所は以禮銭相課、大坂よりは五千貫分出之由候、
堺南北へも二万貫矢銭被相懸候處、不能承引、城樓を上、堀をほり、北の口々に樋を埋み候間、矢銭之儀相延由候、
(書き下し文)
一、この度東国衆(信長ナリ)摂州入りの時、大勢が山崎の家々居取に乱妨の由に候。
このほか国中の郡・山・所々を相破られ候寺々、吉所は礼銭を以て相課し、大坂(石山本願寺)よりは五千貫分これを出す由に候。
堺南北へも二万貫の矢銭を相懸けられ候ところ、承引能わず、城樓を上げ、堀をほり、北の口々に樋を埋み候間、矢銭の儀は相延べの由に候。
10月2日
足利義昭(武家)、芥川に陣を移す。『言継卿記』
(備考)
『信長公記』の記述は以下の通りである。
晦日、山崎御着陣、先陣ハ天神ノ馬場陣取、芥川尓細川六郎殿・三好日向守楯籠、夜尓入退散、幷篠原右京亮居城越水、瀧山是又退城、然間、芥川之城信長被成供奉、公方様被移御座、
『信長公記』巻一
(書き下し文)
(九月)晦日、山崎に御着陣。
先陣は天神の馬場に陣取る。
芥川に細川六郎殿・三好日向守(三好長逸)立て籠もる。
夜に入り退散す。
ならびに篠原右京亮が居城越水・瀧山もこれまた退城す。
然る間、芥川の城は信長に供奉なされ、公方様御座を移せらる。
このように、芥川攻略の日と越水・瀧山退城の日、芥川に移陣するを一緒にしてしまっている。
さらに、同文書は芥川攻略の日も正確に記していないようだ。
同日
摂津池田城が陥落。
池田勝正降伏する。『言継卿記』『多聞院日記』『細川両家記』など
武家以下芥川に御陣取云々、近日可有御上洛之由有之、池田、日向守等降参云々、
『言継卿記』永禄十一年十月二日条より
(書き下し文)
武家(足利義昭)以下芥川に御陣を取り云々。
近日御上洛有るべしの由これ有り。
池田(池田勝正)・日向守(三好長逸?)等降参し云々。
同九月卅日に上總介五万人計池田城取巻、火水と被攻候處、城の内より切て出、十四人討取、其外に手負數百人有之由候、其以後噯に成、知行二万石賜之、御所様へ被参候、然ば上郡高槻の入江方茨木方も御所様へ被参候上は一國平均也、
『細川両家記』
(書き下し文)
同九月三十日に上総介(織田信長)の五万人ばかり池田城を取り巻く。
火水と攻せられ候ところ、城の内より切って出、十四人を討ち取る。
そのほかに手負い数百人これ有るの由に候。
それ以後は扱いに成り、知行二万石これを賜り、御所様(足利義昭)へ参られ候。
然らば上郡高槻の入江方・茨木方も御所様へ参られ候上は一国平均なり。
十月二日に池田之城筑後居城へ御取かけ、信長ハ北之山尓御人数被備御覧候、水野金吾内尓無歴勇士梶川平左衛門とて在之、幷御馬廻の内、魚住隼人・山田半兵衛是も無歴武篇者也、両人争、先外構乗込、爰尓て押つおされつ暫之闘尓、梶川平左衛門骼をつかれて罷退討死也、魚住隼人も爰尓て手を負、被罷退ヶ様尓きひしく候之間、互尓討死数多在之、終尓火をかけ、町を放火候也、今度御動座之御伴衆、末代之高名と諸家存之士力日ころにあらた尓して戦て、如風發攻て如河決とハ夫是ヲ謂歟、池田筑後守致降参、人質進上之間、御本陣芥川之城へ御人数被打納、五畿内隣國皆以て被任御下知、
『信長公記』巻一
(書き下し文)
十月二日に池田の城、筑後(池田勝正)が居城へ御取りかけ、信長は北の山に御人数を備えられ御覧に候。
水野金吾(水野忠政カ)のうちに無歴の勇士梶川平左衛門とてこれ在り。
並びに御馬廻の内、魚住隼人・山田半兵衛これも無歴の武辺者なり。
両人争い、先に外構えに乗り込み、ここにて押しつおされつ、これをしばし闘うに、梶川平左衛門腰骨をつかれて罷り退き討死なり。
魚住隼人もここにて手を負い、罷り退かる。
かようにきびしく候之間、互いに討死数多これ在り。
しまいに火をかけ、町を放火し候なり。
この度御動座の御伴衆、末代の高名と諸家これを存じ士力(しりき)日頃にあらたにして戦いて、風の発する如く攻めて、河の決するが如しとは、それこれを云うか。
池田筑後守降参致す。
人質進上の間、御本陣を芥川の城へ御人数を打ち納められ、五畿内隣国皆もって御下知に任せらるる。
(備考)
両家記には30日とあるだけで、その他の記述はない。
池田氏は摂津池田城を根城とした豪族。
勝正は永禄6年(1563)2月、父長正の死去に伴い家督を継いだ。
通称名は八郎三郎。
家督継承後に筑後守を名乗る。『滝安寺文書』
ほかに「民部少輔」「勝政」とする史料もあるが、同一人物だろうか。
この件の『多聞院日記』は本年10月6日の項に記載。
三好家内紛の際は三好三人衆方に属し、松永久秀らとしばしば戦っている。『多聞院日記』『細川両家記』など
このたびの信長上洛軍に敗れたのは、徹底抗戦を貫いたからであろう。
近江を攻めて以来、日付に誤りがあった『信長公記』が、ここにきて正確な日付を記しだした。
同文書にある「水野金吾」は、25年も前に没した水野忠政のことだろう。
「水野金吾内」の表現はわかりかねるが、その子水野信元の家臣と見てよいだろう。
ほかにも水野家臣には梶川姓を名乗る人物が複数名いる。
梶川平左衛門はこの戦いで討死するが、その子高盛は天正元年(1573)7月の宇治・槇島の戦いで抜群の軍功を立て、信長より馬を賜っているようだ。『甫庵信長記』『寛永伝』『老人雑話』
信長馬廻の魚住隼人正は永禄3年(1560)5月の桶狭間の合戦時からすでにその名が見える。『信長公記』
この後も信長の側近として活躍し続け、取次や奉行などを歴任している。
「風の発する如く攻めて、河の決するが如し」は恐らく故事の引用であろう。
同日
信長、摂津・和泉の両国に矢銭を懸ける。(出展不明)
同日
松永久秀(松少)、足利義昭(公方)へ御礼のため国元を出発。『多聞院日記』
松少ハ公方へ爲御礼、今日にて八幡山迄被越了、
『多聞院日記』永禄十一年十月二日条
10月3日
畠山高政(両畠山)・松永久秀(松永弾正忠)・池田勝正(池田筑後守)、公家の竹内長治(三位入道)・入江氏ら、芥川に参向し足利義昭と織田信長に謁見。『言継卿記』『信長公記』
本領を安堵される。『多聞院日記』『細川両家記』『足利季世記』など
一方、阿波三好衆や筒井方に属していた井戸・窪之庄・豊田氏らは中坊駿河守の仲介により服属を申し出るも、義昭・信長はこれを拒絶。『多聞院日記』
一、當時一乗院殿も信長も芥川御入城候、然ば三好左京大夫殿霜臺も御所様信長へ芥川城にて御禮御申之由候、此とき左京大夫殿へは河内半國渡也、残半國は畠山殿へ渡由申候也、霜臺へは大和切取次第之由候、攝州は和田方、伊丹方、池田方へ之由風聞候也、
『細川両家記』
(書き下し文)
一、当時一乗院殿(足利義昭)も信長も芥川へ御入城に候。
然らば三好左京大夫殿(三好義継)霜台(松永久秀)も御所様(足利義昭)・信長へ芥川城にて御礼を御申すの由に候。
このとき左京大夫殿へは河内半国を渡すなり。
残る半国は畠山殿(畠山昭高)へ渡す由を申し候なり。
霜台へは大和を切り取り次第の由に候。
摂州は和田(和田惟政)・伊丹方、池田(池田勝正)方への由の風聞に候なり。
一、松少昨日上意幷織尾へ礼在之、和州一國ハ久秀可爲進退云々、依井戸・窪庄・豐田・筒与力十余人中坊駿河噯ニテ、號無事公方へ御礼ニ同道ノ處、尾州依無同心空下了、
一、郡山向井松少へ叉歸参了、當國大天广也、
『多聞院日記』永禄十一年十月五日条
(書き下し文)
一、松少(松永久秀)、昨日上意(足利義昭)並びに織尾(織田信長)へ礼これ在り。
和州一国は久秀の進退たるべく云々。
井戸・窪庄・豊田ら筒(筒井)与力十余人、中坊駿河より扱いにて、無事と号し公方へ御礼に同道のところ、尾州(織田信長)よりの同心無く空しく下りおわんぬ。
一、郡山向井松少へまた帰り参りおわんぬ。
当国の大天魔なり。
松永弾正者我朝無雙のつくもかみ進上申され、今井宗及是又無隠名物松嶋ノ壺幷紹鴎茄子進献、往昔判官殿一谷鉄皆かカケ召れし時之御鎧進上申者も在之、異國本朝之捧珍物信長へ御禮可申上と芥川十四日御逗留之間、門前成市事也、
『信長公記』巻一
(書き下し文)
松永弾正は我朝二つと無きのつくもがみ(九十九髪)を進上申され、今井宗及これまた隠れ無き名物松嶋ノ壺並びに紹鴎茄子を進献す。
往昔、判官殿(源義経)が一ノ谷鉄皆かかげ召されし時の御鎧を進上申す者もこれ在り。
異国本朝の珍物を捧げ、信長へ御礼申し上ぐべしと芥川に十四日御逗留の間、門前は市に成りし事なり。
(備考)
『言継卿記』の引用史料は本年10月4日項を参照のこと。
両家記にある霜台は弾正台の唐名である。
同じように左京職・右京職の唐名が京兆尹のため、史料によっては左京大夫を左京兆と記す場合もある。
『多聞院日記』は久秀が足利義昭に謁見する日を翌日の10月4日としている。
この中にある井戸氏ら大和の諸衆の動向は、他の史料にはあまりなくなかなか興味深い。
「郡山向井」についてはよくわからない。
「松少」は松永弾正少弼の略で、両家記に記される霜台と同義である。
『信長公記』の「芥川に十四日間滞在の間、門前は市のような盛況ぶりだったと」あるのは、決して誇張ではないように思える。
同月14日、義昭と信長は京へ戻るが、それ以降も両者の宿舎には、御礼を求める衆が終日列をなしていた様子が『言継卿記』等の史料に記されているからだ。
同日
山科言継、飛鳥井雅教(飛鳥井)と会談し、足利義昭(武家)の将軍宣下や参内等のことについて話す。『言継卿記』永禄十一年十月三日条
早々飛鳥井へ被呼之間罷向、武家将軍宣下御参内等可有之談合之子細共有之、爲武家之様體共可尋進之由有之云々、一盞有之、晩頭罷向、次於長橋局飛中等調手日記、
(中略)
手日記於燈下調之飛鳥へ遣之、長橋飛鳥等被申分也、
手日記
一、御元服之御禮沙金袋三包、銀之折敷に居、代三萬疋、
一、内侍所刀自以下之事、目録別有之、(千疋神供、千疋御師、九(六)百疋刀二人、三百疋女しゆ一人、此分也、
一、御四品、将軍宣下、宰相中将、禁色、御昇殿等之事、目六別有之、
一、初而御参内之時、御禮御太刀一腰、御馬、代萬疋、
一、七獻、獻之御進物之事、色目上意次第、
一、御直蘆長橋局へ二千疋、
一、御畳以下之事、卅餘状五千疋計、両替は半分、破損無正體之間内内被申云々、
以上
叉御服之事、被尋之間如此、
御参内之時
御烏帽子、御懸、御直垂、御大口、御扇、御袍、冬、御指貫、同、御腰、同、
此外
御冠、御懸、御大帷、御下袴、此三色御元服之時之可有之候、
10月4日
山科言継、信長の右筆明院良政に面会を申し出るも不調に終わる。
次いで飛鳥井雅教(飛鳥)らと芥川へ下向し、昨日の手日記目録を読み聞かせる。『言継卿記』
早々紹巴所へ罷向、菊一茎随身遣之、織田弾正忠物書明院に申度事有之間、雑掌可引合之由申之、堅故障之間不及是非、飛鳥辰刻芥川へ被参、被呼之間罷向、昨夕之手日記讀之、被合點了、烏丸父子、予、正親町等一二町室町迄送了、昨日竹内三位入道、兩畠山、松永弾正忠、池田筑後守等、武家、織田等に於芥川御禮被申云々、高槻之入江同前云々、
(書き下し文)
早々紹巴所へ罷り向かう。
菊一茎を随身しこれを遣る。
織田弾正忠(織田信長)の物書き明院(明院良政)に申したき事これ有るの間、雑掌引き合わすべしの由これを申す。
堅く故障の間是非に及ばず。
飛鳥(飛鳥井)辰の刻芥川へ参らる。
呼ばるるの間罷り向かう。
昨夕の手日記これを読む。
合点せられおわんぬ。
烏丸父子、予、正親町等一・二町室町まで送りおわんぬ。
昨日竹内三位入道、両畠山、松永弾正忠、池田筑後守等、武家(足利義昭)、織田等に芥川に於いて御礼を申され云々。
高槻の入江も同前と云々。
(備考)
紹巴所とは連歌師のいわゆる里村紹巴。
飛鳥は公家の飛鳥井雅教だろう。
烏丸父子は当時大納言の烏丸光康とその子光宣。
10月5日
公家の烏丸光康ら、芥川へ下向する。
飛鳥井雅教(飛鳥井黄門)、山科言継に御袍以下のことを信長被官の村井貞勝(織田雑掌村井)に伝えた旨を話す。『言継卿記』
烏丸芥川へ被参、父子、正親町等也、予、万里辨、富小路父子等室町迄送了、
飛鳥井黄門晩頭自芥川被歸了、罷向之處長橋局へ同道、一盞有之、御袍以下之事、織田雑掌村井直に申付云々、
(書き下し文)
烏丸芥川へ参らるる。
父子(烏丸光康・光宣カ)、正親町等なり。
予、万里辨、富小路父子らが室町まで送りおわんぬ。
飛鳥井黄門、晩頭に芥川より帰られおわんぬ。
罷り向かうのところ長橋局へ同道す。
一盞これ有り。
御袍以下の事、織田の雑掌村井(村井貞勝)へ直に申し付け云々。
(備考)
正親町とは権大納言を極官とする正親町三条家のことで、左大臣三条実房の三男公氏を祖とする。
本家三条氏と区別するため、正親町三条とよく呼ばれた。
当主の実福が昨永禄10年(1567)に正親町天皇の勘気を蒙って以降はよくわからない。
万里辨は弁官局を官職とする万里小路惟房であろう。
黄門は中納言の唐名である。
一盞は酒や食事を取ること。
袍はわたいれ、ぬのこの意で束帯姿の際の上着としても用いられる。
村井貞勝が早くも公家連中から雑掌として認識されていたことが興味深い。
10月6日
足利義昭(武家)と織田信長(織田弾正忠)、使者の正実坊を山科言継へ遣す。
正実坊、飯川信堅・三淵藤英発給の奉書を言継に渡す。『言継卿記』
武家幷織田弾正忠使に正實坊來、御袍以下之事内々談合、勧一盞了、三淵、飯川等折紙持來、
就御参内之儀、入可申御道具共之事、正實坊に被仰付被差上候、可然之様可被仰談由、得貴意可申旨被仰出候、恐々謹言、
十月五日 飯河山城守
信堅(判)
三淵大和守
藤英(判)
山科殿 人々御中
(書き下し文)
武家(足利義昭)並びに織田弾正忠(織田信長)の使に正実坊来たる。
御袍以下の事内々に談合。
一盞勧めおわんぬ。
三淵・飯川等の折紙持ち来たる。
「御参内の儀につきて、御道具ともに申し入るべきの事、正実坊に仰せ付けられ差し上げられ候。
然るべきのよう仰せ談ぜらるべきの由、貴意を得べしの旨を仰せ出され候。恐々謹言(以下略)
同日
松永久通(松右)、筒井城を攻め、城下を焼き払う。
筒井勢のうち、郡山衆が松永方へ寝返る。『多聞院日記』
一、 (ママ)松右人數筒井郷へ打出、平城ノ際迄焼了、郡山衆裏歸故也、一國之躰抑いかゝ可成行哉、無端々々、筒井順慶堅固ニ籠城ト云々、行末ハ難成事也、十市身上無事之由安堵之處、井戸置歟、無心元者也、
(中略)
一、攝州池田も降参申、山城・攝津・河内・丹波・江州悉以落居、昔も如此一時ニ将軍御存分ハ無之事歟、希代勝事也、
『多聞院日記』永禄十一年十月六日条
(書き下し文)
松右(松永久通)人数を筒井郷へ打ち出し、平城の際まで焼きおわんぬ。
郡山衆裏返る故なり。
一国の体、よくよくいかがに成り行くべきかな。
無端無端。
筒井順慶堅固に籠城と云々。
行く末は成し難き事なり。
十市の身上は無事の由に安堵のところ井戸置か。
心元無きものなり。
(中略)
一、摂州池田(池田勝正)も降参申す。
山城・摂津・河内・丹波・江州は悉く以て落居す。
昔もかくの如く一時に将軍御存分はこれ無き事か。
希代の勝事なり。
(備考)
松右は松永右衛門佐の略称である。
先述のとおり、池田城が降ったのは10月2日のこと。
多聞院がこれを聞き、真偽を確認して記述するに至ったのに4日を要したのであろう。
この文脈では、十市氏の身上は義昭・信長に安堵されたが、井戸氏はその限りではないということか。
しかし、同書の後日条では、十市氏の帰順交渉は難航している旨が記されている。
同日
信長、大和法隆寺に家銭として銀子150枚を当日中に納めるように指示する。
織田吉清ら4名、その意を汲んで法隆寺へ連署で奉書を発給。『法隆寺文書』四
昨日申渡候家銭之儀、銀子百五十枚、早々今日中可被相立候、若於延引者、若衆存分候間、不可然候、恐々謹言、
拾月六日
志水悪兵衛尉長次(花押)
奥村平六左衛門尉秀正(花押)
跡辺兵左衛門尉秀次(花押)
織田修理亮吉清(花押)
法隆寺寺家御中
(書き下し文)
昨日申し渡し候家銭の儀、銀子百五十枚、早々今日中に相立てらるべく候。
もし延引に於いては、若衆存分候間、然るべからず候。恐々謹言(以下略)
(備考)
この時期、信長が大和国に対してさまざまな税を課していることは『多聞院日記』にも記されている。
特に同文書の同年10月23日条には、奈良中に制札を下した礼銭として、1000貫文の供出を命じられたことを嘆く記述がある。
(その他の関連記事は本記事の同年10月27日の項、11月27日の項などを参照のこと)
恐らく数日後の大和出兵に際して敵をあぶりだす意図もあったのだろう。
家銭は矢銭と同じ意か。
この時奉行を受け持った織田吉清の詳細は不明。
織田一族の扱いを受けている様子がない。
彼と跡辺秀次、志水長次の3名は後にも先にも文書に姿を現すのはこれきりである。
『甫庵信長記』によると、奥村秀正ははじめ斎藤氏の臣だったようだ。
この時期は信長の奉行人となり、わずかではあるが本能寺の変まで史料にその名が見える。
同文書によると、翌年1月に起きた六条本国寺の戦いで高槻城から出陣し、一番首を挙げて賞されている。
その後は『宗及記』に登場していることを考えると、信長が岐阜に帰った後も摂津付近で奉行の職をこなし、文化人たちと交流を持っていたのかもしれない。
『武家事紀』によると、信長の死後は前田利家に仕えるが、奥村永福とは同族なのかは不明。
10月7日
[参考]『言継卿記』永禄十一年十月七日条
近所諏方信濃守昨夕上洛之間罷向、去夏御元服之時之御服共被請取之儀無之、如何之由相尋之處、書状共軈送之、定香取土佐守無沙汰相届歟之由被申之、別而上意御祝着之由有之、只今之御服以下之事者、織田申沙汰之間不存之由有之、一盞有之、
向陽春院へ正實坊罷向、予に可來之由申候間罷向、飛鳥井黄門、飯河山城守等、光源院殿御服共検知了、酒有之及數盃、武家下袴之絹、一疋、御大帷之布三丈八寸、予に渡之、
(書き下し文)
近所諏方信濃守(晴長)、昨夕上洛の間罷り向かう。
去夏御元服の時の御服共請け取らるるの儀これ無く、如何の由かと相尋ねるのところ、書状ともに軈てこれを送り、定めて香取土佐守が無沙汰を相届けるかの由これを申さる。
別して上意御祝着の由これ有り。
ただ今の御服以下の事は、織田の申し沙汰の間存せずの由これ有り。
一盞これ有り。
陽春院へ向かい、正実坊へ罷り向かう。
予に来たるべしの由を申し候間罷り向かう。
飛鳥井黄門、飯河山城守(飯川信堅)等、光源院殿(故足利義輝)の御服とも検知しおわんぬ。
酒これ有りて数盃に及ぶ。
武家下袴の絹(一疋)・御大帷の布三丈八寸、予にこれを渡す。
(備考)
諏方晴長・飯川信堅・香取土佐守は義昭側近。
「去夏御元服の時の御服が受け取ってもらえなかった」とあるのは、昨永禄10年(1567)4月15日に越前一乗谷で執り行われた足利義昭元服式に関するものだろう。『言継卿記』
この式典に言継も招かれていたが、何らかの行き違いにより参加を見送っている。
しかしながら、この時期には義昭も態度を改め、両者の関係は元通りとなったのだろうか。
足利義輝(光源院殿)が召していた衣服の丈を飯川信堅と公家の飛鳥井氏らが記憶していて、それを参考にしたのだろう。
義輝と義昭の背丈や体形は似ていたのかもしれない。
同文書には翌日にも陽春院(足利義輝の乳母か)へ向かい、義輝の服寸を見ている様子が記されているが割愛する。
この頃
三好義継(三好左京大夫)が河内飯盛山城に入城。『多聞院日記』
10月8日
織田信長、禁裏へ1万疋を献上か。『言継卿記』
織田弾正忠禁裏御不辨之由承及、内々萬疋今朝進上云々、
(中略)
黄昏大典侍殿御局へ参、御詫言之事御申頼存之由申之、
(書き下し文)
織田弾正忠(織田信長)禁裏御不便の由を承り及び、内々に万疋を今朝進上し云々。
(中略)
黄昏大典侍殿御局へ参る。
御詫言の事、御頼み申し存ずるの由これを申す。
(備考)
山科言継は足利義栄の将軍宣下へ動いた当事者の一人である。
事情が一変した今、詫言か蟄居か亡命かの決断に迫られていたのだろう。
同日
松永久秀(松少)、多聞山城に帰還。『多聞院日記』
一、飯盛城ニ三好左京大夫被入、松少今日此城へ歸了、奈良中へ人數不入之様申噯由也、先以安堵、乍去不可有此望云々、
『多聞院日記』永禄十一年十月八日条
(書き下し文)
飯盛城に三好左京大夫(三好義継)が入られ、松少(松永久秀)は今日この城へ帰りおわんぬ。
奈良中へ人数入れずのよう、申し扱うの由なり。
まず以て安堵。
さりながら、この望み有るべからず云々。
(備考)
『多聞院日記』の記主である英俊は、足利義昭・織田信長が大和国の筒井・十市などを討伐する風聞に接したのだろう。
大軍が入ると所領が荒らされる。
そうならないように和議の調停がなされているが、望みは薄いだろうとの見解を示している。
同日
[参考]『多聞院日記』永禄十一年十月九日条
一、昨日筒井ノ平城退了、今朝早々松右被打出了、高田殿多聞山へ礼ニ被上了、四年ほと籠城、布施ヨリ廻ニ十三押ノ城、惣ノマワリニ堀ヲ二重ホリ、モカリヲユヰ廻テ、二間・三間ニナルコヲ懸テヒキシク責了、雖然是ニ不落して開名了、一身ノ面目也、
10月9日
足利義昭側近の松田頼隆と松田秀雄、仁和寺へ所領安堵の奉書を連署で発給。『仁和寺文書』五
(附箋)
「永禄十一 義昭公」
当御門跡領所々散在・同境内等事、任当知行之旨、弥可令全領知給之由、被仰出候也、仍執達如件、
永禄十一
十月九日 秀雄(花押)
頼隆(花押)
御室御門跡雑掌
(書き下し文)
当御門跡領の所々散在・同じく境内等の事、当知行の旨に任せて、いよいよ全く領知せしめ給うべきの由を仰せ出され候なり。仍って執達くだんの如し(以下略)
同日
信長、前述の義昭側近の連署奉書をうけて、仁和寺へ副状を発給。『仁和寺文書』五
当御門跡領所々散在・同境内等事、被任御下知之旨、御領知不可有相違之状如件、
永禄十一
十月九日 弾正忠
信長(朱印)
御室御門跡雑掌
成多喜御坊
(書き下し文)
当御門跡領の所々散在・同じく境内等の事、御下知の旨に任せられ、御領知相違有るべからざるの状くだんの如し(以下略)
(備考)
「御室御門跡」は任助法親王。
その領知経営の事務を司る雑掌が宛所となっているが、無論実質的な宛所は親王である。
仁和寺は仁和4年(888)に、先代の意志を継いだ宇多天皇によって建立された真言宗御室派の総本山である。
宇多天皇は譲位ののち、この寺の南方に居室をつくり、そこを住まいとしたので、御室御所と呼ばれるようになった。
丹州街道の入り口に位置するためか、戦国期にはたびたび戦火に見舞われている。
同日
日野輝資(日野)、摂津芥川の足利義昭・織田信長に礼参のため下向する。『言継卿記』
日野今朝芥川へ御禮に下向、烏丸父子被來、令同道一條迄送之、
(書き下し文)
日野(日野輝資)今朝芥川へ御礼に下向す。
烏丸父子(烏丸光康・光宣)も来らる。
同道せしめ一条までこれを送る。
10月10日
佐久間信盛(佐久間)・細川藤孝(細川兵部大輔)・和田惟政(和多伊賀守)ら、2万の兵で大和国招提寺辺りに布陣。織田勢は各所の社を訪れる。
大和森屋城に入るか。『多聞院日記』
京ヨリ細川兵部大輔・和多伊賀守公方方ノ兩大将、佐久間織田尾張守方大将、以上二万ほとにて西京招提寺邊へ打越了、今日ハ何方へも人數不遣之、窪城之城開了、井戸・柳本・豐田・森屋・十市・布施・楢原・万歳ハ今日迄ハ城堅固ニ被持了、
(中略)
尾張衆所々社参了、奈良中堅被申付間穏便也、併神慮迄也、珍重々々、
『多聞院日記』永禄十一年十月十日条
(書き下し文)
京より細川兵部大輔・和田伊賀守(公方方の両大将)、佐久間(織田尾張守方の大将)、以上二万ほどにて西京招提寺辺りへ打ち越しおわんぬ。
今日はいずれ方へも人数を遣わさず。
窪城の城は開けおわんぬ。
井戸・柳本・豊田・森屋・十市・布施・楢原・万歳ハ今日迄は城堅固に持たれおわんぬ。
(中略)
尾張衆所々の社へ参りおわんぬ。
奈良中へ堅く申し付けらるの間穏便なり。
併わせて神慮までなり。珍重珍重。
(備考)
森屋城の記述は翌11日の『多聞院日記』を参照のこと。
「奈良中へ堅く申しつけらるの間穏便」とあるのは、奈良中に禁制が下されているとの意か。
同日
三河徳川家康の名代として松平親乗(松平和泉守)が上洛。
礼として山科言継へ樽代三十疋を贈る。
親乗はその日の内に国元へ下向する。『言継卿記』
三川國松平和泉守上洛とて、門外迄禮に來、樽代三十疋送之、於門外對面了、誓願寺に寄宿云々、彼寺西堂玄易被同道、
松平所へ澤路隼人佑使に遣之禮申之、則今日下向云々、織田手前無殊之間先下向云々、
(書き下し文)
三河国松平和泉守上洛とて、門外まで礼に来たる。
樽代三十疋これを送る。
門外に於いて対面しおわんぬ。
誓願寺に寄宿と云々。
かの寺西堂玄易も同道せらる。
松平所へ澤路隼人佑使に遣し礼を申す。
則ち今日下向と云々。
織田手前こと無きの間、まずは下向すと云々。
同日
陽春院、村井貞勝家臣(村井若党)と織工(織手)を連れて山科言継を訪問。
足利義昭(武家)の衣服や指貫・直垂について尋ねる。『言継卿記』永禄十一年十月十日条
自陽春院使被相副、尾州之村井若黨、織手両人召具來、武家御袍・御指貫・御直垂等之事、種々尋之間、各令對面申聞候了、
(書き下し文)
陽春院より使を相添えられ、尾州の村井若党、織手両人を召し連れ来たる。
武家(足利義昭)の御袍・御指貫・御直垂等の事、種々に尋ねるの間、各々対面せしめ申し聞かせ候おわんぬ。
(備考)
陽春院は足利義輝の乳母か。
10月11日
信長、堀秀政(久太郎)に消息を出す。『本国寺文書』二
信長公、惣構土手寄附之時之状、
土手万端油断有間敷候、
普請無油断之旨、委細心得候、近日可帰候、尚其節見物候之条、いよいよ馳走尤候、可しこ
十一日
久太郎
(書き下し文)
信長公、惣構え土手寄附の時の状
土手万端油断有るまじく候。
普請油断無きの旨、委細心得候。
近日帰るべく候。
なおその節見物候の条、いよいよ馳走もっともに候。かしこ(以下略)
(備考)
宛所の堀秀政は信長の側近である。
消息のためか署名と花押影はない。
また、「殿」も「とのへ」もない。
足利義昭は3日後となる10月14日に、本国寺を御座所とする。
どうやら本国寺では、この10月に境内の大土手を築く普請をしていたようだ。『本圀寺志』
まさかそれが大きな効果を生むことになるとは、どれほどの者が思っていただろうか。
なお、奥野高廣著『織田信長文書の研究(吉川弘文館)』によると、”この信長の消息は自筆かもしれない”とある。
同日
足利義昭・織田信長に属する軍勢、井戸表へ兵を繰り出す。『多聞院日記』
昨日森屋渡了、今日窪城迦了、井戸表へ諸勢打寄了、噯在之云々、弥三郎高田へ下了、今井筋ノ事也、
『多聞院日記』永禄十一年十月一十一条
(備考)
森屋城はもとは秋山氏の拠点か。
同永禄11年2月20日の『多聞院日記』には「十市が支配する森屋城が落ちた」とある。
この時松永方であった秋山直国(家慶)が十市遠勝から城を奪い返したのだろうか。
であるならば、秋山氏の森屋に足利義昭・織田信長に属する軍勢が入り、昨日開城させた窪城(窪之庄城)を検分したのだろうか。
添上郡の井戸城は、当時筒井方に属する。
歴代の井戸氏はたびたび「良弘」を諱としている。
彼は筒井順昭の娘を妻としているため、順慶とは義兄弟の間柄である。
以降の文脈はよくわからないが、このとき井戸が降伏したのだろうか。
なお、窪ノ庄と井戸は、同月3日か4日に足利義昭に謁見し、服属を申し出るが拒否されている。『多聞院日記』永禄十一年十月五日条
10月12日
織田家被官の蜂屋頼隆(蜂屋兵庫頭)・森可成(森三左衛門尉)・坂井政尚(坂井右近将監)・柴田勝家(柴田修理亮)が連署で某所に禁制を発給。『武家事紀』中
禁制
一、当手之軍勢乱妨・狼藉之事、
一、猥山林・竹木伐採事、
一、押買・押売・追立夫等之事、
右条々、於違犯之輩者、速処厳科者也、仍如件、
永禄十一年十月十二日 柴田修理亮
坂井右近将監
森三左衛門尉
蜂屋兵庫頭
(書き下し文)
禁制
一、当手の軍勢乱妨・狼藉の事
一、猥りに竹木・山林を伐採の事
一、押し買い・押し売り・追立夫等の事
右条々、違犯のともがらに於いては、速やかに厳科に処すものなり。仍ってくだんの如し
永禄十一年十月十二日 柴田修理亮
坂井右近将監
森三左衛門尉
蜂屋兵庫頭
(備考)
どこへ発給されたのか判然としない。
『武家事紀』のみのため、花押影や具体的な宛所がない。
しかしながら、この時期に柴田・坂井・森・蜂屋の4名が京~摂津を中心にチームを組んで活動していたことはその他の史料からも明らかである。
真実だと断定できるほど史料が豊富ではなく、虚説だと言い切れるほど矛盾しているわけでもない。
「追立夫」は強制的に農民などを人夫にかりだすこと。
またはかりだされた者を指す。
「おったてぶ」とする読みは、促音化させたに過ぎない。
どちらで読んでも誤りではない。
同日
足利義昭・織田信長に属する軍勢、大和柳本城を攻める。『多聞院日記』
柳本へも先衆打出了、堅固ニ在之云々、十市儀内々噯在之、幾度探雖取之、不可調トアリ、
『多聞院日記』永禄十一年十月一十二条
(書き下し文)
柳本へも先衆打ち出でおわんぬ。
堅固にこれ在りと云々。
十市の儀、内々に扱いこれ在り。
幾度もこれを探り取るといえども調うべからずとあり。
(備考)
式上郡にある柳本城は黒塚古墳の上にある。
古墳の周りには堀らしき跡があり、平地に居館を築くならば好都合の地であろう。
当時は十市氏の持城か。
同史料の十月二十一日条には、柳本氏が「多聞へ裏帰」とある。
十市氏の帰順の交渉が進展しないのを見て、先に降ったのかもしれない。
十市郡十市郷を拠点とする十市遠勝は、当時阿波三好衆や筒井方に属する勢力。
これまで激しく松永久秀と交戦してきた十市氏であるが、ここにきて足利義昭の威光に伏そうとしているのだろう。
翌年に彼は没するが、その後に指導者となった十市常陸介との関係は定かではない。
さまざまな史料に頻繁に登場する割には、謎の多い一族である。
10月13日
足利義昭奉行人の松田頼隆・松田秀雄が、久我荘名主百姓中へ奉書を発給。『久我文書』四
久我家雑掌申、城州築山下司・公文分事、可被遂御糺明之子細在之条、年貢・諸公事物等、堅可相拘候、若於他納者、二重成之上、可被加御成敗之由、所被仰出之状如件、
永禄十一
十月十三日 秀雄(花押)
頼隆(花押)
当所名主百姓中
(書き下し文)
久我家雑掌へ申す。
城州築山の下司・公文分の事、御糺明を遂げらるべきの子細これ在るの条、年貢・諸公事物等、堅く相拘うべく候。もし他納に於いては、二重に成るの上、御成敗を加えらるべきの由、仰せ出さるる所の状くだんの如し(以下略)
(備考)
ここでの「相拘うべく」とは、久我家以外に他納することを防ぐために、調査が済むまでどこへも納めず、保管しておけとの通達である。
この文書に関連する内容は、同年10月20日の項を参照のこと。
同日
足利義昭・織田信長に属する軍勢(他国衆)、観禅院に陣取るか。『多聞院日記』
及晩観禅院ノハヤ鐘ツク、何事トモ不知、他國衆寺内可陳取ト申間其押ト云々、仰天了、
『多聞院日記』永禄十一年十月十三条
(書き下し文)
晩に及び観禅院の早鐘つく。
何事とも知らず。
他国衆が寺内を陣取るべしと申す間、それを押すと云々。
仰天しおわんぬ。
(備考)
観禅院は多聞院と同じく、興福寺の塔頭の一つか。
乱妨・狼藉があったのかは不明。
同日
[参考]『言継卿記』永禄十一年十月十三日条
安禅寺殿昌蔵主被來、於長橋局御寺之支證共撰事被申之間、則参撰之、織田弾正忠に爲訴訟之用云々、
(書き下し文)
安禅寺殿昌蔵主来らる。
長橋局に於いて御寺の支証ともに選り事申さるるの間、則ちこれを選り参る。
織田弾正忠に訴訟たるの用と云々。
(備考)
安禅寺殿昌蔵主という者が、織田信長に対して何かを訴え出る意図があったのだろうか。
10月14日
足利義昭上洛。
法華宗の六条にある本国寺に移る。
信長は清水寺を宿所とする。『言継卿記』『信長公記』
今日自芥川武家御上洛云々、六條本國寺江被移御座云々、烏丸父子、日野等御迎に被参了、未刻各被帰了、
廣橋亜相南都上洛、去夜八幡に逗留云々、今日出京、
(書き下し文)
今日芥川より武家(足利義昭)御上洛し云々。
六条本国寺へ御座を移せられ云々。
烏丸父子(烏丸光康・光宣)、日野(日野輝資)等御迎えに参られおわんぬ。
未刻に各々帰られおわんぬ。
広橋亜相南都より上洛。
去夜は八幡に逗留と云々。
今日出京。
(備考)
『信長公記』の記述は同月18日の項にまとめた。
同日
足利義昭・織田信長に属する軍勢、柿森・結崎の辺りを焼き払う。『多聞院日記』
今日柿森・結崎之邊焼云々、國中不依敵味方、大略焼ト見タリ、
『多聞院日記』永禄十一年十月十四条
(書き下し文)
今日柿森・結崎の辺りが焼け云々。
国中敵味方によらず、大略は焼けたと見たり。
(備考)
柿森がどこかはわからないが、結崎は式下郡(現磯城郡川西町)にある地か。
この地域の東が恐らく十市氏の所領であろう。
この頃
将軍足利義栄病死か。
(備考)
現職の将軍として残念だが正確な没日は不明である。
10月15日
山科言継ら公家連中、足利義昭の宿す本国寺を見舞う。
次いで清水寺の信長を訪ねるが、多忙により会えず。『言継卿記』
葉室巳刻出京都、令同道参本國寺、倉部召具、葉室馬三疋有之、三人乗之、聖護院新門主、左大将、予、庭田、葉室、若王子、三條兒、倉部、水無瀬少将、理性院、萬松軒以下僧俗數十人御禮申之、申次一色式部少輔、細川兵部大輔兩人也、予、葉(「室」脱カ)倉部等御太刀金、或絲巻、法中御扇、杉原、巻数等重畳有之、次清水寺本願所へ罷向、左大将、予、庭田、葉室、倉部等也、不及對面、取亂云々、明院に申置了、諸家禮者群集也、五人令同道歸了、葉室軈被歸在所了、於此方晩湌各用意、供廿餘人有之、
『言継卿記』永禄十一年十月十五日条
(書き下し文)
葉室巳刻に京都を出る。
同道せしめ本国寺に参る。
倉部を召し連れ、葉室と馬三疋これ有り。
三人これに乗る。
聖護院新門主(聖護院尊澄法親王)、左大将、予、庭田(庭田重保)、葉室(葉室頼房)、若王子、三條兒、倉部、水無瀬少将(水無瀬兼成)、理性院、萬松軒以下、僧俗数十人御礼申す。
申次は一色式部少輔(一色藤長)、細川兵部大輔(細川藤孝)両人なり。
予、葉室、倉部等御太刀(金)、或は絲巻き、法中御扇、杉原(杉原紙)、巻数等重畳これ有り。
次いで清水寺の本願所へ罷り向かう。
左大将、予、庭田、葉室、倉部等なり。
対面及ばず、取り乱し云々。
明院(明院良政)に申し置きおわんぬ。
諸家の礼者群集なり。
五人同道せしめて帰りおわんぬ。
葉室はやがて在所に帰られおわんぬ。
此方に於いて晩湌各々用意。
供は二十余人これ有り。
(備考)
この日、公家連中が礼物を持参して六条にある本国寺を訪問。
足利義昭側近の一色藤長と細川藤孝の取次(申次)のもとで戦陣を見舞った。
次いで清水寺へ向かうも、周辺の国々から信長に面会を求める客でいっぱいだったとある。
本国寺は義昭が宿し、清水寺には信長が宿していたのだろう。
ここに見える明院とは、信長の書記官を務める明院良政である。
この時期の義昭と最大のスポンサーである信長の勢いが窺える。
同日
足利義昭・織田信長に属する軍勢、大和豊田城を攻め落とし、菩提山を放火。諸方へ刈り田を行う。『多聞院日記』
豊田城落了、菩提山放火ニて云々、諸方苅田沙汰と見、咲止々々、
『多聞院日記』永禄十一年十月十五条
(書き下し文)
豊田城落ちおわんぬ。
菩提山放火にて云々。
諸方苅田沙汰と見ゆ。
笑止笑止。
(備考)
豊田城(現天理市)は井戸城の近く。
少し南に下ると柳本城や龍王山城がある。
10月16日
足利義昭(武家)、七騎を従えて細川亭に移る。
織田信長(織田弾正忠)は古津所に移る。『言継卿記』
巳刻武家細川亭へ被移了、御供七騎云々、織田弾正忠古津所此間入道殿御座、移了、猛勢云々、
久我内信濃兵部丞來、武家御袍以下織手小島子禮に來、令同道御袍之事可然之様頼入之由申之、三十疋送之、
『言継卿記』永禄十一年十月十六日条
(書き下し文)
巳刻、武家(足利義昭)が細川亭へ移られおわんぬ。
御供は七騎と云々。
織田弾正忠(織田信長)古津所(この間入道殿御座)へ移りおわんぬ。
猛勢云々。
久我の内、信濃兵部丞来たる。
武家御袍以下織手小島子礼に来たる。
同道せしめ御袍の事然るべきのよう頼み入るの由を申す。
三十疋これを送る。
(備考)
『永禄記』にもこの記述が見える。
同文書によると、この「細川亭」とは細川右京兆の旧宅のようだ。
古津所と入道殿は誰を指すのか不明。
分かり次第追記したい。
信濃兵部丞の諱は「治毘」。
読みはわからない。
久我家の老臣の一人で、奉行をよく勤めている。
同年十一月四日付で他の奉行人とともに、久我家の領所を私曲なく所務する旨を誓約している。『久我文書』
[参考]『多聞院日記』永禄十一年十月十六日条
備前衛門二郎、十市儀無為調由申ト、不審也、
10月17日
山科言継、織田信長(織田弾正忠)と足利義昭(武家)を訪問するも、多忙により不調に終わる。『言継卿記』
織田弾正忠所へ罷向之處、取亂之由申之、以飯田内々申之如此、仍武家へ参、御禮申之輩數多、僧俗不知數也、以一色式部少輔、祐阿等申入了、不及對面也、
及黄昏、武家御袍同御腰御指貫等織出之間、正實坊持來了、
『言継卿記』永禄十一年十月十七日条
(書き下し文)
織田弾正忠(織田信長)所へ罷り向かうのところ、取り乱すの由これを申す。
飯田を以て内々にかくの如くを申す。
仍って武家(足利義昭)へ参る。
御礼申すのともがら数多、僧俗は数知れずなり。
一色式部少輔(一色藤長)を以て、祐阿等に申し入れおわんぬ。
対面は及ばずなり。
黄昏に及び、武家の御袍同じく御腰、御指貫等織出の間、正実坊持ち来たりおわんぬ。
(備考)
ここに見える「飯田」とは信長奉行衆の1人。
谷口克広著『織田信長家臣人名辞典(吉川弘文館)』によると、飯田宅重(いえしげ)とは別人として扱っているが、同一人物かもしれないとの記述もある。
飯田宅重(弥兵衛)は弘治3年(1557)4月9日に、信長より飯田彦太郎の跡職と所領を宛行われて以来、史料にはほとんど姿を現さなくなる。
以後、この「飯田」と山科言継との関りは永禄12年(1569)7月まで続く。『言継卿記』
足利義昭、征夷大将軍となる
10月18日 夜
足利義昭、第15代征夷大将軍に任ぜられる。
夜に室町殿左馬頭源朝臣義昭・征夷将軍・参議・左近中将・従四位下・禁色・昇殿の6ヶ条の陣宣下を受ける。『御湯殿上日記』『言継卿記』
信長、足利義昭が宝鏡寺を尋ねる際、これに同道する。『言継卿記』

今夜将軍宣下有之、日野参陣辨也、仍罷向折重調之、一盞有之、次萬里小路右大辨宰相奏慶也、衣文之事被申候間、罷向折重調之、一盞有之、酉下刻萬里小路へ罷向、右大辨束帯令着之、次庭田へ罷向束帯令着之、一盞有之、次向日野へ罷向令着之、又一盞有之、次高辻へ罷向、坊城令着之、次甘露寺於萬里小路被着之間罷向之處、二獻也、同三獻等に逢了、次甘露寺に令着之、次参内了、室町殿左馬頭源朝臣義昭、征夷将軍、参議、左近中将、従四位下、禁色、昇殿等六ヶ條陣宣下、小叙位小除目等有之、上卿源中納言、右筆右大辨宰相、奉行職事頭辨経元朝臣、参陣辨権左小辨輝資、大内記菅盛長、大外記師廉朝臣、左大史朝芳宿禰以下、六位外記、史、内記等皆参也、作法無殊事之間不及注、御警固伊勢守者也、於御末入麺一盞有之、次於常御所御庇御通有之、御酌伊與局、被参之輩中山前大納言、萬里小路大納言、予、持明院宰相、新宰相中将、爲仲朝臣、親綱朝臣、雅英、橘以繼等也、大樹正五下先日之分也、可為消息宣下、六ヶ條之儀餘過分也、禁色昇殿、後日消息宣下可然之儀也、自大内記大帷・太刀・沓下・襲襟等、従日野裾薄、下襲襟石帯沓、官務石帯玉、等借用之間遣之、自飯田方今日織田所へ可同道之由申候間、巳刻彼旅宿へ罷向令同道、但寶鏡寺殿へ武家御成、織田同道之由有之間、彼御寺へ参、奉公衆入麺有之、於御前御酒有之、織田弾正忠に同道申之了、
『言継卿記』永禄十一年十月十八日条
十四日芥川より公方様御歸洛、六條本國寺被成御座、天下一同尓開喜悦之(属?)訖、信長も被成御安堵之思、當手之勢衆被召列直尓、清水へ御出、諸勢洛中へ入候てハ、下々不届族も可在之哉之被加御思慮警固ヲ洛中洛外へ被仰付、猥儀無之、既畿内之逆徒等數ヶ所城郭を溝、雖相支風尓草木之靡ヵ如、十餘日之内尓悉退散シ、天下属御存分細川殿屋形御座として、信長被成供奉、於御殿御太刀・御馬御進上、忝も御前へ信長被召出、三献之上、公儀御酌尓て御盃幷御劔御拜領、
『信長公記』巻一
(書き下し文)
十四日芥川より公方様(足利義昭)御帰洛す。
六条本国寺に御座なされ、天下一同に(「開喜悦之(属?)」おわんぬ。
信長も御安堵の思いをなされ、当手の勢衆を召し列れられ、直に清水(清水寺)へ御出、諸勢洛中へ入り候ては、下々届かぬやからもこれ在るべきかなの御思慮を加えられ、警固を洛中洛外へ仰せ付けられ、猥りな儀はこれ無し。
既に畿内の逆徒等は数ヶ所城郭を構え、相支えるといえども、風に草木の靡くが如く、十余日の内に悉く退散し、天下は御存分に属す。
(足利義昭は)細川殿の屋形を御座として、信長供奉成され、御殿に於いて御太刀・御馬を御進上。
忝も御前へ信長を召し出され、三献の上、公儀の御酌にて御盃並びに御剣を御拝領す。
(備考)
『言継卿記』の読み下しは後日行う。
消息宣下とは陣儀を招集せずに上卿以下が在宅のまま手紙の遣り取りによって持ち回り形式で宣下するもの。
つまり、太政官や院庁が発する公式な命令を消息(手紙)形式の文書で行う略式の手続きを取る。
鎌倉時代以降、陣儀での宣下は親王宣下や摂関等の高官に限られるようになり、それ以下の職は消息宣下による命令交付が主流となった。
今回の『言継卿記』には消息宣下で6ヶ条の陣宣下は過剰であるので、禁色昇殿については後日行われると記されている。(実際に義昭の参内は同月22日に行われている)
同文書にある「宝鏡寺(殿)」は尼僧である。
近衛尚通の娘であり、腹違いの姉妹の1人に足利義輝・義昭生母の慶寿院がいる。
つまり、義昭は将軍宣下のその日のうちに叔母に会いに行ったことになる。
10月19日
山科言継、足利義昭へ将軍御四品の位記を渡す。
中原師廉(師廉朝臣)・壬生朝芳(官務朝芳)は宣旨を渡す。『言継卿記』永禄十一年十月十九日条
東坊城被呼朝飡、雖精進餘醉、度々被申候間、倉部同道、高辻、坊之兄宗林等相伴了、次今日将軍御四品之位記持参之間、束帯令着之、同局務師廉朝臣、官務朝芳宿禰等宣旨持参云々、同束帯也、
(書き下し文)
東坊城に朝食に呼ばる。
精進するといえども、余酔う。
たびたび申され候間、倉部が同道し、高辻、坊之兄宗林等も相伴いおわんぬ。
次いで今日将軍御四品の位記を持参の間、束帯これを着けせしむ。
同局務の師廉朝臣(中原師廉)、官務の朝芳(壬生朝芳)、宿祢等は宣旨を持参し云々。同じく束帯なり。
(備考)
「位記(いき)」とは位を授けられる者が与えられる文書のこと。
宿祢についてはよくわからない。
同日
松永勢ら、4ヶ所2城を攻撃する。
その他の織田・足利勢は南方へ進撃。『多聞院日記』永禄十一年十月十九日条
井戸表ニハ白土、城山サキ、豊田ニ秋山ノマ、森本多聞衆成福院四ヶ所ニ押城拘之、今日諸勢引退南へ遣之、布施行ト申、不知、日中前より雨下了、
10月20日
足利義昭奉行人の諏方俊郷・松田頼隆が、久我荘名主百姓中へ奉書を発給。『久我文書』四
久我家雑掌申、城州久我庄内森分事、為旧領之上者、退他妨、如先々対彼雑掌可致其沙汰由、所被仰出之状如件、
永禄十一
十月廿日 頼隆(花押)
俊郷(花押)
当所名主百姓中
(書き下し文)
久我家雑掌へ申す。
城州久我庄内森分の事、旧領たるの上は、他の妨げを退け、先々の如くかの雑掌に対し、その沙汰を致すべきの由を仰せ出さるる所の状くだんの如し(以下略)
(備考)
文中の「森分」とは、久我家雑掌である森氏旧領の意。
「他の妨げを退け」とは、これに異を唱えて訴え出ているものの意見を排しの意。
これは同年10月13日に同所へ発給された足利義昭奉行人奉書に関するものである。『久我文書』
13日付では、他納して二重払いになる可能性があるので、年貢・諸公事物等はどこへも納めずに保管しておくようにとの通達であった。
久我家の領地関係の糺明(詳しく調査)した上で出されたのがこの判物だろう。
詳細は同日付の信長が久我晴通(宗入)へ発給した書状で述べる。
同日
織田信長、久我晴通(宗入)へ安堵状を発給。『久我文書』五(永禄十一年十月二十日付織田信長朱印状写)
久我殿御知行分事
一、久我上下庄・樋爪入組・所々散在、本役・加地子分一職之事、
一、同所森分之事、
一、東久世庄築山一職之事、
一、大藪庄寺庵・御被官人・名主等一職之事、
一、勢多分直務之事、
依御旧領、無紛如此被成御下知上者、悉以一円全可有領知事、肝要存之状如件、
永禄十一年十月廿日 織田弾正忠
信長御朱印
(書き下し文)
久我殿御知行分の事
一、久我上下庄・樋爪の入り組み・所々散在、本役・加地子分一職の事
一、同所森分の事
一、東久世庄築山一職の事
一、大藪庄寺庵・御被官人・名主等一職の事
一、勢多分直務の事
御旧領により、紛れ無くかくの如く御下知を成さるるの上は、悉く以て一円に全く領知有るべき事、肝要に存ずるの状くだんの如し(以下略)
(おおまかな語訳は下記の通り)
久我家の御知行分は
1.久我上下庄・東寺領樋爪の入り組んだ分の収得権、所々に散在している年貢(本役)や・それ以外の租税(加地子分)をすべて(一職)
2.久我荘雑掌である森氏の管理分
3.東寺領の東久世庄と同築山庄で、久我家が知行する分
4.東寺領の大藪庄の寺庵・被官人・名主らの収得権のうち、久我家が知行する分
5.勢多判官の分は、久我家が直接管理する
以上が久我家の前々からの所領であるので、幕府はすべてこれを保証する。
(備考)
これは、同日付で幕府奉行人が発給した判物に副えた安堵状である。
久我晴通は近衛尚通の次男。
久我邦通が嗣子無く没したので、享禄4年(1531)に久我家に養子入りした。
近衛尚通の娘は足利義輝・義昭生母である。
久我庄は乙訓郡の桂川沿いにある久我家名字地の荘園で、上庄と下庄が存在する。
『京都市の地名(平凡社)』によると、応永3年(1396)の検注帳写に久我上庄の総面積は104町余、久我下庄は50町1段余あるようだ。
久世は久我より桂川沿いを少し北に進んだところに位置し、このたびの合戦の主戦場である。
この地は古くから東寺領が多くあり、戦国期まで東寺荘園の中核としてその経済を支えた。
しかし、南北朝期に久我家がこの地に進出し、戦国初期には細川被官の寒川などが関係を持つなど、水利や所領関係の訴訟が後を絶えなかった。
特に下久世庄は南北朝以降、東寺、久我、一条家等30余の本所によって分割領有されており、その後も東寺への寄進や押領が繰り返されるなど、権利関係が非常に複雑な地である。
久我家の老臣に竹内・春日・森・信濃氏らがあり、このたびの安堵状に関係しているのが久我家雑掌である森氏旧領である。
『言継卿記』にたびたび登場する竹内長治(左兵衛)はこれである。
なお、戦国期末期頃から竹内領内では日蓮宗系の寺院が乱立するようになり、全村が日蓮宗徒に改宗している。
同日
山科言継、長橋局からの女房奉書2通を賜り、これを以て不知行となって久しい旧領還付を足利義昭と織田信長に願い出る。
正親町天皇は広橋国光・飛鳥井雅教へ、これを認めて足利義昭に働きかけるように通達。『言継卿記』永禄十一年十月二十日条
長橋局へ参、名字之地之事、女房奉書、武家織田所へ被出候様に申入了、則両通被出之、
仰 永禄十一十廿
山しなの中納言申入候、山しな大やけの郷のむらにしの山なとの事、けんめいの地にて候へは、このたひ返しつけられ候へく候、さやうに候はすは、たちまちたんせつし候へきほとに、よくヽヽ御心え候て、むろまちとのへ申され候へく候よし、心え候て申とて候、可しこ、
日ろはし大納言とのへ
あすか井中納言とのへ
仰 永禄十一十廿
山しなの中納言申入候、七郷のうち、大やけのむらにしの山なとの事、けんめいの地にて候へは、このたひ返しつけられ候やうに、むろまちとのへとり申さた候やうにと、をたのたん正によくヽヽおほせつたへられ候へく候、さやうに候はすは、たちまちたんせつにをよひ候へき事候ほとに、へつして申とヽのへられ候へのよし、よくヽヽ申とて候、可しこ、
あすか井中納言とのへ
武家へ文者、同以飯田申遣之、武家に参暫祗候、一色式部少輔、上野中務大輔等に、知行分之事御取合頼入之由申候了、御乳人大蔵卿局へ罷向禮申之、一盞有之、武家御直垂御大口等織出之、自正實坊送之、晩景又参武家、自禁裏御使見入、率分等八ヶ條之儀也、手日記、女房奉書等持参、以一色式部少輔披露、軈可被仰、聊以御疎略有間敷之由了、則歸参、其由申入了、
一日御もく六のうちそつふんの事、きとヽヽ申つけ候やうに、のふなかにおほせ出され候へく候よし申とて候、てんそうひま入候まヽ、御まいり候ていそき御申入候へ、このそつふんともたいてん候へは、をのヽヽほうこう候へ、きやうも候はぬ、よくおほせ出され候やうに申され候へく候よし、申とて候、可しこ、
仰 永禄十一十廿
そちの中納言とのへ
手日記
※「名字の地」とは名字の由来となった地のことで、多くは父祖伝来の地を指す。
※「懸命の地」とは一所懸命の地の略。主君から与えられた土地して代々守り継がねばならいない地。
※「歎切」とは嘆き悲しむこと。
※「一盞」は1つのさかずき。1杯の酒を呑むこと。
※「晩景」は夕日・夕刻のこと。
(書き下し文)
長橋局へ参る。
名字の地の事、女房奉書、武家(足利義昭)織田(織田信長)所へ出され候ように申し入れおわんぬ。
則ち両通これを出さる。
「仰せ 永禄十一(年)十(月)二十(日)
山科の中納言(山科言継)申し入れ候。
山科大宅の郷のむらにしの山などの事、懸命の地にて候へば、このたび返しつけられ候べく候。
左様に候はずは、たちまちたんせつし候べきほどに、よくよく御心得候て、室町殿(足利義昭)へ申され候べく候由、心得候て申とて候。かしこ
広橋大納言(広橋国光)とのへ
飛鳥井中納言(飛鳥井雅教)とのへ」
「仰せ 永禄十一(年)十(月)二十(日)
山科の中納言申し入れ候。
七郷のうち、大宅のむらにしの山などの事、懸命の地にて候へば、このたび返しつけられ候ように、室町殿へとり申し沙汰候ようにと、織田の弾正(織田信長)によくよく仰せ伝えられ候べく候。
左様に候はずは、たちまちたんせつにおよび候べき事候ほどに、別して申ととのえられ候への由、よくよく申とて候。かしこ
飛鳥井中納言とのへ」
武家(足利義昭)への文は、同飯田を以てこれを申し遣わす。
しばらく武家に参り祗候す。
一色式部少輔(一色藤長)、上野中務大輔(上野秀政)等に、知行分の事御取り合いを頼み入るの由を申し候おわんぬ。
御乳人大蔵卿局へ罷り向い礼を申す。
一盞これ有り。
武家の御直垂・御大口等これを織り出す。
正実坊よりこれを送る。
晩景また武家へ参る。
禁裏より御使見が入る。
率分等八ヶ条の儀なり。
手日記、女房奉書等持ち参る。
一色式部少輔を以て披露す。
やがて仰せらるべく、いささか以て御疎略有るまじきの由おわんぬ。
則ち帰り参る。
その由を申し入れおわんぬ。
「一日御もく六のうち率分の事、急度急度申しつけ候ように、信長に仰せ出され候べく候よしを申しとて候。
伝奏ひま入り候まま、御まいり候て、急ぎ御申し入れ候へ。
この率分とも退転候へば、各々奉公候へ。
今日も候はぬ、よく仰せ出され候ように申され候べく候由、申しとて候。かしこ
仰せ 永禄十一(年)十(月)二十(日)
帥(太宰師)の中納言(山科言継)とのへ」
手日記
(備考)
「飯田を以てこれを申し遣す」とあるのは、織田家臣の飯田某か。
言継との関りの初見は同年十月十七日条の『言継卿記』である。
同日
大和国布施氏の領内が焼かれる。『多聞院日記』永禄十一年十月二十日条
布施へ人數遣之、悉以焼拂了、
10月21日
幕府奉公衆の松田頼隆と諏方俊郷、上下京中へ連署で禁裏御料所の諸役等を無沙汰にする者を成敗する旨の奉書を発給。
織田信長も同日付で諸本所雑掌中へ同様の副状を発給。『言継卿記』永禄十一年十月二十一日条
(備考)
この日記の内容と書状の手控えは、同日項の下記に記載。
同日
公家の山科言継、不知行となって久しい山科の大宅野村西山地頭職回復の件を織田信長(弾正忠殿・霜台)に陳情する。『言継卿記』永禄十一年十月二十一日条
(備考)
この日記の内容と書状の手控えは、同日項の下記に記載。
同日
山科言継、明日参内する際に用いる御服以下について足利義昭(武家室町殿)を見舞う。
その後言継は春日殿へ赴き、足利義昭の衣装を正実坊に渡す。『言継卿記』永禄十一年十月二十一日条
織田物書明院所へ書状遣之、
尚々一重に貴所頼申候事候間、急度霜臺上意へ御申所仰候、
先日者面謝令祝着候、仍知行分名字地大宅野村西山地頭職之事、此間貴所飯田御兩所頼入申、自弾正忠殿以御執申、爲上意被返付候様に頼存候處、于今御返事無之候間、昨日又被成女房奉書候、急度被(□□)入、則無御別儀之様御馳走所仰候、就中前皇宸筆三首和歌座右(□□)進入候、尚々此度知行分於(「不」脱カ)被仰付者、可為一家斷絶候間、偏霜臺可為御合力候、別而頼申候、猶澤路隼人佑可申候、恐々謹言、
十月廿一日 言継
明院 参
武家室町殿へ爲御見舞参、御服以下検知之、明日御参内之故也、於向春日殿武家御服共正實坊に相渡之、大帷御指貫御下袴生、御直垂、御大口等也、御袍同御腰者明日出来次第可相渡者也、葉室出京、明日御参内参會に被参之間被出了、今朝早旦可参武家、昨夕之御返事可催促申之由候間、参申入之處、織田所へ以上野中務大輔、和田伊賀守両使被仰出之處、則御返事に、御請之折紙調進之、同御下知被相添被渡下之、則禁裏へ以万里小路披露申候了、
禁裏御料所諸役等事、自然於致無沙汰輩者可被加御成敗之條、令存知之可致其沙汰之由、所被仰出之状如件、
永禄十一
十月廿一日 頼隆 判
俊郷 判
上下京中
禁裏御料所諸役等之儀、如先規被任御當知行之旨、爲御直務可被仰付之状如件、
永禄十一
十月廿一日 織田弾正忠
信長 朱判
諸本所 雑掌中
和田伊賀守副折紙後日に調出之、
禁裏御料所諸公事諸役等之事、如先規爲諸本所直被仰付候、自然爲問屋幷宿以下、隠置輩於在之者、可爲曲事者也、仍状如件、
永禄十一
霜月十一日 和田伊賀守
惟政 判
上下京 問屋中
※()の中に記した□の部分は『言継卿記』 第四 (国書刊行会刊行書)の記述のまま。
(書き下し文)
織田の物書き明院(明院良政)所へ書状を遣す。
「先日は面謝、祝着せしめ候。
仍って知行分名字地の大宅・野村・西山の地頭職の事、この間貴所の飯田(織田の臣飯田某)御両所へ頼み入り申す。
弾正忠殿(織田信長)より御執り申しを以て、上意として返付せられ候ように頼み存じ候ところ、今に御返事これ無く候間、昨日また女房奉書を成され候。
急度被(□□)入、則ち御別儀無きのよう、御馳走仰ぐ所に候。
就中、前皇(後奈良天皇)の宸筆三首の和歌座右(□□)まいらせ入り候。
尚々この度の知行分を仰せ付けられずに於いては、一家は断絶たるべく候間、ひとえに霜台(織田信長)の御合力たるべく候。
別して頼み申し候。
なお澤路隼人佑申すべく候。恐々謹言
十月二十一日 言継(山科言継)
明院 参る
尚々一重に貴所へ頼み申し候事に候間、急度霜台(織田信長)も上意(足利義昭)へ御申し仰ぐところに候。」
武家室町(足利義昭)殿へ御見舞として参る。
御服以下これを検知す。
明日御参内の故なり。
春日殿へ向かうに於いて、武家御服共に正実坊にこれを相渡す。
大帷・御指貫・御下袴(生)、御直垂、御大口等なり。
御袍・同御腰は明日出来次第に相渡すべくものなり。
葉室(葉室頼房)は出京、明日御参内参会に参らるるの間出られおわんぬ。
今朝早旦に武家(足利義昭)参るべく、昨夕の御返事を催促すべしと申すの由に候間、参り申し入るのところ、織田所へ上野中務大輔(上野秀政)・和田伊賀守(和田惟政)の両使を以て仰せ出さるるのところ、則ち御返事に、御請けの折紙これを調い進らす。
同じく御下知を相添えられ、これを渡し下さる。
則ち禁裏へ万里小路(万里小路惟房)を以て披露申し候おわんぬ。
「禁裏御料所諸役等の事、自然無沙汰を致すのともがらに於いては、御成敗を加えらるべきの条、存知せしめ、その沙汰を致すべきの由、仰せ出さるるところの状くだんの如し。
永禄十一
十月二十一日 頼隆(松田頼隆) 判
俊郷(諏方俊郷) 判
上下京中」
「禁裏御料所諸役等の儀、先規の如く御当知行の旨に任せられ、御直務として仰せ付けらるべきの状くだんの如し。
永禄十一
十月二十一日 織田弾正忠
信長 朱判
諸本所 雑掌中」
和田伊賀守の折紙を副う。
後日にこれを調え出す。
「禁裏御料所諸公事・諸役等の事、先規の如く諸本所として直に仰せ付けられ候。
自然問屋並びに宿以下として、隠し置くの輩これ在るに於いては、曲事たるべきのものなり。仍って状くだんの如し。
永禄十一
霜月十一日 和田伊賀守
惟政 判
上下京 問屋中
(備考)
まず、明日参内する際の足利義昭衣装について
ここに記される「春日殿」についてはよくわからない。
正実坊は人物名ではなく、当時京都を中心に手広く金融を扱っていた酒屋・土倉業者の1業社か。
この時期の正実坊は、足利義昭の参内用衣装を担当していたのであろう。
次に山科名字地不知行の件は、同書昨日条の続きである。
山科家の名字地をはじめとする山科東庄・大宅郷・四宮川原・山科西庄・野村郷・西野山郷等は、足利将軍家に押領されて久しい。
この状況を改善させるべく、言継は前年(永禄10)の10月にも三好長逸や石成友通に陳情している。『言継卿記』永禄十年十月二日条など
それでも効果がなかったのだろう。
足利義昭政権に代わった今、今度は織田信長に旧領還付を陳情し、その窮状を訴えている。
女房奉書や後奈良天皇の宸筆和歌を持ち出すあたりに本気度が窺える。
なお、ここでの「霜台」は織田弾正忠信長のことである。
最後に禁裏御料所の諸役等について
こちらは少々内容が込み入っているので、奥野高廣著『織田信長文書の研究(吉川弘文館)』の記述を引用する。
“宮廷では京都上京に四府駕輿丁座・鳥之座、図書寮の宿紙座、大舎人座・箔屋座・青花座・青苧座・楮座・九条藍座・小破座・塩合物西座などの商業ギルド(座)や柴公事(燃料にたいする公事、税)・紙公事・絹布等駄別役などの課税権を所有している。これが禁裏(宮廷)の御料所であり、その収益が諸役である。その座や公事には廷臣(貴族)が代官になり、またその代官のあった例もある。宮廷では永禄十一年十月二十日将軍義昭と信長にたいし、山科言継の旧領を還付するように命令した。その翌二十一日幕府は上京・下京にたいし、禁裏御料所の諸役を完納するよう下令した。信長はこの御料所の代官(本所)にたいし、直務(又代官を排除し直接知行する)せよと命じた。また和田惟政は、問屋や宿(宿駅)が課税品を秘匿してはならないとの折紙(古文書の形式、用紙を二つに折って書く)を出した。和田惟政は、将軍義昭をはじめにかくまったり、その後も上洛に努力した功績によって、中央政界でも羽振りがきくようになったのである。”
同日
大和国では佐久間信盛(佐久間)勢以外が、少々引き上げる。
柳本氏ら、松永方へ寝返る。『多聞院日記』永禄十一年十月二十一日条
國勢少々引歸了、佐久間計残云々、
一、尊教院近日京へ上之間、寺門条々一書取遣之、廿二日被上了、
一、柳本・福智堂多聞へ裏歸了、
一、大乗院殿へ参、尊被申申談了、
以降の記述精度低し。後日再編集の予定
10月22日
足利義昭、参内する。(御湯殿の上の日記) 『細川両家記』
一、松永方へ尾張衆二万計相添大和へ手遣候、則筒井平城は被明退候也、同又井手城へ被懸候得ば、近々と寄付させて内より切て出、あまた討取、手負不知其數と云、然ば年内無餘日と云、先々京へ引やとて、それより下國候也、
一、一乗院殿如御本意御入洛、當時細川殿の屋形に御坐候、
『細川両家記』
(書き下し文)
一、松永方へ尾張衆二万ばかりを相添え大和へ手遣わし候。
則ち筒井の平城は開け退かれ候なり。
同じくまた井手城へ懸けられ候えば、近々と寄せ付けさせて、内より切りて出、あまたを討ち取り、手負いはその数を知れずという。
然らば年内余日無しといい、先々京へ引くやとて、それより下国し候なり。
一、一乗院殿(足利義昭)は御本意の如く御入洛し、当時細川殿の屋形に御座し候。
(備考)
両家記にある2万ばかりの兵で大和へ入り、筒井城、井戸城などを攻略し、国中が大きく荒れたとする記述は『多聞院日記』と一致する。
信長の供奉によって念願の地位に就いた義昭は、信長を「わが父」とか「武勇天下第一」と称賛し、副将軍か管領に就任するように要請するが断られ、かつて尾張守護職であった斯波家の名跡を継がせようと信長に持ち掛けたが、これも断られた。(出展は『総見記』カ 後日再編集予定)
信長はその代わりに堺、大津、草津に代官を置くことを許された。(信長公記、足利季世紀)
10月23日
織田信長、奈良中に制札を掲げる。
その判銭として1000貫文を課す。『多聞院日記』永禄十一年十月二十三日条
今度ナラ中防禦制札上總ヨリ被出、判銭トテ過分ニ申懸、兩奉行承仕へ繾責被付了、咲止也、凡千貫余も申懸歟、如何可成行哉覧、
(書き下し文)
この度奈良中防御の制札、上総(織田信長)より出さる。
判銭とて過分に申し懸け、両奉行承仕へ譴責を付けられおわんぬ。
笑止なり。
およそ千貫余りも申し懸くるか。
いかが成り行くべきかな。
(備考)
制札に記された具体的な文言はわからないが、恐らく乱妨や狼藉を禁止したり、住民に還住を呼びかけるといった内容だろう。
同日
[参考] 『多聞院日記』永禄十一年十月二十三日条
小柳弓新左衛門高畠ホリ切ニテ落馬了、大略可死歟云々、先度神人生害簀川、柳生沙汰之處、スカウハ母、女房同時ニ死了、柳生ハ大将之處如此、殊其用害ノ所不苦云々、當座ニ苦痛外聞かたヽヽ、
(備考)
「小」はわかりかねるが、もし柳生新左衛門であれば、高畠の堀切から落馬したのは柳生宗厳の可能性が高い。
詳細は不明。
???
この信長の在京中にさまざまなことが取り決められている。
主要な一部の街道の関所撤廃はその一つである。
この時織田家の奉行として特に京都で活躍したのが、村井貞勝、丹羽長秀、明智光秀、木下秀吉らである。
(備考)信長上洛直後は町中大混乱であったが、織田軍の「一銭斬り」ともいわれる徹底した軍律で平静を取り戻し、公家や商人、町人までもが信長に信頼を寄せるようになった。
10月26日
信長、岐阜に帰るために京を発つ。佐久間信盛、丹羽長秀、木下秀吉、村井貞勝らは京に残した。
(備考)この時の信長は、天下に対していささかの野心もないという体裁をアピールしておきたかったのであろう。
10月27日
松永久秀(松永少弼久秀)、法隆寺へ贈り物を謝す旨の書状を発給。『法隆寺文書』四
信長へ要脚ニ付而、堺へ八木被出候、路次之折帋進之候、堺にて銀子拾六貫かねニ渡申候条、可被成其意候、兼又綿廿把給候、何様之御心遣、却而如何候、乍去被持候間、留申候、喜怡之至候、猶宝光院へ申候、恐々謹言、
十月廿七日 松永少弼
久秀(花押)
法隆寺御役者中
(書き下し文)
信長へ要脚に付きて、堺へ八木を出され候。
路次の折り紙これを進らせ候。
堺にて銀子十六貫かねに渡し申し候条、その意を成さるべく候。
兼ねてまた、綿二十把を給い候。
何様の御心遣い、却って如何に候。
去りながら持ちせられ候間、留め申し候。
喜怡の至りに候。
なお宝光院へ申し候。恐々謹言(以下略)
(備考)
ここでの「要脚」は同年十月六日付で法隆寺に発給された家銭としての銀子150枚を指すのだろう。『法隆寺文書』
「八木(はちぼく)」は米の異称。
八と木を足すと米の字になる。
その金を工面するために、堺で米を売り、銀子16貫を入手し、これを金貨(かね)に交換したか。
「喜怡(きたい)」とは喜ばしい意で、2字同じ意味を重ねることで喜びを強調した表現である。
10月28日
岐阜に帰城する。
11月24日
京で政務に当たっている丹羽長秀と村井貞勝が、長命寺惣坊に坊領の知行分の年貢の収納を認める。(長命寺文書)
同日
丹羽長秀と村井貞勝が、沖島地下人に沖島における堅田の知行分を認める。(堅田村旧郷士共有文書)
11月27日
法隆寺、織田家に課された銀子を松永久秀に納入する。『法隆寺文書』四
尚々、田舎衆火急ニ被申候条、一日も於延引者、御寺可被及御迷惑候、則宝光院境へ御越候て、質屋方へ被請候て、馳走候之様ニ憑存之由、久秀直ニ被申渡候、従各々も其通宝可有御入魂候、来朔日より内ニ不調候へは、無曲由候間、御調専一候、此外不申候、
信長へ之御礼銭之儀、霜台へ被請取候条、委細宝光院へ申渡候、悉境へ直ニ被渡候間、御急候而、御済肝要ニ候、丹五左下国候条、佐久右一筆取候而可進之候、上使前々分も先堺へ渡申度候之条、是又宝光院可被仰談候、少も御寺家之御越度には成申間敷候、其段者可被任置候、恐々謹言、
十一月廿七日 竹下
秀勝(花押)
年預御坊
御返事
(書き下し文)
信長への御礼銭の儀、霜台(松永久秀)へ請け取られ候条、委細は宝光院へ申し渡し候。
悉く堺へ直に渡され候間、御急ぎ候て、御済まし肝要に候。
丹五左(丹羽長秀)が下国し候条、佐久右(佐久間信盛)一筆取り候てこれを進らすべく候。
上使前々の分も、まず堺へ渡し申したく候の条、これまた宝光院に仰せ談ぜらるべく候。
少しも御寺家の御落ち度には成り申すまじく候。
その段は任せ置かるべく候。恐々謹言
十一月二十七日 竹下
秀勝(花押)
年預御坊
御返事
尚々、田舎衆火急に申され候条、一日も延引に於いては、御寺御迷惑に及ばるべく候。
則ち宝光院堺へ御越し候て、質屋方へ請われ候て、馳走候のように頼み存ずるの由、久秀直に申し渡され候。
各々よりもその通り、宝(宝光院)御昵懇有るべく候。
来たる一日より内に調わずに候へば、曲無きの由に候間、御調え専一に候。
このほかは申さず候。
(備考)
これは、同年10月6日に織田家が法隆寺に対して課した銀子150枚に関する書状である。
法隆寺が同年11月27日付で、金の工面に苦心している様子が窺える書状が遺されている。『法隆寺文書』
同様に『多聞院日記』等には、信長が10月に奈良中に制札を下した礼銭(判銭)として、1000貫文の供出を命じる旨の記述がある。
織田家が急ぎ金を要求する理由は、戦線を支える軍用金のほかに、朝廷や将軍を支える費用もあっただろう。
文書の発給者である竹内秀勝は、松永久秀の老臣でこの時期大きく活躍した人物。
『多聞院日記』では彼の名が頻繁に登場し、受領名の下総守を入れて「竹下」と記すことが多い。
文中の霜台は弾正台の唐名で、松永久秀を指す。(松永弾正少弼)
丹五左は丹羽長秀(丹羽五郎左衛門)で、佐久右は佐久間信盛(佐久間右衛門)である。
以後、丹羽と佐久間は政治面でも大きく活躍する。
主に丹羽は京都の政務が中心で、木下秀吉・村井貞勝・中川重政らと連署で発給した書状が多く遺されている。
一方、佐久間は大和・堺方面での活躍が華々しい。
このたびの上洛戦を始める何年も前から、彼は大和方面における織田家の窓口を担当していた。『柳生文書』『岡文書』など
その功を考えると、この時期の信長政権でもっとも大きな活躍をしたのは佐久間信盛かもしれない。
12月9日
法隆寺、織田家に課された礼銭六百貫文を松永久秀に渡し、その後の処置を頼む。『法隆寺文書』四
(端裏書)
「信長へ礼物渡ス請取也」
信長へ御礼銭六百貫文請取候て、即宗頸・宗純へ渡申候、始末之儀者、於多聞可申談候、恐々謹言、
永禄十壱辰
十二月九日 喜多土佐守
重政(花押)
竹内下総守
秀勝(花押)
法隆寺
年会御坊
(書き下し文)
信長へ御礼銭六百貫文請け取り候て、即ち宗頸・宗純へ渡し申し候。
始末の儀は、多聞(松永久秀)に於いて申し談ずべく候。恐々謹言(以下略)
(備考)
発給者の竹内・喜多は、このたびの奉行に当たった松永家臣。
松永久秀がこれを処理し、金を織田家に支払ったのだろう。
法隆寺は一連の支払いを終え、臨時の会式を執行して無事を祈ったようだ。『斑鳩旧記類集』『勅会梵音衆集会曳付』
12月16日
公卿の二条晴良、近衛前久に替わり関白・氏長者となる。『公卿補任』
12月
正親町天皇の嫡男であり、皇太子である誠仁親王が、親王宣下を受けて元服する。
(備考)朝廷の資金難で元服の儀が延び延びになっていたが、信長の拠出した資金により、ようやく元服することができた。
この後、信長は誠仁親王と友情を深め、のちに信長が正親町天皇と疎遠になってからも、二人の交流は続いたという。
六条本圀寺の戦いと殿中御掟
永禄12年(1569)
36歳
1月4日
三好長逸(日向守)、三好宗渭(釣竿斎)、岩成友通らが京へ侵入し、町中騒動となる。(言継卿記)
1月5日
上記の三好三人衆が足利義昭が宿所としている六条本圀寺を包囲し、攻撃する。=六条本圀寺の戦い
織田家の警護部隊と将軍奉公衆が必死の防戦をし、足軽衆20余人が討死、三好三人衆勢にも多数の死傷者を出す。(言継卿記・信長公記)
1月6日
三好長逸、陣を七条口に移す。(言継卿記)
(備考)南方の所々に火の手が上がるのを公家の山科言継が見ている。
同日
織田・足利方の援軍として池田勝正、伊丹衆が西方から、若江城主の三好義継(左京大夫)が南方から駆けつけ、さらに幕府奉公衆が北方から加わり、三好三人衆勢を打ち破る。(言継卿記・多聞院日記・信長公記)
(備考)『多聞院日記』によると、桂川の合戦で池田勝正軍が三好三人衆勢に敗れかかったところを三好義継が陣に馳せつけ、三人衆勢を打ち破ったとある。
また、『言継卿記』には東寺の西方の戦闘で岩成友通が北野社松梅院へ敗走し、1000余人の死傷者が出たことが記されている。
同じく『言継卿記』には三好義継が討死したとの風聞、久我晴通(入道愚庵)、細川藤孝(兵部大輔)、池田勝正(筑後守)の身の上は不明なこと、三好長逸らは八幡へ陣を引き下げたことが記されている。
かなりの戦闘だったようだ。(『多聞院日記』には三好康長は行き方知れずと記述)
1月8日
信長、この報せを聞くとすぐさま岐阜を出陣。
大雪の中を一騎掛けで京へ向かう。 (信長公記)
1月10日
織田信長、松永久秀(弾正少弼)を従えて美濃より入京する。(信長公記・言継卿記・多聞院日記)
(備考)信長、岐阜からわずか2日で京へ入る。
供の者は10騎にすぎなかったが、やがて諸将らも岐阜へ参着する。
同日
丹羽長秀(五郎左衛門尉)が京都八条遍照心院へ、信長の寄宿免除について約した朱印に、別儀ないことを通達。(大通寺文書)
1月11日
石山本願寺の門跡・顕如、織田信長へ新年の慶賀を祝す旨の書状を発給。『顕如上人御書札案留』
年甫之吉慶、殊以可屬芳意の條、珍重候、仍太刀一腰金、馬一疋進之候、表嘉儀計候、猶下間丹後法印可令演說候、穴賢、
正月十一日 — —
織田弾正忠殿
(書き下し文)
年甫の吉慶、殊に芳意を以て属すべきの条、珍重に候。
仍って太刀一腰(金)・馬一疋これをまいらせ候。
嘉儀を表すばかりに候。
猶下間丹後法印(下間頼総カ)演説せしむべく候。穴賢
1月14日
信長、幕府の職務規定を定める殿中御掟全9ヶ条を定め、将軍義昭もこれを承認。(仁和寺文書、蜷川家文書、毛利家文書)
1月15日
石山本願寺の門跡顕如、織田信長へ上洛を歓迎する旨の書状を発給。『顕如上人御書札案留』
御上洛尤珍重候、仍太刀一腰金、毛氈五枚赤、馬一疋栗毛進之候、猶下間丹後法印可申候也、穴賢
正月十五日 — —
織田弾正忠殿
(書き下し文)
御上洛尤も珍重に候。
仍って太刀一腰(金)・毛氈五枚(赤)・馬一疋(栗毛)これをまいらせ候。
猶下間丹後法印(下間頼総カ)申すべく候なり。穴賢(以下略)
(参考)
御上洛尤珍重候、仍五種十荷□、毛氈五枚赤進之、猶下間丹後法印可申候也、穴賢
正月十五日 — —
織田弾正忠殿
○此御札子細アリテ不被遣之
(書き下し文)
御上洛尤も珍重に候。
仍って五種十荷物□・毛氈五枚(赤)これをまいらせ、猶下間丹後法印(下間頼総カ)申すべく候なり。穴賢
正月十五日 — —
織田弾正忠殿
○この御札、子細ありてこれを遣わされず
1月16日
幕府に出した「殿中御掟」に、信長はさらに7条を追加。
これも義昭もこれを承認。 (仁和寺文書)
(備考)この計16ヶ条に及ぶ「殿中御掟」は、一見将軍である足利義昭をないがしろにし、実権を奪うものだと見られがちであるが、近年の研究ではそれは否定されている。
足利義昭自身が大名の家臣に対しても大名の頭越しに御内書が出したり、幕臣(義昭の家臣)が寺社領を押領する事態が頻発するなどの問題が起き、上方の社会が混乱した。
天下の静謐の為には、信長が義昭の権力行使を規制しなければならなかったという見方もある。
この「殿中御掟」は義昭との不和を決定的にさせるものではなく、この頃はまだ義昭は信長を頼りに思っていたのではないだろうか。
1月18日
信長、明日開催予定の左義長の準備を見物し、朝廷へ警固役を申し出る。(言継卿記)
1月19日 早朝
信長、日の出以後に警護衆500人ほどを率いて禁裏へ到着。
門の各所を警護させる。(言継卿記)
同日
朝廷の主催で声聞師の松拍子にて左義長が開催される。
のちに信長を小御所の庭に呼んで酒肴を与える手はずだったのだが、既に信長が到着しているにも関わらず、銚子がなかなかこなかったため、信長はこれを辞して退出する。(言継卿記)
同日
信長、近江堅田へ全五ヶ条の定を下す。(堅田村旧郷士共有文書)
(備考)内容は堅田の権益を保護するもの。
同日
南禅寺塔頭竜華院領の件で、一卜軒が僧籍でありながら院領所有権を手放そうとしないことに対する通達を行う。(鹿王院文書)
1月21日
信長、将軍義昭の御下知の通り、烏丸光康へ摂津国上牧の知行を安堵する。(烏丸家文書)
1月24日
公家の飛鳥井雅敦、自身が影響力を持つ摂津国本興寺に織田軍が陣取りをしないように、織田信長に陳情書を出す。(本興寺文書)
(備考)どうやらこの時、織田軍の柴田勝家(修理亮)、森可成(三左衛門尉)、蜂屋頼隆(兵庫助)、坂井政尚(右近尉)が摂津表へ兵を繰り出していたようだ。
二条御新造の建設
1月26日
織田信長、真如堂蓮光院へ、将軍御座所を新設するので、場所替えをするよう命を下す。(真正極楽寺文書)
(備考)その替地として信長から真如堂蓮光院へ一条西の四丁町を寄進すること、堂領諸所の散在は歴代将軍の御下知通りに安堵することなどを通達する文書を発している。
ここが亡き将軍・足利義輝の旧邸だったのだろうか。
1月27日
山科言継、さっそく工事に取り掛かる信長と会い、しばらく雑談する。(言継卿記)
2月2日
先の六条本圀寺の変の教訓から、信長は強固な将軍家の新御所の建設を決断する。=二条御新造の着工(言継卿記)
(備考)場所は勘解由小路室町の真如堂の跡地であり、ここは足利将軍家代々の直轄地のようだ。
大工奉行には村井貞勝、島田秀満が司り、畿内近国14ヵ国から人夫が動員され、一日数千人が工事に使われたという。
この造営は信長自らが陣頭指揮に立ち、突貫工事で行われた。
造営中の逸話として、ある時、工事に従事していた一人の武士が、その前を通りかかった婦人のかぶりものを上げ、顔を見ようとした。
するとそれを目撃した信長は、一刀のもとに首を刎ねたという(フロイス日本史)
なお、フロイス日本史は大げさな記述が多い点に注意。
2月11日
織田信長と足利義昭からの使者として堺に赴いた佐久間信盛・森可成・柴田勝家・蜂屋頼隆・坂井政尚・和田惟政・結城進斎ら100人ばかりが、豪商として名を馳せる津田宗及の自宅に招かれ、茶会を開く。(宗及茶湯日記他会記)
3月1日
撰銭令を定める(京都上京文書)
3月2日
正親町天皇、信長に副将軍就任を求めるが、信長は奉答せずに勅使を帰している(言継卿記)
(備考)昨年に足利義昭が信長に求めて断られていたが、義昭は諦めきれず、朝廷に働きかけたのだろうか
3月
信長の仲介により、河内若江城主の三好義継が足利義昭の妹を娶る。『言継卿記』
寶鏡寺殿新御所、今夜三好左京大夫所へ嫁娵云々、信長中媒云々、
(宝鏡寺殿新御所、今夜三好左京大夫(三好義継)所へ嫁を娶り云々。信長の中媒と云々。)
『言継卿記』永禄十二年三月十七日条より
4月1日
柴田勝家・佐久間信盛・森可成・蜂屋頼隆が連署で堺両惣中に宛てて書状を送る。
その内容は矢銭の催促であった。
(備考)これにより堺は信長に屈服し、合戦で三好家が衰退してゆくにつれて、堺の町は織田家の直轄化となっていった。
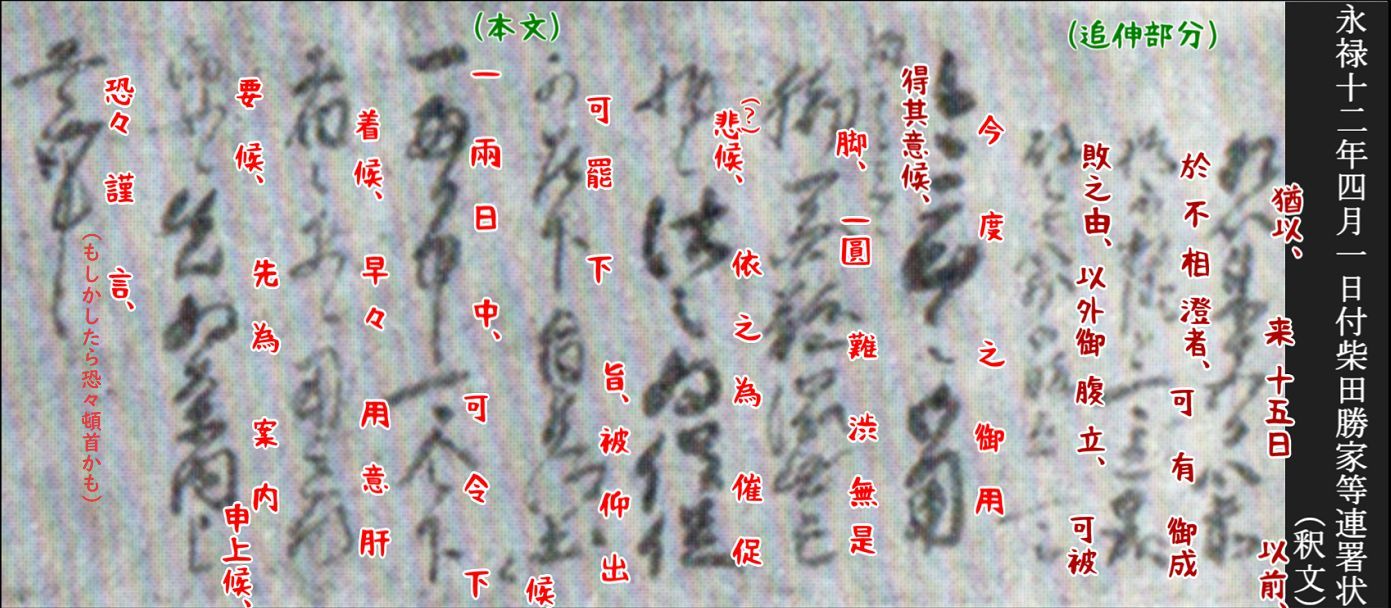
(永禄十二年四月一日付柴田勝家等連署状a+釈文)
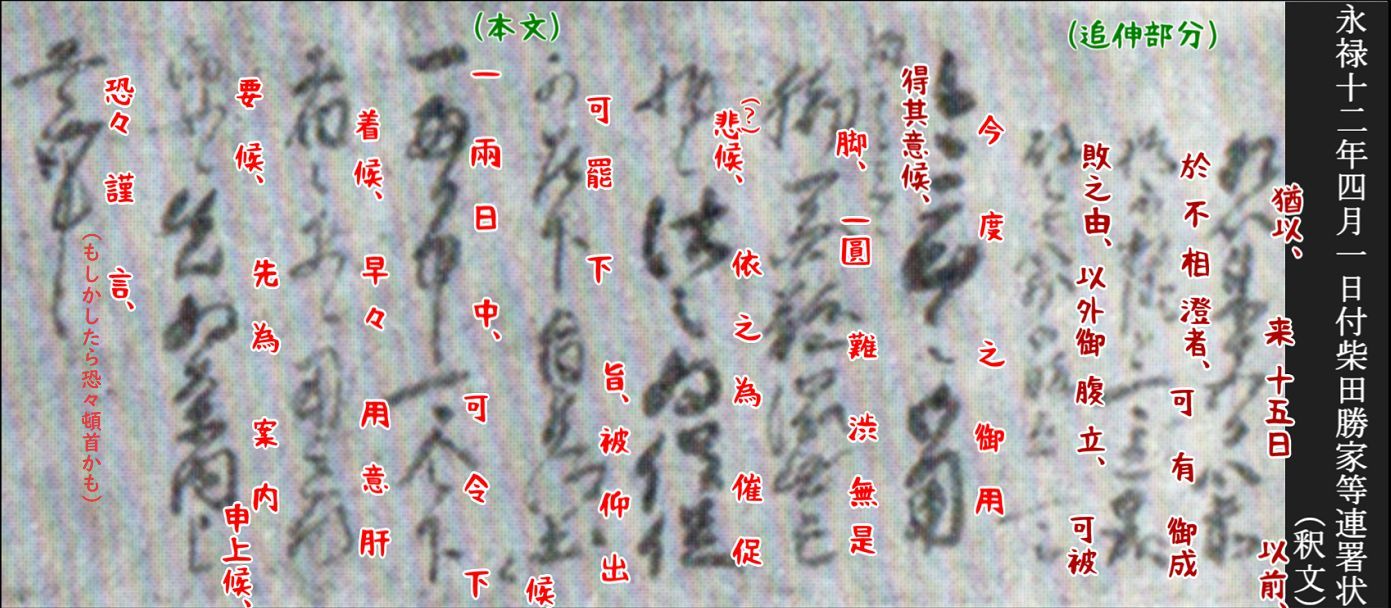
(永禄十二年四月一日付柴田勝家等連署状b+釈文)
関連記事:堺の町を脅迫?柴田勝家・佐久間信盛・森可成らが大金を要求した時の書状
4月8日
宣教師のルイス・フロイス、キリスト教布教の許可を得に二条御新造を陣頭指揮中の信長を訪ねる。
(備考)フロイスは西洋人では初めて信長に会見した人物であるが、その模様を次のように書き留めている。”造営を自ら指揮していた信長は、虎の皮を腰に巻き、粗末な衣服を身に着けていた。容貌は年齢・37歳くらい。中くらいの背で、華奢な身体であり、髭は少なく、甚だ声は快調であった”これがフロイスの信長への第一印象だと言われている。これはあの一番有名な信長の肖像画と一致する部分が多いのではあるまいか。

4月13日
信長、宿所を妙覚寺に移す。(言継卿記)
(備考)二条御新造を着工してからの信長の宿所は不明であるが、恐らく現場に泊まり込んでいたのであろう。
4月14日
二条御新造が完成し、足利義昭がそこに移り住む。
4月16日
朝山日乗に命じて朝廷に内裏の修理費用一万貫を献上する(御湯殿の上の日記)
(備考)現在の価値で換算すると約9億円以上か。
同月一日に堺から巻き上げた2万貫のうち、半分を献納したとみて間違いないだろう。
4月21日
帰国の挨拶のため、足利義昭に謁見する。義昭は信長の忠節に感謝し、信長を門外まで送り出し、その姿が栗田口に消えるまで見送ったという(言継卿記)
(備考)在京中の信長は、公家衆や寺社に対して安堵状を与えているが、幕府将軍家の奉行人奉書が出されている。この事実は両者の安堵状なくしては現実に機能しえないことを表現しており、足利幕府と信長の二重行政、二重政権であることを示している。
4月下旬
信長、岐阜に帰城。
5月14日
京で政務に当たっている明智光秀、村井貞勝、武井夕庵が、妙智院に対し北山等持院が天竜寺の末寺である証明を求める。(天竜寺文書)
5月
伊勢国司・北畠具教の弟である木造具政が信長に内応を申し入れる。
7月10日
石山本願寺の門跡・顕如、織田信長へ久しく無音にしていたことを謝し、贈り物を送る旨の書状を発給。『顕如上人御書札案留』
其以後不能音問候、依遠路兎角遅引之儀候、就中金襴十端、絞手綱、腹帯五十具進之候、任見來計候、猶下間丹後法印可申候、穴賢
七月十日 — —
織田弾正忠殿
(書き下し文)
それ以後音問能わず候。
遠路により、とかく遅引の儀に候。
就中、金襴十端・絞手綱・腹帯五十具これをまいらせ候。
見来に任せるばかりに候。
猶下間丹後法印(下間頼総カ)申すべく候。穴賢(以下略)
7月27日
公家の山科言継、岐阜に下向する。
(備考)以下はこのとき言継が目撃した事件である。信長は故斎藤義龍の後家が所持していたという壷を強引に所望するが、彼女は戦乱によって壷は紛失したと申し立て、なおこれ以上の詮議に及べば自害するほか道はないと答えた。この時、「信長本妻兄弟女子十六人自害たるべし、国衆大なる衆十七人、女子の男卅余人切腹すべし」といい、信長本妻の斎藤一族らが結束して信長に抵抗するという事件が起きている。ここに見える「信長本妻」とは、あの斎藤道三の娘・帰蝶のことではあるまいか。かなり大きな事件のように思えるのだが・・・。(言継卿記)
???
岐阜に帰った信長は、美濃の土豪に対して所領の宛行、所領の安堵、さらに座の組織に諸役を免除するなど国内の経営に専念している。
8月18日
佐久間信盛が堺の北庄に宛てて書状を送る。
内容は、人足の供出が滞っていることを責めるものだった。
急度申候、地頭詰夫並諸役以下難渋不相届由、信長被仰出候、早速可被勤事肝要候、不可有油断候、恐々
(今井宗久書札留)
八月十八日 佐久間信盛
さかい 北庄端郷中
伊勢北畠家討伐戦と蒲生賦秀(氏郷)の初陣
8月20日
信長、三河、遠江、尾張、美濃、近江、北伊勢などの軍勢10万を率いて出陣。伊勢北畠家討伐に向かう。この日は桑名に着陣。
8月21日
鷹狩りののち白子観音寺に移陣。
8月23日
木造に着陣。信長自身は降雨のため26日まで逗留する。
8月26日
木下秀吉らが阿坂城を攻め落とす。=阿坂城の戦い
8月28日
北畠具教、具房父子の籠る大河内城を包囲する。=大河内城の戦い
9月8日
丹羽長秀、稲葉一鉄、池田恒興ら三人に夜攻めを命ずるが降雨のため味方の鉄砲が役に立たず、多くの侍が戦死する。
10月3日
北畠具房、開城して和議を乞い、信長の次男・茶筅丸に家督を譲ることを約す。(信長公記、多聞院日記)
(備考)残念ながら南伊勢攻めの詳細な記録は少ない。信長は10万の兵を動員しながら苦戦したことは事実のようで、なんとか外交によって決着をつけたといった感じだ。南伊勢が信長の支配下に入る。
(追記 2021.10.3)
『多聞院日記 十五(十月五日条)』より抜粋
「五日、井戸へ太郎ニ書狀遣之、竹下返事在之、去三日ニ勢州國司ノ城落了由返事ニ在之、」
(十月)五日、井戸へ太郎に書状遣わし、竹下の返事これあり。去三日に勢州国司の城落ちおわんぬの由との返事にこれあり。
『信長公記 巻二(大河内國司退城之事)』より抜粋
「九月九日 瀧川左近被仰付、多藝山國司の御殿を初として悉焼拂、作毛薙捨、忘國にさせられ、城中ハ可被成干殺御存分尓て御在陣候の處、俄走入候の既端々及餓死付て、種々御詫言して 信長公の御二男 お茶箋へ家督を譲り申さるヽ御堅約尓て
十月四日 大河内之城 瀧川左近 津田掃部両人尓相渡、國司父子ハ 笠木坂ないと申所へ退城候し也、」
(九月九日
滝川左近(滝川一益)に仰せ付けられ、多芸山国司の御殿を始めとして悉く焼き払い、作毛を薙ぎ捨て、亡国にさせられ、城中は干殺に成さるべく、御存分にて御在陣候のところ、俄かに走り入り候の、既に端々餓死に及ぶに付きて、種々御詫言して、信長公の御二男 お茶筅へ家督を譲り申さるる御堅約にて、
十月四日、大河内の城を滝川左近(滝川一益) 津田掃部(津田一安)両人に相渡し、国司父子は笠木坂ないと申す所へ退城候しなり。)
織田家の人質となって岐阜城にいた蒲生賢秀の嫡男・鶴千代は、元服して「蒲生忠三郎賦秀(やすひで)」と名乗っていた。
信長はこの少年を大変気に入り、自ら烏帽子親(えぼしおや)となって織田弾正忠信長の「忠」の字を与えて忠三郎となった。
賦秀はこの大河内城攻めで初陣を果たしたのであるが、蒲生家臣の目から離れて行方不明となってしまった。
あわや忠三郎討死かと現場が騒然としたところ、賦秀は敵の兜首を取って戻ってきた。
これを聞いた信長は感激。
戦後、信長は自身の娘を賦秀に娶らせ、さらに人質の処遇をやめて日野城に帰した。
この後も蒲生賦秀は信長麾下として大活躍し、豊臣秀吉の時代に蒲生氏郷と名を改め、会津120万石の大大名となるのである。

10月5日
伊勢山田に着陣。 (信長公記)
10月6日
伊勢神宮に参拝。 (信長公記)
10月7日
木造に着陣。 (信長公記)
10月8日
上野に着陣し、兵を国もとに戻す。伊勢の仕置きとして茶筅丸の後見役に津田一安を命じ、滝川一益に安野津、渋見、木造を、弟の織田信包には上野の諸城をそれぞれ守らせる。 (信長公記)
(備考)
北伊勢における「北勢四十八家」とも呼ばれた群小地侍たちは、織田軍の伊勢侵攻に対し多少の抵抗を示すものもあったが、ほとんどは和睦・降伏してその家臣団に属した。
鈴鹿・河曲二郡を治める関一党は神戸信孝に、安濃・奄芸二郡の長野一党は織田信包に、南勢地域の北畠国司家は北畠信意(信雄)にそれぞれ引き継がれたが、信長による国外各国での戦役に駆り出されることが多く、領国治政の成果ははかばかしくなかった。
伊勢はやがて、北畠一族謀殺をはじめ、それぞれ領国内での温存勢力粛清を経ながら、旧地侍・織田系家臣混成の家臣団再編成が進められることとなる。
10月9日
大雪の中、千草峠を越える 。(信長公記)
10月10日
近江市原に宿泊。(信長公記)
10月11日
馬廻衆率いて上洛し、将軍・足利義昭に伊勢平定を報告する。 (信長公記) 『多聞院日記』
『多聞院日記 十五(十月十一日条)』
十一日、信長出京、人數三万騎云々
10月12日
京で政務にあたっている村井貞勝が、浄福寺への寄宿を免除する。(浄福寺文書)
10月13日
参内し、天盃を賜る
10月14日
松永久通(松右)、竹内秀勝(竹下)が上洛する。『多聞院日記』
10月17日
京都滞在を終えて岐阜へと発つ。(御湯殿の上の日記、信長公記)
(備考)足利義昭はかねてより北畠家の討伐に反対で、このとき信長との間に決定的な亀裂があったのではなかろうか。この信長突然の帰国は多くの人々を驚かせ、不安に陥れたらしい。それは正親町天皇が自筆の女房奉書を認めて信長を慰めていることからも窺える。(東山御文庫記録) また、多聞院日記は突然の帰国を「上意トセリアイテ下リ了ト」と記している。
10月19日
岐阜帰城か。
11月20日
石山本願寺の門跡・顕如、幕府奉公衆の明智光秀へ、阿波国の門下たちを扇動しての敵対行為を否定する旨の書状を発給。『顕如上人御書札案留』
御内書之趣、致拜見候、仍就阿州表之儀、門下之族、爲此方依申付致馳走之由、曾以不能分別候、惣別如此之段、雙方合力助言之儀、一切無之事候、此等之旨可然様可令申入給候、恐々
十一月廿日
明智十兵衛尉殿
○此時之御使梅咲也、表書彼御使よりこのみによつて如此沙汰外〱〱
(書き下し文)
御内書の趣き、拝見致し候。
仍って阿州表の儀に就きて、門下の族、此方のためによりて申し付け、馳走致すの由、かつて以て分別能わず候。
惣別はかくの如くの段、双方合力助言の儀、一切これ無き事に候。
これらの旨、然るべき様に申し入れせしむべき給い候。恐々
十一月二十日
明智十兵衛尉(光秀)殿
○この時の御使梅咲なり。表書かの御使よりこのみによってかくの如く沙汰外々々
【参考】北畠具教参宮・瀧川一益礼銭等入途日記『太田家古文書』
(表紙)
「
辰霜月多気大御様御参宮之時よりの入みち
今度瀧川殿へ之いり道之日記
永禄十二年ミつのとのみ(ママ)(恐らく己巳)九月吉日 」
金ノかたへノ米御取かへ之分
弐石五斗 善五郎殿
三石此内壱石長一大大夫殿へ銀かたへ渡候 蔵人殿
壱石五斗 ひかし殿
壱石五斗 中沢殿
五斗 善七郎殿
五斗 又十郎殿
五斗 彦二郎殿
五斗 善八郎殿
五斗 善三郎殿
ひる川殿雑用 同送舟入ミち米取かへ之分
三升半つゝ三度ニ合壱斗半つゝ出ゆひ米
又六郎殿 与六郎殿 喜三郎殿 弥二郎殿
与十郎殿 善八郎殿 中西殿 中沢殿
浄(カ)かん 善三郎殿 う京殿 ませ殿
与二郎殿 蔵人殿 弥七郎殿 七郎衛門殿
又十郎殿 藤七郎殿 与左衛門殿 善五郎殿
与八郎殿 与七郎殿 起介殿 善七殿
彦二郎殿 善七郎殿 助八殿 ひかし殿
以上廿八人より出候
(中略)
瀧川殿御礼之時酒肴取かへ之分 九月十六日
二斗 さけ 善五郎殿
壱斗 さけ う京殿
五升 さけ 与十郎殿
五升 さけ 彦二郎殿
のしひとつ内三はもとし申候 新三郎殿
二連一ふし かつほ 与七郎殿
四丁ひやうこより 同まけ屋の物
馬ノ大豆一升つゝ取かへ之分
七郎衛門殿 彦二郎殿 浄かん 善三郎殿
与十郎殿 孫六郎殿 ほり殿 ひかし殿
弥二郎殿 又十郎殿 藤七郎殿 弥七郎殿
蔵人殿 与七郎殿 又六郎殿 与六郎殿
馬瀬殿 与八郎殿 善七郎殿 中沢殿
合廿人まめ弐斗
壱石 米出 長一大夫殿渡 与七郎殿
同日
壱石 米出 同長一大夫殿渡候 おくノ大夫殿
(この間、一紙分あく)
御礼銭渡申日記
弐牧(枚) 金子 桑名矢部右馬亮殿・水谷三郎左衛門殿 両人渡申候
又於小畑千貫文、瀧川殿御用銭被仰付候時、金子三牧(枚)にて御侘(詫)言申、金子渡申候分
弐牧(枚)朱中金子、巳ノ年(恐らく永禄12年1569)十月六日、於長楽寺、ひる川長二郎殿渡申候、又五両金、ひる川長二郎殿渡候、
午卯月(恐らく永禄13・元亀元年1570)渡、使長一大夫殿
金取かへ之分
十月六日長楽寺ニ取分
五両内朱中不足 与十郎殿
同
五両 善五郎殿
同
弐両弐分三朱々中 蔵人殿
同
壱両朱中 中西殿
同
壱両 善八郎殿
同
壱両 中沢殿
同
壱両 又六郎殿
同
壱両 ひかし殿
同
壱両弐朱此内米弐石帳役にて申渡候、来五月廿一日まて四斗八升俵也、一石五斗、四斗六升ひやう、卅五石かへノね(カ)ニすまし申候、四斗七升渡候、未六月晦日
白子
又兵衛殿御出
同
壱両三朱 弥七郎殿
合二牧(枚)朱中 ひる川長二郎殿渡口入長一大夫殿うけ取あり
右之内弐朱々中金あまりあり
(中略)
午卯月 (恐らく永禄13・元亀元年1570)
五両金 ひる川長二郎殿渡申候、使長一大夫殿
申六月(元亀三1572?)晦日右京進殿会合ニ
長一大夫殿めし、同つかい銭、彼是取かへ、まへニも米出候て、只今ひた銭弐拾貫文渡候て、前後すミ候、

次回は元亀元年(1570)から。
信長包囲網序章からとなります!
信長覇業の一番面白い所。
私が一番好きな時代です。\(^o^)/ヤッター!!

織田信長公の年表を御覧になりたい方は下記のリンクからどうぞ。
- 誕生~叔父信光死去まで(1534~1555)
- 叔父信光死去~桶狭間の戦い直前まで(1555~1560)
- 桶狭間の戦い~小牧山城移転直後まで(1560~1564)
- 美濃攻略戦(1564~1567)
- 覇王上洛(1567~1569) イマココ
- 血戦 姉川の戦い(1570.1~1570.7)
- 信長包囲網の完成(1570 7.~12.)
- 比叡山焼き討ち(1571 1.~9.)
- 義昭と信長による幕府・禁裏の経済改革(1571 9下旬~1571.12)
- 元亀3年の大和動乱(1572 1.~1572.6)
- 織田信重(信忠)の初陣(1572 7.~1572 9.)
- 武田信玄 ついに西上作戦を開始する(1572 9.~1572 12.)
- 将軍・足利義昭の挙兵と武田信玄の死(1573 1.~1573 4.)
- 将軍追放 事実上の室町幕府滅亡(1573 5.~1573 7.)
- 朝倉・浅井家滅亡(1573 8.~1573 10.)
- 三好義継の最期(1573 10.~1573 12.)