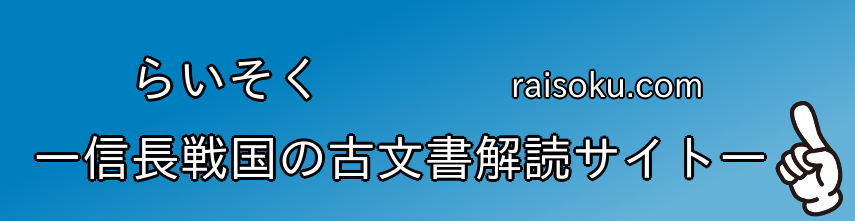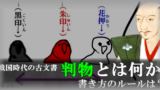今回は異見十七ヶ条を幕府へ送り付けるあたりから、三方ヶ原の合戦で武田信玄に敗れる12月末までの年表です。
近年は「元亀の動乱」と称されることが多くなりましたが、まだまだ不明な点も多く、学者先生の間でも見解が大きく異なります。
ぜひ、皆さんご自身の自説を立ててみてください。
歴史の面白さはこうしたところにあるのですから。
それでは、今回は元亀3年(1572)9月下旬からはじめる。
(ここまでの流れ)
- 誕生~叔父信光死去まで(1534~1555)
- 叔父信光死去~桶狭間の戦い直前まで(1555~1560)
- 桶狭間の戦い~小牧山城移転直後まで(1560~1564)
- 美濃攻略戦(1564~1567)
- 覇王上洛(1567~1569)
- 血戦 姉川の戦い(1570 1.~1570 7.)
- 信長包囲網の完成(1570 7.~12.)
- 比叡山焼き討ち(1571 1.~9.)
- 義昭と信長による幕府・禁裏の経済改革(1571 9下旬~1571.12)
- 元亀3年の大和動乱(1572 1.~1572.6)
- 織田信重(信忠)の初陣(1572 7.~1572 9.)
- 武田信玄 ついに西上作戦を開始する(1572 9.~1572 12.) ←イマココ
- 将軍・足利義昭の挙兵と武田信玄の死(1573 1.~1573 4.)
- 将軍追放 事実上の室町幕府滅亡(1573 5.~1573 7.)
- 朝倉・浅井家滅亡(1573 8.~1573 10.)
- 三好義継の最期(1573 10.~1573 12.)
この年表の見方
- 当サイトでは、信長の人生で大きな転換期となった時代時代で、一区切りにしている
- 他サイトや歴史本、教科書で紹介されている簡単な年表に書いている内容は、赤太文字
- 年代や日付について諸説ある場合は、年代や日付の個所に黄色いアンダーライン
- 内容に関して不明確で諸説ある場合は、事績欄に黄色いアンダーライン
- 当時は数え年であるから、信長の年齢は生まれた瞬間を1歳とする。誕生日についても詳細不明のため、1月1日で1つ歳を取る
- 太陽暦、太陰暦がある。当サイトでは、他のサイトや歴史本と同じように、太陰暦を採用している。中には「閏」なんていう聞きなれないワードがあるかもしれないが、あまり気にせず読み進めていってほしい
- キーとなる合戦、城攻め、政治政策、外交での取り決めは青太文字
- 翻刻はなるべく改変せずに記述した。そのため、旧字や異体字が頻繁に登場する。しかしながら、日本語IMEではどうしても表記できない文字もあるため、必ずしも徹底しているものではない。
- 何か事柄に補足したいときは、下の備考欄に書く
元亀3年(1572)
39歳
武田信玄の不穏な行動
9月19日
信長、山城国天龍寺坊頭の妙智院にたいし、院領の山城西院である安弘名を直務(管理人を廃し直接知行させる)旨の黒印状を発給。
詳細は側近の武井夕庵に伝達。『妙智院文書』
(ウハ書)
「 弾正忠
妙智院 信長
尊報」
西院の内、院領安弘名事、相違ニ付、委細承候、本懐之至候、自今已後為御直務、院納不可有相違候、仍菓子箱、舟皿、室盆贈給候、令拝受候、塗色已下不尋常間、自愛候、度々御懇情大慶候、猶夕庵可申候、恐惶敬白
九月十九日 信長(黒印)
妙智院
尊報
(書き下し文)
西院の内、院領安弘名の事、相違に付き、委細承り候。
本懐の至りに候。
自今以後は御直務として、院納相違あるべからず候。
仍って菓子箱・舟皿・室盆贈り給い候。
拝受せしめ候。
塗色以下尋常ならざる間、自愛(少なからず?)候。
度々の御懇情大慶に候。
なお夕庵(武井)申すべく候。恐惶敬白(以下略)
9月20日
武井夕庵と木下秀吉が連署で、妙智院領の百姓に対し連署状を発給。
内容は、信長が黒印状を発給された以上、年貢や公事物は、妙智院に直接納めること、いままで介在していた石成友通にも指令したので、指出(土地台帳)を整備して妙智院に渡すこと、隠田や上田を下級田にすり替えることを禁止したもの。『妙智院文書』
西院之内、妙智院策彦東堂御寺領分安弘名之事、殿様より被仰付、御寺へ可為御直納之旨、被成御印判上ハ、年貢、諸公事物、又無不法、懈怠可致其沙汰候、石成方へも右之分被仰出候間、聊以不可有別条候、指出之儀相調候て、妙智院納所へ可渡進候、或者隠田、或物上田迄、薄地ニ替、恣々族於有之者、可被処厳科候、此旨従両人可申之由候、恐々謹言
夕庵
九月廿日 爾云(花押)
木下藤吉郎
秀吉(花押)
西院之内妙智院領
百姓中
(書き下し文)
西院のうち、妙智院策彦東堂の御寺領分(安弘名)の事、殿様より仰せ付けられ、御寺へ御直納たるべきの旨、御印判をなさるるの上は、年貢・諸公事物、又は不法・懈怠なく、その沙汰を致すべく候。
石成(友通)へも右の分を仰せ出され候間、いささか以って別条あるべからず候。
指出の儀を相調え候て、妙智院納所へ渡しまいらすべく候。
あるいは隠田、あるいは上田までを薄地に替え、恣々の族有るに於いては、厳科に処せらるべく候。
この旨両人より申すべきの由にて候。恐々謹言(以下略)
(備考)
なお、織田家が発給した妙智院宛判物は、同年12月16日付の明智・村井連署状が2通存在する。
9月22日
近江の一揆衆である中島惣左衛門、朝倉方の小松原孫三郎へ「武田信玄がもし約定を違えて出馬しないのであれば、近江近辺の戦況は最悪になる」とする書状を送る。『誓願寺文書』
9月26日
信長、越後の上杉謙信へ江北の戦況を伝える書状を送る。(九月二十六日付織田信長書状写)『米沢市立図書館所蔵』『新集古案』『温故足微抜萃』
朝倉義景至于江北小谷籠城候、種々帰国調儀之由候へ鞆、懸留候間、難測、一日一日与在之旨ニ候、是非共打果候、但夜中敗北ニ付てハ、不及了簡候、此為体ニ候条、其節一揆等ニ朝倉加勢不実候、爰元之趣、専柳斎如見及候、小谷を押詰、虎御前山と申ニ、地理三ヶ所申付候、此山と横山之間ニ宮部と申地候、是にも一城相構、人数陶々入置候、信長ハ横山ニ移候、東国辺事、弥可聞合候、其表備堅固ニ可被仰付儀、簡要候、追々可申候、恐々謹言
九月廿六日 信長
不識庵
進覧之
(書き下し文)
朝倉義景江北小谷に至りて籠城に候。
種々、帰国を調儀の由に候へども、懸け留まり候間、測り難く、一日一日とこれある旨に候。
是非とも討ち果たし候。
ただ、夜中に敗北に付きては、了簡に及ばず候。
このていたらくに候条、その節一揆等に朝倉の加勢は不実に候。
爰元の趣き、専柳斎(山崎=上杉方の使者)の見及ぶ如くに候。
小谷を押し詰め、虎御前山と申すに、地理三ヶ所申し付け候。
この山と横山との間に宮部と申す地候。
是にも一城相構え、人数よなよなと入れ置き、信長は横山に移り候。
東国辺の事、いよいよ聞き合すべく候。
その表の備え堅固に仰せ付けらるべき儀、簡要に候。
追々申すべく候。恐々謹言(以下略)
同日
武田信玄、木曽氏の家老山村良利(三郎左衛門尉殿)へ、飛騨国衆の調略を労う旨の書状を発給。『山村家文書(九月二十六日付武田信玄判物写)』
定
飛州之調略、別而馳走、祝着候、因茲、於濃州之内一所可相渡候、名所等可有言上候者也、仍如件
元亀三年壬申
九月廿六日 信玄(花押)
山村三郎左衛門尉殿
定
飛州(飛騨国)の調略、祝着に候。
これにより、濃州(美濃国)の内に於いて、一所相渡すべく候。
名所等言上有るべく候ものなり。仍ってくだんの如し
元亀三年壬申
九月二十六日 信玄(花押)
山村三郎左衛門尉(良利)殿
同日
武田信玄、遠藤胤基の家老である遠藤加賀守へ、信濃の地百貫の知行を与える約束する。『鷲見栄造氏所蔵文書』
当方之儀、別而荷担之由候間、於于信州百貫之地進之候、猶三村兵衛尉可申候者也、仍如件、
元亀三年壬申
九月廿六日 信玄(判)
遠藤加賀守殿
(書き下し文)
当方の地、別して荷担の由候間、信州に於いて百貫の地、これをまいらせ候。
なお三村兵衛尉申すべく候ものなり。仍って状くだんの如し
元亀三年壬申
九月二十六日 信玄(判)
遠藤加賀守殿
同日
武田信玄、遠藤一族の忠節を期待する旨の書状を発給。『鷲見栄造氏所蔵文書(九月二十六日付武田信玄書状写)』
態使者喜悦、仍而向後別而可被相談旨、得御意候、然者同名中在一味、一逢之忠節、此時極候、委細露条候間、略紙面候、恐々謹言
九月廿六日 「晴信御判」
遠加賀殿へ
(書き下し文)
わざと使者喜悦、仍って向後は別して相談ぜらるべき旨、御意を得候。
然らば同名中一味在り、一応の忠節、この時の極みに候。
委細露条候間、紙面を略し候。恐々謹言
(備考)
信玄の調略の手が飛騨のみならず、美濃にまで及んでいたのは興味深い。
木越城主の遠藤胤基は分家であり、本家は郡上八幡に住している。
万が一内通が露見した際は、本家に類が及ばぬよう対策したのだろう。
同日
甲斐の武田信玄、加賀の杉浦玄任(壱岐法橋)へ作戦等を伝える旨の書状を発給。『尊経閣文庫所蔵文書』
至于今日出馬遅々、定而無曲可被思召候、飛州之儀相調、又遠州表の備、聞合候故、如此之猶予、可被存不審候、此上者無用捨出馬候、畢竟富山之地無油断普請、極此一ヶ条候、漸及寒気候間、至于越後長陣不可叶候、其分別尤候、委曲附与彼口上候、恐々謹言
九月廿六日 信玄(花押)
杉浦壱岐法橋
長延寺
(備考)長延寺の住職は実了か。
寒気に差し掛かってきたので、越後勢の長陣は難しいだろうと楽観視している様子が興味深い。
同年10月1日付の信玄・勝頼書状も参照されたい。
9月28日
信長、革島一宣(越前守)、革島秀存(市介)へ再度知行を安堵する朱印状を発給。
詳細は滝川一益に伝達させる。『九月二十八日付織田信長朱印状(革島文書)』『古簡雑纂』
貴方へ遺候知行、自何方違乱候共、不可被許容候、尚滝川可申候、恐々謹言
九月廿八日 信長(朱印)
革嶋越前守殿
革嶋一介殿
(書き下し文)
貴方へ遣わし候知行、いずれ方より違乱候へども、許容せらるべからず候。
なお滝川(一益)申すべく候。恐々謹言
九月二十八日
革嶋越前守(一宣)殿
革嶋一介(秀存)殿
同日
滝川一益、革島氏へ去る9月3日付の信長朱印状を廃し、改めて革島氏へ知行を安堵する旨の副状を発給。
芳墨拜領候、仍革嶋知行之儀申聞候、如此申拵候段、失面目候、然者、重而朱印遣候条、自然猥ニ彼知へ不謂儀被申懸候はヽ、可有成敗之由候、其分可被仰付候、恐々謹言
滝川左近
九月廿八日 一益(花押)
細兵様
尊報
(書き下し文)
芳墨拝領候。
仍って革嶋知行の儀申し聞かせ候。
かくの如くに申し拵え候段、面目を失い候。
然らば重ねて朱印を遣わし候条、自然みだりにかの地へ言われざる儀を申し懸けられ候はば、成敗あるべきの由に候。
その分仰せ付けらるべく候。恐々謹言(以下略)
(備考)
同年9月3日付け信長朱印状により、革島氏の知行安堵が成立した。
しかし、文面があやふやであったためか問題が起きてしまった。
のちに改めて知行を安堵する旨を滝川一益から指令した。
一益はこの措置で面目を失ったと憤慨している。(本状)
重ねて信長の朱印状が出され(同日付の『革島文書』)、一益は副状を発給した。(本状)
宛名の細川藤孝は山城勝竜寺城を守り、西岡に住す革島氏らの土豪に対して強い影響力をもっていた。
そのため問題が起きたと考えられる。
なお、天正4年(1576)2月に革島一介(秀存)は、一益の斡旋を謝して米三十石を毎年進呈すると約すこととなる。
本状は宛名を「様」としている。
この時代には珍しい書札礼である。
冒頭に「芳墨」としているあたりからも、一益がいかに怒りを抑えてこの書を書いているのかを伝えたかったのだろうか。
9月29日
武田信玄・勝頼が連署で飛騨の三木顕綱(豊前守殿)へ、雪解け次第姉小路(三木)自綱を討伐する旨の書状を発給。『国立国会図書館所蔵「武家事紀 三三(九月二十九日付武田信玄・勝頼連署状写)」』
江馬中務少輔、三村右兵衛門尉所来翰、具被閲、抑自綱対当方、年来辜負無念千万之条、無二及行可決是非之旨、令覚悟候半、以御媒介一往和平ニ被取成候処ニ、無幾程変化、遺恨不浅候、因茲当来両月中、向其国動干戈可退治自綱之旨、雖議定候、漸及寒天、就中其表深雪之時分候之条、先延引、来春者雪も消馬足も融候者、必令出馬可散鬱憤候、然則貴辺御本意不可有程候、誠自綱如此被変色之上、浮沈共不可有心疎候、委曲江間中務少輔、三村右兵衛門尉可申候、恐々謹言
九月廿九日 信玄(花押影)
勝頼(花押影)
豊前守殿
(書き下し文)
江馬中務少輔(江馬輝盛)・三村右兵衛門尉所の来簡、つぶさに被閲。
そもそも自綱(姉小路頼綱)当方に対し、年来孤負(=裏切ること)無念千万の条、無二のてだてに及び、是非を決するの旨、覚悟せしめ候はん。
御媒介を以て一応の和平に取り成され候ところに、幾程無く変化、遺恨浅からず候。
これにより、当・来の両月中、その国に向いて干戈を働き、自綱を退治すべきの旨、議定に候といえども、ようやく寒天に及び、なかんずく、その表深雪の時分に候の条、まず延引す。
来春は雪も消え馬足も融け候はば、必ず出馬せしめ、鬱憤を散らすべく候。
然らば則ち、貴辺の御本意ほど有るべからず候。
誠に自綱かくの如く変色せらるの上、浮沈とも心疎有るべからず候。
委曲江間中務少輔(江馬輝盛)・三村右兵衛門尉申すべく候。恐々謹言(以下略)
(備考)
信玄は姉小路(三木)氏に対し、遺恨深重な様子である。
宛名である三木顕綱は姉小路頼綱(三木自綱)の弟にあたる。
飛騨国はこれまで、上杉謙信が大きな影響力を持っていたが、織田方の遠藤氏(郡上八幡)・斎藤利治(加治田)と懇意にしている領主もいた。
また、武田方の木曾氏と多年に渡り親しい関係を持つ領主もあり、飛騨の情勢は複雑微妙な情勢であった。
このたび上杉謙信が越中の戦いを有利に進めていたので、武田信玄は加賀の杉浦氏と連携して飛騨の国衆を切り崩す調略を行っていた。
しかし、これが信長が信玄へ疑念を抱く要因の一つとなるのである。
9月
武田信玄、美濃遠藤加賀守(遠藤胤基の家老)へ知行宛行状を発給。『鷲見栄造氏所蔵文書(元亀三年九月日付武田信玄判物写)』
今度当方江荷担忠節、仍而於東美濃百貫地進之候、尚三村兵衛尉可申候、仍而如件、
元亀三申年
九月 日 「晴信御判」
遠藤加々守とのへ
(書き下し文)
この度当方へ荷担、忠節。
仍って東美濃に於いて百貫の地これをまいらせ候。
尚三村兵衛尉申すべく候。
仍ってくだんの如し。(以下略)
(備考)信玄は同年9月26日付で、同じく遠藤加賀守へ信州百貫の地を当てる旨の知行宛行状を発給していることから、ここ文書にはやや疑問が残る。
信長、 異見十七ヶ条を将軍へ送りつける
9月
この時期、将軍・足利義昭に異見十七ヶ条を送りつける。『尋憲記 九(元亀四年二月二十二日条)』『年代記抄節』『吉川友康氏所蔵文書』『原本信長記(信長公記)』※以下『信長公記』と記す
一、当将軍へ自信長十七ヶ条、一書以申入候、一書新持参之条、写置也、
公方様江従信長条々
(書き下し文)
一、当将軍へ信長より十七ヶ条、一書を以て申し入れ候。
一書新(祐岩)持参の条、写し置く也。
公方様へ信長よりの条々
一、御内裏之儀、(〇原本信長記、「御」以下ノ五字ヲ「御参内之儀」ニ作ル、)光源院(義輝)殿様御無沙汰付而、果而御冥加なき次第、事旧候、従是当御代之儀、年々無懈怠様ニと、御入洛之刻みヨリ申上候処、早被思召忘、近年御退転無勿躰存候事、
(書き下し文)
一、御内裏の儀、(〇原本信長記、「御」以下の五字を「御参内の儀」に作る。)光源院(足利義輝)殿様御無沙汰に付きて、果たして御冥利なき次第、ことふり候。
これによりて、当御代の儀、年々懈怠なき様にと、御入洛のきざみより申し上げ候ところ、早くも思し召し忘れられ、近年御退転、もったいなく存じ候こと。
(現代語訳)
1.宮廷のことを故足利義輝殿は、等閑に付したため、果たして神仏の加護を受けられなかった顛末は、よくご存知のこと。
だから当将軍に対しては、いつでも宮廷によく勤めるようにと、初めて御入洛なされた頃(1568年10月14日)から申し上げてあるのに、すぐにお忘れなされ、近年は勤められないのは不謹慎であること。
一、諸国江御内書ヲ被遣、馬其外御所望之躰(〇原本信長記「躰」ノ次ニ「外聞」の二字アリ、)如何存候間、被加御遠慮、尤存候、但、被仰付候ハて不叶子細者、信長ニ被仰聞、副状を可仕之旨、兼而申上、被成御心得由候つれ共、左も無御座、遠国江被成御内書、御用被仰付候儀、㝡前之首尾相違ニ候、何方ニも可然馬なと御耳に入候者、信長馳走進上可申由、申旧候キ、左様ニ候ハて、以密々(〇原本信長記、「密々」ノ次ニ「直ニ」ノ二字アリ、)被仰遣候儀、不可然存候事、
(書き下し文)
一、諸国へ御内書を遣わされ、馬そのほか御所望の躰(〇原本信長記「躰」の次に「外聞」の二字があり。)如何と存じ候間、御遠慮を加えられ、もっともに存じ候。
ただし、仰せつけられ候はて叶わざる子細は、信長に仰せ聞かせられ、副状を仕るべきの旨、兼ねて申し上げ、御心得をなさるるの由に候つれども、左も御座なく、遠国へ御内書をなされ、御用を仰せ付けられ候儀、最前の首尾相違に候。
いずれかたにも然るべき馬など御耳に入り候はば、信長馳走し進上申すべき由、申しふり候き。
左様に候はて、密々(〇原本信長記、「密々」の次に「直に」の二字あり。)を以て仰せ遣わされ候儀、然るべからず存じ候こと。
(現代語訳)
2.諸国に御内書を発給し、馬などをご所望なされるのはいかがなものかと存じますゆえ、お考え直しいただきたい。
ただし、ぜひとも下知なさりたい理由があるなら、一旦信長に仰せ付けられて、副状を添えるようにと既に申し上げ、公方様も承知されているはずである。
しかし、それを無視して遠国に御内書を出し、御用を命じられているのはお約束と違う。
どこでも、よい馬のことが御耳に入ったなら、信長が奔走して進上するとのお約束は、よくご存じであるはずだ。
ところが内密で命じられているのは約定に反する。(殿中御掟の約定)
一、諸唯衆方々、御伴(〇原本信長記、「伴」ノ次ニ「御届」ノ二字アリ、)申、忠節無油断輩ニハ、似合ニ(〇原本信長記、「合」ノ次ニ「之御恩賞」ノ四字アリ、)不被宛行、今ニ指者ニもあらさるニハ、被加御扶助候、左様ニ候てハ、忠不忠も不入ニ罷成候、諸人ノをもわく不可然存候事、
(書き下し文)
一、諸侯衆の方々、御伴(〇原本信長記、「伴」の次に「御届」の二字あり。)申し、忠節油断無き輩には、似合いに(〇原本信長記、「合」の次に「之御恩賞」の四字あり。)宛行われず、今に指せる者にもあらざるには、御扶助を加えられ候。
左様に候ては、忠・不忠も入らざるに罷りなり候。
諸人の思惑然るべからず存じ候こと。
(現代語訳)
3.諸大名のうちで、将軍の御供をするなど、忠義怠りないものに対し、相当の知行を与えられず、さほどの者ではない者に扶持を加増なされている。
それでは忠義・不忠も区別がなく、褒賞が適切にはならない。
それでは諸人が困惑するのは当然である。
一、今度雑説付而、御物をのけらるゝ由候、都鄙無其隠候、就其京都以外さハきたる由、驚入候、御構之御普請以下辛労造作ヲ仕、御安座之儀候処、御物ヲのけられ候てハ、併(〇原本信長記、「併」ヲ、「再」に作ル、)何方へ可被移御座候哉、無念子細候、左候時者、信長辛労もいたつらニ罷成候事、
(書き下し文)
一、この度雑説に付きて、御物をのけらるるの由に候。
都鄙その隠れなく候。
それに就きて京都以っての他騒ぎたる由、驚き入り候。
御構えの御普請以下辛労して造作を仕り、御安座の儀に候ところ、御物をのけられ候ては、併わし(〇原本信長記、「併」は、「再」に作る。)何方へ御座を移さるべく候哉。
無念の子細に候。
さ候時は、信長の辛労もいたずらに罷りなり候こと。
(現代語訳)
4.この度の風説について、御物を隠匿されるとの噂は都鄙(とひ=都会と田舎)隔たり無く広まっている。
そのため、京都では特に大騒ぎになっているとのこと。
誠に驚くばかりである。
将軍御座所(二条御所)の普請も苦労して拵え、御安座できているのに、御物を隠匿なさっているのは、どこに御座所を移される所存なのか。
残念で仕方がない。
そんなことになれば、信長のいままでの苦労は徒労に帰する。
一、賀茂之儀、石成ニ被仰付、百姓前等御糺明候由、表向ハ御沙汰候て、御内儀者御用捨之様ニ申触(〇原本信長記、「申触」ヲ、「申鳴シ」ニ作ル、)候、惣別か様之寺社方御勘落、(〇原本信長記、「勘」ヲ、「欠」に作ル、)如何ニ存候へ共、石成堪忍不届之由、(〇原本信長記、「之由」ノ二字ナシ、)令難儀旨候者、先此分ニ被仰付、御耳をも被伏(〇原本信長記、「御」以下ノ六字ヲ、「御呵をも被休」に作ル、)又、一方之御用ニも被立様ニと存之処、御内儀如此候者、不可然存候事、
(書き下し文)
一、賀茂の儀、石成(友通)に仰せ付けられ、百姓前等を御糾明候由、表向きは御沙汰候て、御内儀は御用捨の様に申し触れ(〇原本信長記、「申触」を、「申鳴し」に作る。)候。
惣別か様の寺社方御勘落、(〇原本信長記、「勘」を、「欠」に作る、)如何に存じ候へども、石成堪忍不届きの由、(〇原本信長記、「之由」の二字なし。)難儀せしむる旨に候はば、まずこの文に仰せ付けられ、御耳をも伏せられ(〇原本信長記、「御」以下の六字を、「御呵をも被休」に作る。)又一方の御用にも立てらるる様にと存ずるのところ、御内儀かくの如くに候はば、然るべからず存じ候こと。
(現代語訳)
5.賀茂の件で石成友通に命じられた百姓前などを調査される由、表向きは下令したが、裏では捨て置くように命じられたとの噂がある。
このように寺社の領地を没収するのはどうかと思うが、石成が辛抱できかね、困惑しているならば、まず石成の言い分に耳を傾けなされ、あるいは雑音は聞かれず、そして一方の御用に立てられるようにと思っていたのに、面従腹背の態度はよろしからず。
一、対信長無等閑輩、女房衆以下迄、思食あたらるゝ由、令迷惑候、我等ニ疎略なき者ヲ(〇原本信長記、「ヲ」ヲ「と」二作ル、)被聞召候者、一入被懸御目様ニ候てこそ忝可存を、かいさまニ御心得参候、如何様之子細候哉之事、
(書き下し文)
一、信長に対し等閑無き輩、女房衆以下迄、思し召しあたらるるの由、迷惑せしめ候。
我らに疎略なき者を(〇原本信長記、「を」を「と」に作る。)聞こし召され候はば、一入御目に懸からるる様に候てこそ忝けなく存ずべきを、かいさまに御心得参り候。
いかようの子細に候哉の事。
(現代語訳)
6.信長と親しい者は、女房衆であっても遠ざけられることはいかがなことか。
親しくしている者を承知されたら、一層取り立てられてこそ忝く思うのに、わがままな御心と思わずにはいられない。
いかなる理由によるものか。
一、無恙致奉公、何之罪(〇原本信長記、「罪」ヲ「科」二作ル、)も御座候ハねとも、不被加扶持、京都ニ堪忍不届者共、信長ニたより候て、歎申候、定私言上候者、何とそ御あわれミも可在之かと存知候ての事ニ候、且者、不便ニ存知、且ハ公儀御為と存候間、御扶持之儀申上候へ共(〇原本信長記、「共」ノ次ニ「一人も」ノ三字アリ、)無御許容候、余ニかたき御意(〇原本信長記、「余」以下ノ七字ヲ「余又緊なる御諚共」二作ル、)候間、其身ニ対しても無面目候、観世与左衛門尉、古田可兵衛尉、上野紀伊守類之事、
(書き下し文)
一、恙無く奉公を致し、何の罪(〇原本信長記、「罪」を「科」に作る。)も御座候はねども、御扶持も加えられず、京都に堪忍届かざるもの共、信長に頼り候て、嘆き申し候。
定めて私に言上候へば、何とぞ御哀れみも在るべきかと存じ候ての事に候。
且つは不憫に存じ、且つは公儀の御為と存じ候間、御扶持の儀申し上げ候へども、(〇原本信長記、「ども」の次に「一人も」の三字あり。)御許容無く候。
余にかたき御意(〇原本信長記、「余」以下の七字を「余又緊なる御諚共」に作る。)候間、その身に対しても面目無く候。
観世与左衛門尉(国広)、古田可兵衛尉、上野紀伊守(豪為)たぐいの事。
(現代語訳)
7.何事もなく奉公し、何の罪も無いのに扶持を与えられず、京都で辛抱できかねる者が、信長を頼って泣きついてきた。
定めて私の方から申し上げれば、公方様の御哀れみもあるかと知ってのことである。
一方では哀れに思い、他方では公儀の御為と考え、扶持のことを申し上げたが許されない。
余りにも狭い御考えで、彼らに対して面目ない。
彼らとは観世国広、古田可兵衛尉、上野豪為らのことである。
一、若州安賀庄御代官職(〇原本信長記、「職」ノ一字ナシ、)之事、粟屋弥四郎(〇原本信長記、弥四郎ヲ「孫八郎」ニ作ル、)訴訟申上候、(〇原本信長記、「候」ノ次ニ「間」ノ一字アリ、)難去(〇原本信長記、「去」ノ次ニ「存」ノ一字アリ、)種々執次(〇原本信長記、「次」ノ一字ナシ、)申候へ共、御心得不行過来候事、
(書き下し文)
一、若州安賀庄御代官職(〇原本信長記、「職」の一字なし。)の事、粟屋弥四郎(〇原本信長記、弥四郎を「孫八郎」に作る。)訴訟申し上げ候。(〇原本信長記、「候」の次に「間」の一字あり。)
去り難く(〇原本信長記、「去」の次に「存」の一字あり。)種々取次(〇原本信長記、「次」の一字なし。)申し候へ共、御心得は行き過ぎで来らず候こと。
(現代語訳)
8.幕府御料所である若狭国安賀庄の代官職の件で、粟屋弥四郎が訴訟した。
拒否しがたく、色々と取り次いだが、公方様の御心得は遠く離れてしまい、合意点に達し得なかった。
一、小泉女房衆預ヶ置候雑物幷質物ニ置候腰刀、脇指類迄、被召置候由候、小泉何とそむほんをも仕候て、造意曲事之子細も候者、根断茂枯れも勿論ニ候、是ハ不叶喧嘩(くちへんに花 PCで変換できず)ニ而相果候、一旦者被守法度尤候、是程迄被仰付候儀、唯御よくとくの儀ニよりたると、世上ニ可存候事、
(書き下し文)
一、小泉の女房衆が預け置き候雑物並びに質物に置き候腰刀・脇差の類まで、召し置かれ候由に候。
小泉何とぞむほんをも仕り候て、造意曲事の子細も候はば、根断も枯らしても勿論に候。
これは叶わざる喧嘩にて相果て候。
一旦は法度を守られて尤もに候。
これほどまでに仰せ付けられ候儀は、唯御よくとくの儀によりたると、世上に存ずべく候こと。
(現代語訳)
9.小泉某が法度である喧嘩をして殺された。
公方様はその責任を問い、小泉の女房たちが某所に預けた雑物や質物の腰刀・脇差まで没収した。
もし小泉が謀叛をし、悪計曲事の証拠があるならば、根葉を枯らすような処置も必要だ。
しかし、小泉は喧嘩のために死亡したのだから、その罪には法度に背いた件のみを責めるべきだ。
公方様がそれほどまでに命じられるのは、ただ欲得のためだと世間の人々は考えるだろう。
一、元亀之年号不吉候者、(〇原本信長記、「者」ヲ「間」ニ作ル、)かいけん可然之由、天下執沙汰仕候付而、(〇原本信長記、「天」以下の九字ヲ、「天下之沙汰に付て申上候」ニ作ル、)禁中ニも御催之処、聊之雑用不被仰付、于今遅々候、是は天下之御為候処、如此御油断、不可然存候事、
(書き下し文)
一、元亀の年号不吉に候はば、(〇原本信長記、「者」を「間」に作る。)改元然るべきの由、天下執り沙汰仕り候につきて、(〇原本信長記、「天」以下の九字を、「天下之沙汰に付て申上候」に作る。)禁中にも御催のところ、いささかの雑用を仰せ付けられず、今に遅々に候。
これは天下の御為に候ところ、かくの如くの御油断、然るべからずと存じ候こと。
(現代語訳)
10.元亀の年号は不吉なので、改元することは天下の世論となった。
禁中からも幕府に指令したのに、公方様から少額の御用金も献上なされないために実行されていない。
これは天下のためであるのに、実行しないのはよくないことである。
一、烏丸御勘気かうむる由候、息之儀者、いきとおりも無余儀候、親父御赦免候様ニと、雖申上候、御心得不行候者、不及是非候処、(〇原本信長記、「親父」以下ノ二十六字ナシ、)誰哉覧内儀之御使申候て、金子ヲ被召置、出頭させられ候由、歎敷存候、人ニより罪ニよりて、過怠として被仰付候趣も可在之段、是ハ堂上之仁ニ候、当時公家ニハ此仁之様ニ候処、如此次第、外聞笑止存候事、
(書き下し文)
一、烏丸(光康)御勘気蒙る由に候。
息(光宣)之儀は、憤りも余儀無く候。
親父御赦免候様にと、申し上げ候といえども、御心得行かず候はば、是非に及ばず候のところ、(〇原本信長記、「親父」以下の二十六字なし。)誰や覧内儀の御使い申し候て、金子を召し置かれ、出頭させられ候由、嘆かわしく存じ候。
人により罪によりて、過怠として仰せ付けられ候趣もあるべくの段、これは堂上の仁に候。
当時、公家にはこの仁の様に候ところ、かくの如きの次第、外聞笑止に存じ候こと。
(現代語訳)
11.烏丸光康が公方様の御勘気を蒙ったとのこと。
息子である烏丸光宣もこれを憤り出奔した。
信長は光康を赦免してくれるようにと申し上げたが承知されず、それも致し方なく思っていたところ、密かに金子(黄金)をとり、出仕をさせられたとのこと。
まことに嘆かわしいことである。
当然、罪により過怠として金子を取る例もある。
しかし、烏丸は堂上の人である。
当時、公家のうちでは、光康が優れた人物であるのに、このような顛末では、外聞は如何なものであろうか。
一、他国ヨリ御礼申上候金銀を、進上歴然ニ候処、御隠蜜候て被召、御用ニも不相立候段、何之御為候哉之事、
(書き下し文)
一、他国より御礼を申し上げ候金銀を、進上歴然に候ところ、御隠密候て召され、御用にも相立てず候段、何の御為に候哉のこと。
(現代語訳)
12.諸国から御礼として金子を進上したことは歴然としているのに、これを隠されて、御用にも立てないというのは、何のためであるか。
一、明智地子銭を納置候て、買物之かハリニ渡遣候ヲ、山門領之由被仰懸ケ(〇原本信長記、「懸」ノ次ニ「預」ノ一字アリ、)置候者之かたへ御押候事、
(書き下し文)
一、明智(光秀)地子銭を納め置き候て、買物のかわりに渡し遣わし候を、山門領の由、仰せ懸け(〇原本信長記、「懸」の次に「預」の一字あり。)られ置き候者のかたへ御押し候こと。
(現代語訳)
13.明智光秀が地子銭(貸地代)を収納しておいて、買物の代銭に渡したところ、そこは叡山領だと言い懸け、渡した者から横領したことは不法である。
一、去度御城米を被出、金銀ニ御売買之由候、公方様御商買之儀、古今不及承候、今時分之儀候間、御蔵ニ兵粮在之躰候て、(〇原本信長記、「候て」ヲ、「こそ」ニ作ル、)外聞も尤存候、如此次第驚存候事、
(書き下し文)
一、去度御城米を仰せ出され、金銀に御売買の由に候。
公方様御商買の儀、古今承り及ばず候。
今時分の儀に候間、御蔵に兵糧あるの躰(てい)候て(〇原本信長記、「候て」を、「こそ」に作る。)外聞も尤もに存じ候。
かくのごときの次第驚き存じ候こと。
(現代語訳)
14.この夏に御蔵の米を放出し、金銀に交換されたと聞いた。
公方様が御商買のことは古今未曾有のことだ。
今時分のことだから、御蔵に兵糧がある状態であれば外聞も良い。
にもかかわらず、それを金銀に交換するなど驚くばかりである。
一、御とのいニ被召置候若衆ニ、御扶持を被加度思召候者、当座之何成共可有御座候処、或御代官職被仰付、或非分公事被申次候事、天下之ほうへん沙汰限存候事、
(書き下し文)
一、御宿直に召し置かれ候若衆に、御扶持を加えられたく思し召し候はば、当座の何なりとも御座あるべく候ところ、あるいは御代官職を仰せつけられ、あるいは非分の公事を申し次がれ候こと、天下のほうへん沙汰の限りに存じ候こと。
(現代語訳)
15.宿直をさせた若衆に扶持を加増したいと思し召されたならば、当座の品が何でもあるはずなのに、彼らへ御代官職を与え、あるいは不法な公事を取次がせるので、天下の評判は論外である。
一、諸唯衆武具、兵粮已下も耆ハ無之、金銀を専ニ商買(〇原本信長記、「商買」ヲ「蓄」ニ作ル、)之由承及候、牢人之したくと存候、是も上様金銀を被召置、雑説之砌者、御構ヲ被出候付而、下々迄、さてハ京都ヲ被捨趣と見及候ての儀たるへく候、上人まもる段(〇原本信長記、「上」以下ノ六字ヲ、「上一人を守之段」ニ作ル、)ハ、不珎候事、
(書き下し文)
一、諸侯衆の武具・兵糧以下も蓄えはこれなく、金銀を専らに商買(〇原本信長記、「商買」を「蓄」に作る。)の由、承り及び候。
浪人のしたくと存じ候。
これも上様金銀を召し置かれ、雑説の砌は、御構を出られ候に付きて、下々までもさては京都を捨てらるる趣きと見及び候ての儀たるべく候。
上人まもる段(〇原本信長記、「上」以下の六字を、「上一人を守之段」に作る。)は珍しからざるのこと。
(現代語訳)
16.諸大名衆が武具・兵糧等の準備もせず、もっぱら金銀を売買しているとの世評を承知している。
浪人のした場合に備えてのことと思われる。
これも公方様が金銀を備蓄しており、不穏の場合には御所を脱出するについて、下々の者までも、「さては公方が京都を捨てるおつもりかな」と見ているだろう。
公方様が御自分一人を守るのは当然のことである。
(最後の一文は、義昭が都からの逃避を準備しているのは何故かと問うているのだろうか。信長の真意は不明)
一、諸事付而、御欲ニふけられ候儀、理非ニも外聞ニも不被立入之由、其聞候、然者不思儀之土民、百姓ニいたる迄も、あしき御所と申なし候由候、普広院殿様ヲ左様ニ申たると伝承候、それハ各別候、何故(〇原本信長記、「故」ノ次ニ「如此」ノ二字アリ、)御かけ事を申候哉、是を以御分別可参候哉之事、
(書き下し文)
一、諸事に付きて、御欲にふけられ候儀、理非にも外聞にも立ち入らざるの由、その聞こえ候。
然らば不思議の土民・百姓にいたる迄も、あしき御所と申しなし候由に候。
普広院(足利義教)殿様を左様に申したると伝え承り候。
それは各別に候。
何故(〇原本信長記、「故」の次に「如此(かくのごとく)」の二字あり。)御かげ事を申し候哉。
是を以て御分別参るべく候哉のこと。
(現代語訳)
17.万事について貪欲で、道理も外聞も無視なさるとの噂である。
それゆえに下層の農民・百姓にいたるまでも「悪しき御所」と噂しているのである。
普広院(足利義教)殿様も、そのような悪口をされていたと聞いている。
これは別の例である。
何故に人々が陰口を叩くのか。
このことでも御分別なさるべきことである。
以上
一、当将軍へ信長より十七ヶ条、一書を以て申し入れ候、一書新(祐岩)持参の条、写し置く也、
公方様江信長よりの条々、
一、御内裏の儀、(〇原本信長記との異同を註した。「御」以下の五字は「御参内之儀」とある。)御入洛の刻より申し上げ候処、早くも思召し忘れられ、近年御退転、勿躰なく存じ候事、
9月
信長、近江国金森へ全3ヶ条の条書を下す。『善立寺文書』
定 条々
一、楽市、楽座たる上ハ、諸役令免許畢、幷国質、郷質不可押□、付、理不尽之催促使停止之事、
一、往還之荷物当町江可着之事、
一、年貢之古未進幷旧借米銭已下、不可納所之事、
右於違背之輩者、可処罪科之状如件、
元亀三年九月日 (信長朱印)
(書き下し文)
定 条々
一、楽市・楽座たる上は、諸役を免許せしめおわんぬ。
並びに国質・郷質を押□べからず。
付けたり、理不尽の催促を使い、停止の事。
一、往還の荷物は、当町へ着くべきの事。
一、年貢の古き未進並びに旧借米銭以下は、納所すべからざるの事。
右、違背の輩に於いては、罪科に処すべきの状くだんの如し。(以下略)
(備考)
金が森は守山に位置し、中山道沿いの商業に適した地であった。
この隣接地三宅の両城に、本年1月、六角承禎父子が一向一揆と連絡して籠城していた。
7月には佐久間信盛が金森城を攻略し、三宅城を降している。
この条書は、戦後の復興と町人を町へ還住させるための一時的な措置であろう。
第一条では、諸役の免除に加えて国質(くにじち)・郷質(ごうじち)を取らないこと。
さらに不法な催促を禁じている。
国質・郷質とは、国か郷で抵当権を執行することを指す。
第二条では、中山道を往復する荷物は、守山宿ではなく、金が森に入れるとの意味である。
第三条では、年限の古い未進や旧借の米銭等を無効にする処置のこと。
なお、当時の善立寺は廃寺となっていたようだ。
2年後の天正2年(1574)5月日付で佐久間信栄が金森町に禁制を下し、引き続き楽市・楽座を認めている。
武田信玄 徳川家康討伐のため甲府を出陣
10月1日
武田信玄・勝頼父子、越中国勝興寺へ援軍を出せなかったことを謝罪する旨の書状を発給。『勝興寺所蔵文書(十月一日付武田信玄・勝頼連署状)』
其国之様子余無心許候条、以飛脚申候、抑々不慮之仕合故、富山落居、無是非次第候、
昨年以来加越両州対陣之事候之間、随分手合之備無油断候き、雖然信玄自身至于越後乱入之儀は、遠三之動無拠故遅々、其已後彼表明隙帰陣候、直に向越府可動干戈之旨令儀定、既信越之境迄先衆立遣候之処、於于途中得病気躊躇之砌、輝虎退散に付而、無役に納馬候、信玄煩平元之願候、然則後詰之行、聊不可有用捨候、無二父子可令出馬候間、加州衆重而出張、其国静謐候之様、御肝煎尤に候、委曲期来信之時候、恐々敬白
十月朔日 信玄(花押)
勝頼(花押)
勝興寺
几下
(書き下し文)
其の国の様子心許無き余りに候条、飛脚を以て申し候。
そもそも不慮の仕合ゆえ、富山落居、是非無き次第に候。
去年以来加(加賀国)越(越中国)両州対陣の事に候の間、随分手合いの儀、油断無く候き。
然りといえども、信玄自身が越後へ乱入に至るの儀は、遠(遠江国)三(三河国)の動き無きによるゆえ、遅々、それ以後かの表へ、隙明きに帰陣候。
直に越府へ向かい干戈働くの旨儀定せしめ、既に信(信濃国)越(越後国)の境まで先衆を立ち遣わし候のところ、途中病気を得るに於いて、躊蹰(動けないという意)のみぎり、輝虎(上杉謙信)退散について、無役に納馬候。
信玄の煩い、平元の願いに候。
然らば後詰の、いささか用捨あるべからず候。
無二に父子出馬せしめ候間、加州衆重ねて出張、其の国静謐に候の様、御肝入り尤もに候。
委曲、来信を期すの時に候。恐々敬百
十月一日
信玄(花押)
勝頼(花押)
勝興寺
几下
(備考)
上杉の動きを封じようと、信玄と本願寺が大規模な一向一揆を扇動した。
しかし、去る9月に上杉謙信がこれを打ち破っている。
どうやら武田は、勝興寺の要請を受けて兵を出すつもりであったらしい。
本状には、先衆の者たちに国境まで出陣を命じたところで、私が病にかかってしまってどうしようか思案に暮れていた。
その間に上杉勢が兵を退いたので、戦果なく兵を納めたところだ。
次は援軍に必ず駆けつけるとしている。
なお、実際の武田家の動きは、信玄自らが大軍を率いて遠江の徳川領へ攻め入る準備をしていたようである。
信玄は同年9月26日付で杉浦壱岐法橋にも援軍を出せない旨を伝えている。
同日
甲斐の武田信玄、越前の朝倉義景(左衛門督殿)へ越中・加賀の一向宗へ加勢しないのを意外とし、自らが徳川家康討伐へ出陣したことを通達。『静嘉堂文庫所蔵文書「南行雑録(十月一日付武田信玄書状写)」』
於越中賀州衆輝虎対陣、此表出陣遅々意外候、一昨日三州衆先衆被遣候、信玄者今朔日打出候、可御心安候、畢竟其表堅固御備肝要候、恐々謹言
十月朔日 信玄
謹上 朝倉左衛門督殿
(書き下し文)
越中賀州衆輝虎対陣に於いて、この表出陣遅々、意外に候。
一昨日三州衆の先衆遣わされ候。
信玄は今一日打ち出で候。
御心安かるべく候。
畢竟、その表堅固の御備え肝要に候。恐々謹言(以下略)
同日
甲斐の武田信玄、浅井長政(備前守殿)へ出陣したこと伝え、励ます旨の書状を発給。『静嘉堂文庫所蔵文書「南行雑録(十月一日付武田信玄書状写)」』
如露先書、今朔日既打立候、弥其表被得勝利候様、義景被遂談合、無油断行肝要候、猶陣中より可申候、恐々謹言
十月朔日 信玄
浅井備前守殿
(書き下し文)
先書露の如く、今一日既に打ち立ち候。
いよいよその表勝利を得られ候様、義景と談合を遂げられ、油断無きてだて肝要に候。
猶陣中より申すべく候。恐々謹言(以下略)
10月3日
武田信玄、甲斐国府中を出陣。
遠江への進撃を開始する。
10月7日
信長、山城国妙心寺へ壬生西五条の田および塔頭領を安堵する。『妙心寺文書』
当寺領城州壬生西五条田、諸塔堂、祠堂、買得之田畠、寄進分所々散在等之事、不混自余、任御下知之旨、永全可有寺納之状如件、
元亀三
十月七日 信長(朱印)
妙心寺
(書き下し文)
当寺領城州壬生西五条田・諸塔堂・祠堂・買得の田畠・寄進分所々散在等の事、自余に混せず、御下知の旨に任せ、永く全く寺納あるべきの状くだんの如し(以下略)
山城壬生西五条田名主百姓中宛上野秀政等連署折紙案『妙心寺文書』
□□□□□(当寺領城州カ)壬生西五条田、同諸塔領所々散在等之事、依為勅願所、不混自余、被成御朱印候条、別而各御馳走候而、任当知行之旨、寺納候様、御入魂専一存候、為其一筆令啓候、尚言上之刻、可申述候、恐惶謹言
元亀三
十月七日 矢部善七郎
光佳(判)
上野中務大輔殿
嶋田但馬守殿
村井民部少輔殿
人々御中
(書き下し文)
□□□□□(当寺領城州カ)壬生西五条田・同じく諸塔領所々散在等の事、勅願所たるに依り、自余に混せず、御朱印をなされ候条、別しておのおの御馳走候て、当知行の旨に任せて、寺納候の様に、御昵懇専一に存じ候。
そのために一筆啓せしめ候。
なお言上のきざみ、申し述ぶべく候。恐惶謹言(以下略)
(備考)
矢部光佳は信長直臣。のちに家定と改名する。
京都が不穏になってきたためなのか、京都の妙心寺が信長に安堵を申請したのだろう。
上野秀政(中務大輔)は幕府奉公衆。島田秀満(但馬守)と村井貞勝(民部少輔)は織田家の吏僚である。
連署折紙案の方は同年10月18日付で実際に発給されている。
10月5日
信長、甲斐の武田信玄(法性院殿)へ、上杉との和睦に関する書状を発給。『十月五日付織田信長書状(個人所蔵)』
今度以赤澤申展候処、
回報之旨、快然之至候、甲・
越和与之儀、申噯候趣、都
鄙可為其聞候き、然而於御
出馬者、外聞如何之由、及
其理候鳧、御同心之条、大
慶不少候、無事模様之
儀付而、双方使者通路信
越堺目向雪候間、不自由之
故、雖相究候歟、来春可
申償候、是非共御入眼所希候、
随而江北敵城之儀、弥無
正躰候、然者、押之諸城ニ番
勢淘々与入置候、依之敵
閉山下式候間、信長不及
在城候之条、横山与岐阜
程近候間、切々令往還、分
国之儀承合候、於様躰者
可御心易候、猶以、今度御
働御遠慮候、為其、御礼啓
達候、恐々謹言、
十月五日 信長(花押)
謹上 法性院殿
(書き下し文)
この度赤澤を以て申し述べ候ところ、回報の旨、快然の至りに候。
甲・越和与の儀、申し噯(あつかい)候の趣き、都鄙(とひ)その聞こえたるべく候き。
然して御出馬に於いては、外聞如何の由、その理に及び候鳧(かも?)。
御同心の条、大慶少からず候。
無事模様の儀に付きて、双方使者の通路、信・越境目は向雪に候間、不自由の故といえども、相究め候か。
来春申し償うべく候。
是非とも御昵懇望む所に候。
従って江北敵城の儀、いよいよ正体無く候。
然らば、押しの諸城に番勢よなよなと入れ置き候。
これにより、敵は山を閉ざしき候間、信長は在城に及ばず候の条、横山と岐阜は程近き候間、切々と往還せしめ候。
分国の儀、承り合い候。
様躰(ようだい)に於いては御心安かるべく候。
なお以て、この度御働き御遠慮に候。
その為、御礼啓達候。恐々謹言(以下略)
(備考)
信長が信玄(甲)と上杉謙信(越)の和睦を調停していることは、都鄙の知るところである。
信玄の出馬は、世間の聞こえ如何なものかと思っていたが、同意を得ることができたのは喜ばしいことであるとしている。
これは信長の皮肉であろうか。
また和睦に関しては、双方の使者の通路である信濃~越後間は降雪の時期でのため、来春に取り決めたいとしている。
是非とも甲・越間の和睦が成立することを願っている。
江北の浅井長政の勢いはもはや見る影もない。
小谷近辺に詰め城を築き、人数を入れ置いておいたので、敵は城に籠り動く気配がない。
その為信長は同地に滞在する必要がない。
近江横山城と岐阜との距離は近いので、往還はたやすいことである。
そして最後には、信玄の遠慮ぎみの行動には、御礼を申し上げたいと、これまた恐らく皮肉であろう文言で文章を締め括っている。
しかし、信長がこの書簡を送った頃には、信玄はもう甲府にはいなかった。
10月3日に信玄は自ら大軍を率いて甲府を出陣し、駿河から遠江へ進撃したのだ。
本状には徳川を攻めることなど記されていないので、信長にとって信玄の遠江進撃は寝耳に水だったのかもしれない。
数日後の22日に信長は、徳川家康へ作戦を含めた内容の書簡を送っている。
なお、この史料は『織田信長文書の研究(1988)』には収録されておらず、『織田信長の古文書(2016)』には収録されている。
10月18日
上野秀政・島田秀満・村井貞勝が連署で、山城国妙心寺へ副状を発給。(同年10月7日付信長安堵状分)『妙心寺文書』
壬生之内、西五条田妙心寺領之事、任御下知、御朱印之旨、前々如有来、無他妨可寺納事、肝要候、若於他納者、可被加御成敗候、仍折紙之状如件
元亀三
十月十八日 上野中務大輔
秀政(判)
嶋田但馬守
秀満(同)
村井民部少輔
貞勝(同)
名主百姓中
(書き下し文)
壬生の内、西五条田の妙心寺領の事、御下知・御朱印の旨に任せて、前々有り来たりの如く、他の妨げ無く寺納すべき事、肝要に候。
もし他納(妙心寺以外に納入)に於いては、御成敗加えらるべく候。
仍って折紙の状くだんの如し。(以下略)
10月22日
吉田兼和(兼見)、病に臥している織田家家臣の島田秀満の息子を見舞い、病気回復を祈念。
祓鎮札を贈る。『兼見卿記』
同日
信長、武田信玄の大軍が迫った遠江の徳川家康に、作戦を申し含めた簗田広正を派遣した旨を通達。『田島文書』
其表為見廻、簗田左衛門太郎令進之候、存分具申含候、万端御分別専要候、畢竟御本意案之内候間、其思慮尤候、恐々謹言
十月廿二日 信長(花押)
三河守殿
進覧之候
(書き下し文)
その表の見廻りとして、梁田左衛門太郎(広正)、これをまいらしめ候。
存分はつぶさに申し含め候。
万端御分別専要に候。
畢竟御本意案のうち候間、その思慮尤もに候。恐々謹言(以下略)
(備考)
信長は佐久間信盛と平手汎秀を徳川への援軍として派遣し、このたび梁田広正も派遣した。
梁田は戦目付として遣わしたのだろうか。
10月24日
織田家家臣の島田秀満・村井貞勝が、上京で建設中の信長御座所のために吉田社(吉田郷)に藁の徴発をするも、吉田兼和側の要請によりこれを撤回。『兼見卿記』
10月25日
公家の吉田兼和、村井貞勝を訪問し、藁徴発免除を謝す。『兼見卿記』
10月29日
足利義昭の和議調停により、毛利輝元が浦上・宇喜多両氏と和睦し、横井左衛門に居城を破却させる。『萩藩閥閲録 二十五』
10月30日
武田信玄、浅井父子へ出陣を知らせる書状を発給。『南行雑録所収文書』『東浅井郡志』巻弐
只今出馬候。
この上は猶予無くてだてに及ぶべく候。
八幡大菩薩、富士浅間大菩薩、氏神新羅大明神照覧偽にあらず候。
義景と相談ぜられ、この時運を開くべき行尤もに候。恐々謹言
十月三十日 信玄
浅井下野守(久政)殿
浅井備前守(長政)殿
この時期
信長、織田信広と河尻秀隆を岩村城の保護を名目に派遣。『河田重親宛上杉謙信書状写』
(備考)
遠山景任の死後、にわかに不安定となった東美濃の地。
織田と武田の境目に位置するこの地で、遠山氏に従属する小領主たちの動きにも注目する必要がある。
10月
信長、近江国西庄永明寺へ全3ヶ条の禁制を下す。『永明寺文書』
(備考)
同地は近江八幡市西庄町にある。
六角氏残党の動きや、朝倉・浅井・甲斐武田・本願寺勢の調略により、近江国も未だに不安定な情勢であったと考えられる。
11月2日
木下秀吉(藤吉郎)、塙直政(九郎左衛門尉)が京都紫野大徳寺へ寺領の件で、信長朱印が2度に渡って発給されているので、不審に思い問い詰める。
寺社側は白状したようで、今後は秀吉、直政の両名に
- 疎意に存してはならぬこと
- 賀茂社領の件は石成友通へ申し届けること
- 詳細は蜂須賀正勝へ通達させること
を約束。『大徳寺文書』
11月3日
浅井・朝倉勢が小谷から兵を繰り出し、浅井七郎(浅井井規)を先陣に虎御前山から宮部に到る築地を攻撃。
木下秀吉ら、撃退に成功する。『信長公記』
『信長公記 巻五(奇妙様御具足初尓虎御前山御要害事)』より抜粋
霜月三日 浅井 朝倉人數を出し、虎御前山より宮部迄つかせられ候、築地可引崩行として 浅井七郎足輕大將尓て先を仕懸り來、則 羽柴藤吉郎人數を出し取合、 梶原勝兵衞、 毛屋猪介、 富田彌六、 中野又兵衛、 瀧川喜左衛門 先懸尓て暫支合、追崩し各高名無比類、 瀧川喜左衛門事、日比御近習尓被召使者候、此以前大谷表尓て大さし物を仕罷出させる働も無之、曲事と被仰出此頃蒙御勘當、虎御前山尓居残、今度目尓見へ候働を仕、各御取合尓て御前へ被召出、播面目也、
(書き下し文)
霜月三日 浅井・朝倉人数を出し、虎御前山より宮部まで突かせられ候。
築地を引き崩すべく、てだてとして浅井七郎(浅井井規)を足軽大将にて先を仕りかかり来て、すなわち羽柴藤吉郎(木下秀吉)人数を出して取り合い、梶原勝兵衛・毛屋猪介・富田弥六・中野又兵衛・滝川喜左衛門が先駆けにて暫し支え合い、追い崩しておのおの高名比類無し。
瀧川喜左衛門の事、日頃(信長の)御近習に召し使わさる者なり。
これ以前、小谷表(本年7月~9月の江北攻め)にて、大指物を仕り罷り出で、させる働きもこれ無く。
曲事と仰せ出され、この頃御勘当を蒙り、虎御前山に居残る。
このたび目に見え候働きを仕り、おのおの御取り合いにて御前へ召し出され、面目を施すなり。
11月5日
甲斐の武田信玄、美濃武儀郡の遠藤胤基、越前の朝倉義景、美濃国安養寺に遠江・三河の状況を記した書状を送る。『鷲見栄造氏所蔵文書』『安養寺文書』
(備考)
この当時、朝倉家の武田への取次ぎ役には山崎吉家が務めていたようだ。
朝倉義景は引き続き江北に留まり、信長を釘付けにする作戦だったようだ。
遠藤氏は郡上八幡一帯を治める国衆で、信長に仕えつつも武田家に内通していた。
11月12日
武田信玄、美濃武儀郡の遠藤加賀守(遠藤胤基の家老)へ書状を発給。『鷲見栄造氏所蔵文書(十一月十二日付武田信玄書状写)』
於其表、別而当方荷担之由、祝着候、当国過半任存分候事、岩村江移人数候条、至春者、濃州江可令出馬候、其以後、向岐阜江被顕敵対候、悉皆馳走、可為本望候、委細三村兵衛尉口上候、謹言
十一月十二日 信玄 御判
遠加々殿へ
(書き下し文)
其の表に於いて、別して当方に荷担の由、祝着に候。
当国過半存分に任せ候か。
岩村(美濃国)へ人数を移す候条、春に至るは、濃州へ出馬せしむべく候。
其れ以後、岐阜へ向かい敵対(の意を)顕わされ候。
悉く皆馳走、本望たるべく候。
委細、三村兵衛尉口上候。謹言
(元亀三年)十一月十二日 信玄(御判)
遠加々守(遠藤加賀守)殿へ
(備考)
なお、遠藤氏は北近江の浅井長政とも気脈を通じており、領内の寺で武田・浅井氏の仲介をしていたような節がある。
11月13日
信長、曽我助乗(兵庫頭)へ安宅神太郎の件について、自身の考えを述べた書状を送る。『古簡雑纂』十一
安宅神太郎事被仰聞候、尤以可然存候、去春已来之儀、無其聞存之由、一旦者無余儀候、但彼雑掌共申候趣、一向難題之模様候シ、其分ニ至てハ、果而入眼不実存候ける、抛万端、此節可抽忠節之由、寔神妙之至候、然間、領知方儀、彼方申様被聞召合可被仰付候、於信長不可存疎略候、此等之旨可有御披露候、恐々謹言
元亀三
十一月十三日 信長(花押)
(ウハ書)
「曽我兵庫頭殿 織田弾正忠
信長」
(書き下し文)
安宅神太郎の事仰せ聞かれ候。
尤も以って然るべく存じ候。
去春以来の儀、その聞こえ無く存ずるの由、一旦は余儀無く候。
但し、かの雑掌ども申し候趣き、一向難題の模様候し。
その分に至っては、果たして入眼不実に存じ候ける。
万端をなげうち、この節忠節を抜きんずべきの由、誠に神妙の至りに候。
然る間、領知方の儀、彼方の申し様聞こし召し合わせられ、仰せ付けらるべく候。
信長に於いては、疎略に存ずべからず候。
これらの旨、御披露あるべく候。恐々謹言(以下略)
(備考)
曽我助乗(兵庫頭)は幕府奉公衆の一人。
のちの宇治槙島城籠城戦や、義昭が若江城に落ち延びた時もこれに従った。
安宅神太郎のことに関する公方様の説示を諒承したが、その雑掌(荘園や知行に関する訴訟)の申し立ては難題であるとし、しかし領知は神太郎の要請を容れてよいと考えている。
恐らく足利義昭の調略により、洲本の安宅神太郎が降ったのだろう。
近年の説によると、安宅信康とは別人のようだ。
同日
信長、薬師寺弥太郎へ一雲と小次郎の借銭を無効とし、小二郎の時に売却した田畠も早々に取り返して知行を安堵する。『向井英太郎氏所蔵文書』
一雲幷小次郎借銭之事、令免許畢、同小二郎(ママ)時、田地沽却之由、是又早々召返、可令領知之状如件
元亀参
十一月十三日 信長(朱印)
薬師寺弥太郎とのへ
(書き下し文)
一雲並びに小次郎借銭の事、免許せしめおわんぬ。
同じく小二郎(ママ)の時に、田地沽却之由、これまた早々と召し返し、領知せしむべきの状くだんの如し(以下略)
(備考)
なお、幕府は元亀元年(1570)10月4日に徳政を出している。
岩村城が武田家の手に渡る
11月14日
岩村城の遠山氏、織田軍を城から追い出し、一転して武田の陣営に加わる。
岩村城は即日武田勢が入城し、遠山家の当主となっていた信長子息・御坊丸は捕らえられて甲斐へ送られる。『鷲見栄造氏所蔵文書』
11月15日
信長、落ち延びた神篦城主・延友信光(佐渡守)に、岩村城が落城したにも関わらず、織田家へ忠節を尽くしてくれたことを賞し、美濃国日吉郷と釜戸本郷を与える。『上原準一氏所蔵文書』
今度岩村之儀、無是非題目候、雖然其方事無疎略、覚悟之通神妙候、仍日吉郷、釜戸本郷令扶助候、弥忠節簡要候、恐々謹言
元亀三
十一月十五日 信長(朱印)
延友佐渡守殿
(書き下し文)
このたび岩村の儀、是非無き題目に候。
然りといえども、其方の事疎略無く、覚悟の通り神妙に候。
仍って日吉郷・釜戸本郷を扶助せしめ候。
いよいよ忠節簡要に候。恐々謹言(以下略)
(備考)
なお、翌年9月6日に信長嫡男の信重(織田信忠)も、佐渡守の忠節を労い、同地を安堵する旨の判物を発給している。『上原準一氏所蔵文書』
同日
北近江の浅井長政、美濃武儀郡の遠藤加賀守(遠藤胤基の家老)へ、武田信玄との密約が締結された旨を知らせる書状を発給。『岐阜県史(十一月十五日付浅井長政書状)』『古今消息集』
未だ申し通せず候といえども、啓せしめ候。
仍って甲州の役者(奉行人)差し越し候ところ、胤繁御昵懇の段、謝り難く存じ候。
殊に貴辺種々御馳走の由、快然至極に候。
遠(遠江国) 三(三河国)早速信玄に属され存分の儀、珍重比事候。
向後は飛脚に切々と罷り通すべき候条、御退屈無く御調え、畏悦たるべく候。
万吉来音を期し候。恐々謹言
(元亀三年)十一月十五日 長政(花押)
遠藤加賀守殿
御宿所
(備考)
この時期の遠藤氏が、信長に面従腹背を重ねていたことを示す貴重な史料である。
武田信玄 遠江で目覚ましい進撃を見せる
この頃
信長、武田軍が遠江二俣城を取り囲んだことを知る。『信長公記』
11月18日
織田家と本願寺との間で和睦が成立か。
信長、本願寺へ書状を送る。『本願寺文書(十一月十八日付織田信長書状案)』
芳墨令拝悦候、抑一種号白天目、贈給候、名物之条、連々一覧之望候鳧、旁以自愛不鮮候、度々御懇信快然之至候、随而条目之通、聊無疎意候、委曲大坂肥前法橋申含候、恐惶敬白
十一月十八日 (信長黒印)
本願寺回報
(書き下し文)
芳墨拝悦せしめ候。
そもそも一種(白天目と号す)、贈り給い候。
名物の条、連々一覧の望みに候けり。
かたがたもって自愛少からず候。
たびたび御懇信快然の至りに候。
従って条目の通り、いささかも疎意無く候。
委曲、大坂の肥前法橋に申し含め候。恐惶敬白
十一月十八日 (信長黒印)
本願寺回報
(備考)
本状は翌年天正元年(1573)のものであるとする説もある。
本願寺顕如は、講和の証として信長に白天目茶碗を贈った。
信長はこれを大変気に入ったようで、11月23日に京都妙覚寺の茶会でこの白天目を使用している。
このつかの間の和平により、本願寺系の寺への参詣の自由が保証され、その高札が京都に立てられた。
11月19日
松永久秀、大和国片岡の近辺へ出撃して放火する。『多聞院日記』
同日
武田信玄、越前の朝倉義景へ岩村城へ兵を移し入れたこと、来春に美濃へ出兵し、そのときに信長へ敵性を顕わす旨の書状を発給。『徳川黎明会所蔵文書(十一月十九日付け武田信玄書状)』
(備考)
「岩村江移人数候条、至春者、濃州江可令出馬候、其以後、向岐阜江被顕敵対候、」
の一文が特に議論を呼んでいる模様。
同日
武田信玄、美濃武儀郡の遠藤氏へ書状を発給。『鷲見栄造氏所蔵文書(十一月十九日付武田信玄書状写)』
(備考)
近年では本状に「十四日に岩村城を請け取り、人数を籠め置いた」と伝えていることから、岩村城は武田勢が攻め落としたのではなく、自発的に武田方に帰順したのではないかとする説が有力になりつつある模様。
通説であった秋山信友なる人物が、岩村城のおつやの方云々の話はかなり怪しいものとなる。
11月20日
この日も松永久秀は片岡近辺を放火。『多聞院日記』
同日
信長、越後の上杉謙信(不識庵)へ5ヶ条の条書を送る。『歴代古案』九『古証文』五『古今消息集』十『武家事紀』二十九
(備考)
内容は、信玄の悪行は前代未聞の無道であり、この儀に徳川と織田・上杉で武田を挟み撃ちにして討ち取ろうとするもの。
過去にこの書状について記事にしたことがあるので、下記の関連記事をご参照されたい。
関連記事:信玄西上!息子を人質に取られた信長が、上杉謙信に送った決意とは(1)
関連記事:信玄西上!息子を人質に取られた信長が、上杉謙信に送った決意とは(2)
関連記事:信玄西上!息子を人質に取られた信長が、上杉謙信に送った決意とは(3)
11月22日
松永久秀が大和多聞山城から出陣し、今市を放火。
筒井順慶勢が出撃し、これを撃退。『多聞院日記』
11月24日
信長、尾張国西御堂方へ反銭を徴する。『氷室和子氏所蔵文書』
納 西御堂方反銭之事、
合拾貫文 金子五両 足立清左衛門尉
祖父江五郎右衛門持分之内、
右且納如件、
元亀参年十一月廿四日 (信長黒印)
(書き下し文)
納む 西御堂方反銭の事。
合せて拾貫文、金子五両、足立清左衛門尉、祖父江五郎右衛門持分の内。
右、且つは納むるところくだんの如し(以下略)
(備考)
西御堂は一宮市萩原町西御堂にある。
同地は父の代からの蔵入分(直轄地)であった。
祖父江氏は、同地における信秀父祖の代からの代官であった。
なお、反銭・段銭(たんせん)とは中世の租税の一つで、即位・内裏修理・社寺造営などの費用にあてるため、権力者が臨時に徴発する税のこと。
11月26日
細川藤孝と吉田兼和が近江坂本へ下向。『兼見卿記』
(備考)
恐らく明智光秀に用があって面会したのだろう。
光秀はこの年の9月中旬に軍を解き、上洛した後坂本に戻っていた。
11月27日
武田家の臣である山県昌景、長篠城主の奥平氏へ4ヶ条の条書を発給。『奥平家文書』
如御札二俣諸手垪際へ被押詰、殊方々ニ候水之手五三日以前被取り之候間、天流之水を汲候、因慈被厳船城岸へ被着置、綆を切候間、是も一円不叶、三日中可為落居候之条、可御心安候、
一、自尾州熱田罷越候者如申者、岐越衆於于江北遂一戦、濃尾者多数討死之由申候哉、剰大身之人二三輩越前へ同意仕之段、弥以可然存候、於実儀被聞召届、重而可蒙仰候、
一、海賊田原表放火候歟、彼動之様子委承度候、
一、貴辺御出陣之儀、何時も秋伯令談合、可申届聞者、無御気遣い御在滞尤候、
一、御息九八郎殿へ源次郎殿其外御親類衆、万端御吉左右、自是可申宣候、恐々謹言
追而、爰元へ申来候、日野之蒲生、越前へ同意之由候ニ而、此所被聞召届候、実説待入候、以上
山三兵
十一月廿七日 昌景(花押)
奥美
御報
(備考)
天流=天竜川
綆=なわ
秋伯=秋山伯耆守
御息九八郎=奥平九八郎(貞昌・信昌)
日野之蒲生=蒲生賢秀
奥美=奥平定能(美作守)
11月28日
柴田勝家、狛氏に対し以下の内容の書状を発給。『斎藤献氏所蔵文書』『保阪潤治氏所蔵文書』六
上狛延命寺之儀、拙者為与力、殿様江申上召置、還住之候、彼知行以下聊無御違乱、御近所之儀候間、以来御馳走可為祝着候、恐々謹言
柴田
十一月廿八日 勝家(花押)
狛左馬進殿
御宿所
(書き下し文)
上狛の延命寺の儀、拙者与力として、殿様へ申し上げ召し置き、還住の候。
かの知行以下は、いささかも御違乱無く、御近所の儀に候間、以来御馳走祝着たるべく候。恐々謹言(以下略)
(備考)
当時、柴田勝家は山城国南部地域を所領として持っており、近所の有力農である狛氏を、被官に加えるよう信長にも上奏した。
同年十一月日付けで信長判物も存在する。
越前を領すまでの柴田勝家家臣団の断片をうかがい知れる貴重な史料かもしれない。
11月
信長、狛氏に山城国相楽郡狛郷及び家来等を安堵する。『丹波柏原狛忠雄氏文書』『古文書纂』七
対此方無疎略通聞届候、狛郷之事、如前々可為領知候、幷家来等之儀、不可有相違之状如件
元亀参
十一月 日 信長(朱印)
狛左京亮□
(書き下し文)
こなたに対して疎略無きの通り聞き届け候。
狛郷の事、前々の如くに領知たるべく候。
並びに家来等の儀、相違あるべからざるの状くだんの如し
元亀三
十一月 日 信長(朱印)
狛左京亮(秀綱)□(殿カ)
(備考)
狛氏は山城国狛郷(山城国相楽郡山城町上狛と精華町下狛にあたる)の豪族。
同年11月28日付で柴田勝家が副状を発給している。
なお、翌年年頭の挨拶として、狛左馬進が祝物を贈呈している。
狛氏の由緒書では、左馬進と左京亮は同一人物とあるが、詳細は不明。
12月2日
信長、尾張の豪商である伊藤惣十郎に朱印状を与え、改めて尾張・美濃両国における唐人方(輸入呉服)と国産呉服方の商人司に任命する。(元亀三年十二月二日付織田信長朱印状写)『寛延旧家集』『金鱗九十九之塵』巻第十八『名古屋叢書』六
一、私先祖伊藤惣十郎、法名安中ゟ代々、尾濃両国商人司被仰付、信長公ゟ御朱印頂戴仕、信雄公、信忠公、秀次公、忠吉公御黒印頂戴仕、源敬様御意書、其外方々御判物数通頂戴、所持仕来候、写左之通ニ御座候、
一、高祖父助三郎儀、慶長十五戌年、清州ゟ御当地本町江引越候迄、五代住居仕候、
尾濃両国之唐人方並呉服方商買司之儀、改而申付訖、依之雖為売子、対吾分、夷子講之裁許可在之、然者他国之商人茂於当所令商売者、可及其届、為扶助申付候上者、猥之儀不可有之状如件
元亀三
十二月二日 御朱印
惣十郎へ
(書き下し文)
一、私先祖伊藤惣十郎、法名安中より代々、尾・濃両国の商人司を仰せ付けられ、信長公より御朱印を頂戴仕り、信雄(織田信雄)公、信忠(織田信忠)公、秀次(豊臣秀次)公、忠吉(松平忠吉)公御黒印頂戴仕る。
源敬(徳川義直)様御意書、そのほか方々の御判物を数通頂戴、所持仕り来たり候。
写し左の通りに御座候。
一、高祖父助三郎儀、慶長十五(1610)戌年、清州より御当地本町へ引越し候まで、五代住居仕り候。
尾・濃両国の唐人方並びに呉服方商買司の儀、改めて申し付けおわんぬ。
これにより売子たりといえども、我が分に対し、夷子講の裁許これあるべし。
しからば他国の商人も、当所に於いて商売せしめば、その届けに及ぶべし。
扶助として申し付け候上は、みだりの儀有るべからざるの状くだんの如し(以下略)
(備考)
この時惣十郎は改めて尾張・美濃両国の唐人方と呉服方の商人司とした。
そして売り子であっても信長の収取分にたいし、夷子講(伊藤惣十郎が結成した同業者組合)の裁許をさせ、他国の商人も尾張・美濃両国で商売しようとするならば、届け出るように指示した。
この副状と見られる判物は同月6日に発給されている。
商人の伊藤惣十郎は、この頃から頭角を現し始める。
以後、惣十郎は織田家の御用商人として信忠、信雄に仕え、さらに豊臣秀次、松平忠吉、徳川義直に仕えて御朱印を与えられている。
のちの伊藤松坂屋である。
翌年(1573)正月4日にも関連文書がある。
なお、役銭とは所得に応じて課された銭納の雑税のこと、唐人方は輸入雑貨のこと、呉服方は国産の雑貨を指す。
関連記事:戦国時代の古文書 判物とは何か 書き方のルールは?
朝倉義景 突然の帰国
12月3日
江北に在陣中の朝倉義景、越前へ帰陣。
(備考)この朝倉義景突然の帰国については、さまざまな見解がある。
大雪で北国街道が閉ざされる前に帰陣したかったとする従来の説のほか、上杉謙信が越中富山城を攻略したことで、それに対処せねばならなかったこと、織田勢の大半が本年10月16日に撤兵したことで、浅井氏救援という目的がひとまず達成できたこと、武田信玄の侵攻が予想よりも鈍足なことなどが挙げられる。
私はこれらの複合的な要素を義景が総合的に判断した結果、今回の撤兵に繋がったと考える。
なお、この撤兵に関し、信玄は同年12月28日付で義景を非難する書状を発給。『千葉県伊能家所蔵文書』
本願寺顕如も同日付で同様の書状を発給している。『顕如上人御書札案留』
同日
木下秀吉、松尾神社領を安堵。『松尾神社文書』
同日
葛野郡革島庄の土豪である革島秀存、松尾月読社神官の松室左衛門佐へ所領の権利を手放す旨の放状を発給。『松尾月読社文書 7-1 (京都大学総合博物館所蔵)』元亀三年十二月三日付革島秀存放状
松尾月読神領事、
今度我等仁被仰付、
雖被且納、 (闕字)御代々
被帯 (闕字)御判御下知、
當知行無紛候間、即
持返申候、然上者、田
畠・山林所々散在、如有
來悉可有御社納事
簡要候、向後於子々
孫々不可有違乱者也、
仍放状如件、
元亀三
十二月三日 革嶋市介
秀(花押)
松室左衛門佐殿
御宿所
(書き下し文)
松尾月読神領の事、この度我等に仰せ付けられ、且つ納めらるるといえども、 (闕字)御代々の (闕字)御判御下知を帯びられ、当知行は紛れ無きに候間、即ち持ち返り申し候。
然る上は、田畠・山林所々散在、有り来たりの如く、悉く御社納有るべきの事簡要に候。
向後に於いて、子々孫々違乱有るべからざるものなり。
仍って放状くだんの如し。(以下略)
(備考)
松尾月読神領は、このたび当家(革島氏)の領有が室町幕府から認められました。しかし、松尾月読社殿は、御代々幕府から領有権を認められていることに疑いはないので、当家はあなた方の訴えを尊重します。この上は、田畠・山林など所々に散在するあなた方の所領からは、一切の徴収や取り立てを行いません。仍ってここに放状を発給します。といった文意である。
細川藤孝が織田信長より桂川西地一職支配を認められる半年以上前のことであり、なかなか興味深い。
この放状により、一時的にせよ松尾月読社は失った神領支配を回復したようだ。
同日
石山本願寺門跡の顕如、甲斐の武田信玄(法性院)・勝頼(四郎殿)父子へ戦勝を祝した旨の書状を発給。『顕如上人御書札案留』
先度者芳禮之趣令薰讀候、仍如御兼約遠州表御出馬之儀尤珍重候、殊被得勝利之由其聞候、大慶此事候、随而太刀一腰金、紅糸十斤進之候、表祝儀計候、尙賴充法眼可申入候、— —
十二月三日 — —
法性院殿
〔貼紙〕
此時音物未被遣候、
取次ヘハ段金二端
(書き下し文)
先度は芳礼の趣き薫読せしめ候。
仍って御兼約の如く遠州表御出馬の儀尤も珍重に候。
殊に勝利を得らるの由その聞こえに候。
大慶この事に候。
従って太刀一腰(金)・紅糸十斤これをまいらせ候。
祝儀を表すばかりに候。
尚頼充法眼(下間頼充)申し入るべく候、— —
十二月三日 — —
法性院(武田信玄)殿
〔貼紙〕
この時の音物未だ遣わされず候。
取次へは段金二端。
其表御進發之儀、早々可属御本意事勿論候、仍太刀一腰金、虎皮二枚進之候、聊顯祝儀計候、委曲上野法眼可申入候、— —
十二月三日
四郎殿
(書き下し文)
その表御進発の儀、早々御本意に属すべき事勿論に候。
仍って太刀一腰(金)・虎皮二枚これをまいらせ候。
いささか祝儀を表すばかりに候。
委曲上野法眼(下間頼充)申し入るべく候。(以下略)
12月6日
成田長重(成田杉長重)・木下秀吉(木藤秀吉)・岩弥三吉勝・金森長近(金五郎八長近)・塙直政(塙九郎左衛門直政)・森長可(森勝蔵可長)・丹羽長秀(丹羽五郎左衛門長秀)・島田秀満(嶋田但馬守秀満)、尾張の豪商である伊藤惣十郎に副状を発給。(元亀三年十二月六日付織田信長朱印状写)『寛延旧家集』『金鱗九十九之塵』巻第十八『名古屋叢書』六
同日
信長、成田義金(与左衛門尉)へ尾張国内で津田又十郎の知行している秋定方六十貫文を没収して宛行う判物を発給。『阿波潮文書』
尾州之内津田又十郎分秋定方六拾貫文、為闕所宛行畢、糾明次第全可領知之状如件
元亀三
十二月六日 信長(朱印)
成田与左衛門尉とのへ
(書き下し文)
尾州の内津田又十郎分秋定方六拾貫文、闕所として宛行いおわんぬ。
糾明次第に全く領知すべきの状くだんの如し(以下略)
(備考)
成田氏はおそらく尾張の土豪。
成田義金にたいし、尾張国内の津田又十郎の知行している秋定方六拾貫文を没収して宛行い、調査の済み次第領知させた朱印状である。
12月11日
明智光秀が吉田兼和に書状を送る。
内容は、一族である某の山王社敷地内での新城普請に際し、不快に思い悩んでいる内容のようだ。
吉田兼和は返書で鎮札・地鎮を送付する旨を伝える。『兼見卿記』
12月12日
吉田兼和、明智光秀へ山王社敷地の安鎮札を整える。『兼見卿記』
12月19日
石山本願寺門跡の顕如、浅井長政(備前守殿)・久政(下野守殿)父子へ、激励と武田信玄が勝利を重ねている旨の書状を発給。『顕如上人御書札案留』
其表之儀如何候哉、城中堅固之段専用候、信玄進發遠三口大利之由候間、此砌彌可被廻調略事、肝要候、次黄金二十兩進之候、比興々々、猶上野法眼可令演說候間抛筆候也、穴賢
十二月十九日
浅井備前守殿
(書き下し文)
その表の儀いかが候哉。
城中堅固の段専要に候。
信玄進発遠・三口大利の由に候間、このみぎりいよいよ調略廻さるべき事肝要に候。
次いで黄金二十両これをまいらせ候。
比興比興。
猶上野法眼(下間頼充)演説せしむべく候間、筆をなげうち候也。穴賢(以下略)
其表之儀、堅固之由珍重候、信玄遠三口本意候由候條、此節彌其許可被廻計策候、尤肝要候、將又黄金二十兩遣之候、顯音問計候、委細上野法眼可申展候也、— —
十二月十九日
浅井下野守殿
(書き下し文)
その表の儀、堅固の由珍重に候。
信玄遠・三口本意に候由に候条、この節いよいよ其許計策廻さるべく候。
尤も肝要に候。
将又黄金二十両これを遣わし候。
音問を表すばかりに候。
委細上野法眼(下間頼充)申し述ぶべく候也。(以下略)
三方ヶ原の合戦 徳川・織田連合軍が武田信玄に敗北
12月22日
遠江国三方ヶ原において、武田軍と徳川・織田連合軍が交戦。
武田軍が勝利。
徳川家康は命からがら浜松城へ撤退。
織田家臣は長谷川橋介・佐藤藤八・山口飛騨・加藤弥三郎・平手汎秀らは悉く討死。『信長公記』など
同日
吉田兼和(兼見)、明智光秀を見舞うため近江坂本へ下向。
城中の天主普請を見物して驚く。『兼見卿記』
12月26日
信長、大和国興福寺等に、過料として銀子100枚の徴発を命じる。『多聞院日記』
12月27日
石山本願寺門跡の顕如、去る十月二十日付の武田信玄からの書簡を読み、遠州で勝利を重ねている旨の書状を発給。『顕如上人御書札案留』
十月廿日之芳墨、至當月中旬遂被覽、尤本懐至極候、抑遠州口御進發、殊早速被得大利之由珍重□此事候、彌御本意勿論候、其以後打續御勝利之趣、風聞無其隱候、先日態令啓達候、漸可令參着?候、爰元之儀上野法眼委曲可申入候條、不能委細候、— —
十二月二十七日 — —
法性院殿
(書き下し文)
十月二十日の芳墨、当月中旬に至りて被覧を遂げ、本懐至極尤もに候。
そもそも遠州口御進発、殊に早速大利を得らるの由、珍重□この事に候。
いよいよ御本意勿論に候。
それ以後打ち続いて御勝利の趣き、風聞その隠れ無く候。
先日わざと啓達せしめ候。
漸く参着(?)せしむべく候。
爰元の儀上野法眼(下間頼充)が委曲申し入るべく候条、委細は能わず候。(以下略)
12月28日
武田信玄、越前の朝倉義景へ書状を発給。『千葉県伊能家所蔵文書』
使僧を以て承り候条、其の意を得候。
仍って二俣(遠江国)の普請出来候間、三州(三河国)に向かい進陣のみぎり、家康人数を出し候の条、去る二十二日、当国(遠江国)に見方原(三方ヶ原)に於いて一戦を遂げ、勝利を得、三(三河国) 遠(遠江国)両国の凶徒並びに岐阜の加勢衆を千人余人討ち取り、本意を達し候間、御心易かるべく候。
また、巷説のごとくは、御手前(朝倉義景)の衆、過半は帰国の由、驚き入り候。
各々の労兵は勿論に候。
然りといえども、この節信長滅亡の時刻到来候ところ、唯今ただいま寛宥の御備労に功無く候か。
御分別に過ぎべからず候。
なお、かの口上に与え付け候。恐々謹言
(元亀三年)十二月二十八日 信玄(花押)
謹上 朝倉左衛門督殿
(備考)
これは、当年12月3日に朝倉義景が本国へ撤兵したことを受けてのものである。
「各々の労兵は勿論に候」とした上で、「せっかく信長を滅亡に追い込む好機なのに」と遠慮しつつも義景の決断を非難する内容となっている。
同日
石山本願寺門跡の顕如、朝倉義景の件で武田信玄(法性院)へ書状を発給。『顕如上人御書札案留』
従義景以山門大蔵院被申越之趣、密々之儀ニ候、於様子者上野法眼可申入候間、能々被加御思慮御報待入計候、事々令省略候、— —
十二月廿八日 — —
法性院殿
(書き下し文)
義景(朝倉義景)より山門大蔵院を以て申し越さるの趣き、密々の儀に候。
様子に於いては上野法眼(下間頼充)申し入るべく候間、よくよく御思慮を加えられ、御報を待ち入るばかりに候。
事々省略せしめ候。(以下略)
石山本願寺門跡の顕如、朝倉義景(左衛門督殿)へ越前勢の突然の帰国に憤り、武田信玄と深重に連絡を取る旨の書状を発給。『顕如上人御書札案留』
以山門大蔵院承候通得其意候、雖然當寺之儀者、毎篇甲州深重申談筈有之事候間、則尋下善惡之一途、急度從是可申述候、尙上野法眼可申入候、— —
十二月廿八日
左衛門督殿
(書き下し文)
山門大蔵院を以て承り候とおり、その意を得候。
然りといえども、当寺の儀は、毎篇甲州と深重に申し談ずるはずにこれ有る事候間、則ち尋下善悪の一途、急度これより申し述ぶべく候。
尚上野法眼(下間頼充)申し入るべく候。(以下略)
- 誕生~叔父信光死去まで(1534~1555)
- 叔父信光死去~桶狭間の戦い直前まで(1555~1560)
- 桶狭間の戦い~小牧山城移転直後まで(1560~1564)
- 美濃攻略戦(1564~1567)
- 覇王上洛(1567~1569)
- 血戦 姉川の戦い(1570 1.~1570 7.)
- 信長包囲網の完成(1570 7.~12.)
- 比叡山焼き討ち(1571 1.~9.)
- 義昭と信長による幕府・禁裏の経済改革(1571 9下旬~1571.12)
- 元亀3年の大和動乱(1572 1.~1572.6)
- 織田信重(信忠)の初陣(1572 7.~1572 9.)
- 武田信玄 ついに西上作戦を開始する(1572 9.~1572 12.) ←イマココ
- 将軍・足利義昭の挙兵と武田信玄の死(1573 1.~1573 4.)
- 将軍追放 事実上の室町幕府滅亡(1573 5.~1573 7.)
- 朝倉・浅井家滅亡(1573 8.~1573 10.)
- 三好義継の最期(1573 10.~1573 12.)